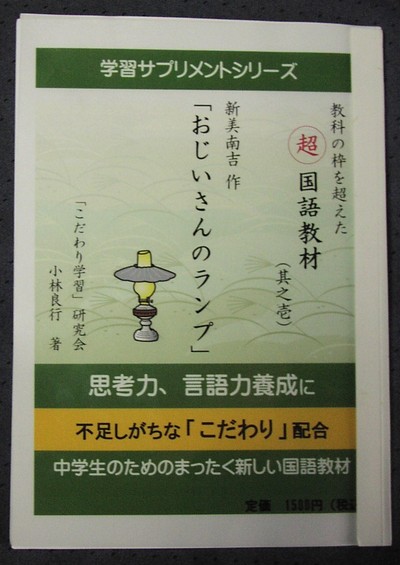2011年08月09日
言語力の差
ようやく夏期講習も終わり、中3の模試も済んで通常の日々に戻った。
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。
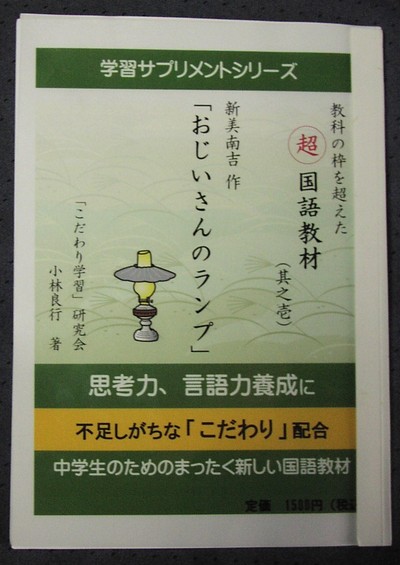
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。