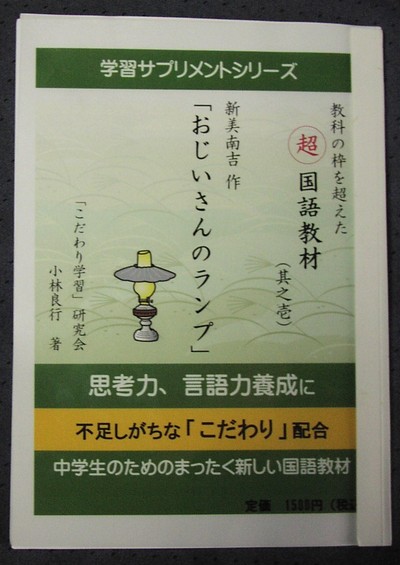2011年08月27日
買ってしまった...
子どもが小さい頃は写真をよく撮った。
一眼レフを買ってからはカメラの世界にのめり込み、
絞りやシャッター速度、構図や測光方式などについて勉強したものだ。
やがてはキャノンNEW F-1というマニュアル機の最高峰機種(ボディだけで10万はしたと思う)を
手に入れ、オートに頼らない撮影を楽しんだ。
子どもを始め、人物の写真ではあえて逆光や半逆光で撮ってラインライト(輪郭が光る)効果を狙った。
当然のことながら、まだ銀塩カメラの時代だったのでお金はかかった。
フィルムはリバーサル(スライド用)のASA50。
ネガフイルムより色が鮮やかだが、失敗はできない。
リバーサルは後から修正が効かないのだ。
でも、だからこそ手応えがあった。
ピントも露出もすべてマニュアルで、思い通りの写真が撮れたときの満足感は忘れられない。
展覧会に応募して金賞をもらったこともある。
カメラ雑誌にもしょっちゅう掲載されていた。
ところが、子どもが大きくなるに連れて写真が減ってくる。
よくあることだが、最初の子どもの写真は多いが、3人目となるとぐんと減る。
時を同じくして脱サラで忙しくなり、さらにカメラの世界もデジタルへと移行していった。
デジカメは便利だし経済的だが、後からいくらでも加工できる分つまらない。
かつてのような緊張感や充実感は得られないのだ。
結局、私もデジカメに移ったが、一眼デジカメには魅力を感じなかった。
それでも、コンパクトカメラの中ではレンズの性能が優れ、マニュアル撮影も可能な機種を選んだのは、まだどこかに写真小僧の血が流れていたのかも知れない。
先日お盆に実家に帰ったとき、昔のカメラ雑誌を大量に発見した。
うちにもあるはずなのだが、引っ越しの繰り返しで荷物に紛れてしまい、久しく見ていなかったものだ。
なつかしがって掲載作を見ているうちに、ふつふつと撮影意欲が甦ってきた。
最近興味を持っていた「ミラーレス一眼」のことが、俄然気になり出したのだ。
ネットで調べ、店頭で触り、とうとう買ってしまった。
オリンパスのPENシリーズ、E-PL1S(ダブルズームセット)。
ボディだけで5万はするという印象だったのが、ズームレンズ2本付きで4万2千円!
安くなったものだ...。
この機種にした一番の理由は小さくて軽いこと。
本格的な一眼レフだと、ごっつくて重い。
昔のNEWF-1は、なんやかや付けて1.5kg以上あったと思う。
これでは気軽に持ち歩くというわけにはいかない。
標準ズームを付けて450gなら、毎日連れ出しても苦にならない。
もちろん写りはさすがである。
コンパクトデジカメとは雲泥の差だ。
あとは、10月に販売になるという新型のファインダーを付ければ完璧だ。
どうも液晶モニタを見ての撮影は肌に合わない。
写真はファインダーを覗いて撮らなくちゃ...。
眠っていた趣味が復活した意味は大きい。
ありふれた毎日がずっと楽しくなりそうである。

一眼レフを買ってからはカメラの世界にのめり込み、
絞りやシャッター速度、構図や測光方式などについて勉強したものだ。
やがてはキャノンNEW F-1というマニュアル機の最高峰機種(ボディだけで10万はしたと思う)を
手に入れ、オートに頼らない撮影を楽しんだ。
子どもを始め、人物の写真ではあえて逆光や半逆光で撮ってラインライト(輪郭が光る)効果を狙った。
当然のことながら、まだ銀塩カメラの時代だったのでお金はかかった。
フィルムはリバーサル(スライド用)のASA50。
ネガフイルムより色が鮮やかだが、失敗はできない。
リバーサルは後から修正が効かないのだ。
でも、だからこそ手応えがあった。
ピントも露出もすべてマニュアルで、思い通りの写真が撮れたときの満足感は忘れられない。
展覧会に応募して金賞をもらったこともある。
カメラ雑誌にもしょっちゅう掲載されていた。
ところが、子どもが大きくなるに連れて写真が減ってくる。
よくあることだが、最初の子どもの写真は多いが、3人目となるとぐんと減る。
時を同じくして脱サラで忙しくなり、さらにカメラの世界もデジタルへと移行していった。
デジカメは便利だし経済的だが、後からいくらでも加工できる分つまらない。
かつてのような緊張感や充実感は得られないのだ。
結局、私もデジカメに移ったが、一眼デジカメには魅力を感じなかった。
それでも、コンパクトカメラの中ではレンズの性能が優れ、マニュアル撮影も可能な機種を選んだのは、まだどこかに写真小僧の血が流れていたのかも知れない。
先日お盆に実家に帰ったとき、昔のカメラ雑誌を大量に発見した。
うちにもあるはずなのだが、引っ越しの繰り返しで荷物に紛れてしまい、久しく見ていなかったものだ。
なつかしがって掲載作を見ているうちに、ふつふつと撮影意欲が甦ってきた。
最近興味を持っていた「ミラーレス一眼」のことが、俄然気になり出したのだ。
ネットで調べ、店頭で触り、とうとう買ってしまった。
オリンパスのPENシリーズ、E-PL1S(ダブルズームセット)。
ボディだけで5万はするという印象だったのが、ズームレンズ2本付きで4万2千円!
安くなったものだ...。
この機種にした一番の理由は小さくて軽いこと。
本格的な一眼レフだと、ごっつくて重い。
昔のNEWF-1は、なんやかや付けて1.5kg以上あったと思う。
これでは気軽に持ち歩くというわけにはいかない。
標準ズームを付けて450gなら、毎日連れ出しても苦にならない。
もちろん写りはさすがである。
コンパクトデジカメとは雲泥の差だ。
あとは、10月に販売になるという新型のファインダーを付ければ完璧だ。
どうも液晶モニタを見ての撮影は肌に合わない。
写真はファインダーを覗いて撮らなくちゃ...。
眠っていた趣味が復活した意味は大きい。
ありふれた毎日がずっと楽しくなりそうである。
2011年08月16日
言語力の差~その2~
中学生より高い国語力を持つ小学生の話の続き。
これも「おじいさんのランプ」に収録されている問題だ。
町で初めてランプを見た巳之助は、その明るさに驚く。
さらに...。
それにランプは、その頃としてはまだ珍らしいガラスでできていた。
煤(すす)けたり、破れたりし やすい紙でできている行燈より、
これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。
(問)「これ」は何を指していますか。
解答欄は「( )こと」となっている。
「こと」に続く形で答よということだ。
指示語の問題はかなり出してある。
内容は合っていても、形(答え方)が適切でなければ〇はもらえない。
言語能力(国語力)を育てる良質な問題が作りやすいのだ。
「これ」が指すものを答える場合は、名詞の形で終わる必要がある。
本文中には出てこなくても、「~もの」や「~こと」を付け加えなければならないことが多い。
教材の後半ではそこを自力で調整できる力を求めているが、
ここはまだ冒頭に近いので、「~こと」を予め提示しておいた。
だから、この問いも他の箇所と同様直感的に作ったものではあるが、
特別難しいとも思っていなかった。
ところが市販前に中学生に解かせてみると、実に出来が悪い。
多いのは「ガラスでできているランプ」的な答だ。
塾でやるなら大人がアドバイスできるが、自習で解くとなると苦労する子が多く出そうだ。
そういう問題にはヒントを入れた。
ここではこんな具合だ。
<ヒント>「巳之助には」の後に「~が」を補って考える。
もちろん、ここに入るべきは「ランプが」である。
これが答えられないと話にならない。
答えられても、問いに対する正解を出せるのは、全体の3割以下ではなかろうか...。
前回ご紹介した小6男子のうち、
一人は1回で正解、一人は2回目で正解だった。
もう一人はまだ保留中。
この子は他の問題では真っ先に正解していたことも多いので、
やはり小学生だとムラがあるるのかも知れない。
それでも、いくらアドバイスしてもトンチンカンな答しか書いてこない中2、中3の生徒を前に途方に暮れているときには心から思うのだ。
言語能力の土台は、小学生のうちに固めておくべきだと...。
ちなみに、上記の問題の答は「ガラスでできていること」でした。

※お盆に千葉の実家に帰るついでに、今年は神宮球場に行ってきました。ネット裏の2階席で、
料金のわりによい席でしたが、5回終了時の花火は、屋根が邪魔で半分しか見えず...。
試合は阪神が4-1で快勝!
これも「おじいさんのランプ」に収録されている問題だ。
町で初めてランプを見た巳之助は、その明るさに驚く。
さらに...。
それにランプは、その頃としてはまだ珍らしいガラスでできていた。
煤(すす)けたり、破れたりし やすい紙でできている行燈より、
これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。
(問)「これ」は何を指していますか。
解答欄は「( )こと」となっている。
「こと」に続く形で答よということだ。
指示語の問題はかなり出してある。
内容は合っていても、形(答え方)が適切でなければ〇はもらえない。
言語能力(国語力)を育てる良質な問題が作りやすいのだ。
「これ」が指すものを答える場合は、名詞の形で終わる必要がある。
本文中には出てこなくても、「~もの」や「~こと」を付け加えなければならないことが多い。
教材の後半ではそこを自力で調整できる力を求めているが、
ここはまだ冒頭に近いので、「~こと」を予め提示しておいた。
だから、この問いも他の箇所と同様直感的に作ったものではあるが、
特別難しいとも思っていなかった。
ところが市販前に中学生に解かせてみると、実に出来が悪い。
多いのは「ガラスでできているランプ」的な答だ。
塾でやるなら大人がアドバイスできるが、自習で解くとなると苦労する子が多く出そうだ。
そういう問題にはヒントを入れた。
ここではこんな具合だ。
<ヒント>「巳之助には」の後に「~が」を補って考える。
もちろん、ここに入るべきは「ランプが」である。
これが答えられないと話にならない。
答えられても、問いに対する正解を出せるのは、全体の3割以下ではなかろうか...。
前回ご紹介した小6男子のうち、
一人は1回で正解、一人は2回目で正解だった。
もう一人はまだ保留中。
この子は他の問題では真っ先に正解していたことも多いので、
やはり小学生だとムラがあるるのかも知れない。
それでも、いくらアドバイスしてもトンチンカンな答しか書いてこない中2、中3の生徒を前に途方に暮れているときには心から思うのだ。
言語能力の土台は、小学生のうちに固めておくべきだと...。
ちなみに、上記の問題の答は「ガラスでできていること」でした。
※お盆に千葉の実家に帰るついでに、今年は神宮球場に行ってきました。ネット裏の2階席で、
料金のわりによい席でしたが、5回終了時の花火は、屋根が邪魔で半分しか見えず...。
試合は阪神が4-1で快勝!
2011年08月09日
言語力の差
ようやく夏期講習も終わり、中3の模試も済んで通常の日々に戻った。
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。
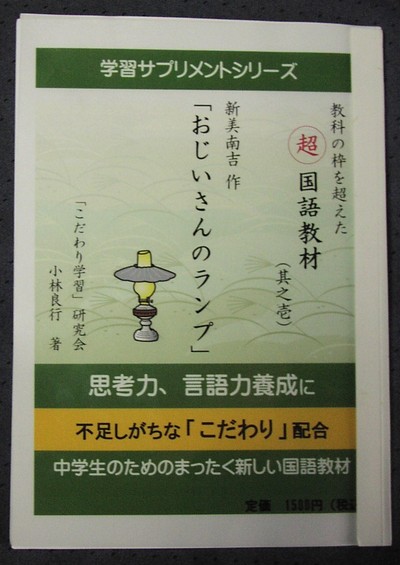
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。