2010年06月30日
投扇興のテレビ取材を受けました
先日SBCテレビから電話があり、
投扇興の取材をさせてほしいとのこと。
松代の町を散策するという番組で、
投扇興を楽しんでいるところにレポーターがやってきて、
話を聞いたり実際に体験したりするという内容だそうです。
さっそく仲間にも声を掛け、今日の午前中、収録が行われました。
場所は山寺常山邸。雰囲気のある所です。
いろいろ説明した後、
アナウンサーのFさんが初体験。
いつも初心者に対するときように、扇の持ち方、投げ方をご指導させていただき、
さあ、記念すべき第一投。
...みごとに飛びました!
「蝶」(的のことです)には当たらなかったものの、
初めはスムーズに扇を飛ばすこと自体難しいのです。
なかなか筋がいいと、皆から拍手喝采です。
2投目で蝶をとらえ、1点。
だんだん慣れてきて、そのうち8点技も出されました。
すぐにコツをつかまれたようです。
SBC内でサークルを作ろうか、なんておっしゃってました。
本当にそうなったら面白いのですが...。
放送は7月14日(水)午後7時からの予定。
「SBCスペシャル」です。
物好きな方はご覧ください。

投扇興の取材をさせてほしいとのこと。
松代の町を散策するという番組で、
投扇興を楽しんでいるところにレポーターがやってきて、
話を聞いたり実際に体験したりするという内容だそうです。
さっそく仲間にも声を掛け、今日の午前中、収録が行われました。
場所は山寺常山邸。雰囲気のある所です。
いろいろ説明した後、
アナウンサーのFさんが初体験。
いつも初心者に対するときように、扇の持ち方、投げ方をご指導させていただき、
さあ、記念すべき第一投。
...みごとに飛びました!
「蝶」(的のことです)には当たらなかったものの、
初めはスムーズに扇を飛ばすこと自体難しいのです。
なかなか筋がいいと、皆から拍手喝采です。
2投目で蝶をとらえ、1点。
だんだん慣れてきて、そのうち8点技も出されました。
すぐにコツをつかまれたようです。
SBC内でサークルを作ろうか、なんておっしゃってました。
本当にそうなったら面白いのですが...。
放送は7月14日(水)午後7時からの予定。
「SBCスペシャル」です。
物好きな方はご覧ください。
2010年06月29日
ペット嫌いは悪なのか?
私はペットが嫌いだ。
虫や魚、小鳥など、狭い空間から出てこないものならまだいいが、犬や猫はダメ。
以前、養鶏場で犬を飼っていたことがあるが、あくまでも番犬としてである。
特に、家の中で犬猫を飼うのは考えられない。
言っておくが、わが家は決して整理整頓、掃除が行き届いているわけではない。
むしろホコリだらけである。
きれい好きだから嫌っているのではないのだ。
「家族の一員」などと言って、屋内で放し飼いにしたり、一緒に寝たり、
服まで着せて喜んでいるのには、とてもついて行けない。
それにしても、なぜこんなにもペットを飼っている、あるいはペット大好きという人が多いのか?
周りの家を見ても、特に犬を飼っている割合は相当高い。
ブログでもペットの話題や写真は至るところにある。
動画サイトでも、テレビ番組でも、犬や猫を対象としたものは大人気だ。
それだけ日本が豊かということか、はたまた人との付き合いが希薄だからか...。
まあ、好きなのは勝手だから文句は言わない。
問題は、ペット嫌いが異端視されるような風潮である。
みんながペット好きだなどと思わないでもらいたい。
散歩中にリードを外して「おとなしいから大丈夫」と言われても、
そばに寄ってこられるだけで不快or怖いのだ。
よその家を訪ねて上がらせてもらったはいいが、
猫がこちらの膝の上にまでのぼってくるのは勘弁してもらいたい。
ペット嫌いはどんどん肩身が狭くなっている。
犬と猫どちらが好きかと聞かれて、「どちらも嫌い」などと答えたら、白い目で見られそうだ。
「ペット好きに悪い人はいない」という、何の根拠もない価値観が幅をきかせ、
ペット嫌いが冷たい人、変わり者、果ては非人間扱いされる世の中はどこかがおかしい...。

虫や魚、小鳥など、狭い空間から出てこないものならまだいいが、犬や猫はダメ。
以前、養鶏場で犬を飼っていたことがあるが、あくまでも番犬としてである。
特に、家の中で犬猫を飼うのは考えられない。
言っておくが、わが家は決して整理整頓、掃除が行き届いているわけではない。
むしろホコリだらけである。
きれい好きだから嫌っているのではないのだ。
「家族の一員」などと言って、屋内で放し飼いにしたり、一緒に寝たり、
服まで着せて喜んでいるのには、とてもついて行けない。
それにしても、なぜこんなにもペットを飼っている、あるいはペット大好きという人が多いのか?
周りの家を見ても、特に犬を飼っている割合は相当高い。
ブログでもペットの話題や写真は至るところにある。
動画サイトでも、テレビ番組でも、犬や猫を対象としたものは大人気だ。
それだけ日本が豊かということか、はたまた人との付き合いが希薄だからか...。
まあ、好きなのは勝手だから文句は言わない。
問題は、ペット嫌いが異端視されるような風潮である。
みんながペット好きだなどと思わないでもらいたい。
散歩中にリードを外して「おとなしいから大丈夫」と言われても、
そばに寄ってこられるだけで不快or怖いのだ。
よその家を訪ねて上がらせてもらったはいいが、
猫がこちらの膝の上にまでのぼってくるのは勘弁してもらいたい。
ペット嫌いはどんどん肩身が狭くなっている。
犬と猫どちらが好きかと聞かれて、「どちらも嫌い」などと答えたら、白い目で見られそうだ。
「ペット好きに悪い人はいない」という、何の根拠もない価値観が幅をきかせ、
ペット嫌いが冷たい人、変わり者、果ては非人間扱いされる世の中はどこかがおかしい...。

2010年06月28日
信州人は方角に強い?
店や施設の位置を人に説明するとき、
私なら、たとえば「郵便局の右」とか「コンビニの向かい」という言い方をする。
それが普通の教え方だと思っていた。
ところが長野では、方角を使う人が多いように感じる。
「郵便局の東」「コンビニの南」という具合に...。
実際はどうか知らないが、少なくとも私の周りに数人はいる。
確かにこの方が誤解はない。
「右」「左」はどちらを向いているかによって変わってしまう。
「東」「南」なら絶対的なものだから正確だ。
私が塾で指導中の様子を外から見かけた人に、後日言われた。
「この前東向いて立ってたね?」
...これには面食らった。
塾の中でどっちが東だか、とっさには出てこない。
私は決して方向音痴ではない。
地図を読むのは大好きだし、
カーナビの指示より自分の方向感覚を信じる。
それでも、人との会話に方角を使うことは稀である。
母親(三浦半島出身)から聞いた話だが、
彼女の知り合いに、方角ではなく「太平洋側」「日本海側」を使う人がいたという。
「もう少し太平洋側」とか「そこから3軒日本海側」とか...。
これはこれで、スケールが大きくて気持ちいい。
やはり、海が近くにあるゆえの発想だろうか...。
信州人にとって方角が身近なのも、自然条件と関係があるのか?
四方に山があり、その名前や姿から容易に方角がわかるからだろうか。
農業県ゆえに、また雪国ゆえに、太陽のありがたみを身に浸みて感じ、
その動きに敏感になったからだろうか。
いずれにしても、観光客や出張で来たビジネスマンなど、
地元に詳しくない人には、方角は使わずに説明する方が親切というものだろう。
地図が手元になければ、方角を言われてもさっぱりわからない。
太陽があれば少しは参考になるが...。
方角を知るために、最近ではもっぱらBSアンテナを探している。
それで南西がわかれば何とかなる...。
話は変わるが、方角と言えばイスラム教の信者である。
彼らほど、日々の生活の中で方角を意識している者はいないだろう。
一日5回、メッカの方角を向いて祈りを捧げなければならないのだから、
どこにいようと正確に東西南北を把握している必要がある。
と、ここで考え込んでしまった。
日本から見て「メッカの方角」とはどっちだろう?
見慣れた世界地図で考えて「西」と答えると×である。
「日本から真東に進むと初めに到達する大陸はどこか?」という問に、
ほとんどの中学生は「北アメリカ」と答える。
正解は「南アメリカ」だ。
人間は球面上に住んでいることを忘れてはならない。
日本から真東に進むとチリに着くはずである。
同様に、日本から真西に進むと、
インドを経由してケニア、タンザニア辺りに到達する ことになるだろう。
方角を正確に地図上に表したのが「正距方位図法」である。
これで見るとメッカは日本から西北西というところか...。
今まで真西を向いて祈りを捧げていたイスラム信者の方がいらっっしゃれば、
今日からは少しだけ北寄りに方向を修正することをお勧めする。

ただ、一般的には、方角を聞いてピンとくる人は少ない
私なら、たとえば「郵便局の右」とか「コンビニの向かい」という言い方をする。
それが普通の教え方だと思っていた。
ところが長野では、方角を使う人が多いように感じる。
「郵便局の東」「コンビニの南」という具合に...。
実際はどうか知らないが、少なくとも私の周りに数人はいる。
確かにこの方が誤解はない。
「右」「左」はどちらを向いているかによって変わってしまう。
「東」「南」なら絶対的なものだから正確だ。
私が塾で指導中の様子を外から見かけた人に、後日言われた。
「この前東向いて立ってたね?」
...これには面食らった。
塾の中でどっちが東だか、とっさには出てこない。
私は決して方向音痴ではない。
地図を読むのは大好きだし、
カーナビの指示より自分の方向感覚を信じる。
それでも、人との会話に方角を使うことは稀である。
母親(三浦半島出身)から聞いた話だが、
彼女の知り合いに、方角ではなく「太平洋側」「日本海側」を使う人がいたという。
「もう少し太平洋側」とか「そこから3軒日本海側」とか...。
これはこれで、スケールが大きくて気持ちいい。
やはり、海が近くにあるゆえの発想だろうか...。
信州人にとって方角が身近なのも、自然条件と関係があるのか?
四方に山があり、その名前や姿から容易に方角がわかるからだろうか。
農業県ゆえに、また雪国ゆえに、太陽のありがたみを身に浸みて感じ、
その動きに敏感になったからだろうか。
いずれにしても、観光客や出張で来たビジネスマンなど、
地元に詳しくない人には、方角は使わずに説明する方が親切というものだろう。
地図が手元になければ、方角を言われてもさっぱりわからない。
太陽があれば少しは参考になるが...。
方角を知るために、最近ではもっぱらBSアンテナを探している。
それで南西がわかれば何とかなる...。
話は変わるが、方角と言えばイスラム教の信者である。
彼らほど、日々の生活の中で方角を意識している者はいないだろう。
一日5回、メッカの方角を向いて祈りを捧げなければならないのだから、
どこにいようと正確に東西南北を把握している必要がある。
と、ここで考え込んでしまった。
日本から見て「メッカの方角」とはどっちだろう?
見慣れた世界地図で考えて「西」と答えると×である。
「日本から真東に進むと初めに到達する大陸はどこか?」という問に、
ほとんどの中学生は「北アメリカ」と答える。
正解は「南アメリカ」だ。
人間は球面上に住んでいることを忘れてはならない。
日本から真東に進むとチリに着くはずである。
同様に、日本から真西に進むと、
インドを経由してケニア、タンザニア辺りに到達する ことになるだろう。
方角を正確に地図上に表したのが「正距方位図法」である。
これで見るとメッカは日本から西北西というところか...。
今まで真西を向いて祈りを捧げていたイスラム信者の方がいらっっしゃれば、
今日からは少しだけ北寄りに方向を修正することをお勧めする。

ただ、一般的には、方角を聞いてピンとくる人は少ない
2010年06月27日
田舎の朝は早い
私は典型的な夜型人間だ。
昼間眠くても、夜になると元気になる。
仕事も夜で帰宅するのは11時近くになるので、尚更夜に適応している。
2時頃寝て、9~10時に起きる生活だ。
わが家は町から3km、車なら5分の距離だが、山に挟まれた田舎だ。
高齢化率は高く、どこの家も畑仕事に忙しい。
夏ともなれば5時6時から草刈り機の音が鳴り響き、安眠を妨げる。
3年が過ぎたとは言え、新参者だし、
私のような異色の生活リズムの者は他にいないので、文句も言いづらい。
自然が豊かなのは嬉しいが、地区の役がいろいろあって、
毎年何らかの役が回ってくる。
昔ながらの行事も多く、特に春から夏は何だかんだと駆り出される。
それが朝早いのだ。
いつも決まって5時半である。
以前住んでいた信州新町では、早くても7時だった。
昔からそうなのだろうが、もう少し遅くしようという動きはない。
祭のノボリ立てなどは平日に行われるので、
最近では勤め人の出勤への配慮という面もあるようだ。
夏祭りは御輿をかついで地区内を練り歩き、次の地区へバトンタッチする。
町の中の地区まで一日がかりでそれが続く。
うちの地区は一番上なので、やはり5時半に集まってスタート。
7時には次の地区へ引き渡し、公民館で「なおらい」(慰労会)が始まる。
10時頃にはすっかりできあがってしまい、一日が終わってしまう...。
今朝も5時半から、地区を流れる川の草刈りがあった。
この川、私の家の前でもホタルが出るので、
本当は刈らない方がいいのだろうが...。
せめて時期をずらせないか、来年の総会には提案してみようと思う。
今年はあと3回、5時起きが待っている...。

昼間眠くても、夜になると元気になる。
仕事も夜で帰宅するのは11時近くになるので、尚更夜に適応している。
2時頃寝て、9~10時に起きる生活だ。
わが家は町から3km、車なら5分の距離だが、山に挟まれた田舎だ。
高齢化率は高く、どこの家も畑仕事に忙しい。
夏ともなれば5時6時から草刈り機の音が鳴り響き、安眠を妨げる。
3年が過ぎたとは言え、新参者だし、
私のような異色の生活リズムの者は他にいないので、文句も言いづらい。
自然が豊かなのは嬉しいが、地区の役がいろいろあって、
毎年何らかの役が回ってくる。
昔ながらの行事も多く、特に春から夏は何だかんだと駆り出される。
それが朝早いのだ。
いつも決まって5時半である。
以前住んでいた信州新町では、早くても7時だった。
昔からそうなのだろうが、もう少し遅くしようという動きはない。
祭のノボリ立てなどは平日に行われるので、
最近では勤め人の出勤への配慮という面もあるようだ。
夏祭りは御輿をかついで地区内を練り歩き、次の地区へバトンタッチする。
町の中の地区まで一日がかりでそれが続く。
うちの地区は一番上なので、やはり5時半に集まってスタート。
7時には次の地区へ引き渡し、公民館で「なおらい」(慰労会)が始まる。
10時頃にはすっかりできあがってしまい、一日が終わってしまう...。
今朝も5時半から、地区を流れる川の草刈りがあった。
この川、私の家の前でもホタルが出るので、
本当は刈らない方がいいのだろうが...。
せめて時期をずらせないか、来年の総会には提案してみようと思う。
今年はあと3回、5時起きが待っている...。

2010年06月26日
わかりやすい文を書く~素材13~
問1:次の文を、わかりやすいように書き換えなさい。
いつものように部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、
掃除を始めた。
「いつものように」はどこに係っているのか?
文の内容を考えれば、「散らかっている」を修飾するのは不自然だ。
「(掃除を)始めた」に係っていると考えるべきだろう。
ならば、修飾・被修飾の関係にある2語をできるだけ近づけてやればいい。
部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、
いつものように掃除を始めた。
これですっきりした。
次はどうだろう。
問2:次の文は意味がいくつにも取れます。
それぞれの指示に従って、誤解が生じないよう書き換えなさい。
昨日学校で友達に借りた本を汚してしまった。
①「借りた」時は昨日。場所は学校。「汚した」時、場所は不明。
②「借りた」時は昨日。場所は不明。「汚した」時は不明。場所は学校。
③「借りた」時は不明。場所は学校。「汚した」時は昨日。場所は不明。
④「借りた」時、場所は不明。 「汚した」時は昨日。場所は学校。
読点(「、」)を打つだけではなく、語順を変えて意味が明確に伝わるようにしてください。
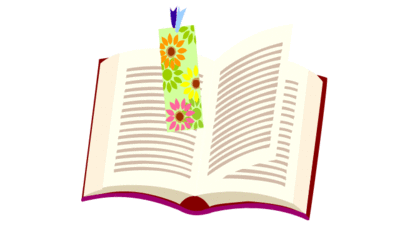
いつものように部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、
掃除を始めた。
「いつものように」はどこに係っているのか?
文の内容を考えれば、「散らかっている」を修飾するのは不自然だ。
「(掃除を)始めた」に係っていると考えるべきだろう。
ならば、修飾・被修飾の関係にある2語をできるだけ近づけてやればいい。
部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、
いつものように掃除を始めた。
これですっきりした。
次はどうだろう。
問2:次の文は意味がいくつにも取れます。
それぞれの指示に従って、誤解が生じないよう書き換えなさい。
昨日学校で友達に借りた本を汚してしまった。
①「借りた」時は昨日。場所は学校。「汚した」時、場所は不明。
②「借りた」時は昨日。場所は不明。「汚した」時は不明。場所は学校。
③「借りた」時は不明。場所は学校。「汚した」時は昨日。場所は不明。
④「借りた」時、場所は不明。 「汚した」時は昨日。場所は学校。
読点(「、」)を打つだけではなく、語順を変えて意味が明確に伝わるようにしてください。
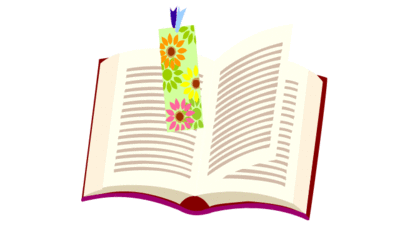
2010年06月25日
スポーツの夏
「スポーツの夏」と言っても、やるわけではない。
もっぱら観戦、しかも on TV が主である。
サッカーW杯日本vsデンマークは、録画しておいて先ほど観た。
起きてからパソコンもつけず、
テレビからDVDへの切り替えも、うかつに情報番組を観ないように慎重に行い、
結果を知らない状態でどきどきしながら観戦。
途中早送りにしたために2点目は入ってから気づいたが、
ほぼライブ感覚で興奮を味わうことができた。
決勝トーナメント進出が決まってめでたし、めでたし...。
今年はW杯があるので尚更だが、
そうでなくても、毎年この時期はスポーツ観戦に忙しい。
CSの「プロ野球セット」に入っているので、阪神の試合はすべて視聴できる。
仕事柄、生で観られるのは土日くらいだが(妻はすべて生観戦)、
勝った試合は録画を夜中にじっくり観る。
ウィンブルドンのテニスも始まった。
男子シングルス1回戦で、とんでもない記録が誕生。
日没コールド2回を挟んで3日間、11時間5分という、史上最長時間の試合だ。
初日に第4セットまで終了。
タイブレイクのない第5セットだけで、足かけ2日かかっている。
決着したときの最終セットのスコアは70-68!!
13-11くらいでも大接戦だと思うのに、なんだこれ...?
総ゲーム数は183。
すべてがラブゲームでも、ポイント数は732である。
実際は1ゲームに平均6ポイントは要しているだろうし、
第3、第4セットがタイブレイクになっているので、
1,000ポイントは軽く超えているだろう。(追記:980ポイントだったそうです。)
選手はもとより、審判、ボールボーイ、観客も疲労困憊だったのではないか。
...それにしてもすごすぎる...。
ウィンブルドンが終わればすぐに、
同じイギリスを舞台にゴルフの全英オープンだ。
自分ではゴルフなどやったことがないが、これにもつい見入ってしまう。
同じ頃に大相撲の名古屋場所も...と言いたいところだが、
これは今年はどうなるかわからない。
困ったものだ...。
7月には高校野球の県予選も始まる。
長男が高校球児だったこともあり、
毎年妻と二人で結構観に行っている。
オリンピック球場が近いのもラッキー!
そうそう、今年はオリスタに阪神が来るのだ。
8月17日の横浜戦。
もちろんチケットは入手してある。
信濃グランセローズも何度か応援に行っているが、あまり勝ってくれない。
また後期も行ってみるか...。
長野パルセイロも調子良さそうだし...。
かくして、プロ野球が終わるまで「暑い夏」は続くのである。

もっぱら観戦、しかも on TV が主である。
サッカーW杯日本vsデンマークは、録画しておいて先ほど観た。
起きてからパソコンもつけず、
テレビからDVDへの切り替えも、うかつに情報番組を観ないように慎重に行い、
結果を知らない状態でどきどきしながら観戦。
途中早送りにしたために2点目は入ってから気づいたが、
ほぼライブ感覚で興奮を味わうことができた。
決勝トーナメント進出が決まってめでたし、めでたし...。
今年はW杯があるので尚更だが、
そうでなくても、毎年この時期はスポーツ観戦に忙しい。
CSの「プロ野球セット」に入っているので、阪神の試合はすべて視聴できる。
仕事柄、生で観られるのは土日くらいだが(妻はすべて生観戦)、
勝った試合は録画を夜中にじっくり観る。
ウィンブルドンのテニスも始まった。
男子シングルス1回戦で、とんでもない記録が誕生。
日没コールド2回を挟んで3日間、11時間5分という、史上最長時間の試合だ。
初日に第4セットまで終了。
タイブレイクのない第5セットだけで、足かけ2日かかっている。
決着したときの最終セットのスコアは70-68!!
13-11くらいでも大接戦だと思うのに、なんだこれ...?
総ゲーム数は183。
すべてがラブゲームでも、ポイント数は732である。
実際は1ゲームに平均6ポイントは要しているだろうし、
第3、第4セットがタイブレイクになっているので、
1,000ポイントは軽く超えているだろう。(追記:980ポイントだったそうです。)
選手はもとより、審判、ボールボーイ、観客も疲労困憊だったのではないか。
...それにしてもすごすぎる...。
ウィンブルドンが終わればすぐに、
同じイギリスを舞台にゴルフの全英オープンだ。
自分ではゴルフなどやったことがないが、これにもつい見入ってしまう。
同じ頃に大相撲の名古屋場所も...と言いたいところだが、
これは今年はどうなるかわからない。
困ったものだ...。
7月には高校野球の県予選も始まる。
長男が高校球児だったこともあり、
毎年妻と二人で結構観に行っている。
オリンピック球場が近いのもラッキー!
そうそう、今年はオリスタに阪神が来るのだ。
8月17日の横浜戦。
もちろんチケットは入手してある。
信濃グランセローズも何度か応援に行っているが、あまり勝ってくれない。
また後期も行ってみるか...。
長野パルセイロも調子良さそうだし...。
かくして、プロ野球が終わるまで「暑い夏」は続くのである。

2010年06月24日
日本語は難しい?
毎日大量に届く迷惑メール...。
タイトルだけで判断して削除しているが、
たまにまともなメールのとの区別がつかず、開封してみるものもある。
その中に面白いのがあったのでご紹介。
中国からの発信のようだ。
ブランド激安 新しい店は開業します
(中略)
新しい店は開業します、 絶対にすばらしいです、 ご愛顧賜ることを歓迎します。
まだ 、送 料 無 料でございます!!
(中略)
本店は次のとおりに特恵の活動をします :
1.商品の総金額は1万円まで達して、10% off!
2.商品の総金額は2万円まで達して、15% off!
(中略)
5.10萬円を上回ってメールに相談してもらいます。
言いたいことはわかるので、かなり日本語を勉強されたのだろう。
ただ、「ご愛顧賜ることを歓迎」「特恵の活動」など、英文を直訳したようなぎこちなさがある。
もしかして翻訳ソフトの日本語か...?
日本では領収証にしか使わない「萬」の字(なぜか10萬円だけ...)も面白い。
「まだ」は「また」の間違いだろうか。
翻訳ソフトを使っているなら、「送料無料期間継続中」という意味合いか...?
最後の文は、「10万円を超える場合はメールでご相談ください」という意味だろう。
「メールに相談」してどうする...。
「は」と「が」の使い分けも含め、
日本語を学ぶ外国人のための上級教材としては格好ではなかろうか。
送信者には、参考書として画像の本をお薦めしたい。

タイトルだけで判断して削除しているが、
たまにまともなメールのとの区別がつかず、開封してみるものもある。
その中に面白いのがあったのでご紹介。
中国からの発信のようだ。
ブランド激安 新しい店は開業します
(中略)
新しい店は開業します、 絶対にすばらしいです、 ご愛顧賜ることを歓迎します。
まだ 、送 料 無 料でございます!!
(中略)
本店は次のとおりに特恵の活動をします :
1.商品の総金額は1万円まで達して、10% off!
2.商品の総金額は2万円まで達して、15% off!
(中略)
5.10萬円を上回ってメールに相談してもらいます。
言いたいことはわかるので、かなり日本語を勉強されたのだろう。
ただ、「ご愛顧賜ることを歓迎」「特恵の活動」など、英文を直訳したようなぎこちなさがある。
もしかして翻訳ソフトの日本語か...?
日本では領収証にしか使わない「萬」の字(なぜか10萬円だけ...)も面白い。
「まだ」は「また」の間違いだろうか。
翻訳ソフトを使っているなら、「送料無料期間継続中」という意味合いか...?
最後の文は、「10万円を超える場合はメールでご相談ください」という意味だろう。
「メールに相談」してどうする...。
「は」と「が」の使い分けも含め、
日本語を学ぶ外国人のための上級教材としては格好ではなかろうか。
送信者には、参考書として画像の本をお薦めしたい。

2010年06月23日
虫を愛でる文化
知らなかった。
アメリカでは虫を飼う習慣はないのだそうだ。
欧米人の耳には秋の虫の声も雑音にしか聞こえない、ということは知っていた。
それでも子どもたちは、日本と同じようにカブトムシやセミを捕まえるのだろうと思っていた。
ところが、アメリカでは虫好きは変わり者扱いされるというのだ。
20日付の朝日新聞「ひと」欄で、
ジェシカ・オーレックという若い女性の話を読んだ。
幼い頃から大の虫好きで、アメリカでは肩身の狭い思いをしていた彼女は、
来日して日本人の「昆虫愛」に感激し、映画まで作ってしまった。
彼女は言う。
日本で虫が愛される理由の根底には「もののあはれ」があると...。
「日本の人々は虫たちのはかない生命に美を感じることができる。
米市民にはその文化がない」
他の国はどうなのだろう。
虫の姿や声に季節の移ろいを感じ取るのは
日本独特の文化なのだろうか...。
古来、短歌や俳句には様々な虫たちが登場してきた。
チョウ、トンボ、セミ、キリギリス...。
ホタルやチョウはときに魂の象徴ともされてきた。
メジャーな昆虫ばかりではない。
一茶を始めとして、ハエ、蚊、ハチやアリなどを詠んだ句や歌は多い。
小さな虫たちへの温かい目が感じられる。
そう言えば、蛾や毛虫まで可愛がるお姫様の話もあった。
堤中納言物語の中の「虫めづる姫君」。
私は高校時代にこれに出会って、古典の魅力に取り憑かれたのだった。
アメリカでは蛾もチョウも「バグ」と一括りで扱うという話も聞いた。
対人間以上に「差別」がない。
それだけ虫に対する関心が薄いということだろう。
あるいは繊細さの問題か...。
もっとも、最近では日本でも、虫を極端に嫌う子どもが少なくない。
夜、小さな羽虫が入ってきただけで、男の子も大騒ぎだ。
チョウを怖がる女の子も珍しくない。
生活様式と共に、日本人の虫に対する意識も、徐々にアメリカナイズされてきたということか...。
夏休みの定番だった昆虫採集も、とんと見かけなくなった。
残酷だとか、自然保護だとかの声に押され、旗色が悪い。
子どもの昆虫採集くらいで破壊されるほど、自然はヤワではないという意見も多いのだが...。
虫を遠ざける背景には、前にも書いた異常な清潔志向もあると思う。
虫は汚い、不潔だ、すぐに捨てなさい...!
こうして虫から遠ざけられた子どもたちは、
はかない命に対する美意識とは無縁に育つ。
本来子どもは残酷なものであり、小さな虫を殺したり、
大切に飼っていたカブトムシを死なせてしまったりという体験を通して
命について学んできたはずだからだ。
一方でホタルを増やしたり、
オオムラサキの棲息地を整備しようという動きも盛んである。
しかし今本当に必要なのは、そういう特別な活動よりも、
身の周りの名もない虫たちとの距離を縮めることだと思う。
虫を愛でる文化、「もののあはれ」を解する心は日本人の宝である。
これを将来に渡って守り続けていくためには、
その伝統を自覚し、誇りを持つことが何より重要であろう。
今年はハルゼミの声を聞かない...。
行水の 捨て所なし 虫の声 (上島鬼貫)

※数年前、庭先に来たオオムラサキである。
アメリカでは虫を飼う習慣はないのだそうだ。
欧米人の耳には秋の虫の声も雑音にしか聞こえない、ということは知っていた。
それでも子どもたちは、日本と同じようにカブトムシやセミを捕まえるのだろうと思っていた。
ところが、アメリカでは虫好きは変わり者扱いされるというのだ。
20日付の朝日新聞「ひと」欄で、
ジェシカ・オーレックという若い女性の話を読んだ。
幼い頃から大の虫好きで、アメリカでは肩身の狭い思いをしていた彼女は、
来日して日本人の「昆虫愛」に感激し、映画まで作ってしまった。
彼女は言う。
日本で虫が愛される理由の根底には「もののあはれ」があると...。
「日本の人々は虫たちのはかない生命に美を感じることができる。
米市民にはその文化がない」
他の国はどうなのだろう。
虫の姿や声に季節の移ろいを感じ取るのは
日本独特の文化なのだろうか...。
古来、短歌や俳句には様々な虫たちが登場してきた。
チョウ、トンボ、セミ、キリギリス...。
ホタルやチョウはときに魂の象徴ともされてきた。
メジャーな昆虫ばかりではない。
一茶を始めとして、ハエ、蚊、ハチやアリなどを詠んだ句や歌は多い。
小さな虫たちへの温かい目が感じられる。
そう言えば、蛾や毛虫まで可愛がるお姫様の話もあった。
堤中納言物語の中の「虫めづる姫君」。
私は高校時代にこれに出会って、古典の魅力に取り憑かれたのだった。
アメリカでは蛾もチョウも「バグ」と一括りで扱うという話も聞いた。
対人間以上に「差別」がない。
それだけ虫に対する関心が薄いということだろう。
あるいは繊細さの問題か...。
もっとも、最近では日本でも、虫を極端に嫌う子どもが少なくない。
夜、小さな羽虫が入ってきただけで、男の子も大騒ぎだ。
チョウを怖がる女の子も珍しくない。
生活様式と共に、日本人の虫に対する意識も、徐々にアメリカナイズされてきたということか...。
夏休みの定番だった昆虫採集も、とんと見かけなくなった。
残酷だとか、自然保護だとかの声に押され、旗色が悪い。
子どもの昆虫採集くらいで破壊されるほど、自然はヤワではないという意見も多いのだが...。
虫を遠ざける背景には、前にも書いた異常な清潔志向もあると思う。
虫は汚い、不潔だ、すぐに捨てなさい...!
こうして虫から遠ざけられた子どもたちは、
はかない命に対する美意識とは無縁に育つ。
本来子どもは残酷なものであり、小さな虫を殺したり、
大切に飼っていたカブトムシを死なせてしまったりという体験を通して
命について学んできたはずだからだ。
一方でホタルを増やしたり、
オオムラサキの棲息地を整備しようという動きも盛んである。
しかし今本当に必要なのは、そういう特別な活動よりも、
身の周りの名もない虫たちとの距離を縮めることだと思う。
虫を愛でる文化、「もののあはれ」を解する心は日本人の宝である。
これを将来に渡って守り続けていくためには、
その伝統を自覚し、誇りを持つことが何より重要であろう。
今年はハルゼミの声を聞かない...。
行水の 捨て所なし 虫の声 (上島鬼貫)

※数年前、庭先に来たオオムラサキである。
2010年06月21日
この言い方は正しいのか?~その8~
久々にツッコミを入れたくなる表現に出会った。
まずは、フジテレビCSの「プロ野球ニュース」から。
6月1日ぶりの出場となった○○
「6月1日以来18日ぶり」と言おうと思ったのが縮まってしまったのだろう。
かなりの違和感であった。
もう一つはYahooのスポーツニュース(スポニチ)から。
例のサッカーW杯、対オランダ戦での、惜しかった場面の記述だ。
(岡崎の蹴った)ボールはクロスバーの上を越えた
「クロスバーを越えた」あるいは「クロスバーの上を通過した」ではなかろうか。
この「上」はクロスバーの「上辺」という意味ではないだろう。
「越える」のは「上辺」に決まっているのだから、わざわざ言及するまでもない。
ということは、「上」はクロスバーの上の空間を指していることになる。
それを「越えた」とは、すなわち、バーのはるか上を通過したことを示すのではないか...。
もしかして、変な表現であることを承知の上で、
「そんなにギリギリじゃなかった」というニュアンスを、暗に伝えているのかも...。
まさかね...。

まずは、フジテレビCSの「プロ野球ニュース」から。
6月1日ぶりの出場となった○○
「6月1日以来18日ぶり」と言おうと思ったのが縮まってしまったのだろう。
かなりの違和感であった。
もう一つはYahooのスポーツニュース(スポニチ)から。
例のサッカーW杯、対オランダ戦での、惜しかった場面の記述だ。
(岡崎の蹴った)ボールはクロスバーの上を越えた
「クロスバーを越えた」あるいは「クロスバーの上を通過した」ではなかろうか。
この「上」はクロスバーの「上辺」という意味ではないだろう。
「越える」のは「上辺」に決まっているのだから、わざわざ言及するまでもない。
ということは、「上」はクロスバーの上の空間を指していることになる。
それを「越えた」とは、すなわち、バーのはるか上を通過したことを示すのではないか...。
もしかして、変な表現であることを承知の上で、
「そんなにギリギリじゃなかった」というニュアンスを、暗に伝えているのかも...。
まさかね...。

2010年06月20日
コン・コン...
今日は軽~くことば遊び。
ここに出てくる「コン」はどれも英語を省略したものですが、
元の英語はすべて異なります。
正しく復元できますか?
今日も暑いが、どうもエアコンの調子が悪い。
リモコンを押してもなかなかONにならない。
私はお気に入りのボディコンを身につけ、
パソコンでツアコンの資格を取得する勉強をしていた。
合コンで知り合ったマザコンの彼は、
学生時代にロボコンに出たことがあるそうだ。
ゼネコンへの就職の夢叶わず、
今はミキサー車で生コンを運んでいる。
バリコン(バリアブルコンデンサー)なんてのもありますが、
あまり一般的ではないので入れませんでした。
野球のノーコン(ノーコントロール)は、
リモコンやラジコンの「コン」と大差ないので却下。
メニコン(眼にコンタクト?)は商品名なので反則かな...。
他にご存知の「コン」ありますか?

ここに出てくる「コン」はどれも英語を省略したものですが、
元の英語はすべて異なります。
正しく復元できますか?
今日も暑いが、どうもエアコンの調子が悪い。
リモコンを押してもなかなかONにならない。
私はお気に入りのボディコンを身につけ、
パソコンでツアコンの資格を取得する勉強をしていた。
合コンで知り合ったマザコンの彼は、
学生時代にロボコンに出たことがあるそうだ。
ゼネコンへの就職の夢叶わず、
今はミキサー車で生コンを運んでいる。
バリコン(バリアブルコンデンサー)なんてのもありますが、
あまり一般的ではないので入れませんでした。
野球のノーコン(ノーコントロール)は、
リモコンやラジコンの「コン」と大差ないので却下。
メニコン(眼にコンタクト?)は商品名なので反則かな...。
他にご存知の「コン」ありますか?
2010年06月19日
健康に「だけ」は気をつけて!
新解さん(新明解国語辞典)で「だけ」を引くとこう書いてある。
①その程度を持って限度とすることを示す。
「いい--取りなさい・やれる--やろう」
②その事柄が許容される限度であることを表す。
「これ--は確かだ・君に--話す・二人--でやろう」
③やった・(思った)事に応じて、その結果が十分なものであることを表す。
「わざわざ行った--のことはあった・がんばった--あって成績が上がった・
練習すればする--進歩する」
①②はともに限度を表している。
英語ならonly,just、場合によってはat least,as much asと言ったところか...。
③の使い方は少々変わっている。
英訳する場合も、個々の事例によって様々な表現が必要になるだろう。
言葉の違いに敏感になってもらおうと作った教材がある。
複数の文で、ニュアンスがどう異なるかを書かせるものだ。
簡単な例を挙げよう。
1.歩いて10分かかる。
2.歩いて10分もかかる。
3.歩いて10分しかかからない。
客観的な事実を述べているだけの1と比べて、2や3には話者の主観が入っている。
それを説明させようというわけだ。
その中にこんな問題を入れた。
1.健康には気をつけてね。
2.健康にだけは気をつけてね。
「2は、他のことは気をつけなくていいと言っている」と書いてくる生徒がいる。
そうだろうか...。
新解さんの用例にある「これだけは確かだ」なら、他のことは確かでないという意味が含まれよう。
しかし、2の「だけ」にonlyやjustのニュアンスは感じられない。
私には、1と比べて2の方が、相手への思いやりが強いように取れるのだ。
他のことに気をつけるのはもちろんだが、
中でも健康に最大限の注意を払ってほしいというメッセージが感じられないだろうか。
英語にするならespeciallyだ。
あるいは最上級を使うか...。
こんな「だけ」の使い方、他にあるだろうか?
辞書にもぜひ言及してほしい言い方なのだが...。

①その程度を持って限度とすることを示す。
「いい--取りなさい・やれる--やろう」
②その事柄が許容される限度であることを表す。
「これ--は確かだ・君に--話す・二人--でやろう」
③やった・(思った)事に応じて、その結果が十分なものであることを表す。
「わざわざ行った--のことはあった・がんばった--あって成績が上がった・
練習すればする--進歩する」
①②はともに限度を表している。
英語ならonly,just、場合によってはat least,as much asと言ったところか...。
③の使い方は少々変わっている。
英訳する場合も、個々の事例によって様々な表現が必要になるだろう。
言葉の違いに敏感になってもらおうと作った教材がある。
複数の文で、ニュアンスがどう異なるかを書かせるものだ。
簡単な例を挙げよう。
1.歩いて10分かかる。
2.歩いて10分もかかる。
3.歩いて10分しかかからない。
客観的な事実を述べているだけの1と比べて、2や3には話者の主観が入っている。
それを説明させようというわけだ。
その中にこんな問題を入れた。
1.健康には気をつけてね。
2.健康にだけは気をつけてね。
「2は、他のことは気をつけなくていいと言っている」と書いてくる生徒がいる。
そうだろうか...。
新解さんの用例にある「これだけは確かだ」なら、他のことは確かでないという意味が含まれよう。
しかし、2の「だけ」にonlyやjustのニュアンスは感じられない。
私には、1と比べて2の方が、相手への思いやりが強いように取れるのだ。
他のことに気をつけるのはもちろんだが、
中でも健康に最大限の注意を払ってほしいというメッセージが感じられないだろうか。
英語にするならespeciallyだ。
あるいは最上級を使うか...。
こんな「だけ」の使い方、他にあるだろうか?
辞書にもぜひ言及してほしい言い方なのだが...。

2010年06月18日
宴もたけなわ
「宴もたけなわではございますが...」
幹事からこの言葉が発せられたら、そろそろお開きにしたいのだと推測できる。
盛り上がっているときに水を差すようなことを言うのは無粋だという声も出そうだが、
実際には皆そろそろ潮時と思っている頃合いのことが多い。
「宴もたけなわ」はお決まりの、美辞麗句的なものだと思って来た。
ところが、そうでもないようなのである。
「たけなわ」は漢字では「酣」もしくは「闌」と書く。
語源は「宴(うたげ)なかば」あるいは「長(た)ける+成る」であるという。
辞書を引いてみると、
「物事の最も盛んな時」「行事・季節などが最も盛んになった時」といった説明が第一義である。
これしか載っていない辞書もある。
私が持っているイメージも同じであった。
だが、二つ目として、微妙にニュアンスの異なるこんな定義も載せているものが多い。
「さかりを少し過ぎておとろえかけた時」
「盛りが極まって、それ以後は衰えに向かう時」
直感としては、こちらの方が元々の意味だったのではないかと思う。
「旺文社国語辞典」では「酣」は「酒宴の最中」、
「闌」は「酒宴や物事の半分を過ぎたこと」と区別している。
上りつめればあとは落ちていくだけだ。
満開を過ぎれば、あっという間に花は散る。
絶好調の後には不調の時期が来る。
人生楽ありゃ苦もあるさ...ちょっと違うか...。
諸行無常、盛者必衰の理を知り尽くした上で、
だからこそ盛りを少し過ぎたところに美しさや趣、「もののあはれ」を感じる...。
そんなニュアンスのこもった素敵な言葉だと思う。
「花の色はうつりにけりな...」の歌も彷彿とさせるような...。
「新解さん」(新明解国語辞典)による「たけなわ」の説明には、その無常観が最も現れている。
括弧の中に注目。
「(比較的短い期間しか続かない状態について)ピーク時の称」
楽しい時間はそう長くは続かないことを、みんなわかっているのだ。
祭が終われば、また厳しい現実が待っている。
楽しくも切ないひとときが「たけなわ」なのである。
してみると、冒頭の「宴もたけなわ」も少し捉え方が違ってくる。
ピークをやや過ぎたことを的確に判断した、機微をわかった発言ということになる。
ただ、それなら、「宴もたけなわでございますので...」とするべきだろう。
今度使ってみようか...。

幹事からこの言葉が発せられたら、そろそろお開きにしたいのだと推測できる。
盛り上がっているときに水を差すようなことを言うのは無粋だという声も出そうだが、
実際には皆そろそろ潮時と思っている頃合いのことが多い。
「宴もたけなわ」はお決まりの、美辞麗句的なものだと思って来た。
ところが、そうでもないようなのである。
「たけなわ」は漢字では「酣」もしくは「闌」と書く。
語源は「宴(うたげ)なかば」あるいは「長(た)ける+成る」であるという。
辞書を引いてみると、
「物事の最も盛んな時」「行事・季節などが最も盛んになった時」といった説明が第一義である。
これしか載っていない辞書もある。
私が持っているイメージも同じであった。
だが、二つ目として、微妙にニュアンスの異なるこんな定義も載せているものが多い。
「さかりを少し過ぎておとろえかけた時」
「盛りが極まって、それ以後は衰えに向かう時」
直感としては、こちらの方が元々の意味だったのではないかと思う。
「旺文社国語辞典」では「酣」は「酒宴の最中」、
「闌」は「酒宴や物事の半分を過ぎたこと」と区別している。
上りつめればあとは落ちていくだけだ。
満開を過ぎれば、あっという間に花は散る。
絶好調の後には不調の時期が来る。
人生楽ありゃ苦もあるさ...ちょっと違うか...。
諸行無常、盛者必衰の理を知り尽くした上で、
だからこそ盛りを少し過ぎたところに美しさや趣、「もののあはれ」を感じる...。
そんなニュアンスのこもった素敵な言葉だと思う。
「花の色はうつりにけりな...」の歌も彷彿とさせるような...。
「新解さん」(新明解国語辞典)による「たけなわ」の説明には、その無常観が最も現れている。
括弧の中に注目。
「(比較的短い期間しか続かない状態について)ピーク時の称」
楽しい時間はそう長くは続かないことを、みんなわかっているのだ。
祭が終われば、また厳しい現実が待っている。
楽しくも切ないひとときが「たけなわ」なのである。
してみると、冒頭の「宴もたけなわ」も少し捉え方が違ってくる。
ピークをやや過ぎたことを的確に判断した、機微をわかった発言ということになる。
ただ、それなら、「宴もたけなわでございますので...」とするべきだろう。
今度使ってみようか...。

2010年06月17日
「大人もハマる」だと?!
携帯電話で遊べる無料ゲームのCMがかまびすしい。
中でも最近多いのが、対戦型と呼ばれるものだ。
相手と戦って宝物を奪ったり、領土を奪って「天下統一」を目指したりするようだ。
見知らぬ参加者と仲間になって、敵と戦う場合もあるらしい。
隙をついて宝を盗み取るという、低俗な(?)ゲームのCMをよく目にする。
登場するの社会人ばかりで、
奪い取るときのスリルがどうとか、成功したときの快感がなんとか言っている。
そこにナレーションで「大人もハマる...」。
バッカじゃなかろうか...。
いい大人が何をやっているのか!
他にやることはいくらでもあるだろうに...。
そんなに暇なら新聞を読め!読書に浸れ!!
どうしてもやりたいなら、もっと頭を使うゲームをやれ!
「息抜き」と称す者もあるだろうが、
携帯の小さな画面に夢中になって、ピコピコやっている(音はしないのか?)姿は異様である。
何もしないでボンヤリしている方がよほどマシだ。
その方が頭も心もリフレッシュできると思うのだが...。
ゲームもマンガも、一つの文化として認められつつあるが、
私はそこまでの価値を認めていない。
今どき、時代遅れな意見であろうが...。
マンガには確かに読み応えのあるものも存在するが、
だからと言って、マンガすべてを容認する気にはなれない。
スーツでびしっと決めたビジネスマンが、
何の臆するところもなく、堂々と少年マンガ誌を読みふけっている光景は嘆かわしい。
子どもが対象だから「少年○○」なのである。
青年や壮年には、他に読むべきものがいくらでもあるはずだ。
ゲームやマンガの隆盛は、日本人の幼児化を世界にPRしているようなものだ。
CMの内容はもちろん誇張されたものだろうが、
身近に同様の人たちがいても、全く不自然でないと思えるところが恐ろしい。
こんな国は日本だけではないのか...。
大人としてのプライドとか品格とか教養とか...。
そんなことについて、じっくり考えてみるべき時代ではないだろうか。
怪盗ごっこにハマっている場合ではない...。

中でも最近多いのが、対戦型と呼ばれるものだ。
相手と戦って宝物を奪ったり、領土を奪って「天下統一」を目指したりするようだ。
見知らぬ参加者と仲間になって、敵と戦う場合もあるらしい。
隙をついて宝を盗み取るという、低俗な(?)ゲームのCMをよく目にする。
登場するの社会人ばかりで、
奪い取るときのスリルがどうとか、成功したときの快感がなんとか言っている。
そこにナレーションで「大人もハマる...」。
バッカじゃなかろうか...。
いい大人が何をやっているのか!
他にやることはいくらでもあるだろうに...。
そんなに暇なら新聞を読め!読書に浸れ!!
どうしてもやりたいなら、もっと頭を使うゲームをやれ!
「息抜き」と称す者もあるだろうが、
携帯の小さな画面に夢中になって、ピコピコやっている(音はしないのか?)姿は異様である。
何もしないでボンヤリしている方がよほどマシだ。
その方が頭も心もリフレッシュできると思うのだが...。
ゲームもマンガも、一つの文化として認められつつあるが、
私はそこまでの価値を認めていない。
今どき、時代遅れな意見であろうが...。
マンガには確かに読み応えのあるものも存在するが、
だからと言って、マンガすべてを容認する気にはなれない。
スーツでびしっと決めたビジネスマンが、
何の臆するところもなく、堂々と少年マンガ誌を読みふけっている光景は嘆かわしい。
子どもが対象だから「少年○○」なのである。
青年や壮年には、他に読むべきものがいくらでもあるはずだ。
ゲームやマンガの隆盛は、日本人の幼児化を世界にPRしているようなものだ。
CMの内容はもちろん誇張されたものだろうが、
身近に同様の人たちがいても、全く不自然でないと思えるところが恐ろしい。
こんな国は日本だけではないのか...。
大人としてのプライドとか品格とか教養とか...。
そんなことについて、じっくり考えてみるべき時代ではないだろうか。
怪盗ごっこにハマっている場合ではない...。

2010年06月16日
「物心」はついたか?
「物心がつく」という言葉がある。
これはいったい何歳くらいからだろう?
もちろん個人差はあるだろうが、私は一般的に3、4歳だと思っていた。
ところが、小学校中学年とか、高学年という意見もある。
辞書では、「物心」はこんな定義になっている。
「人情・世態などを理解する力」(広辞苑)
「人情・世態についての知識」(新明解)
「人情や世の中のことがわかる心」(旺文社国語辞典)
「世の中の物事や人間の感情などについて理解できる心。分別」(大辞泉)
「世の中の物事や人情について、おぼろげながら理解・判断できる心」(大辞林)
広辞苑は味も素っ気もない。
期待した「新解さん」も大差なし。
「心」を「力」や「知識」と定義しているところが異色ではある。
他も似たようなものだが、大辞林の「おぼろげながら」は評価したい。
これがないと、かなり大人になってからでないと、「物心」がつかなくなってしまう。
大辞泉に至っては「分別」だ。
今の日本、成人になっても老人でも、分別のない輩がどれだけいることか...。
「物心がつく」を別に採り上げて説明しているのは2つだけだ。
「幼児期を過ぎて、世の中のいろいろなことがなんとなくわかり始める」(大辞泉)
「いろいろなこと」「なんとなく」という曖昧さがいい。
そもそも、「わかる」「理解する」という表現に幅がありすぎるのだ。
そして「新解さん」。
「子供が、世の中の裏表や、デリケートな人間関係、人の気持などについてわかり始める」(新明解)
う~ん。...「世の中の裏表や、デリケートな人間関係」...。
これはハードルが高い。
五十を過ぎた私は、はたして「物心」がついているだろうか...。
それはともかく、こう見てくると、
一般的な「物心がつく」の使用例と、辞書の定義が合っていないように思う。
よく目にするのは次のような使い方だろう。
物心がついてから、飛行機に乗ったことはない。
まだ物心がつかないうちに、家は人手に渡った。
両方とも、世の中のことがわかるかどうかより、
そのことを覚えているかどうか、記憶にあるか否かに力点が置かれているのではないか。
少なくとも私は、そういう観点からこの言葉を理解してきた。
ところが辞書にはそんな定義は一切ない。
いろいろ調べていたらYahooの辞書サイトでこんな例を見つけた。
和英辞典の英訳例である。
「物心がつくようになってからずっと」→ ever since I can remember
(プログレッシブ和英辞典)
これが私の感覚に一番近い。
国語辞典も、「物心」は別にして、「物心がつく」の定義には一考の余地があると考える。

これはいったい何歳くらいからだろう?
もちろん個人差はあるだろうが、私は一般的に3、4歳だと思っていた。
ところが、小学校中学年とか、高学年という意見もある。
辞書では、「物心」はこんな定義になっている。
「人情・世態などを理解する力」(広辞苑)
「人情・世態についての知識」(新明解)
「人情や世の中のことがわかる心」(旺文社国語辞典)
「世の中の物事や人間の感情などについて理解できる心。分別」(大辞泉)
「世の中の物事や人情について、おぼろげながら理解・判断できる心」(大辞林)
広辞苑は味も素っ気もない。
期待した「新解さん」も大差なし。
「心」を「力」や「知識」と定義しているところが異色ではある。
他も似たようなものだが、大辞林の「おぼろげながら」は評価したい。
これがないと、かなり大人になってからでないと、「物心」がつかなくなってしまう。
大辞泉に至っては「分別」だ。
今の日本、成人になっても老人でも、分別のない輩がどれだけいることか...。
「物心がつく」を別に採り上げて説明しているのは2つだけだ。
「幼児期を過ぎて、世の中のいろいろなことがなんとなくわかり始める」(大辞泉)
「いろいろなこと」「なんとなく」という曖昧さがいい。
そもそも、「わかる」「理解する」という表現に幅がありすぎるのだ。
そして「新解さん」。
「子供が、世の中の裏表や、デリケートな人間関係、人の気持などについてわかり始める」(新明解)
う~ん。...「世の中の裏表や、デリケートな人間関係」...。
これはハードルが高い。
五十を過ぎた私は、はたして「物心」がついているだろうか...。
それはともかく、こう見てくると、
一般的な「物心がつく」の使用例と、辞書の定義が合っていないように思う。
よく目にするのは次のような使い方だろう。
物心がついてから、飛行機に乗ったことはない。
まだ物心がつかないうちに、家は人手に渡った。
両方とも、世の中のことがわかるかどうかより、
そのことを覚えているかどうか、記憶にあるか否かに力点が置かれているのではないか。
少なくとも私は、そういう観点からこの言葉を理解してきた。
ところが辞書にはそんな定義は一切ない。
いろいろ調べていたらYahooの辞書サイトでこんな例を見つけた。
和英辞典の英訳例である。
「物心がつくようになってからずっと」→ ever since I can remember
(プログレッシブ和英辞典)
これが私の感覚に一番近い。
国語辞典も、「物心」は別にして、「物心がつく」の定義には一考の余地があると考える。

2010年06月15日
文のイロハ
文章がうまくなるためには、当然のことながら、その一歩前が大切だ。
すなわち一つ一つの文がしっかりしていなくてはならない。
別に名言や名文である必要はない。
日本語として正しい文、読む者に誤解を与えない文であればいいのだ。
細かいことを言えばキリがない。
主述の対応、修飾部の扱い、言葉の選び方、文末表現などなど...。
しかし、文の第一歩は何と言っても句読点の扱いだろう。
小学校低学年以外は句点(。)は心配ないので、主に読点(、)の使い方になる。
と思っていたら、5月から入塾した中3生が「。」のない文を書く。
「、」もないので、どこで切ったらいいか、こちらが判断しなくてはならない。
今までずっとこれで通してきたのだろう。
当然のように、英文にもピリオドがない...。
数感覚は優れたものを持っているのだが、言語力に大きな問題がある。
漢字や送り仮名の間違いも多いし、何が言いたいのかわからない文章を書く。
そこで彼には、算数や数学の解法を文で説明する、という課題を多くさせている。
自分の考えや思いを言葉にする、その難しさを痛感しているようだ。
本題に戻る。
読点の打ち方に厳密な決まりはない。
読み手のことを考えて打てばいい。
読みやすいこと、誤解を生まないことが基本だ。
少なすぎくても、多すぎてもいけない。
生徒に読点の役割の重要性を説くとき、よく例に挙げるのがこんな文だ。
①昨日、父と母の墓参りに行った。
②昨日父と、母の墓参りに行った。
①では両親とも亡くなっているが、②では父親は健在であることがわかる。
英語なら主語や修飾関係が変わってくるので問題ないが、
日本語では、読点を打ち間違えると大変なことになる。
自分自身の文については、少々読点を多用しすぎではないかと分析している。
特にブログでは、つい読みやすさを優先して、多くの「、」を付けてしまう...。
先日、自治会の規約をwordで打ち直す作業に携わった。
主語の後に必ず読点が入るのが煩わしく、一部勝手に削ってしまった所もある。
憲法を初めとして、法律や規約にはこういう書き方が多い。
とにかく誤解のないように、正確さを追求した結果であろうが、
あまりに機械的な読点の打ち方もどうかと思う。
英語ならよほどの意図がない限り、主語の後に「,」など打たないのではないか...。

すなわち一つ一つの文がしっかりしていなくてはならない。
別に名言や名文である必要はない。
日本語として正しい文、読む者に誤解を与えない文であればいいのだ。
細かいことを言えばキリがない。
主述の対応、修飾部の扱い、言葉の選び方、文末表現などなど...。
しかし、文の第一歩は何と言っても句読点の扱いだろう。
小学校低学年以外は句点(。)は心配ないので、主に読点(、)の使い方になる。
と思っていたら、5月から入塾した中3生が「。」のない文を書く。
「、」もないので、どこで切ったらいいか、こちらが判断しなくてはならない。
今までずっとこれで通してきたのだろう。
当然のように、英文にもピリオドがない...。
数感覚は優れたものを持っているのだが、言語力に大きな問題がある。
漢字や送り仮名の間違いも多いし、何が言いたいのかわからない文章を書く。
そこで彼には、算数や数学の解法を文で説明する、という課題を多くさせている。
自分の考えや思いを言葉にする、その難しさを痛感しているようだ。
本題に戻る。
読点の打ち方に厳密な決まりはない。
読み手のことを考えて打てばいい。
読みやすいこと、誤解を生まないことが基本だ。
少なすぎくても、多すぎてもいけない。
生徒に読点の役割の重要性を説くとき、よく例に挙げるのがこんな文だ。
①昨日、父と母の墓参りに行った。
②昨日父と、母の墓参りに行った。
①では両親とも亡くなっているが、②では父親は健在であることがわかる。
英語なら主語や修飾関係が変わってくるので問題ないが、
日本語では、読点を打ち間違えると大変なことになる。
自分自身の文については、少々読点を多用しすぎではないかと分析している。
特にブログでは、つい読みやすさを優先して、多くの「、」を付けてしまう...。
先日、自治会の規約をwordで打ち直す作業に携わった。
主語の後に必ず読点が入るのが煩わしく、一部勝手に削ってしまった所もある。
憲法を初めとして、法律や規約にはこういう書き方が多い。
とにかく誤解のないように、正確さを追求した結果であろうが、
あまりに機械的な読点の打ち方もどうかと思う。
英語ならよほどの意図がない限り、主語の後に「,」など打たないのではないか...。

2010年06月14日
頭の柔らかさ~素材12~
数学の小問集にこんな問題がある。
中学生用とは言え、小学生レベルの算数の問題だ。
問:斜線を引いた三角形の面積を求めなさい。

解答集には次のような模範解答が載っている。
4×4=16
4×2×1/2×2=8
2×2×1/2=2
16-(8+2)=6
要するに、三角形を囲む正方形の面積から、周りの3つの三角形の面積を引くわけだ。
実際、ほとんどの子がこの方法で出している。
ところが、ときどきユニークな方法で正解を導き出す子がいるのだ。
先日も中3の女の子が、
かなり長時間悩んだ挙げ句正解したのだが、
こんな式を書いている。
4+2=6
後の「2」はわかる。
右上の小さな三角形の面積だろう。
しかし「4」が何だかわからない...。
どう考えたのか、さんざん説明を聞いてわかった。
下図の青い部分を赤い部分に移して、2×2の正方形にしていたのだ!
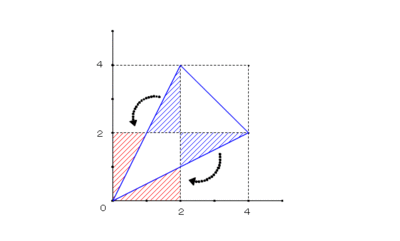
なるほど...うまいやり方を考えたものだ。
中学入試などでよく使われるテクニックだが、もちろん彼女はそんなことは知らない。
自分で考え出した解法である。
こういう頭の柔らかさはどこから来るのか?
ときどき考えてみる。
今回の子もそうだが、ユニークな発想を見せてくれるのは女子が多い。
しかも、決して数学が得意とは言えない子が多いのだ。
数学ができる子は、楽々正解するが、解き方は模範解答どおりの平凡なものだ。
ある意味画一的でつまらない..。
教わったことは正確にできるけれど、
初めて見た問題、今までのやり方が通用しない問題には固まってしまう。
前にも書いたが、なまじ知識や技量があるために、
新たな発想や工夫ができないということがあるのではないか。
何でも方程式に頼って、かえって難しくしてしまう子がいる。
図やグラフで考えれば一目瞭然なのに、
計算にこだわってミスをする子もいる。
幅広く考えられる力をつけるために、
受験生にはときどき算数の難問を解かせている。
中学数学の使用は厳禁であり、解答に至る道筋を言葉で説明させる。
冒頭の問題の別解を考えさせる、というのもここに組み入れていきたいと考えている。
中学生用とは言え、小学生レベルの算数の問題だ。
問:斜線を引いた三角形の面積を求めなさい。

解答集には次のような模範解答が載っている。
4×4=16
4×2×1/2×2=8
2×2×1/2=2
16-(8+2)=6
要するに、三角形を囲む正方形の面積から、周りの3つの三角形の面積を引くわけだ。
実際、ほとんどの子がこの方法で出している。
ところが、ときどきユニークな方法で正解を導き出す子がいるのだ。
先日も中3の女の子が、
かなり長時間悩んだ挙げ句正解したのだが、
こんな式を書いている。
4+2=6
後の「2」はわかる。
右上の小さな三角形の面積だろう。
しかし「4」が何だかわからない...。
どう考えたのか、さんざん説明を聞いてわかった。
下図の青い部分を赤い部分に移して、2×2の正方形にしていたのだ!
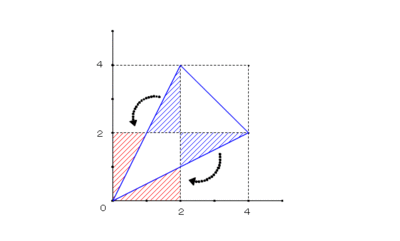
なるほど...うまいやり方を考えたものだ。
中学入試などでよく使われるテクニックだが、もちろん彼女はそんなことは知らない。
自分で考え出した解法である。
こういう頭の柔らかさはどこから来るのか?
ときどき考えてみる。
今回の子もそうだが、ユニークな発想を見せてくれるのは女子が多い。
しかも、決して数学が得意とは言えない子が多いのだ。
数学ができる子は、楽々正解するが、解き方は模範解答どおりの平凡なものだ。
ある意味画一的でつまらない..。
教わったことは正確にできるけれど、
初めて見た問題、今までのやり方が通用しない問題には固まってしまう。
前にも書いたが、なまじ知識や技量があるために、
新たな発想や工夫ができないということがあるのではないか。
何でも方程式に頼って、かえって難しくしてしまう子がいる。
図やグラフで考えれば一目瞭然なのに、
計算にこだわってミスをする子もいる。
幅広く考えられる力をつけるために、
受験生にはときどき算数の難問を解かせている。
中学数学の使用は厳禁であり、解答に至る道筋を言葉で説明させる。
冒頭の問題の別解を考えさせる、というのもここに組み入れていきたいと考えている。
2010年06月13日
くたばれ清潔志向!
屋内の砂場が人気だそうだ。
ショッピングセンター内にある有料施設で、
砂には抗菌処理を施し、備長炭も敷いてあるという。
犬や猫の糞もなく安心とのこと。
こんな砂場で遊んで楽しいのか?
服を汚したり、耳に砂が入ったり、
雨の後にはベチャベチャになりながら団子を作ったり...。
それが砂遊びというものではないのか...。
東京ドームを思い出してしまった。
阪神戦を観に何度も行ったが、あの息苦しさには閉口する。
2階席から見るとまさに「箱庭」(もしくは野球盤)で、
簡単にホームランが出るのも納得だ。
一度だけ行った甲子園球場とは雲泥の差である。
あの広さ、開放感、夜空に上がる白球の美しさ...。
野球を観に来ているとうだけで幸せになれる球場だった。
雨や風、気温に左右されないのがドーム球場の長所だが、
それらの要素も含めて戦うのが野球の醍醐味であろう。
そもそも「野」ではないのだから、あれは別の競技である。
人工的な要素が増えるほど、管理されればされるほど、
「快適さ」と引き替えに楽しさ、面白さは減少する。
子どもの遊びも、スポーツも同じである。
だいたい、何から何まで「抗菌」なのは異常ではないか?
抗菌仕様にさえしておけば売れるということか...。
消費者の側が本当にそれを求めているのか、
うまく踊らされているだけなのか...。
手洗いやうがいが無意味だとは言わないが、
あまりにも神経質になりすぎているのではないか?
清潔に、清潔に...汚いものは遠ざけて...と、
子どもを「隔離」していたのでは免疫はできない。
ちょっとした発熱や下痢を繰り返すことで、子どもは逞しくなっていくのだ。
アレルギーやアトピー体質の増加も、
過剰な清潔志向と無縁ではないだろう。
今の日本は、抵抗力の弱い、ひ弱な子どもを育てることに懸命になっているようだ。共用のスリッパなど履けない、小さな虫一つに男の子まで大騒ぎする...。
砂場に犬猫の糞などあってはとんでもない、という発想になるのもむべなるかなである。
日本人は退化していくしかないのか...。

ショッピングセンター内にある有料施設で、
砂には抗菌処理を施し、備長炭も敷いてあるという。
犬や猫の糞もなく安心とのこと。
こんな砂場で遊んで楽しいのか?
服を汚したり、耳に砂が入ったり、
雨の後にはベチャベチャになりながら団子を作ったり...。
それが砂遊びというものではないのか...。
東京ドームを思い出してしまった。
阪神戦を観に何度も行ったが、あの息苦しさには閉口する。
2階席から見るとまさに「箱庭」(もしくは野球盤)で、
簡単にホームランが出るのも納得だ。
一度だけ行った甲子園球場とは雲泥の差である。
あの広さ、開放感、夜空に上がる白球の美しさ...。
野球を観に来ているとうだけで幸せになれる球場だった。
雨や風、気温に左右されないのがドーム球場の長所だが、
それらの要素も含めて戦うのが野球の醍醐味であろう。
そもそも「野」ではないのだから、あれは別の競技である。
人工的な要素が増えるほど、管理されればされるほど、
「快適さ」と引き替えに楽しさ、面白さは減少する。
子どもの遊びも、スポーツも同じである。
だいたい、何から何まで「抗菌」なのは異常ではないか?
抗菌仕様にさえしておけば売れるということか...。
消費者の側が本当にそれを求めているのか、
うまく踊らされているだけなのか...。
手洗いやうがいが無意味だとは言わないが、
あまりにも神経質になりすぎているのではないか?
清潔に、清潔に...汚いものは遠ざけて...と、
子どもを「隔離」していたのでは免疫はできない。
ちょっとした発熱や下痢を繰り返すことで、子どもは逞しくなっていくのだ。
アレルギーやアトピー体質の増加も、
過剰な清潔志向と無縁ではないだろう。
今の日本は、抵抗力の弱い、ひ弱な子どもを育てることに懸命になっているようだ。共用のスリッパなど履けない、小さな虫一つに男の子まで大騒ぎする...。
砂場に犬猫の糞などあってはとんでもない、という発想になるのもむべなるかなである。
日本人は退化していくしかないのか...。

2010年06月12日
ウルトラマンは超メタボ
ウルトラマンの身長は40m、体重は3万5千トンということになっている。
ゴジラは身長40m、体重2万トンでちょっと細身だ。
だいたいこのあたりが相場なのだろう。
小学生の頃、怪獣映画をよく観ていたときには、そんなものかと思って気にも留めなかった。
しかし、今になって改めて考えてみると、
ずいぶんいい加減な設定であったことがわかる。
ウルトラマンで検討してみよう。
平均的な成人男性の身長を170cm、体重を70kgと仮定して比較する。
身長は40÷1.7で約23.5倍である。
3次元の話だから、高さが23.5倍になれば、幅も奥行きも23.5倍にならなければ釣り合いが取れない。
従って体積は23.5の3乗で約13,000倍になる。
当然体重もそうなるので、70を13,000倍して、910トンが適正体重という計算になる。
ところが上述のように、ウルトラマンの体重は3万5千トンである。
実に38.5倍の重さだ!
身長170cmなら2,700kgの体重ということになる。
...とんでもない肥満である。
たぶん体を形作っている素材が、人間とは比べものにならないくらい重いのだろう。
だからあんなにスラッとしているのだ。
それにしても、それだけの重さの体で激しい戦いを繰り広げるわけだ。
無重力の宇宙ならともかく、
地球上では重力に打ち勝って体を支えるだけでも大変ではないか...。
でも、だからこそウルトラマンなのだ!
人間が及びも付かぬパワーを持っているに違いない。
恐るべし、M78星雲である...。

ゴジラは身長40m、体重2万トンでちょっと細身だ。
だいたいこのあたりが相場なのだろう。
小学生の頃、怪獣映画をよく観ていたときには、そんなものかと思って気にも留めなかった。
しかし、今になって改めて考えてみると、
ずいぶんいい加減な設定であったことがわかる。
ウルトラマンで検討してみよう。
平均的な成人男性の身長を170cm、体重を70kgと仮定して比較する。
身長は40÷1.7で約23.5倍である。
3次元の話だから、高さが23.5倍になれば、幅も奥行きも23.5倍にならなければ釣り合いが取れない。
従って体積は23.5の3乗で約13,000倍になる。
当然体重もそうなるので、70を13,000倍して、910トンが適正体重という計算になる。
ところが上述のように、ウルトラマンの体重は3万5千トンである。
実に38.5倍の重さだ!
身長170cmなら2,700kgの体重ということになる。
...とんでもない肥満である。
たぶん体を形作っている素材が、人間とは比べものにならないくらい重いのだろう。
だからあんなにスラッとしているのだ。
それにしても、それだけの重さの体で激しい戦いを繰り広げるわけだ。
無重力の宇宙ならともかく、
地球上では重力に打ち勝って体を支えるだけでも大変ではないか...。
でも、だからこそウルトラマンなのだ!
人間が及びも付かぬパワーを持っているに違いない。
恐るべし、M78星雲である...。

2010年06月11日
シャーペンは凶器だ!
10時になって塾も終了。
最後まで残っていた高校生も帰って、後かたづけをしていた。
左手に赤ペンとシャーペンを持ったまま、
机にあった計算用紙をクシャクシャと丸めたら、右手に激痛が!
...シャーペンの先がモロに手のひらに刺さったのだ。
推定入射角60°。芯が折れて1mmくらい肉に食い込んでいる...。
芯を抜いたら血があふれてきた。
シャーペンは怖い。
尖った鉛筆ももちろん危険だが、
あの先っぽの、芯を支えている金属部分が曲者だ。
小学生は、シャーペン使用は禁止にしている。
危険だからという理由だけではない。
勉強の途中で芯が途切れると、その度に作業や思考が中断される。
カチャカチャが面白くてつい芯を出し過ぎてしまったり、
ちょっと調子が悪いと分解し出したり...。
ほとんどオモチャになってしまうのだ。
筆圧が小さいため字が薄くなってしまう子もいれば、
逆に大きすぎて書く度にポキポキ芯を折ってしまう子もいる。
やはりその子に合った濃さの鉛筆が最適のようだ。
中学生になると、ほとんどの子がシャーペンを使っている。
私の中学時代は、まだ鉛筆が主流だった。
一時期、なぜか極端に硬い芯の鉛筆ばかり使っていた。
2Hとか3Hとか...。
周りのみんなも同様だったように思う。
今でもときどき、硬い芯のシャーペンで、
薄ーーい字を書いてくる生徒がいる。
遠近両用メガネの身には、読みにくいことこの上ない。
でも、昔の自分を思い出して、なんだか微笑ましい気分にもなるのだ。
あれは思春期のツッパリの一つだったのかも知れない。
あえて見えにくい薄さで書くことがカッコイイと思っていた。
濃い鉛筆は幼児が使うもので、
4Bより2B、それよりHB、H...と、薄くなるほど大人のような気がしていたのだろう。
...可愛いものだ。
シャーペンの話から、思わぬ昔話になってしまった。

最後まで残っていた高校生も帰って、後かたづけをしていた。
左手に赤ペンとシャーペンを持ったまま、
机にあった計算用紙をクシャクシャと丸めたら、右手に激痛が!
...シャーペンの先がモロに手のひらに刺さったのだ。
推定入射角60°。芯が折れて1mmくらい肉に食い込んでいる...。
芯を抜いたら血があふれてきた。
シャーペンは怖い。
尖った鉛筆ももちろん危険だが、
あの先っぽの、芯を支えている金属部分が曲者だ。
小学生は、シャーペン使用は禁止にしている。
危険だからという理由だけではない。
勉強の途中で芯が途切れると、その度に作業や思考が中断される。
カチャカチャが面白くてつい芯を出し過ぎてしまったり、
ちょっと調子が悪いと分解し出したり...。
ほとんどオモチャになってしまうのだ。
筆圧が小さいため字が薄くなってしまう子もいれば、
逆に大きすぎて書く度にポキポキ芯を折ってしまう子もいる。
やはりその子に合った濃さの鉛筆が最適のようだ。
中学生になると、ほとんどの子がシャーペンを使っている。
私の中学時代は、まだ鉛筆が主流だった。
一時期、なぜか極端に硬い芯の鉛筆ばかり使っていた。
2Hとか3Hとか...。
周りのみんなも同様だったように思う。
今でもときどき、硬い芯のシャーペンで、
薄ーーい字を書いてくる生徒がいる。
遠近両用メガネの身には、読みにくいことこの上ない。
でも、昔の自分を思い出して、なんだか微笑ましい気分にもなるのだ。
あれは思春期のツッパリの一つだったのかも知れない。
あえて見えにくい薄さで書くことがカッコイイと思っていた。
濃い鉛筆は幼児が使うもので、
4Bより2B、それよりHB、H...と、薄くなるほど大人のような気がしていたのだろう。
...可愛いものだ。
シャーペンの話から、思わぬ昔話になってしまった。

2010年06月10日
「トン」の不思議
1mの1000倍は1km、1gの1000倍は1kgだ。
k(キロ) は1000倍を表す接頭語である。
kのさらに1000倍はM(メガ)だが、1000kmを1Mmとは言わない。
リットルやアンペアも同じだ。
質量に関しても「1Mg」はないが、代わりに1000Kgを1t(トン)と言う。
考えてみれば不思議な話だ。
国際単位系では、統一性を重視する観点から「Mg」を推奨しているそうだが、
慣習的に「t」の使用も認めているようだ。
1mmや1cm、1mgや1kgはメートル法の基準に沿っている。
長さの基本であるm(メートル)や、重さの基本のg(グラム)に、
m(ミリ)、c(センチ)、k(キロ)といった接頭語が付いて単位となっているからだ。
ところが「t」だけは、質量の単位なのに「g」が付いていない。
メートル法の単位の中では極めて異色な存在である。
メートル法の「t」は、正式には「メトリックトン」あるいは「仏トン」と言うらしい。
「t」はもともとヤード・ポンド法の単位だっだが、
「k」以上の接頭語がなかった時代に、メートル法に採り入れられたようだ。
因みに、イギリスで使っている「英トン」は約1016kg、
アメリカの「米トン」は約907kgで、メートル法のそれとは微妙なズレがある。
ここに「t」を採用したときの事情が伺える。
1000kgに比較的近いということで、表舞台に出る幸運を得たのであろう。
しかし、質量の場合だけ、kの1000倍にあたる単位が設定されているのも特異なことだ。
長さ(距離)にはkmの上の手頃な単位はないので、地球の周囲の長さや
太陽までの距離でさえ、kmを使って表現せざるを得ない。
その上は一挙に「光年」(約9.42×10の12乗km)になってしまう...。
これは、質量を表す単位には、それだけ大きいものを用意する必要があったということだろう。
1000kmの1000倍の距離はなかなかピンと来なくても、
1000gの1000倍の物は比較的身近にあったということだ。
大木でも石でも、自然の中にそういう存在があったからこそ、
「t」の必要性が生まれたのであろう。
それでもなお、統一性を図るために、「t」よりも「Mg」を推したいA型の私である。

k(キロ) は1000倍を表す接頭語である。
kのさらに1000倍はM(メガ)だが、1000kmを1Mmとは言わない。
リットルやアンペアも同じだ。
質量に関しても「1Mg」はないが、代わりに1000Kgを1t(トン)と言う。
考えてみれば不思議な話だ。
国際単位系では、統一性を重視する観点から「Mg」を推奨しているそうだが、
慣習的に「t」の使用も認めているようだ。
1mmや1cm、1mgや1kgはメートル法の基準に沿っている。
長さの基本であるm(メートル)や、重さの基本のg(グラム)に、
m(ミリ)、c(センチ)、k(キロ)といった接頭語が付いて単位となっているからだ。
ところが「t」だけは、質量の単位なのに「g」が付いていない。
メートル法の単位の中では極めて異色な存在である。
メートル法の「t」は、正式には「メトリックトン」あるいは「仏トン」と言うらしい。
「t」はもともとヤード・ポンド法の単位だっだが、
「k」以上の接頭語がなかった時代に、メートル法に採り入れられたようだ。
因みに、イギリスで使っている「英トン」は約1016kg、
アメリカの「米トン」は約907kgで、メートル法のそれとは微妙なズレがある。
ここに「t」を採用したときの事情が伺える。
1000kgに比較的近いということで、表舞台に出る幸運を得たのであろう。
しかし、質量の場合だけ、kの1000倍にあたる単位が設定されているのも特異なことだ。
長さ(距離)にはkmの上の手頃な単位はないので、地球の周囲の長さや
太陽までの距離でさえ、kmを使って表現せざるを得ない。
その上は一挙に「光年」(約9.42×10の12乗km)になってしまう...。
これは、質量を表す単位には、それだけ大きいものを用意する必要があったということだろう。
1000kmの1000倍の距離はなかなかピンと来なくても、
1000gの1000倍の物は比較的身近にあったということだ。
大木でも石でも、自然の中にそういう存在があったからこそ、
「t」の必要性が生まれたのであろう。
それでもなお、統一性を図るために、「t」よりも「Mg」を推したいA型の私である。





