2011年08月09日
言語力の差
ようやく夏期講習も終わり、中3の模試も済んで通常の日々に戻った。
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。
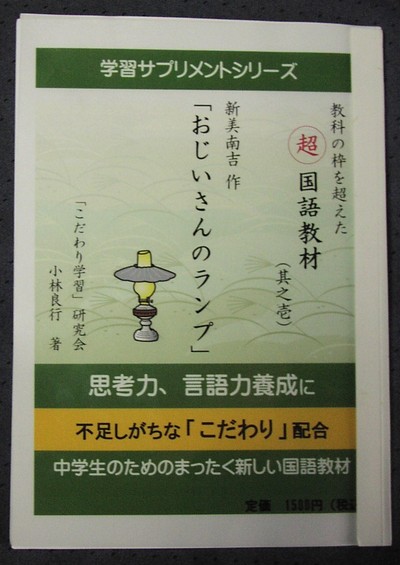
生徒も増えてやれやれである。
今春から小学生の入塾が増えている。
来年開講する県立屋代高校附属中学へ行きたいという5、6年生が多い。
自転車でも十分通える松代では、小学生が塾生の半数を超えた。
同校は、長野県では初の公立中高一貫校である。
「入試」はないことになっているが、実際には他県同様「適性検査」が実施される。
細かな知識よりも、資料を分析して考察を書いたり、
他者に正確に事実や意見を伝えたりできる力が問われるものだ。
思考力・言語力の育成に力を入れているウチの塾の方針に、ぴったりマッチする。
開講3年目の松代の塾にとっては、地域での評価を固める大チャンスだ。
通りに面した窓いっぱいに貼ってあるカッティングシート(言語力・論理的思考力など)を、
前から気にして見ていたという声も多い。
春からは入口に、墨黒々と(ワープロです)「屋代中学受験指導受付中」の貼り紙も...。
ただ、入試は12月である。
もう4ヶ月しかない。
6年の今からでは、すでにある程度の力が備わっている子しか難しいのではないか?
せめて5年生のうちに来てほしいのだが...。
春から入った6年生は、その力が高い子が多い。
特に男子3人の言語力が素晴らしい。
初めは今まで同様、小学生向けの国語教材を使っていたのだが、
試しに、先に紹介した「おじいさんのランプ」を与えてみた。
中学生向けの設問が多いのだが、予想以上に的確な答を書いてくる。
一例を挙げよう。
皆さんも解いてみてください。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。岩滑新田(やなべしんでん)の村に巳之助(みのすけ)という十三の少年がいた。
巳之助は、父母も兄弟もなく、親戚のものとて一人もない、まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使いをしたり、女の子のように子守をしたり、米を搗いてあげたり、そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一生を送るとするなら、男とうまれた甲斐がないと、つねづね思っていた。
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助は毎日、ご飯を喰べてゆくのが やっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころひそかに待っていた。
すると或る夏の日のひるさがり、巳之助は人力車の先綱を頼まれた。
(問)「身を立てる」ための方法の一つとして、作者が考えていることは何ですか。
ヒント:巳之助にはこれができなかった。
「身を立てる」の意味については、この前の段階で調べさせてある。
さて、どうでしょう?
...正解は「本を読むこと」です。
これが、中3生でもなかなか答えられない。
「人力車の先綱」や「きっかけを待つこと」といった答が多くなる。
ところが、先の6年生たちはみごとに答えた。
2人は1回目は惜しいところで、ヒントを与えたら正解。
1人は初めから、模範解答通りの答を書いてきたのである。
この言語力があれば、十分に合格できるのではないか...。
あとは、個々の弱い部分を補強してあげるだけだ。
それにしても、こういった言語能力・言語感覚の差はどこで生まれるのか?
やはり読書量や家庭での会話などが影響しているのか...。
そもそも、中学生の言語力が低すぎるのか、
あるいは3人の小学生のそれが高すぎるだけなのか...。
調べてみたいのが、松代小学校における教育である。
先の3人はすべて松代小の生徒だ。
町内には他にもいくつかの小学校があるが、塾に来ている生徒については、
同校の生徒が一味違う力を持っているように感じる。
たまたまかも知れないが、
ひょっとしたら、旧松代藩文武学校の伝統が受け継がれているのではないか?
松代小は昭和48年まで文武学校の建物を利用。
1853年(ペリー来航の年)に文武学校ができて以来、158年の歴史を誇ると謳っている。
続編は次回。
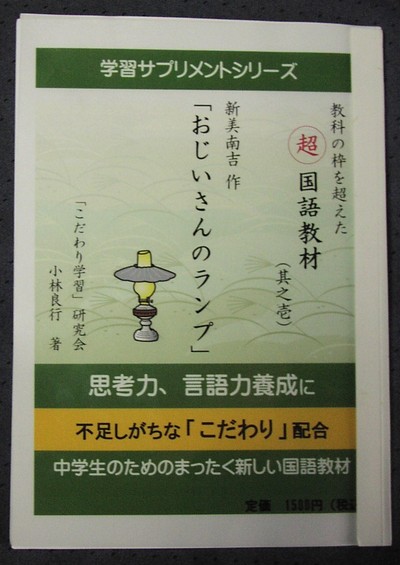
2011年04月18日
「てん」で話にならない
小学生の国語の問題。
(問)次の2つの文を1つの文にしなさい。
風が吹いた。そして雨が降ってきた。
ただ「○」を「、」に換えるだけの子がいる。
風が吹いた、そして雨が降ってきた。
う~ん...。
実はこれはまだいい方で、「、」さえ付けない子もいる。
風が吹いたそして雨が降ってきた。
こうなるともはや日本語とは言い難い。
正解例はもちろん、
風が吹き、雨が降ってきた。
あるいは
風が吹いて、雨が降ってきた。
後の方は「、」がなくてもいいが、「風が吹き」には「、」がほしい。
「、」のない答えの子に「どこかに点がいるなあ」と言うと、こうやった。
風が、吹き雨が降ってきた。
そんなとこで切らないだろう!
声に出して読んでごらん...。
中学生を見ていても、どうも主語の後に自動的に読点を付けたがる子が多い。
おじいさんは、山へ柴刈りに、おばあさんは、川へ洗濯に...。
読点は多ければいいというものではない。
こう細切れにされてはリズムが悪すぎて読みにくい。
「~柴刈りに」の後に打つだけで十分だろう。
逆に、中3になってもまったく読点のない文章を書いてくる生徒もいる。
ひどいのになると句点(○)さえない...。
句読点の打ち方は筆者の裁量に任される部分も多いが、
基本的なルールだけは全員に身につけさせるべきだろう。
主述関係のねじれ、接続詞や接続助詞のいい加減さなども目につく。
今の学校教育では、そういった技術的な指導はほとんど成されていないのではないか。
新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材とした中学生向け国語教材が、
現在最後の仕上げ段階に入っている。
今月中にはほぼ完成予定だ。
それが終わったら、より基礎的な国語教材を作ろうと思う。
より高度なものを先に作るつもりだったのだが、
どうも順番を逆にした方がよさそうである...。

※画像は松代・尼巌山山頂のヒオドシチョウ。登山記録は後日掲載予定。
(問)次の2つの文を1つの文にしなさい。
風が吹いた。そして雨が降ってきた。
ただ「○」を「、」に換えるだけの子がいる。
風が吹いた、そして雨が降ってきた。
う~ん...。
実はこれはまだいい方で、「、」さえ付けない子もいる。
風が吹いたそして雨が降ってきた。
こうなるともはや日本語とは言い難い。
正解例はもちろん、
風が吹き、雨が降ってきた。
あるいは
風が吹いて、雨が降ってきた。
後の方は「、」がなくてもいいが、「風が吹き」には「、」がほしい。
「、」のない答えの子に「どこかに点がいるなあ」と言うと、こうやった。
風が、吹き雨が降ってきた。
そんなとこで切らないだろう!
声に出して読んでごらん...。
中学生を見ていても、どうも主語の後に自動的に読点を付けたがる子が多い。
おじいさんは、山へ柴刈りに、おばあさんは、川へ洗濯に...。
読点は多ければいいというものではない。
こう細切れにされてはリズムが悪すぎて読みにくい。
「~柴刈りに」の後に打つだけで十分だろう。
逆に、中3になってもまったく読点のない文章を書いてくる生徒もいる。
ひどいのになると句点(○)さえない...。
句読点の打ち方は筆者の裁量に任される部分も多いが、
基本的なルールだけは全員に身につけさせるべきだろう。
主述関係のねじれ、接続詞や接続助詞のいい加減さなども目につく。
今の学校教育では、そういった技術的な指導はほとんど成されていないのではないか。
新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材とした中学生向け国語教材が、
現在最後の仕上げ段階に入っている。
今月中にはほぼ完成予定だ。
それが終わったら、より基礎的な国語教材を作ろうと思う。
より高度なものを先に作るつもりだったのだが、
どうも順番を逆にした方がよさそうである...。

※画像は松代・尼巌山山頂のヒオドシチョウ。登山記録は後日掲載予定。
2011年03月06日
比べる力
白鳥の 沼のほとりを 郵便夫
松代の塾では毎月生徒たちに俳句・短歌を覚えさせている。
月初めに季節に合ったものを7~8個選び、リストを渡す。
同時に教室内にも掲示する。
月の終わりにはチェックだ。
俳句なら初めの「五」だけが書いてあり、残りの「七・五」を埋めさせる。
短歌の場合は上の句の「五」と下の句の「七」がヒントになっている。
リストに挙げたうち、3個できれば合格だが、毎回苦労している子も多い。
冒頭の句は田中憲二郎という人の作である。
2月の俳句に採用した。
これを選んだ子の答を見て、あることに気づいた。
「沼のほとりを」を「沼のほとりに」とする子が多いのだ。
「に」が違うと言うと、「沼のほとりの」にして来る子もいた。
「に」や「の」では元句の情景が伝わらない。
そこで2月のチェックとは別に、単独の問題を急遽作成して中学生全員に与えた。
まず元句を掲載し、「白鳥の群れる沼のほとりを郵便夫が通り過ぎて行く」という解説を付ける。
次に「~を」を「~に」に換えた句を載せ、元の句と比べてどんな違いが感じられるかを答えさせるのだ。
何となく違うのは皆すぐわかるようだ。
問題はそれをどう言葉にするか...。
多いのは、「~に」だと郵便夫がいる感じになるという答。
確かに「~郵便夫」の後に言葉を補うなら(筆が進まない子にはこうヒントを出す)、
「~を」には「行く」や「通る」、「~に」には「いる」である。
しかし、この答では両者の比べ方として物足りない。
「~を」でも、情景の中に郵便夫が「いる」ことに変わりはないのではないか...。
元の句ではこうだが「~に」に換えるとこうなるという、違いを明確にした説明がほしい。
模範解答はこんな感じか...。
「~を」だと郵便夫が通り過ぎて行く様子が浮かぶが、
「~に」だと郵便夫が立ち止まっている感じになる。
もっと簡潔に言うなら、こんなのはどうだろう。
「~を」には郵便夫の動きが感じられるが、「~に」には感じられない。
比べる力を鍛えることは論理力の養成に役立つ。
詳しくは、また次回に...。

<画像について>真田邸の釘隠No.2。何かのスイッチのようなシンプルバージョン。
松代の塾では毎月生徒たちに俳句・短歌を覚えさせている。
月初めに季節に合ったものを7~8個選び、リストを渡す。
同時に教室内にも掲示する。
月の終わりにはチェックだ。
俳句なら初めの「五」だけが書いてあり、残りの「七・五」を埋めさせる。
短歌の場合は上の句の「五」と下の句の「七」がヒントになっている。
リストに挙げたうち、3個できれば合格だが、毎回苦労している子も多い。
冒頭の句は田中憲二郎という人の作である。
2月の俳句に採用した。
これを選んだ子の答を見て、あることに気づいた。
「沼のほとりを」を「沼のほとりに」とする子が多いのだ。
「に」が違うと言うと、「沼のほとりの」にして来る子もいた。
「に」や「の」では元句の情景が伝わらない。
そこで2月のチェックとは別に、単独の問題を急遽作成して中学生全員に与えた。
まず元句を掲載し、「白鳥の群れる沼のほとりを郵便夫が通り過ぎて行く」という解説を付ける。
次に「~を」を「~に」に換えた句を載せ、元の句と比べてどんな違いが感じられるかを答えさせるのだ。
何となく違うのは皆すぐわかるようだ。
問題はそれをどう言葉にするか...。
多いのは、「~に」だと郵便夫がいる感じになるという答。
確かに「~郵便夫」の後に言葉を補うなら(筆が進まない子にはこうヒントを出す)、
「~を」には「行く」や「通る」、「~に」には「いる」である。
しかし、この答では両者の比べ方として物足りない。
「~を」でも、情景の中に郵便夫が「いる」ことに変わりはないのではないか...。
元の句ではこうだが「~に」に換えるとこうなるという、違いを明確にした説明がほしい。
模範解答はこんな感じか...。
「~を」だと郵便夫が通り過ぎて行く様子が浮かぶが、
「~に」だと郵便夫が立ち止まっている感じになる。
もっと簡潔に言うなら、こんなのはどうだろう。
「~を」には郵便夫の動きが感じられるが、「~に」には感じられない。
比べる力を鍛えることは論理力の養成に役立つ。
詳しくは、また次回に...。

<画像について>真田邸の釘隠No.2。何かのスイッチのようなシンプルバージョン。
2011年02月17日
「思う」と「考える」(その2)
前回の続き。
今日は次の2語の違いを考えてみたい。
「思いつく」と「考えつく」
書物とネット、それぞれの代表的な辞書で引いてみよう。
「思いつく」は「考えを心に浮かべる。考えを起こす。」(広辞苑)
「ふと考えが心に浮かぶ。」(大辞林)
「考えつく」は「思いつく。考えが浮かぶ。」(広辞苑)
「ある考えが頭に浮かぶ。思いつく。」(大辞林)
う~ん...違いがあるような、ないような...。
頼りの「新解さん」(新明解国語辞典)も、
「思いつく」=「考えが浮かぶ」
「考えつく」=「思いつく」
...と、今回ばかりは他の辞書以上に歯切れが悪い。
私の感覚では、「思いつく」は短時間でパッとひらめく感じで、
「考えつく」は論理的思考を積み重ねて時間をかけているイメージがある。
明らかに違うと思うのだが...。
注目すべきは大辞泉の解釈かも知れない。
「ふと~心に浮かぶ」と「頭に浮かぶ」の違いである。
「思いつく」の方に直感的、刹那的なニュアンスが感じられる。
「思いつき」という名詞になると、そのイメージがずっとはっきりする。
残念ながら「考えつき」という言葉はないので、
「思う」と「考える」の比較にはならないが...。
広辞苑の定義はこうなっている。
「思いついたこと。工夫。着想。またはいいかげんな考え。気まぐれ。」
この後半部分の悪い意味の分だけ、
「思いつく」にも安易な感じが付きまとうのではないだろうか...。
最後に、前回ご紹介した「語感の辞典」の解釈を載せておこう。
この辞書では前出の2語に加え、「ひらめく」との違いにも言及している。
肝心な所だけを抜粋すると...
「考えつく」/「思いつく」よりも時間をかけて考えた具体的な内容の感じが強い。
「思いつく」/「考えつく」ほどではないが、「ひらめく」より具体的な内容を連想させる。
「ひらめく」/「考えつく」はもちろん「思いつく」と比べても、論理的な思考過程とは
関係に瞬間的に脳裏をよぎる唐突な感じが強い。
...納得...。
やっぱりこの辞書、面白い。
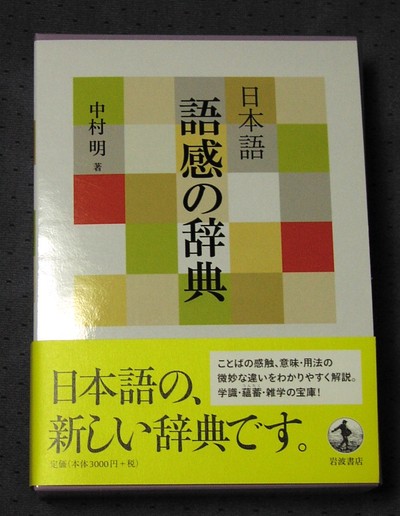
今日は次の2語の違いを考えてみたい。
「思いつく」と「考えつく」
書物とネット、それぞれの代表的な辞書で引いてみよう。
「思いつく」は「考えを心に浮かべる。考えを起こす。」(広辞苑)
「ふと考えが心に浮かぶ。」(大辞林)
「考えつく」は「思いつく。考えが浮かぶ。」(広辞苑)
「ある考えが頭に浮かぶ。思いつく。」(大辞林)
う~ん...違いがあるような、ないような...。
頼りの「新解さん」(新明解国語辞典)も、
「思いつく」=「考えが浮かぶ」
「考えつく」=「思いつく」
...と、今回ばかりは他の辞書以上に歯切れが悪い。
私の感覚では、「思いつく」は短時間でパッとひらめく感じで、
「考えつく」は論理的思考を積み重ねて時間をかけているイメージがある。
明らかに違うと思うのだが...。
注目すべきは大辞泉の解釈かも知れない。
「ふと~心に浮かぶ」と「頭に浮かぶ」の違いである。
「思いつく」の方に直感的、刹那的なニュアンスが感じられる。
「思いつき」という名詞になると、そのイメージがずっとはっきりする。
残念ながら「考えつき」という言葉はないので、
「思う」と「考える」の比較にはならないが...。
広辞苑の定義はこうなっている。
「思いついたこと。工夫。着想。またはいいかげんな考え。気まぐれ。」
この後半部分の悪い意味の分だけ、
「思いつく」にも安易な感じが付きまとうのではないだろうか...。
最後に、前回ご紹介した「語感の辞典」の解釈を載せておこう。
この辞書では前出の2語に加え、「ひらめく」との違いにも言及している。
肝心な所だけを抜粋すると...
「考えつく」/「思いつく」よりも時間をかけて考えた具体的な内容の感じが強い。
「思いつく」/「考えつく」ほどではないが、「ひらめく」より具体的な内容を連想させる。
「ひらめく」/「考えつく」はもちろん「思いつく」と比べても、論理的な思考過程とは
関係に瞬間的に脳裏をよぎる唐突な感じが強い。
...納得...。
やっぱりこの辞書、面白い。
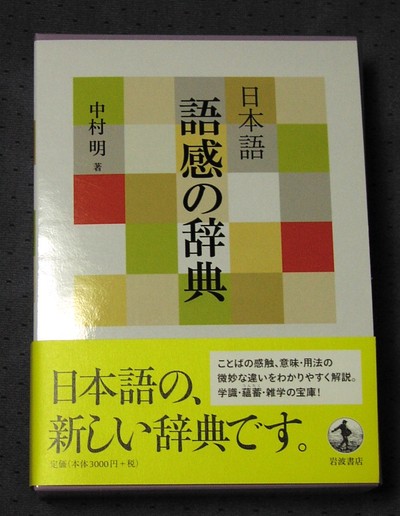
2011年02月11日
「思う」と「考える」(その1)
以前読んだ大野晋の「日本語練習帳」にこんな記述があった。
「思う」と「考える」は似たような意味だが、
たとえば「思い出す」と「考え出す」、「思い込む」と「考え込む」では
全く意味が変わってしまう。
なるほど、と思った。
挙げられた例ではみごとに意味が違う。
これは生徒にも使えそうだと、さっそく教材に盛り込んだ。
両者のニュアンスの違いを説明させるものだ。
そっくり真似てはつまらないから、他にも例を探す。
これと言ったものがなかなか見つからない中で、
次の2組は違いが微妙で興味深かった。
(その1)「思い違い」と「考え違い」
皆さんなら、この2語の使い分けをどう説明しますか?
「思い違い」は単なる勘違いというイメージがある。
新解さん(新明解国語辞典)にもそうある。
問題は「考え違い」の方だ。
頼りの新解さんには見出し自体がない。
広辞苑では「まちがった考えをすること。思い違い。」となっている。
実は広辞苑の「思い違い」も「考え違い」とイコールの説明で、2語の明確な区別はない。
だが、私にはこの2つ、明らかに違うように思われてならない。
「思い違い」は笑って済ませられるが、「考え違い」の方は深刻な感じがしないだろうか...。
「考え違いも甚だしい。」
「それは考え違いというものだ。」
人として間違った考え、道義的・道徳的に良くない考えに使われるように思う。
生徒にもそんな解説をしていたが、自分の感覚に今一つ自信が持てない面もあった。
ところが最近になって、私の説を裏付けてくれる辞書に出会ったのだ。
岩波書店から刊行された「日本語語感の辞典」(中村明著)。
新聞等でずいぶん話題になり、amazonでも一時品切れで待たされた。
この辞書、普通の辞書と違い、多くの言葉を網羅しているわけではない。
似たような意味の言葉をどう使い分けるかの解説に特化された辞書なのだ。
まさに、これこそが私が求めていたものである。
今までの辞書では満たされなかった部分を、しっかり埋めてくれる。
さっそく、載っていることを期待して引いてみた。
結果は十分満足に値するものだった。
「思い違い」の項には「単純な誤解」、
「考え違い」には「道理や道徳に反する意味合い」という記述がある。
みごとに期待に応えてくれた。
私の感覚は間違っていなかったのだ...。
久しぶりに読んで楽しい辞書に出会えた。
これから先、、せいぜい活用したいと思う。
「思う」と「考える」の違い、その2は次回に...。
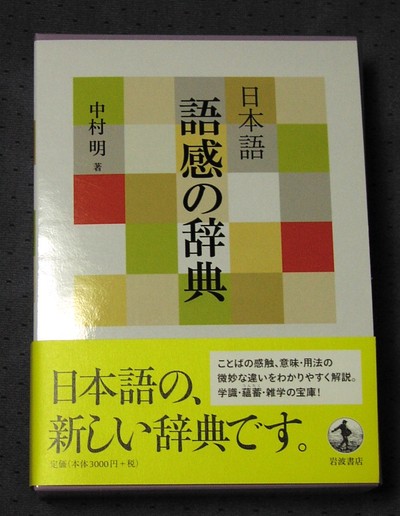
「思う」と「考える」は似たような意味だが、
たとえば「思い出す」と「考え出す」、「思い込む」と「考え込む」では
全く意味が変わってしまう。
なるほど、と思った。
挙げられた例ではみごとに意味が違う。
これは生徒にも使えそうだと、さっそく教材に盛り込んだ。
両者のニュアンスの違いを説明させるものだ。
そっくり真似てはつまらないから、他にも例を探す。
これと言ったものがなかなか見つからない中で、
次の2組は違いが微妙で興味深かった。
(その1)「思い違い」と「考え違い」
皆さんなら、この2語の使い分けをどう説明しますか?
「思い違い」は単なる勘違いというイメージがある。
新解さん(新明解国語辞典)にもそうある。
問題は「考え違い」の方だ。
頼りの新解さんには見出し自体がない。
広辞苑では「まちがった考えをすること。思い違い。」となっている。
実は広辞苑の「思い違い」も「考え違い」とイコールの説明で、2語の明確な区別はない。
だが、私にはこの2つ、明らかに違うように思われてならない。
「思い違い」は笑って済ませられるが、「考え違い」の方は深刻な感じがしないだろうか...。
「考え違いも甚だしい。」
「それは考え違いというものだ。」
人として間違った考え、道義的・道徳的に良くない考えに使われるように思う。
生徒にもそんな解説をしていたが、自分の感覚に今一つ自信が持てない面もあった。
ところが最近になって、私の説を裏付けてくれる辞書に出会ったのだ。
岩波書店から刊行された「日本語語感の辞典」(中村明著)。
新聞等でずいぶん話題になり、amazonでも一時品切れで待たされた。
この辞書、普通の辞書と違い、多くの言葉を網羅しているわけではない。
似たような意味の言葉をどう使い分けるかの解説に特化された辞書なのだ。
まさに、これこそが私が求めていたものである。
今までの辞書では満たされなかった部分を、しっかり埋めてくれる。
さっそく、載っていることを期待して引いてみた。
結果は十分満足に値するものだった。
「思い違い」の項には「単純な誤解」、
「考え違い」には「道理や道徳に反する意味合い」という記述がある。
みごとに期待に応えてくれた。
私の感覚は間違っていなかったのだ...。
久しぶりに読んで楽しい辞書に出会えた。
これから先、、せいぜい活用したいと思う。
「思う」と「考える」の違い、その2は次回に...。
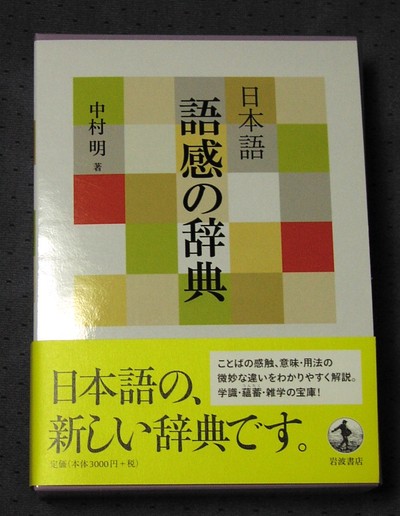
2010年12月28日
CMにつっこむ(1)
最近、CMを見て引っかかったことあれこれ...。
今回は言葉の使い方の巻。
(その1)ダイキンのエアコン。
「空気中の水分を集めて加湿する無給水加湿」
テレビで見たとき「???」と思った。
空気中の水分を集めて、またそれを元にもどすだけ...?
意味ないじゃん!
ネットで調べてやっとわかった。
外の空気の水分を集めて室内を加湿するってことね。
だったら「外気の水分を...」とか言わないと、正確に伝わらないと思うんだけど...。
(その2)ダイハツの軽自動車「ムーヴ」。
「ガソリン車最低燃費」
「TNP」で注目を集めている車だ。
これはテレビではなく、Yahoo BB のトップページにあった広告。
言いたいことはもちろんわかる。
リッター27kmは素晴らしい。
だが、一瞬「え?」と考えてしまう。
「低燃費」なら抵抗ないのだが、「最低」になると違和感がないだろうか?
「あの車、燃費どう?」
「最低...」
やたらガソリンを喰う車と思われかねない。
かと言って、「最高燃費」も「高燃費」を連想してよくない。
「最良燃費」とすべきか...。
「その3」は言葉の問題とは違うので、また明日...。

今回は言葉の使い方の巻。
(その1)ダイキンのエアコン。
「空気中の水分を集めて加湿する無給水加湿」
テレビで見たとき「???」と思った。
空気中の水分を集めて、またそれを元にもどすだけ...?
意味ないじゃん!
ネットで調べてやっとわかった。
外の空気の水分を集めて室内を加湿するってことね。
だったら「外気の水分を...」とか言わないと、正確に伝わらないと思うんだけど...。
(その2)ダイハツの軽自動車「ムーヴ」。
「ガソリン車最低燃費」
「TNP」で注目を集めている車だ。
これはテレビではなく、Yahoo BB のトップページにあった広告。
言いたいことはもちろんわかる。
リッター27kmは素晴らしい。
だが、一瞬「え?」と考えてしまう。
「低燃費」なら抵抗ないのだが、「最低」になると違和感がないだろうか?
「あの車、燃費どう?」
「最低...」
やたらガソリンを喰う車と思われかねない。
かと言って、「最高燃費」も「高燃費」を連想してよくない。
「最良燃費」とすべきか...。
「その3」は言葉の問題とは違うので、また明日...。

2010年12月06日
漢字のこだわり
地元の新聞店が月一度出している通信がある。
B4用紙の両面に、いろいろな新聞に載ったコラムなどが再掲されている。
いつもは信毎と朝日しか見ていないので、なかなか興味深い。
先日その通信に、朝日新聞のコラムが載っていた。
以前に読んだ記憶がないし、館山支局の記者が書いていたので、
千葉県版のみの掲載だったのかも知れない。
しかし、果たしてその新聞店が千葉県版を手に入れることができるのか...。
私が見落としていただけかも知れない。
それはともかく、コラムのタイトルは「「一所懸命」のこだわり」という。
前半は「矢先」という言葉が、「ものごとの直前」という意味だけではなく、
本来は誤用である「直後」の意味でも使われるようになったことに触れている。
三浦哲郎氏の死去を報じた朝日新聞の記事に、
「5年ぶりに随筆集を出した矢先だった」という表現があったらしい。
「随筆集が出版される矢先だった」ならわかるが、これは間違いだと思ったと言う。
ところが最近では「直後」の意味で使われることも多く、
広辞苑にさえ「事の正に始まろうとするとき、または後」とあるらしい。
その後に出てくるのが「一所懸命」だ。
記者は中学生のときの漢字テストで、「一生懸命」を「一所懸命」と書いて×をもらったそうだ。
で、懲りたかと言えば逆である。
言葉は時代とともに変わるものであり、誤用がやがて正しい使い方となるのも認めた上で、
でも、だからこそ、言葉へのこだわりを忘れずに「小さな抵抗」を続けていきたいと結んでいる。
この記者、私とそっくりだ。
以前も書いたが、私も言葉や漢字については極めて保守的な人間だ。
「一所懸命」だけは意地でも譲らない。
「(電車などが)こむ」も、「混」が正式に許容されても、
本来の「込む」を使い続けるつもりだ。
何でも「取る」で済ませるのではなく、
「獲る」「捕る」や「撮る」「録る」「摂る」「採る」「執る」をきちんと使い分けたい。
そう言えば昔、
ラブレターではあえて「思う」を「想う」 、「会う」を「逢う」と書いていたっけ...。
因みに上に挙げた「矢先」、新解さん(新明解国語辞典)では「直後」は認めていない。
「予定の行動にかかろうとする、ちょうどその時」とある。
うん、これでなくっちゃ...。

B4用紙の両面に、いろいろな新聞に載ったコラムなどが再掲されている。
いつもは信毎と朝日しか見ていないので、なかなか興味深い。
先日その通信に、朝日新聞のコラムが載っていた。
以前に読んだ記憶がないし、館山支局の記者が書いていたので、
千葉県版のみの掲載だったのかも知れない。
しかし、果たしてその新聞店が千葉県版を手に入れることができるのか...。
私が見落としていただけかも知れない。
それはともかく、コラムのタイトルは「「一所懸命」のこだわり」という。
前半は「矢先」という言葉が、「ものごとの直前」という意味だけではなく、
本来は誤用である「直後」の意味でも使われるようになったことに触れている。
三浦哲郎氏の死去を報じた朝日新聞の記事に、
「5年ぶりに随筆集を出した矢先だった」という表現があったらしい。
「随筆集が出版される矢先だった」ならわかるが、これは間違いだと思ったと言う。
ところが最近では「直後」の意味で使われることも多く、
広辞苑にさえ「事の正に始まろうとするとき、または後」とあるらしい。
その後に出てくるのが「一所懸命」だ。
記者は中学生のときの漢字テストで、「一生懸命」を「一所懸命」と書いて×をもらったそうだ。
で、懲りたかと言えば逆である。
言葉は時代とともに変わるものであり、誤用がやがて正しい使い方となるのも認めた上で、
でも、だからこそ、言葉へのこだわりを忘れずに「小さな抵抗」を続けていきたいと結んでいる。
この記者、私とそっくりだ。
以前も書いたが、私も言葉や漢字については極めて保守的な人間だ。
「一所懸命」だけは意地でも譲らない。
「(電車などが)こむ」も、「混」が正式に許容されても、
本来の「込む」を使い続けるつもりだ。
何でも「取る」で済ませるのではなく、
「獲る」「捕る」や「撮る」「録る」「摂る」「採る」「執る」をきちんと使い分けたい。
そう言えば昔、
ラブレターではあえて「思う」を「想う」 、「会う」を「逢う」と書いていたっけ...。
因みに上に挙げた「矢先」、新解さん(新明解国語辞典)では「直後」は認めていない。
「予定の行動にかかろうとする、ちょうどその時」とある。
うん、これでなくっちゃ...。

2010年11月11日
出没...
中学生向けの言語力教材(初級編)製作が佳境に入ってきた。
冬期講習に向けて折り込みチラシも作らねばならない。
さらに、ストーブ用の薪を割ったり、来季に備えて切ったりする作業もある。
そんなわけでブログの更新がままならない状況だ...。
今日の題材は「出没」という言葉。
今年は熊が里に下りてくる機会が多いようで、毎日のようにこの言葉を目にする。
熊ほど、この言葉がピタリと来る対象はいないのではないか。
オリジナル教材で、辞書の定義からその言葉を推測させる問題がある。
「現れたり隠れたりすること」という定義を読んでも、すぐには全く言葉が出てこない子が多い。
数分考えた後、「出現」と答える。
「出現」では現れるだけだから、もちろん×である。
ヒントを出すとき使うのが熊だ。
「熊が...」でピンと来ない子には、
「現れっぱなしじゃ撃たれたり捕まったりしちゃうぞ。ちょっと現れてすぐいなくなることだ」
「「出」は合ってるからあと一字を考えろ」などと助け船を出す。
それにしても、「出没」は便利な言葉だ。
熊が出る度にこの表現では、いささか食傷気味だが、他にふさわしい言葉がない。
類語辞典にあたっても「見え隠れ」「隠顕」「散見」くらいしかない。
どれも「出没」のニュアンスとは違う...。
英語ではどう言うのか、Yahoo翻訳で調べてみた。
「出没」と名詞で入れると「haunting」と出てきた。
haunt を調べると、他動詞で「~にたびたび行く」「~に出る、~に取り憑く、~を悩ます」とある。
ははあ...ディズニーランドの「ホーンテッド・マンション」の haunt か...。
haunt は名詞で
「行きつけの所、(動物などの)よく出る所、(犯人などの)巣窟」という意味もあるらしい。
かなり「出没」の匂いがしてきたが、やはり「没」のイメージが伴わない。
他動詞なので、場所を主語にして受動態の文にするしかなさそうだ。
「この地区は熊に取り憑かれている」のような表現になるのだろう。
「熊が出没する」を翻訳すると「A bear appears frequently.」になった。
単に「頻出する」と言っているだけである。
「出没」は「頻繁に」というニュアンスを、必ずしも伴わないのではないか...。
ところで、「出没」という言葉が合う主語は、熊などの獣以外に何が考えられるだろう?
痴漢、空き巣、引ったくり...幽霊...ろくなものがない。
どうもこの言葉は、出て来てほしくない何かに対して用いるようだ。
動物でも、美しいオオムラサキやカワセミ、愛らしいリス、探し求めていたクワガタなどには
「出没」は使われないのではないか...。
そう思っていたら、さすが「新解さん(新明解国語辞典)」。
「(幽霊・強盗・痴漢・獣など好ましくない存在が)時どき姿を現すこと」とあった。
とすれば、かなり主観が入った言葉ということになる。
出て来てほしいと思っていた人の幽霊なら、「出没」ではなく「出現」がふさわしい。
猟師にとっては、熊もそうであるかも知れない。
逆にリスやオコジョでも、畑を荒らしたり人間に危害を加えることがあれば、
好ましくない存在として「出没」を使われることになるだろう。
動物たちにしてみれば甚だ迷惑な言葉である。
それにしても、市街地でもこれだけ熊の出没が度重なると、
イノシシやカモシカが出る山間部ではヒヤヒヤものだ。
夜遅く帰宅し、車を降りてから玄関までたどり着く間の畑が怖ろしい。
鈴でも鳴らして通ろうか...。

冬期講習に向けて折り込みチラシも作らねばならない。
さらに、ストーブ用の薪を割ったり、来季に備えて切ったりする作業もある。
そんなわけでブログの更新がままならない状況だ...。
今日の題材は「出没」という言葉。
今年は熊が里に下りてくる機会が多いようで、毎日のようにこの言葉を目にする。
熊ほど、この言葉がピタリと来る対象はいないのではないか。
オリジナル教材で、辞書の定義からその言葉を推測させる問題がある。
「現れたり隠れたりすること」という定義を読んでも、すぐには全く言葉が出てこない子が多い。
数分考えた後、「出現」と答える。
「出現」では現れるだけだから、もちろん×である。
ヒントを出すとき使うのが熊だ。
「熊が...」でピンと来ない子には、
「現れっぱなしじゃ撃たれたり捕まったりしちゃうぞ。ちょっと現れてすぐいなくなることだ」
「「出」は合ってるからあと一字を考えろ」などと助け船を出す。
それにしても、「出没」は便利な言葉だ。
熊が出る度にこの表現では、いささか食傷気味だが、他にふさわしい言葉がない。
類語辞典にあたっても「見え隠れ」「隠顕」「散見」くらいしかない。
どれも「出没」のニュアンスとは違う...。
英語ではどう言うのか、Yahoo翻訳で調べてみた。
「出没」と名詞で入れると「haunting」と出てきた。
haunt を調べると、他動詞で「~にたびたび行く」「~に出る、~に取り憑く、~を悩ます」とある。
ははあ...ディズニーランドの「ホーンテッド・マンション」の haunt か...。
haunt は名詞で
「行きつけの所、(動物などの)よく出る所、(犯人などの)巣窟」という意味もあるらしい。
かなり「出没」の匂いがしてきたが、やはり「没」のイメージが伴わない。
他動詞なので、場所を主語にして受動態の文にするしかなさそうだ。
「この地区は熊に取り憑かれている」のような表現になるのだろう。
「熊が出没する」を翻訳すると「A bear appears frequently.」になった。
単に「頻出する」と言っているだけである。
「出没」は「頻繁に」というニュアンスを、必ずしも伴わないのではないか...。
ところで、「出没」という言葉が合う主語は、熊などの獣以外に何が考えられるだろう?
痴漢、空き巣、引ったくり...幽霊...ろくなものがない。
どうもこの言葉は、出て来てほしくない何かに対して用いるようだ。
動物でも、美しいオオムラサキやカワセミ、愛らしいリス、探し求めていたクワガタなどには
「出没」は使われないのではないか...。
そう思っていたら、さすが「新解さん(新明解国語辞典)」。
「(幽霊・強盗・痴漢・獣など好ましくない存在が)時どき姿を現すこと」とあった。
とすれば、かなり主観が入った言葉ということになる。
出て来てほしいと思っていた人の幽霊なら、「出没」ではなく「出現」がふさわしい。
猟師にとっては、熊もそうであるかも知れない。
逆にリスやオコジョでも、畑を荒らしたり人間に危害を加えることがあれば、
好ましくない存在として「出没」を使われることになるだろう。
動物たちにしてみれば甚だ迷惑な言葉である。
それにしても、市街地でもこれだけ熊の出没が度重なると、
イノシシやカモシカが出る山間部ではヒヤヒヤものだ。
夜遅く帰宅し、車を降りてから玄関までたどり着く間の畑が怖ろしい。
鈴でも鳴らして通ろうか...。

2010年11月01日
おかしな日本語...なのかな?
久々の小ネタ集。また野球シリーズだ。
①「阪神打線を抑えられることができるか。」
これは明らかに重複表現。
「押さえられるか」と言うか、「抑えることができるか」と表現するか、
一瞬迷った結果だと推察する。
②「今シーズン、巨人からの失点はゼロです。」
正しい言い方のようにも思えるが、どうも違和感がある。
「巨人から点を奪われる」なら「~から」の使い方はおかしくない。
「巨人から点を失う」になると、やはり間違っている気がする。
「巨人に対する失点」あるいは「巨人相手の失点」とすべきではないか...。
③「今年はセ・リーグに優先権があるため、セとパが交互に下位から順番に指名する。」
先日のドラフト会議の仕組みを説明した信毎の記事。
2位指名以降の、いわゆるウェーバー制についてのくだりだ。
「セとパが交互に下位から順番に指名する」のは毎年のことである。
「セとパが」の部分で、今年はセ・リーグが先ということを言いたいのだろうが、
普通に読んだらそういう因果関係には取れない。
パ・リーグに優先権があるときは「交互に」ではない、
もしくは「下位から」ではないという解釈の方が自然であろう。
「セの下位球団から順番に、セ・パが交互に指名する」とすべし。
④「ただいま降雨のため試合が中断しています。」
これは私の疑問である。
「試合が中断する」という言い方は正しいのか?
試合が自分の意志で中断するわけではない。
人間の判断で試合が「中断される」のではないか...。
「新解さん(新明解国語辞典)」で「中断」を引くと、
「今まで続いていた物事が、なんらかの事情でそこで中止されること。
また、そうすること。」とある。
...微妙...。

①「阪神打線を抑えられることができるか。」
これは明らかに重複表現。
「押さえられるか」と言うか、「抑えることができるか」と表現するか、
一瞬迷った結果だと推察する。
②「今シーズン、巨人からの失点はゼロです。」
正しい言い方のようにも思えるが、どうも違和感がある。
「巨人から点を奪われる」なら「~から」の使い方はおかしくない。
「巨人から点を失う」になると、やはり間違っている気がする。
「巨人に対する失点」あるいは「巨人相手の失点」とすべきではないか...。
③「今年はセ・リーグに優先権があるため、セとパが交互に下位から順番に指名する。」
先日のドラフト会議の仕組みを説明した信毎の記事。
2位指名以降の、いわゆるウェーバー制についてのくだりだ。
「セとパが交互に下位から順番に指名する」のは毎年のことである。
「セとパが」の部分で、今年はセ・リーグが先ということを言いたいのだろうが、
普通に読んだらそういう因果関係には取れない。
パ・リーグに優先権があるときは「交互に」ではない、
もしくは「下位から」ではないという解釈の方が自然であろう。
「セの下位球団から順番に、セ・パが交互に指名する」とすべし。
④「ただいま降雨のため試合が中断しています。」
これは私の疑問である。
「試合が中断する」という言い方は正しいのか?
試合が自分の意志で中断するわけではない。
人間の判断で試合が「中断される」のではないか...。
「新解さん(新明解国語辞典)」で「中断」を引くと、
「今まで続いていた物事が、なんらかの事情でそこで中止されること。
また、そうすること。」とある。
...微妙...。

2010年10月19日
逆王手?
プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ(CS)は、
地元甲子園で開催しながら、阪神が2連敗で敗退...。
あまりの情けない試合に、怒りも悔しさも湧かないほどだ。
で、気分を変えてパ・リーグのCSファイナルステージを楽しむ。
シーズン3位から大逆転で勝ち上がってきたロッテを応援。
どこかの球団と違って、ここ一番で勝負強い。
観ていて、実に楽しい試合だ。
3試合を終わって、ソフトバンクが3勝(アドバンテージ分含む)1敗で王手をかけた。
そこからロッテが連勝して、昨日までで3勝3敗。
今日勝った方が日本シリーズ進出だ。
今朝のスポーツ紙には、どこも「ロッテ逆王手!」の見出しが躍っている。
よく目にする言葉だが、考えてみるとこの使い方おかしくないだろうか?
将棋の場合、自分がかけた王手を相手がかわした結果、
今度は相手が王手をかける状況になることはあり得る。
そのときは自分の王手は消滅しているわけだ。
ところが今回のような場合は、ソフトバンクの王手がなくなったわけではない。
相変わらず3勝は挙げているのだから、今日勝てばいいわけだ。
「逆王手」では、ロッテだけにチャンスがあるような誤解を生むのではないか...。
今シーズンはセ・パ両リーグとも終盤まで混戦が続いた。
特にパ・リーグは、西武がマジック4まで行きながら、
最終盤にそれが消え、逆にソフトバンクにマジック1が点いた。
マジック1はすなわち「王手」である。
そのままソフトバンクの優勝が決まったが、
その日の試合で西武が勝ち、ソフトバンクが敗れていれば、
今度は西武にマジック1が点くはずだった。
こういう状況こそ「逆王手」と言うにふさわしい。
チャンスは片方にのみあるのだから...。
では、今回のロッテvsソフトバンクの3勝3敗はどう呼ぶべきか...。
互いに「王手」なのだから、「両王手」はどうかと思ったが、
それは将棋用語に実在し、全く違う意味になるようだ。
「相王手」なんてどうだろう...?
いつ誰が使い始めたの知らないが、どうも「逆王手」はしっくり来ない。
違和感を覚える方、他にいらっしゃいませんか?

※画像は庭で見かけた双子の花。不思議...。
地元甲子園で開催しながら、阪神が2連敗で敗退...。
あまりの情けない試合に、怒りも悔しさも湧かないほどだ。
で、気分を変えてパ・リーグのCSファイナルステージを楽しむ。
シーズン3位から大逆転で勝ち上がってきたロッテを応援。
どこかの球団と違って、ここ一番で勝負強い。
観ていて、実に楽しい試合だ。
3試合を終わって、ソフトバンクが3勝(アドバンテージ分含む)1敗で王手をかけた。
そこからロッテが連勝して、昨日までで3勝3敗。
今日勝った方が日本シリーズ進出だ。
今朝のスポーツ紙には、どこも「ロッテ逆王手!」の見出しが躍っている。
よく目にする言葉だが、考えてみるとこの使い方おかしくないだろうか?
将棋の場合、自分がかけた王手を相手がかわした結果、
今度は相手が王手をかける状況になることはあり得る。
そのときは自分の王手は消滅しているわけだ。
ところが今回のような場合は、ソフトバンクの王手がなくなったわけではない。
相変わらず3勝は挙げているのだから、今日勝てばいいわけだ。
「逆王手」では、ロッテだけにチャンスがあるような誤解を生むのではないか...。
今シーズンはセ・パ両リーグとも終盤まで混戦が続いた。
特にパ・リーグは、西武がマジック4まで行きながら、
最終盤にそれが消え、逆にソフトバンクにマジック1が点いた。
マジック1はすなわち「王手」である。
そのままソフトバンクの優勝が決まったが、
その日の試合で西武が勝ち、ソフトバンクが敗れていれば、
今度は西武にマジック1が点くはずだった。
こういう状況こそ「逆王手」と言うにふさわしい。
チャンスは片方にのみあるのだから...。
では、今回のロッテvsソフトバンクの3勝3敗はどう呼ぶべきか...。
互いに「王手」なのだから、「両王手」はどうかと思ったが、
それは将棋用語に実在し、全く違う意味になるようだ。
「相王手」なんてどうだろう...?
いつ誰が使い始めたの知らないが、どうも「逆王手」はしっくり来ない。
違和感を覚える方、他にいらっしゃいませんか?

※画像は庭で見かけた双子の花。不思議...。
2010年10月17日
「主婦」は忙しい
前回の続き。
「主婦」という言葉を中3生に定義してもらった。
「妻。主に家事をする。」
「家族の中で主に家事をする女性のこと。」
「家にこもり、炊事・洗濯などの家事をしている女性を指す言葉」
この辺は当たり障りのない説明だ。
「家にこもり」は専業主婦をイメージした結果か?
...それにしても「こもり」は行き過ぎではないか...。
あとの3人が注目している点が面白い。
「主に家事を仕事とし、年中無休。」
「結婚して仕事や家事を行い、夫とは違って忙しい。」
とにかく「主婦」は忙しいのだ!
中学生にもそう映っているのだ。
「夫」は、あまり忙しそうに見えないらしい...。
「家庭で夫を支える縁の下の力持ち的存在。むしろ夫より物事に追われて忙しい人。
たいてい夫より強く、夫がおそれる人。」
表には出ず陰で「夫を支える」役回りに徹しながら、
家庭内ではしっかり実権を握っている様子をみごとに表現している。
失礼ながら、つい彼のお母さんの顔を思い浮かべてしまった...。
因みに辞書の定義は以下の通り。
「妻であり、家事をきりもりする人。」(旺文社国語辞典)
「主人の妻で、一家をきりもりしている婦人。女あるじ。」(広辞苑)
「きりもりする」がポイントらしい。
新解さん(新明解国語辞典)ではこうなっている。
「家族が気持ちよく元気に・仕事(勉強)が出来るように生活環境を整え、
食事などの世話を中心になってする婦人。<主として妻に、この役が求められる>」
さすがに定義が具体的だ。
「きりもりする」なんかで誤魔化さない...。
< >の中の補足も効いている。
妻がやらなければいけないのではなく、「求められている」だけなのだ。
またときどき、この「ゲーム」やってみようと思っている。

「主婦」という言葉を中3生に定義してもらった。
「妻。主に家事をする。」
「家族の中で主に家事をする女性のこと。」
「家にこもり、炊事・洗濯などの家事をしている女性を指す言葉」
この辺は当たり障りのない説明だ。
「家にこもり」は専業主婦をイメージした結果か?
...それにしても「こもり」は行き過ぎではないか...。
あとの3人が注目している点が面白い。
「主に家事を仕事とし、年中無休。」
「結婚して仕事や家事を行い、夫とは違って忙しい。」
とにかく「主婦」は忙しいのだ!
中学生にもそう映っているのだ。
「夫」は、あまり忙しそうに見えないらしい...。
「家庭で夫を支える縁の下の力持ち的存在。むしろ夫より物事に追われて忙しい人。
たいてい夫より強く、夫がおそれる人。」
表には出ず陰で「夫を支える」役回りに徹しながら、
家庭内ではしっかり実権を握っている様子をみごとに表現している。
失礼ながら、つい彼のお母さんの顔を思い浮かべてしまった...。
因みに辞書の定義は以下の通り。
「妻であり、家事をきりもりする人。」(旺文社国語辞典)
「主人の妻で、一家をきりもりしている婦人。女あるじ。」(広辞苑)
「きりもりする」がポイントらしい。
新解さん(新明解国語辞典)ではこうなっている。
「家族が気持ちよく元気に・仕事(勉強)が出来るように生活環境を整え、
食事などの世話を中心になってする婦人。<主として妻に、この役が求められる>」
さすがに定義が具体的だ。
「きりもりする」なんかで誤魔化さない...。
< >の中の補足も効いている。
妻がやらなければいけないのではなく、「求められている」だけなのだ。
またときどき、この「ゲーム」やってみようと思っている。

2010年10月14日
「万引き」を定義せよ
心酔してやまない「新解さん」(新明解国語辞典)の魅力を生徒にも紹介した。
(以前に紹介した新解さんはこちらやこちら。)
さすがに中学生に「合体」とか「性交」の解釈を披露するわけにはいかないので、
「動物園」や「憎い」で、他の辞書ではあり得ない定義を体感してもらう。
他にも面白いのがあったはずだと前に書き留めたメモを探し出し、
次は「万引き」と「主婦」を味わってもらおうと決めた。
当日になって思い立った。
いきなり新解さんの解釈を見せる前に、まず彼らに自分なりの定義を書いてもらおう。
その後、一般的な辞書の解釈と新解さんのそれを紹介すれば、
新解さんのユニークさがいっそう際だつだろうと考えたのだ。
その場にいた中3生6名(全員男子)に書いてもらう。
制限時間は5分。
自分が辞書の編集者になったつもりで説明しろと指示した。
ウチの塾は普段からよく辞書を引かせているし、
オリジナル教材にも言葉の定義を書かせる問題があるので、
結構それっぽい答が集まった。
当たり障りのないいかにも辞書的なもの、
自分の経験を元にした新解さん顔負けのユニークなもの...。
生徒それぞれの性格や家庭環境まで垣間見えて面白い。
それぞれに過不足はあるが、どれもなかなかの作品だった。
まずは「万引き」の定義。
「店で売っている品物を、無断で持ち出そうとする行為。」
「店で商品を、お金を払わずに勝手に持ち出すこと。」
この辺りはおとなしい。
「身近にあるコンビニやスーパーから、金ではなく売り物を盗って
いく人。犯罪者。
ときには何十人の連合を組んで物を盗りに来る。」
「コンビニやスーパー」に限定しているところは問題だが、
「ときには」以降がユニークだ。
「店にある商品を許可なく持ち去り、店に損害を与える犯罪。」
「店に損害を与える」という定義を入れたはこの子だけだった。
私が一番気に入ったのがこれ。
「物をこわさず、人に恐怖を与えることなく品物を盗むこと。」
なるほど!
...泥棒や強盗との違いを明確にしたかったようだ。
因みに実際の辞書ではこうなっている。
「物を買うふりをしてそっとぬすむこと、また、その人。」(小学館・新選国語辞典)
「買い物をするふりをして、店頭の商品をかすめとること。また、その人。」(広辞苑)
そして新解さんは...
「店員の見ていない隙に売り場の商品を手に取り、
自分の持ち物(買った物)であるかのように見せかけて店外に持ち出す・こと(人)。」
さすがにリアルだ!
HOW TO 万引きの指南書みたい...。
さらに面白かった「主婦」については、また次回に...。

(以前に紹介した新解さんはこちらやこちら。)
さすがに中学生に「合体」とか「性交」の解釈を披露するわけにはいかないので、
「動物園」や「憎い」で、他の辞書ではあり得ない定義を体感してもらう。
他にも面白いのがあったはずだと前に書き留めたメモを探し出し、
次は「万引き」と「主婦」を味わってもらおうと決めた。
当日になって思い立った。
いきなり新解さんの解釈を見せる前に、まず彼らに自分なりの定義を書いてもらおう。
その後、一般的な辞書の解釈と新解さんのそれを紹介すれば、
新解さんのユニークさがいっそう際だつだろうと考えたのだ。
その場にいた中3生6名(全員男子)に書いてもらう。
制限時間は5分。
自分が辞書の編集者になったつもりで説明しろと指示した。
ウチの塾は普段からよく辞書を引かせているし、
オリジナル教材にも言葉の定義を書かせる問題があるので、
結構それっぽい答が集まった。
当たり障りのないいかにも辞書的なもの、
自分の経験を元にした新解さん顔負けのユニークなもの...。
生徒それぞれの性格や家庭環境まで垣間見えて面白い。
それぞれに過不足はあるが、どれもなかなかの作品だった。
まずは「万引き」の定義。
「店で売っている品物を、無断で持ち出そうとする行為。」
「店で商品を、お金を払わずに勝手に持ち出すこと。」
この辺りはおとなしい。
「身近にあるコンビニやスーパーから、金ではなく売り物を盗って
いく人。犯罪者。
ときには何十人の連合を組んで物を盗りに来る。」
「コンビニやスーパー」に限定しているところは問題だが、
「ときには」以降がユニークだ。
「店にある商品を許可なく持ち去り、店に損害を与える犯罪。」
「店に損害を与える」という定義を入れたはこの子だけだった。
私が一番気に入ったのがこれ。
「物をこわさず、人に恐怖を与えることなく品物を盗むこと。」
なるほど!
...泥棒や強盗との違いを明確にしたかったようだ。
因みに実際の辞書ではこうなっている。
「物を買うふりをしてそっとぬすむこと、また、その人。」(小学館・新選国語辞典)
「買い物をするふりをして、店頭の商品をかすめとること。また、その人。」(広辞苑)
そして新解さんは...
「店員の見ていない隙に売り場の商品を手に取り、
自分の持ち物(買った物)であるかのように見せかけて店外に持ち出す・こと(人)。」
さすがにリアルだ!
HOW TO 万引きの指南書みたい...。
さらに面白かった「主婦」については、また次回に...。

2010年09月27日
調べろよ!
生徒が「できました」と言う。
私はでき具合を確認し、質問はないかと問う。
「ありません」と答えると、こちらから質問だ。
「円周率って、何の何に対する率?」
「力と圧力の違いは何?」
「公地公民ってどういうこと?」
多くの場合まともな答が返ってこないので、こう指示することになる。
「教科書でも辞書でも、何を見てもいいから調べろ!」
辞書類や教科書、参考書などは豊富に揃えてある。
何とか自力で答えさせたいのだ。
用語の意味(定義)について追及されたとき、多くの生徒は辞書を引く。
「わかりました」と言うので確認しに行くと、辞書の説明をそのまま読み上げる。
本当は全く理解できていないことはすぐわかる。
途中でつっかえたり、変な所で区切ったりするのだ。
「で、その説明でわかった?」と聞くと首をかしげる...。
そりゃあそうだ。
例えば「圧力」を国語辞典で引いても、「力」との違いは書かれていない。
私が問うているのは、理科における「圧力」の定義なのだ。
結局、教科書や参考書で調べ直すよう指導することが多い。
ともあれ、わからなかったらまず自分で調べる、
それでもわからなかったら質問する、という姿勢だけは身につけさせたいのだ。
ところが、この当たり前の習慣がついていない大人が多いようだ。
少し前の信毎の記事だが、文化庁の国語に関する世論調査の結果が載っていた。
新聞や雑誌の漢字が読めずに困った経験がある人は41%だった。
以下は、その場合の調べ方に対する回答だ。
「本の形の辞書」が30%。
「携帯電話の漢字変換」が26%。
「電子辞書」12%。
「インターネット上の辞書」11%。
「ワープロ、パソコンの漢字変換」7%。
世代によって、紙の辞書から電子媒体へ大きな変化があるのは当然だが、
ここまでは、とにかく調べようという気持ちはある。
問題は次だ。
「調べない」34%
なんと、これが最も多かったのだ!
紙の辞書しかなかった時代ならわかる。
出先で辞書が近くになかったのなら仕方ない。
広辞苑のような大きな辞書では引くのが億劫で...というのもまだ理解できる。
しかし、今の時代なら先に挙げたような手軽な方法が複数ある。
いつでも、どこでもの範囲は飛躍的に広がったし、
昔より遙かに少ない手間で調べることもできるようになった。
それなのに、面倒だから調べないという回答がこれほど多いとは...。
知識欲の低下...?
こだわりの無さ...?
情報過多の影響...?
いろいろ考えさせられる調査結果であった。
一番怖ろしいのは、何に対してもこだわらず、深く考えようとしない人間が増えることだ。
私自身は「わからなかったら調べる」という基本姿勢だけは忘れたくないし、
子どもたちにもそれを訴え続けていきたいと思っている。

私はでき具合を確認し、質問はないかと問う。
「ありません」と答えると、こちらから質問だ。
「円周率って、何の何に対する率?」
「力と圧力の違いは何?」
「公地公民ってどういうこと?」
多くの場合まともな答が返ってこないので、こう指示することになる。
「教科書でも辞書でも、何を見てもいいから調べろ!」
辞書類や教科書、参考書などは豊富に揃えてある。
何とか自力で答えさせたいのだ。
用語の意味(定義)について追及されたとき、多くの生徒は辞書を引く。
「わかりました」と言うので確認しに行くと、辞書の説明をそのまま読み上げる。
本当は全く理解できていないことはすぐわかる。
途中でつっかえたり、変な所で区切ったりするのだ。
「で、その説明でわかった?」と聞くと首をかしげる...。
そりゃあそうだ。
例えば「圧力」を国語辞典で引いても、「力」との違いは書かれていない。
私が問うているのは、理科における「圧力」の定義なのだ。
結局、教科書や参考書で調べ直すよう指導することが多い。
ともあれ、わからなかったらまず自分で調べる、
それでもわからなかったら質問する、という姿勢だけは身につけさせたいのだ。
ところが、この当たり前の習慣がついていない大人が多いようだ。
少し前の信毎の記事だが、文化庁の国語に関する世論調査の結果が載っていた。
新聞や雑誌の漢字が読めずに困った経験がある人は41%だった。
以下は、その場合の調べ方に対する回答だ。
「本の形の辞書」が30%。
「携帯電話の漢字変換」が26%。
「電子辞書」12%。
「インターネット上の辞書」11%。
「ワープロ、パソコンの漢字変換」7%。
世代によって、紙の辞書から電子媒体へ大きな変化があるのは当然だが、
ここまでは、とにかく調べようという気持ちはある。
問題は次だ。
「調べない」34%
なんと、これが最も多かったのだ!
紙の辞書しかなかった時代ならわかる。
出先で辞書が近くになかったのなら仕方ない。
広辞苑のような大きな辞書では引くのが億劫で...というのもまだ理解できる。
しかし、今の時代なら先に挙げたような手軽な方法が複数ある。
いつでも、どこでもの範囲は飛躍的に広がったし、
昔より遙かに少ない手間で調べることもできるようになった。
それなのに、面倒だから調べないという回答がこれほど多いとは...。
知識欲の低下...?
こだわりの無さ...?
情報過多の影響...?
いろいろ考えさせられる調査結果であった。
一番怖ろしいのは、何に対してもこだわらず、深く考えようとしない人間が増えることだ。
私自身は「わからなかったら調べる」という基本姿勢だけは忘れたくないし、
子どもたちにもそれを訴え続けていきたいと思っている。

2010年09月12日
酒の味を「覚える」
言語力を育てる教材を製作中である。
まずは中学生向けのものから...。
著作権に抵触しないよう、「青空文庫」に収録されているものを題材にする。
第一弾は新美南吉作「おじいさんのランプ」である。
この話、おぼろげな記憶はあったのだが、
今回改めて読んでみて、素晴らしい作品であることを再認識した。
ぜひ皆さんにご一読いただきたい。
さて、これを元に様々な問題を作っているのだが、
市販の国語問題集とは一線も二線も画するものをということで、とても時間がかかる。
なんとか早めに仕上げたいのだが、遅々として進まない...。
物語の中盤、孤児だった主人公の「巳之助」はランプ屋で成功し、
立派に一家を支えるまでになった。
一部を抜粋する。
巳之助はもう、男ざかりの大人であった。家には子供が二人あった。「自分もこれで
どうやらひとり立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまではいっていない
けれども」と、ときどき思って見て、そのつど心に満足を覚えるのであった。
ここの「満足を覚える」という表現を題材にしようと考えた。
「覚える」を他の言葉に言い換えるとどうなるかを考えさせるのだ。
...ここではもちろん「感じる」、あるいは「思う」が正解となろう。
「違和感を覚える」「痛みを覚える」などと同じだ、
改めて読み返すと、今の部分のすぐ前にも「おぼえる」があった。
こちらは平仮名だ。
字が読めなかった巳之助は、区長に字を教わる。
熱心だったので一年もすると、巳之助は尋常科を卒業した村人の誰にも負けないくらい
読めるようになった。
そして巳之助は書物を読むことをおぼえた。
この「おぼえる」はどうだろう?
先ほどの「覚える」とは明らかに意味が違う。
だからこそ、作者もあえて平仮名にしたのかも知れない。
言い換えればどうなるか...。
いっそのこと、いろいろな「覚える」を登場させて、
その使い分けを意識させる問題にしようかと考えた。
まずは辞書を引いてみる。
「広辞苑」は古語辞典の役割も兼ね備えているので、
「覚える」で引くと「覚ゆ」を見ろとあった。
古語としての意味は省いて紹介する。
①自ずとそう思われる。感じる。
②記憶する
③学んで知る。教えられて習得する。
続いて「旺文社国語辞典」。
①記憶する。忘れずに心にとどめる。暗記する。
②学ぶ。会得する。
③感じる。
さて、「書物を読むことをおぼえる」はどれにあたるだろう...。
近いのは「学んで知る。教えられて習得する。」と「学ぶ。会得する。」だが、
なにか違う気もする。
「仕事を覚える」や「料理を覚える」なら
「学んで」「習得する」というイメージでピッタリなのだが...。
この場合、読めなかった字を熱心に学び、ついに読めるようになった。
字を読むことを習得した、つまり「字を覚えた」のだ。
その結果として「書物を読むこと」が可能になっただけだ。
書物の読み方を学んだわけではない...。
困ったときは「新解さん(新明解国語辞典)」だ。
①心やからだで、そう感じる。
②(経験した事や習得した事を)忘れられないものとして心にとどめる。記憶する。
③(習得した事を)身につける。体得する。
④「思われる」意の老人語。
特筆すべきは②だ。
単に暗記する、記憶するではなく、しっかりと心に刻み込むというニュアンスが感じられる。
ただ、ここに挙げられている文例がピンとこない。
「酒の味を覚える」
これは記憶するわけでも、心にとどめるわけでもない。
「知る」「知り始める」くらいの意味ではないだろうか...。
先に挙げた「書物を読むことをおぼえた」も、私はこれと同じだ解釈している。
字を読むことを習得して、本を読むことを知ったのだ。
辞書に「覚える」の意味を追加してほしいところだ。
皆さん、どう思われますか?
「酒の味を覚える」を「習得する」や「記憶する」で説明されて腑に落ちますか?ぜひご意見をお聞かせください。

まずは中学生向けのものから...。
著作権に抵触しないよう、「青空文庫」に収録されているものを題材にする。
第一弾は新美南吉作「おじいさんのランプ」である。
この話、おぼろげな記憶はあったのだが、
今回改めて読んでみて、素晴らしい作品であることを再認識した。
ぜひ皆さんにご一読いただきたい。
さて、これを元に様々な問題を作っているのだが、
市販の国語問題集とは一線も二線も画するものをということで、とても時間がかかる。
なんとか早めに仕上げたいのだが、遅々として進まない...。
物語の中盤、孤児だった主人公の「巳之助」はランプ屋で成功し、
立派に一家を支えるまでになった。
一部を抜粋する。
巳之助はもう、男ざかりの大人であった。家には子供が二人あった。「自分もこれで
どうやらひとり立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまではいっていない
けれども」と、ときどき思って見て、そのつど心に満足を覚えるのであった。
ここの「満足を覚える」という表現を題材にしようと考えた。
「覚える」を他の言葉に言い換えるとどうなるかを考えさせるのだ。
...ここではもちろん「感じる」、あるいは「思う」が正解となろう。
「違和感を覚える」「痛みを覚える」などと同じだ、
改めて読み返すと、今の部分のすぐ前にも「おぼえる」があった。
こちらは平仮名だ。
字が読めなかった巳之助は、区長に字を教わる。
熱心だったので一年もすると、巳之助は尋常科を卒業した村人の誰にも負けないくらい
読めるようになった。
そして巳之助は書物を読むことをおぼえた。
この「おぼえる」はどうだろう?
先ほどの「覚える」とは明らかに意味が違う。
だからこそ、作者もあえて平仮名にしたのかも知れない。
言い換えればどうなるか...。
いっそのこと、いろいろな「覚える」を登場させて、
その使い分けを意識させる問題にしようかと考えた。
まずは辞書を引いてみる。
「広辞苑」は古語辞典の役割も兼ね備えているので、
「覚える」で引くと「覚ゆ」を見ろとあった。
古語としての意味は省いて紹介する。
①自ずとそう思われる。感じる。
②記憶する
③学んで知る。教えられて習得する。
続いて「旺文社国語辞典」。
①記憶する。忘れずに心にとどめる。暗記する。
②学ぶ。会得する。
③感じる。
さて、「書物を読むことをおぼえる」はどれにあたるだろう...。
近いのは「学んで知る。教えられて習得する。」と「学ぶ。会得する。」だが、
なにか違う気もする。
「仕事を覚える」や「料理を覚える」なら
「学んで」「習得する」というイメージでピッタリなのだが...。
この場合、読めなかった字を熱心に学び、ついに読めるようになった。
字を読むことを習得した、つまり「字を覚えた」のだ。
その結果として「書物を読むこと」が可能になっただけだ。
書物の読み方を学んだわけではない...。
困ったときは「新解さん(新明解国語辞典)」だ。
①心やからだで、そう感じる。
②(経験した事や習得した事を)忘れられないものとして心にとどめる。記憶する。
③(習得した事を)身につける。体得する。
④「思われる」意の老人語。
特筆すべきは②だ。
単に暗記する、記憶するではなく、しっかりと心に刻み込むというニュアンスが感じられる。
ただ、ここに挙げられている文例がピンとこない。
「酒の味を覚える」
これは記憶するわけでも、心にとどめるわけでもない。
「知る」「知り始める」くらいの意味ではないだろうか...。
先に挙げた「書物を読むことをおぼえた」も、私はこれと同じだ解釈している。
字を読むことを習得して、本を読むことを知ったのだ。
辞書に「覚える」の意味を追加してほしいところだ。
皆さん、どう思われますか?
「酒の味を覚える」を「習得する」や「記憶する」で説明されて腑に落ちますか?ぜひご意見をお聞かせください。

2010年09月04日
英語ならかっこいいのか!?
今日も信濃毎日新聞の投稿欄「建設標」から...。
「意味分からない横文字はやめて」というタイトルである。
カタカナ語の氾濫は目に余るものがある。
特にお役所や医療関係のそれが多く、
わかりやすい日本語に直そうとする努力を怠っていると批判を浴びてきた。
最近は少しはましになったようにも感じるが、
お年寄りからのこういう投書は後を絶たない。
今回も、内心「またか...」という軽い気持ちで読んでみたのだが、
思わず膝を打ってしまった。
私もつい最近「なんだこりゃ?」と思った言葉だったからである。
「信州デスティネーションキャンペーン」
県の観光PRのキャッチフレーズだ。
初めて聞いたとき「ん?」と思った。
響きはいいのだが、意味がさっぱりわからない。
destiny=「運命」から連想してみたが、観光にふさわしい内容に結びつかない。
「信州再発見」とか「信州の魅力を根源から探ろう」くらいの意味だろうと、
きわめて感覚的に推測していた。
辞書を引いてみると、destinationは「目的地、行き先」だ。
すると「信州行き先キャンペーン」???
だったら素直に「信州へ行こう」の方がよほどわかりやすいだろうに...。
カタカナは外来語を表すのに便利だが、
個人的にはなんだか軽い感じがして好きになれない。
10年続けている塾は、引き継ぎだったのでカタカナ名のままだが、本当は漢字を使いたい。
昨年から始めた2教室目は、思いっきり漢字の塾名にして道場風の看板を掲げている。
英語を使えばおしゃれで洗練された感じがするという思惑があるのかも知れないが、
してみると、かなり年配の担当者の発想か...。
文明開化の時代や戦後の復興期ではあるまいし、
いまどきそんな浅知恵はかえってみっともないと思うのだが...。
庶民をばかにするのもいい加減にしてほしい。

「意味分からない横文字はやめて」というタイトルである。
カタカナ語の氾濫は目に余るものがある。
特にお役所や医療関係のそれが多く、
わかりやすい日本語に直そうとする努力を怠っていると批判を浴びてきた。
最近は少しはましになったようにも感じるが、
お年寄りからのこういう投書は後を絶たない。
今回も、内心「またか...」という軽い気持ちで読んでみたのだが、
思わず膝を打ってしまった。
私もつい最近「なんだこりゃ?」と思った言葉だったからである。
「信州デスティネーションキャンペーン」
県の観光PRのキャッチフレーズだ。
初めて聞いたとき「ん?」と思った。
響きはいいのだが、意味がさっぱりわからない。
destiny=「運命」から連想してみたが、観光にふさわしい内容に結びつかない。
「信州再発見」とか「信州の魅力を根源から探ろう」くらいの意味だろうと、
きわめて感覚的に推測していた。
辞書を引いてみると、destinationは「目的地、行き先」だ。
すると「信州行き先キャンペーン」???
だったら素直に「信州へ行こう」の方がよほどわかりやすいだろうに...。
カタカナは外来語を表すのに便利だが、
個人的にはなんだか軽い感じがして好きになれない。
10年続けている塾は、引き継ぎだったのでカタカナ名のままだが、本当は漢字を使いたい。
昨年から始めた2教室目は、思いっきり漢字の塾名にして道場風の看板を掲げている。
英語を使えばおしゃれで洗練された感じがするという思惑があるのかも知れないが、
してみると、かなり年配の担当者の発想か...。
文明開化の時代や戦後の復興期ではあるまいし、
いまどきそんな浅知恵はかえってみっともないと思うのだが...。
庶民をばかにするのもいい加減にしてほしい。

2010年09月02日
「個性」のはき違え
一昨日の信濃毎日新聞にこんな投書が載っていた。
「正しい日本語で書く力を鍛えて」と題する40代主婦の文章だ。
内容を要約する。
新聞の投稿を利用して国語力を高めようとする上諏訪中学の取り組みは素晴らしい。
私が小学生の頃は、作文におかしな点があれば先生が注意してくれたが、
最近は誤字、脱字、表現の誤用などが見過ごされたままのものが少なくない。
作文限らず「子供が表現したものを大人が修正すれば、その子の個性を否定してしまう」と
考える傾向があるようだ。
しかし、文章で個性を発揮するためには、正しい日本語の知識や正確に伝えるための
表現技法を学ぶことは必須である。
書く力を鍛錬する上諏訪中の取り組みが広がってほしい。
問題は中ほどにある「個性を否定してしまう」という考え方である。
投稿者も「傾向があるようだ」という表現に留めているように、
教師などから直接その言葉を聞いたわけではないのかも知れない。
忙しさで、一人一人の作文をじっくり添削している時間など取れないという実状もあるだろう。
しかし、火のない所に煙は立たない。
何でもかんでも個性、個性と、
その意味をはき違えているのでは?と思う例も少なからず見聞している。
ろくな挨拶もできなかったり、大人に対する言葉遣いが乱れたりしていても、
強制はよくない、個性を潰すと、毅然とした態度が取れない。
好きな科目を伸ばした方が個性が磨かれてよい、
嫌いな科目を無理にさせることはないと、早々に見切りをつけてしまう親もいる。
子どもの方もそんな大人の思いを感じて、
なにも無理する必要はない、これが自分の個性だと、努力することを放棄してしまう...。
だが、投稿者も指摘しているように、
個性というのは最低限の知識や技量を身につけた上に形成されるものではないのか。
各人の思想や文章の主旨まで踏み込むことは許されない。
大人受けするような、正論ばかりの作文に仕向けることも厳禁である。
しかし、日本語として間違っている字、言葉、文や、
論理が破綻したりわかりにくい文章については、的確なアドバイスを惜しんではならない。
前にも書いたが、学校の国語教育では作品の鑑賞にばかり重きが置かれ、「正しい感じ方」を強要される。
一方で「書く力」については個性を、というのでは話が全く逆である。
感じ方や主張は個性に任せ、「伝える日本語」を磨く練習こそ厳格に行うべきである。

「正しい日本語で書く力を鍛えて」と題する40代主婦の文章だ。
内容を要約する。
新聞の投稿を利用して国語力を高めようとする上諏訪中学の取り組みは素晴らしい。
私が小学生の頃は、作文におかしな点があれば先生が注意してくれたが、
最近は誤字、脱字、表現の誤用などが見過ごされたままのものが少なくない。
作文限らず「子供が表現したものを大人が修正すれば、その子の個性を否定してしまう」と
考える傾向があるようだ。
しかし、文章で個性を発揮するためには、正しい日本語の知識や正確に伝えるための
表現技法を学ぶことは必須である。
書く力を鍛錬する上諏訪中の取り組みが広がってほしい。
問題は中ほどにある「個性を否定してしまう」という考え方である。
投稿者も「傾向があるようだ」という表現に留めているように、
教師などから直接その言葉を聞いたわけではないのかも知れない。
忙しさで、一人一人の作文をじっくり添削している時間など取れないという実状もあるだろう。
しかし、火のない所に煙は立たない。
何でもかんでも個性、個性と、
その意味をはき違えているのでは?と思う例も少なからず見聞している。
ろくな挨拶もできなかったり、大人に対する言葉遣いが乱れたりしていても、
強制はよくない、個性を潰すと、毅然とした態度が取れない。
好きな科目を伸ばした方が個性が磨かれてよい、
嫌いな科目を無理にさせることはないと、早々に見切りをつけてしまう親もいる。
子どもの方もそんな大人の思いを感じて、
なにも無理する必要はない、これが自分の個性だと、努力することを放棄してしまう...。
だが、投稿者も指摘しているように、
個性というのは最低限の知識や技量を身につけた上に形成されるものではないのか。
各人の思想や文章の主旨まで踏み込むことは許されない。
大人受けするような、正論ばかりの作文に仕向けることも厳禁である。
しかし、日本語として間違っている字、言葉、文や、
論理が破綻したりわかりにくい文章については、的確なアドバイスを惜しんではならない。
前にも書いたが、学校の国語教育では作品の鑑賞にばかり重きが置かれ、「正しい感じ方」を強要される。
一方で「書く力」については個性を、というのでは話が全く逆である。
感じ方や主張は個性に任せ、「伝える日本語」を磨く練習こそ厳格に行うべきである。

2010年08月31日
辞書に頼るな!
県下で一、二を争う「進学校」に通う高校2年生(♂)の話だ。
さすがにどの教科も進みが速く、英語もかなり難しめのテキストをやっている。
この子、中学時代から決して英語は不得意ではなく、
今でもほぼ十分な理解ができている。
ただ一つ、悪い癖がある。
どうしても和訳したがるのだ。和訳を求められているわけではない。
内容についての質問に答えられればいいのだが、
一々日本語に置き換えないと気が済まないらしい。
「言っていることはわかるけど日本語にできない」と訴えてくる。
内容がつかめていればそれでいい、
英語を英語のまま理解する方がよほど大切だと言うのだが、聞く耳を持たない。
結果、いかにも「翻訳」という、ゴツゴツした和訳を作って満足している。
おまけにと言うべきか、だからと言うべきか、辞書を過信している。
辞書に載っていない日本語は認められないらしい。
しかも私の大嫌いな電子辞書なので、用例もよく見ずに「訳せない」と言ってくる。
この前は issue という単語だった。
前後の文脈から判断して、私は「問題」くらいの意味だろうと教えた。
すると彼が言う。
「issue に「問題」なんて意味あるんですか?」
私はそのとき、おぼろげな記憶でその意味があると思ったのだが、
あまりにも辞書にこだわりすぎる彼の言いぐさに、思わずこう叫んでいた。
「辞書に載っていようがいまいが、ここでは「問題」という意味になるんだ!」
後から確認したら、確かに issue に「問題」が載っていた。
しかし仮に載っていなかったとしても、私は訂正するつもりはない。
あそこでの意味はそれしかなかった。
辞書は決して万能ではない。
あくまでも参考に留めるべきであろう。
世界中で何億、何十億という人間が今も使い続けている、
そのすべての意味が辞書に網羅されているはずはないのだ。
日本語だってそういう例はいくらでもある。
辞書を引いてもピンと来ないなんてことは日常茶飯事だ。
たとえば、今思いついて引いてみた「提供」という言葉。
広辞苑は「さし出して相手の用に供すること」、
旺文社国語辞典は「他の人々の役に立てるために差し出すこと」としか載っていない。
日本語を勉強する外国人が、テレビで「提供は○○です」という表現を耳にして調べても、
辞書ではラチがあかないことは明かであろう。
(さすがに「新解さん」(新明解)には「②商業放送番組に出資すること」というのがあった。)
さて、彼がいつ目覚めてくれるか...。
和訳の呪縛から解き放たれたとき、
もっと速く、もっと大量の英文を読めるようになるはずだ。
そうすれば英文感覚もさらに磨かれ、英語が益々楽しくなることは間違いない。

さすがにどの教科も進みが速く、英語もかなり難しめのテキストをやっている。
この子、中学時代から決して英語は不得意ではなく、
今でもほぼ十分な理解ができている。
ただ一つ、悪い癖がある。
どうしても和訳したがるのだ。和訳を求められているわけではない。
内容についての質問に答えられればいいのだが、
一々日本語に置き換えないと気が済まないらしい。
「言っていることはわかるけど日本語にできない」と訴えてくる。
内容がつかめていればそれでいい、
英語を英語のまま理解する方がよほど大切だと言うのだが、聞く耳を持たない。
結果、いかにも「翻訳」という、ゴツゴツした和訳を作って満足している。
おまけにと言うべきか、だからと言うべきか、辞書を過信している。
辞書に載っていない日本語は認められないらしい。
しかも私の大嫌いな電子辞書なので、用例もよく見ずに「訳せない」と言ってくる。
この前は issue という単語だった。
前後の文脈から判断して、私は「問題」くらいの意味だろうと教えた。
すると彼が言う。
「issue に「問題」なんて意味あるんですか?」
私はそのとき、おぼろげな記憶でその意味があると思ったのだが、
あまりにも辞書にこだわりすぎる彼の言いぐさに、思わずこう叫んでいた。
「辞書に載っていようがいまいが、ここでは「問題」という意味になるんだ!」
後から確認したら、確かに issue に「問題」が載っていた。
しかし仮に載っていなかったとしても、私は訂正するつもりはない。
あそこでの意味はそれしかなかった。
辞書は決して万能ではない。
あくまでも参考に留めるべきであろう。
世界中で何億、何十億という人間が今も使い続けている、
そのすべての意味が辞書に網羅されているはずはないのだ。
日本語だってそういう例はいくらでもある。
辞書を引いてもピンと来ないなんてことは日常茶飯事だ。
たとえば、今思いついて引いてみた「提供」という言葉。
広辞苑は「さし出して相手の用に供すること」、
旺文社国語辞典は「他の人々の役に立てるために差し出すこと」としか載っていない。
日本語を勉強する外国人が、テレビで「提供は○○です」という表現を耳にして調べても、
辞書ではラチがあかないことは明かであろう。
(さすがに「新解さん」(新明解)には「②商業放送番組に出資すること」というのがあった。)
さて、彼がいつ目覚めてくれるか...。
和訳の呪縛から解き放たれたとき、
もっと速く、もっと大量の英文を読めるようになるはずだ。
そうすれば英文感覚もさらに磨かれ、英語が益々楽しくなることは間違いない。

2010年08月12日
暑さで豊作~ちょっと変な日本語3~
コンビニで電話料金を支払った。
3,231円だったので、3,235円出す。
店員が言った。「3,231円ですね。」
一瞬「あれ?」と思ったが、たいして気にもせずお釣りを待つ。
ところが領収証をよこしたきりで、一件落着という顔をしている。
「お釣り...」と言うと、けげんそうな顔で金額を確かめ、
「あ!五円でしたね。失礼しました。
暑さでぼけてしまって...。」
冷房の効いた中にいてもぼけるのだ。
ラジオやテレビから流れる変な日本語も絶好調...!
その1:SBCラジオのニュース。スイスの氷河特急脱線事故の続報。
脱線に不具合があったのではと...
不具合があったかも知れないのは線路だろう。
脱線そのものは「不具合」に決まっている。
その2:同じくSBCラジオ。どこかの行事の報告だ。
炎天下のもと...
「炎天下」とは「炎天のもと」を意味する。
完全に言葉がダブっている...。
その3:CS「GAORA」の野球中継。
下柳から一発を浴びせました。
「下柳に」とするか「下柳から一発を放ちました」とすべし。
その4:天下のNHKラジオ。天気予報の際のアドバイス。
水分補給などこまめに摂って...
これもダブり。
「水分などこまめに摂って」、または「水分補給などをこまめに行って」にしてもらいたい。
※ 明日から3日間千葉の実家に帰省するので、新着記事はお休みです...。

3,231円だったので、3,235円出す。
店員が言った。「3,231円ですね。」
一瞬「あれ?」と思ったが、たいして気にもせずお釣りを待つ。
ところが領収証をよこしたきりで、一件落着という顔をしている。
「お釣り...」と言うと、けげんそうな顔で金額を確かめ、
「あ!五円でしたね。失礼しました。
暑さでぼけてしまって...。」
冷房の効いた中にいてもぼけるのだ。
ラジオやテレビから流れる変な日本語も絶好調...!
その1:SBCラジオのニュース。スイスの氷河特急脱線事故の続報。
脱線に不具合があったのではと...
不具合があったかも知れないのは線路だろう。
脱線そのものは「不具合」に決まっている。
その2:同じくSBCラジオ。どこかの行事の報告だ。
炎天下のもと...
「炎天下」とは「炎天のもと」を意味する。
完全に言葉がダブっている...。
その3:CS「GAORA」の野球中継。
下柳から一発を浴びせました。
「下柳に」とするか「下柳から一発を放ちました」とすべし。
その4:天下のNHKラジオ。天気予報の際のアドバイス。
水分補給などこまめに摂って...
これもダブり。
「水分などこまめに摂って」、または「水分補給などをこまめに行って」にしてもらいたい。
※ 明日から3日間千葉の実家に帰省するので、新着記事はお休みです...。

2010年08月11日
行くも帰るも
これやこの 行くも帰るも 別れては
知るも知らぬも 逢坂の関
言わずと知れた蝉丸の歌である。
百人一首で最も有名な歌と言ってもいいだろう。
「坊主めくり」のとき、名前も姿も坊主らしからぬ蝉丸が出ると、
思わず笑いが出たものだ。
ここでいう「行く」「帰る」は畿内を中心にしている。
そこから出て行く者を「行く」、戻ってくる者を「帰る」と言っているのだ。
視点が変われば、当然「行く」「帰る」は逆転する。
そのため、各人によって視点がバラバラでは困ることには、
明確な基準を設けて誤解が生じないようにしなければならない。
鉄道の「上り」「下り」は最もわかりやすい例だろう。
東京駅に近づく方が「上り」、逆が「下り」である。
東京との直線距離ではなく、東京に行くために結果的に向かう方向が「上り」となる。
たとえば須坂の方が長野よりわずかに東京に近いが、
実際に東京に行くには一度長野に出なくてはならない。
従って須坂→長野が「上り」である。
因みに塩尻駅は、中央本線がここを境に運行系統が分かれているため、
新宿へ向かう列車も名古屋方面の電車も、ともに「上り」という異色の駅だ。
ぐるっと回る山手線や大阪環状線は「内回り」「外回り」で区別。
途中で東京駅を経由する京浜東北線は「北行」「南行」で分けている。
東京の外側を大きく回る武蔵野線は、なぜか西船橋→府中本町が「上り」。
一応、千葉県より東京都の方を上に置いているのか...。
近鉄や名鉄など、路線も複雑で多くの主要駅を結んでいる私鉄では、
「上り」「下り」の基準をどう定めているのか興味深いところである。
生徒が帰りがけにこう言った。
「水曜日は用事で行けません。」
ん?どこに...?
塾に来られないって意味?
自分が今その場所にいるのに「行けません」はおかしくない?
逆に電話で「今日来てもいいですか?」と聞いてくる場合もある。
かなりの違和感だ。
英語では、たとえば母親に「ごはんだよ」と言われたときの「今行くよ」は、
go は使わずに I'm coming. と言う。
使い分けは
come : 話題・意識の中心への移動/正常・望ましい状態への変化
go : 話題・意識から外への移動/異常・望ましくない状態への変化
...ということらしい。
生徒の「来てもいいですか?」にもその意識が含まれているのだろうか。
まさかそんなことはあるまいが、いずれにしても日本語としてはかなり不自然であろう。

知るも知らぬも 逢坂の関
言わずと知れた蝉丸の歌である。
百人一首で最も有名な歌と言ってもいいだろう。
「坊主めくり」のとき、名前も姿も坊主らしからぬ蝉丸が出ると、
思わず笑いが出たものだ。
ここでいう「行く」「帰る」は畿内を中心にしている。
そこから出て行く者を「行く」、戻ってくる者を「帰る」と言っているのだ。
視点が変われば、当然「行く」「帰る」は逆転する。
そのため、各人によって視点がバラバラでは困ることには、
明確な基準を設けて誤解が生じないようにしなければならない。
鉄道の「上り」「下り」は最もわかりやすい例だろう。
東京駅に近づく方が「上り」、逆が「下り」である。
東京との直線距離ではなく、東京に行くために結果的に向かう方向が「上り」となる。
たとえば須坂の方が長野よりわずかに東京に近いが、
実際に東京に行くには一度長野に出なくてはならない。
従って須坂→長野が「上り」である。
因みに塩尻駅は、中央本線がここを境に運行系統が分かれているため、
新宿へ向かう列車も名古屋方面の電車も、ともに「上り」という異色の駅だ。
ぐるっと回る山手線や大阪環状線は「内回り」「外回り」で区別。
途中で東京駅を経由する京浜東北線は「北行」「南行」で分けている。
東京の外側を大きく回る武蔵野線は、なぜか西船橋→府中本町が「上り」。
一応、千葉県より東京都の方を上に置いているのか...。
近鉄や名鉄など、路線も複雑で多くの主要駅を結んでいる私鉄では、
「上り」「下り」の基準をどう定めているのか興味深いところである。
生徒が帰りがけにこう言った。
「水曜日は用事で行けません。」
ん?どこに...?
塾に来られないって意味?
自分が今その場所にいるのに「行けません」はおかしくない?
逆に電話で「今日来てもいいですか?」と聞いてくる場合もある。
かなりの違和感だ。
英語では、たとえば母親に「ごはんだよ」と言われたときの「今行くよ」は、
go は使わずに I'm coming. と言う。
使い分けは
come : 話題・意識の中心への移動/正常・望ましい状態への変化
go : 話題・意識から外への移動/異常・望ましくない状態への変化
...ということらしい。
生徒の「来てもいいですか?」にもその意識が含まれているのだろうか。
まさかそんなことはあるまいが、いずれにしても日本語としてはかなり不自然であろう。

2010年08月06日
どっちの応援?
昨日あるブログを見ていて、また一つ日本語の面白さに気づいた。
実際は野球の話だったのだが、ここでは相撲にたとえることにする。
まだ朝青龍が現役だった頃の話としよう。
白鵬と朝青龍の両横綱が14日目まで全勝。
千秋楽結びの一番に優勝を懸けるとする。
TVを観ていた人がこう言った。
今日は朝青龍に勝ってほしいな。
さて、この人はどちらを応援していると思いますか...?
おそらく8割以上の人が「朝青龍」と答えるだろう。妻に聞いてもそう言った。
それ以外にどんな解釈があるのか、という表情だ。
でも今回のブログの場合は(実際には野球の話だが)、そんなことはあり得ない。
だってこのブログは、白鵬ファンの管理人が彼を応援するために書いているのだから...。
(因みに私は、このたとえでは朝青龍ファンである。)
私も初めは「え?なぜ?」と思ったが、
すぐに納得が行った。
管理人は「白鵬が朝青龍に勝つ」ことを望んでいるのである。
つまりこの文は、意味が二通りに解釈できる曖昧な文ということだ。
①朝青龍が勝ってほしい。
・朝青龍の勝利を望む、朝青龍に望むものは勝利という意味。
・英語なら I want Asashoryu to beat Hakuho.
②白鵬が勝ってほしい。
・白鵬が「朝青龍に勝つ」ことを望むという意味。
・英語なら I want Hakuho to beat Asashoryu.
今回は話者の立場が明らかなので、なんとか②の意味に取れたが、
予備知識なしに読めば、①の解釈の方が優勢であろう。
「白鵬が勝ってほしい」とか「朝青龍を敗ってほしい」とすれば誤解はなかろうが...。
試しにYahoo Japanの翻訳機能を使ってみた。
「朝青龍に勝ってほしい」は I want Asashoryu to win.(①)、
「白鵬に朝青龍に勝ってほしい」は I want Hakuho to beat Asashoryu.(②)でうまく行くが、
正確さを期して「白鵬が朝青龍に...」とすると Hakuho wants Asashoryu to win. になってしまう...。
日本語は実に面白い...。

実際は野球の話だったのだが、ここでは相撲にたとえることにする。
まだ朝青龍が現役だった頃の話としよう。
白鵬と朝青龍の両横綱が14日目まで全勝。
千秋楽結びの一番に優勝を懸けるとする。
TVを観ていた人がこう言った。
今日は朝青龍に勝ってほしいな。
さて、この人はどちらを応援していると思いますか...?
おそらく8割以上の人が「朝青龍」と答えるだろう。妻に聞いてもそう言った。
それ以外にどんな解釈があるのか、という表情だ。
でも今回のブログの場合は(実際には野球の話だが)、そんなことはあり得ない。
だってこのブログは、白鵬ファンの管理人が彼を応援するために書いているのだから...。
(因みに私は、このたとえでは朝青龍ファンである。)
私も初めは「え?なぜ?」と思ったが、
すぐに納得が行った。
管理人は「白鵬が朝青龍に勝つ」ことを望んでいるのである。
つまりこの文は、意味が二通りに解釈できる曖昧な文ということだ。
①朝青龍が勝ってほしい。
・朝青龍の勝利を望む、朝青龍に望むものは勝利という意味。
・英語なら I want Asashoryu to beat Hakuho.
②白鵬が勝ってほしい。
・白鵬が「朝青龍に勝つ」ことを望むという意味。
・英語なら I want Hakuho to beat Asashoryu.
今回は話者の立場が明らかなので、なんとか②の意味に取れたが、
予備知識なしに読めば、①の解釈の方が優勢であろう。
「白鵬が勝ってほしい」とか「朝青龍を敗ってほしい」とすれば誤解はなかろうが...。
試しにYahoo Japanの翻訳機能を使ってみた。
「朝青龍に勝ってほしい」は I want Asashoryu to win.(①)、
「白鵬に朝青龍に勝ってほしい」は I want Hakuho to beat Asashoryu.(②)でうまく行くが、
正確さを期して「白鵬が朝青龍に...」とすると Hakuho wants Asashoryu to win. になってしまう...。
日本語は実に面白い...。





