2010年05月31日
素材11
久々の「素材」シリーズ。
思考力・言語力を育てる教材の例です。
今回は中級編。
以前読んだ秋山仁氏の著書から拝借しました。
問:ハンバーガーを作ります。
肉を片面焼くのに7分(両面で14分)、
具材をパンに挟んでレンジで仕上げるのに1分かかります。
使える器具は一度に2枚焼けるフライパンと、一度に2個調理できるレンジだけです。
この条件で、最も短時間で3個のハンバーガーを作る手順を説明しなさい。

思考力・言語力を育てる教材の例です。
今回は中級編。
以前読んだ秋山仁氏の著書から拝借しました。
問:ハンバーガーを作ります。
肉を片面焼くのに7分(両面で14分)、
具材をパンに挟んでレンジで仕上げるのに1分かかります。
使える器具は一度に2枚焼けるフライパンと、一度に2個調理できるレンジだけです。
この条件で、最も短時間で3個のハンバーガーを作る手順を説明しなさい。

2010年05月30日
型にとらわれるな
おうぎ形の問題は苦手とする子が多い。
円の一部と考えれば難しくないはずだが、なぜか戸惑う。
たとえばこんな問題だ。
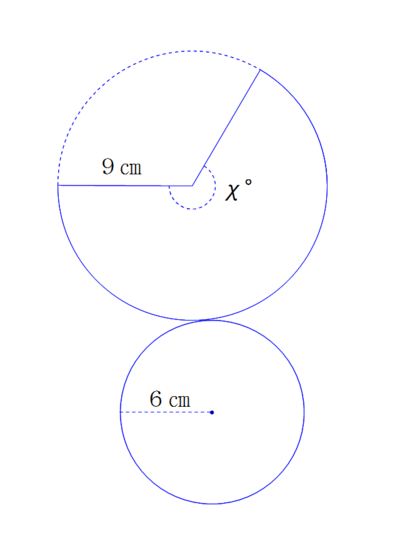
中心角をx°としてπ(パイ)r2乗*(かける)x/360まで書いて、そこでペンが止まってしまう...。
当然である。
これは、中心角がわかっているときにおうぎ形の面積を出す「公式」として教科書に載っているものだ。上図のおうぎ形の面積が示されていればまだ使えるが(それでも計算は面倒になる)、
この場合は使い途がない。ところが多くの生徒は、
「おうぎ形」と聞いた途端、反射的にこの式を書きたがるのだ。
あまりにも型にとらわれすぎている...。
この問題は、扇形の弧の長さと円周を比べれば簡単に解ける。
おうぎ形がその一部となる仮想円の半径は6cmなので直径は12cm。
従って円周は12πcm。
おうぎ形の弧の長さは4πcmなので、このおうぎ形は円の1/3(4π/12π)であることがわかる。
ならば中心角も円の1/3で120°となっておしまい。
中心角が60°、弧の長さが5πであるおうぎ形の半径を求める問題なら、5π×6で円周が30π。
よって直径30、半径15である。
半径、弧の長さ、中心角、面積のうち2つがわかれば、おうぎ形の円に対する割合がわかる。
そうすれば他の2つも容易に求めることができるはずだ。
そういう練習をたくさんすべきなのだ。
公式をいくら覚えても、使いこなせなければ意味がない。
ちょっとパターンが変わったらその公式では使えない、
じゃあまた新たな公式を覚えよう、ではきりがない。
それよりも感覚を磨くことだ。
教科書に書いてあることだけに頼らず、自分のひらめきや感性を信じることだ。
本質をつかめば簡単に忘れることはないし、柔軟な発想もできるようになる。
円周を出すとき小学校では「直径×円周率」と習うが、中学で文字式を終えると2πrと教わる。
文字式のルール上こういう順になるのだが、
この形だけ覚えていて「直径×円周率」を忘れている子が少なくない。
やがて、円周から直径を求めることさえできなくなる。
2πrの意味がが2r×πだとわかっていればこうはならないはずなのだが...。
他にもいくらでも同様の例がある。
型にとらわれることは本質を理解する妨げになるのだ。
円の一部と考えれば難しくないはずだが、なぜか戸惑う。
たとえばこんな問題だ。
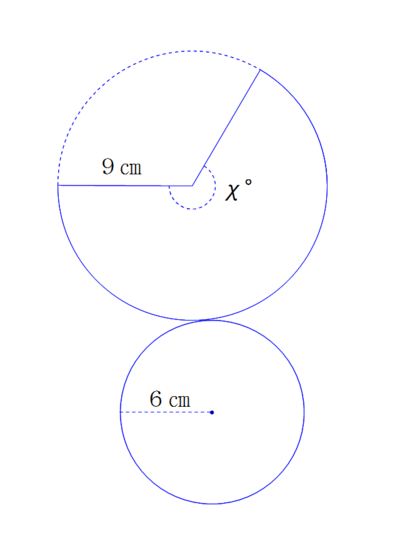
中心角をx°としてπ(パイ)r2乗*(かける)x/360まで書いて、そこでペンが止まってしまう...。
当然である。
これは、中心角がわかっているときにおうぎ形の面積を出す「公式」として教科書に載っているものだ。上図のおうぎ形の面積が示されていればまだ使えるが(それでも計算は面倒になる)、
この場合は使い途がない。ところが多くの生徒は、
「おうぎ形」と聞いた途端、反射的にこの式を書きたがるのだ。
あまりにも型にとらわれすぎている...。
この問題は、扇形の弧の長さと円周を比べれば簡単に解ける。
おうぎ形がその一部となる仮想円の半径は6cmなので直径は12cm。
従って円周は12πcm。
おうぎ形の弧の長さは4πcmなので、このおうぎ形は円の1/3(4π/12π)であることがわかる。
ならば中心角も円の1/3で120°となっておしまい。
中心角が60°、弧の長さが5πであるおうぎ形の半径を求める問題なら、5π×6で円周が30π。
よって直径30、半径15である。
半径、弧の長さ、中心角、面積のうち2つがわかれば、おうぎ形の円に対する割合がわかる。
そうすれば他の2つも容易に求めることができるはずだ。
そういう練習をたくさんすべきなのだ。
公式をいくら覚えても、使いこなせなければ意味がない。
ちょっとパターンが変わったらその公式では使えない、
じゃあまた新たな公式を覚えよう、ではきりがない。
それよりも感覚を磨くことだ。
教科書に書いてあることだけに頼らず、自分のひらめきや感性を信じることだ。
本質をつかめば簡単に忘れることはないし、柔軟な発想もできるようになる。
円周を出すとき小学校では「直径×円周率」と習うが、中学で文字式を終えると2πrと教わる。
文字式のルール上こういう順になるのだが、
この形だけ覚えていて「直径×円周率」を忘れている子が少なくない。
やがて、円周から直径を求めることさえできなくなる。
2πrの意味がが2r×πだとわかっていればこうはならないはずなのだが...。
他にもいくらでも同様の例がある。
型にとらわれることは本質を理解する妨げになるのだ。
2010年05月29日
「沿岸」ってどこ?
中1の地理で、「( )沿岸の国々」の( )に入る言葉を「地中海」と答える問題があった。
ある子が「ヨーロッパ」と書いていたので、「沿岸」の意味を辞書で引かせた。
この( )に入るのは海や湖以外にあり得ないと思ったからだ。
調べた生徒の答は「川・海・湖の陸に近い部分」。
ん?ちょっと待って...。
これだと海の中に国があることになってしまう...。
自分でも調べたら、生徒が答えたのは二番目の意味で、
第一義は「川・海・湖などに沿った陸地の部分」となっていた。
私はこの意味のつもりだったのだが、
なるほど「沿岸漁業」と言うときは二つ目の方だ。
同じ言葉で両方を指すなんて紛らわしい限りである。
「沿道」というのは「道に沿った部分」のことだ。
すると「沿岸」は「岸に沿った部分」。
陸側と海側の両方があり得るということか..。
念のため「岸」を引いてみると、「陸地が川や海などの水面と接している所(に沿った土地)」とある。
う~ん、これにも「沿った」が出てきた。
まあ、「沿岸」という字面からして、もともとは陸の方を言ったのだろう。
少なくとも私の感覚はそちらを支持する。
辞書をめくっていたら「沿海」も出てきた。
こっちは海のことだろうと思ったら、
第一義が「海岸に沿った陸」で、二番目が「陸に沿った海域」だった...。
ますますわけがわからない。

ある子が「ヨーロッパ」と書いていたので、「沿岸」の意味を辞書で引かせた。
この( )に入るのは海や湖以外にあり得ないと思ったからだ。
調べた生徒の答は「川・海・湖の陸に近い部分」。
ん?ちょっと待って...。
これだと海の中に国があることになってしまう...。
自分でも調べたら、生徒が答えたのは二番目の意味で、
第一義は「川・海・湖などに沿った陸地の部分」となっていた。
私はこの意味のつもりだったのだが、
なるほど「沿岸漁業」と言うときは二つ目の方だ。
同じ言葉で両方を指すなんて紛らわしい限りである。
「沿道」というのは「道に沿った部分」のことだ。
すると「沿岸」は「岸に沿った部分」。
陸側と海側の両方があり得るということか..。
念のため「岸」を引いてみると、「陸地が川や海などの水面と接している所(に沿った土地)」とある。
う~ん、これにも「沿った」が出てきた。
まあ、「沿岸」という字面からして、もともとは陸の方を言ったのだろう。
少なくとも私の感覚はそちらを支持する。
辞書をめくっていたら「沿海」も出てきた。
こっちは海のことだろうと思ったら、
第一義が「海岸に沿った陸」で、二番目が「陸に沿った海域」だった...。
ますますわけがわからない。

2010年05月28日
この言い方は正しいのか?~その6~
これはずっと間違いだと思っていたのに、
先日何かのテレビ番組で誤用ではないと言っていたものです。
「被害を被る」
文字にしてみると違和感が増しませんか?
「白い白馬」や「頭痛が痛い」のような重複表現ではないのでしょうか?
「被害」を使うなら「被害に遭う」、
「被る」を生かすなら「損害を被る」でしょう。
ただ、最近では辞書の用例にも「被害を被る」が載っているようです。
愛用の「新明解」にはありません。
ところが「被害を受ける」はあるんです。
意味に「損害・(危害)を受けること」とあるのだから、これも重複しているのでは...?
と思ったら、続けて「また、その損害」という定義もありました。
こちらを採用しているんですね。
それなら「被害を被る」もおかしくないということになりますが...。
どうもスッキリしません。
皆さんはどう思われますか?

先日何かのテレビ番組で誤用ではないと言っていたものです。
「被害を被る」
文字にしてみると違和感が増しませんか?
「白い白馬」や「頭痛が痛い」のような重複表現ではないのでしょうか?
「被害」を使うなら「被害に遭う」、
「被る」を生かすなら「損害を被る」でしょう。
ただ、最近では辞書の用例にも「被害を被る」が載っているようです。
愛用の「新明解」にはありません。
ところが「被害を受ける」はあるんです。
意味に「損害・(危害)を受けること」とあるのだから、これも重複しているのでは...?
と思ったら、続けて「また、その損害」という定義もありました。
こちらを採用しているんですね。
それなら「被害を被る」もおかしくないということになりますが...。
どうもスッキリしません。
皆さんはどう思われますか?

2010年05月27日
「-2倍」という発想
5月の途中から入塾した中学2年生。
数学がサッパリで、小学校の算数段階からあやしい。
特に分数がよくわかっていないようだ。
小学校卒業時に分数、割合、比などが完璧に理解できている子は、
中学校の数学でも間違いなくトップクラスに入れる。
実はわかっていない子が、それほど多いということだ。
そこで、小6~中学生を対象とした分数や割合のオリジナル教材を作った。
たとえば、「3分の1」は読んで字の如く「3つに分けたものの1つ」というところから始まる。
長めの説明の後の第一問。
問1:A、B2本のヒモがある。Aの長さは40cm、Bの長さは20cmである。
(1)Aの長さはBの長さの何倍か。
(2)Bの長さはAの長さの何倍か。
(1) はすぐにわかったようだ。「2倍」と書いてある。
(2)の「1/2倍」は難しいかな?と思っていたのだが、
本人が何か書くまでは決して口出ししない。
しばらく他の子を見てから戻ると...
「-2倍」
一瞬唖然としたが、すぐに彼の思考回路が見えた。
(1) は増えるのだから「2倍」。
だったら減っている(2) は「-2倍」ということなのだろう。
もちろんとんでもない間違いだが、この発想、なかなか面白い。
正負の数の単元で、マイナスを掛けるという概念が理解しづらいのも、
「-」は「引く」「減る」の意味だという意識が強くあるからだろう。
彼にはじっくり説明し直して、
なんとか「500円の4/5」や「1200円の7/6」くらいまではわかるようになった。
まだまだ先は長いが、やる気はある子だ。
彼の考え方も理解しながら、その思考に沿った教え方でとことん付き合って行きたい。

数学がサッパリで、小学校の算数段階からあやしい。
特に分数がよくわかっていないようだ。
小学校卒業時に分数、割合、比などが完璧に理解できている子は、
中学校の数学でも間違いなくトップクラスに入れる。
実はわかっていない子が、それほど多いということだ。
そこで、小6~中学生を対象とした分数や割合のオリジナル教材を作った。
たとえば、「3分の1」は読んで字の如く「3つに分けたものの1つ」というところから始まる。
長めの説明の後の第一問。
問1:A、B2本のヒモがある。Aの長さは40cm、Bの長さは20cmである。
(1)Aの長さはBの長さの何倍か。
(2)Bの長さはAの長さの何倍か。
(1) はすぐにわかったようだ。「2倍」と書いてある。
(2)の「1/2倍」は難しいかな?と思っていたのだが、
本人が何か書くまでは決して口出ししない。
しばらく他の子を見てから戻ると...
「-2倍」
一瞬唖然としたが、すぐに彼の思考回路が見えた。
(1) は増えるのだから「2倍」。
だったら減っている(2) は「-2倍」ということなのだろう。
もちろんとんでもない間違いだが、この発想、なかなか面白い。
正負の数の単元で、マイナスを掛けるという概念が理解しづらいのも、
「-」は「引く」「減る」の意味だという意識が強くあるからだろう。
彼にはじっくり説明し直して、
なんとか「500円の4/5」や「1200円の7/6」くらいまではわかるようになった。
まだまだ先は長いが、やる気はある子だ。
彼の考え方も理解しながら、その思考に沿った教え方でとことん付き合って行きたい。
2010年05月26日
この言い方は正しいのか?~その5~
今回は「綿半ホームエイド」稲里店で見かけた日本語。
出入り口の万引き防止ゲートに、こんな一言が貼ってありました。
「この機械はメーカーの安全性が確認されていますが...」
ん...?
一瞬何を言っているのかわかりませんでした。
「メーカーの安全性」???
これでは「この機械を作ったメーカーは安全な存在だ」と言っていることになります。
危険なメーカーってどんなの...?
機械の安全性が確認されているんですよね。
だったら「この機械はメーカーにより安全性が確認されていますが...」でしょう。
街中の看板や表示を注意して見ていると、結構楽しめますよ...。

出入り口の万引き防止ゲートに、こんな一言が貼ってありました。
「この機械はメーカーの安全性が確認されていますが...」
ん...?
一瞬何を言っているのかわかりませんでした。
「メーカーの安全性」???
これでは「この機械を作ったメーカーは安全な存在だ」と言っていることになります。
危険なメーカーってどんなの...?
機械の安全性が確認されているんですよね。
だったら「この機械はメーカーにより安全性が確認されていますが...」でしょう。
街中の看板や表示を注意して見ていると、結構楽しめますよ...。

2010年05月25日
火のない暮らし
「100円ライター」が姿を消すかも知れないという。
使い捨てライターの安全規制が強まったからだ。
幼児の火遊びによる事故が増えていることを受け、
子どもには簡単に着火できないような構造にするとのこと。
構造が複雑になれば、当然「100円」では販売できなくなるだろう。
子どもの火遊びは昔からあった。
悲劇につながることもあっただろう。
しかし、だからと言って火を暮らしから排除することはできなかった。
火がなければ日々の生活ができなかったからである。
人間は火を扱う術を手に入れることで進化した。
そして長い歴史の中で、火が持つ便利さと怖さの両方を体験してきた。
だから子どもに対しても、火を遠ざけるのではなく、
火との正しい付き合い方を教えてきたのである。
現代は「火のない暮らし」が進んできている。
冬はエアコンや床暖房で暖まる。
ファンヒーターも、火を使っているという感覚は少ない。
調理にも火を使わない「オール電化」とやらが人気だ。
いつかの「天声人語」に、火を「くべる」という言葉が死後に成りつつあるという話があった。
マッチを擦れない子どもが多いという。
何でもスイッチONですんでしまう生活を送っていればそうであろう。
火のありがたさも怖さも知らない世代が、これから増えていくことになる。
長男が小学生の頃、石油ストーブの天板に脱衣カゴを乗せてしまったことがある。
プラスチック製のカゴは簡単に溶けてしまい、危うく火事になるところだった。
それまでファンヒーターしか知らなかった彼は、天板が熱くなることを想像できなかったのだ。
我が家では3年前に薪ストーブを導入した。
焚き火が好きな私の「火遊び」のようなものだが、炎を見ていると落ち着く。
実際の暖房能力以上のぬくもりを感じる。
スイッチ一つで着火というわけにはいかないが、
焚き付け材から火を大きくするのも楽しみの一つである。
風呂釜も灯油と薪(ゴミも)両方焚けるタイプにこだわった。
調理には当然ガスである。
オール電化とは程遠い生活を送っている。
火のある暮らしを大事にしたいのだ。
「安全」「安心」「快適」などの美辞麗句のもと、暮らしからどんどん火がなくなっていく。
野焼きも焚き火も気軽にはできなくなった。
はたしてこれは進歩なのだろうか?
ライターの事故が多いなら、子どもの手の届かないところに置けばいいだけだ。
そして、親の立ち会いの下で火の扱い方を教えることだ。
日々の暮らしの中で無理なら、キャンプに連れ出してもいいし、
河原でバーベキューをするだけでもいい。
ひたすら火を遠ざけることばかりに目を向けていては、
いずれまた事故が起こることになるだろう。
危険の回避を道具だけに頼っていては、人間は退化するばかりである。

使い捨てライターの安全規制が強まったからだ。
幼児の火遊びによる事故が増えていることを受け、
子どもには簡単に着火できないような構造にするとのこと。
構造が複雑になれば、当然「100円」では販売できなくなるだろう。
子どもの火遊びは昔からあった。
悲劇につながることもあっただろう。
しかし、だからと言って火を暮らしから排除することはできなかった。
火がなければ日々の生活ができなかったからである。
人間は火を扱う術を手に入れることで進化した。
そして長い歴史の中で、火が持つ便利さと怖さの両方を体験してきた。
だから子どもに対しても、火を遠ざけるのではなく、
火との正しい付き合い方を教えてきたのである。
現代は「火のない暮らし」が進んできている。
冬はエアコンや床暖房で暖まる。
ファンヒーターも、火を使っているという感覚は少ない。
調理にも火を使わない「オール電化」とやらが人気だ。
いつかの「天声人語」に、火を「くべる」という言葉が死後に成りつつあるという話があった。
マッチを擦れない子どもが多いという。
何でもスイッチONですんでしまう生活を送っていればそうであろう。
火のありがたさも怖さも知らない世代が、これから増えていくことになる。
長男が小学生の頃、石油ストーブの天板に脱衣カゴを乗せてしまったことがある。
プラスチック製のカゴは簡単に溶けてしまい、危うく火事になるところだった。
それまでファンヒーターしか知らなかった彼は、天板が熱くなることを想像できなかったのだ。
我が家では3年前に薪ストーブを導入した。
焚き火が好きな私の「火遊び」のようなものだが、炎を見ていると落ち着く。
実際の暖房能力以上のぬくもりを感じる。
スイッチ一つで着火というわけにはいかないが、
焚き付け材から火を大きくするのも楽しみの一つである。
風呂釜も灯油と薪(ゴミも)両方焚けるタイプにこだわった。
調理には当然ガスである。
オール電化とは程遠い生活を送っている。
火のある暮らしを大事にしたいのだ。
「安全」「安心」「快適」などの美辞麗句のもと、暮らしからどんどん火がなくなっていく。
野焼きも焚き火も気軽にはできなくなった。
はたしてこれは進歩なのだろうか?
ライターの事故が多いなら、子どもの手の届かないところに置けばいいだけだ。
そして、親の立ち会いの下で火の扱い方を教えることだ。
日々の暮らしの中で無理なら、キャンプに連れ出してもいいし、
河原でバーベキューをするだけでもいい。
ひたすら火を遠ざけることばかりに目を向けていては、
いずれまた事故が起こることになるだろう。
危険の回避を道具だけに頼っていては、人間は退化するばかりである。

2010年05月24日
武家屋敷で投扇興
昨日の日曜日、あいにくの雨の中、投扇興の月例会を行いました。
投扇興、ご存知ですか?
扇を投げて的を落とし、落ちた後の「型」による得点を競う遊びです。
江戸時代のお座敷遊びが原点ですが、今では主に東は浅草、西は京都を中心に愛好家が増えています。
私が投扇興と出会ったのは7年前。
たまたま須坂で行われていた会に参加し、優勝してしまったのです。
それから自分でも道具を揃えて猛練習。
2007年には浅草の大会でベスト4にまで進みました(参加約90名)。
2005年からサークルを立ち上げ、篠ノ井で月例会を開始。
その後正式に浅草の支部(信州みすず連)として登録し、
現在は松代と小島田を隔月で交互に会場としています。
3月には地元のNPOと共催で「信州松代投扇興選手権大会」も実施し、
今年で第3回になりました。
今のところ正規のメンバーは9名。
うち4名が初段を取得し、「名取の号(銘)」を貰っています。
因みに私の号は「其扇庵桐扇」。
「型」には源氏物語の「巻」の名前が付いていますが、
これは扇、的、台の位置関係を物語のあらすじや自然現象に見立てたもの。
的に付いた鈴がチリンと鳴る度に、「いとをかし」の雅な世界に遊べます。
一方で競技としての楽しみも多く、
技術だけでなくメンタル面や偶然性にも左右される奥の深さが魅力です。
今月は松代が会場。
これまでは松代支所の和室を借りていたのですが、
せっかく歴史の町で行うのだから、それなりの雰囲気のある所でと思い、
無料で借りられる「山寺常山邸」で初めて開催しました。
ここは母屋等は失われていて、立派な門と書院が残っているだけだが、その書院で十分です。
派手さはありませんが、フスマや欄間に描かれた絵や書が趣を感じさせます。
丸窓の茶室から望む庭もみごと。
東山文化の流れを継いだ、漱石の小説に登場するような佇まいでした。
会場として借りたとはいえ、もちろん貸し切りではないので、
一般の観光客も見学にやって来ます(入場無料)。
PRになっていいのですが、あまりに頻繁に大勢来られると、
気が散るし、風の影響も...。
そんな心配は杞憂に終わりました。
入り口に小さいながら「使用中」という掲示が出たことと、
通路からすぐのガラス戸を閉めておいたお蔭で、
観光客は廊下から見学していきます。
山梨から来られたという夫婦が、私たちの試合の様子を熱心に見学されていて、
特に奥様が興味を示されました。
メンバーの一人がいろいろ解説し、実際に投げて体験してもらったところ、
旦那様が「澪標」(画像参照)を出されて大喝采!
的を倒した扇が台の上にピタッと乗る型で、11点貰える大技です。
我々は常にこれを狙っていますが、初心者で出すのは極めて難しい...。
さっそく携帯で記念写真を撮って行かれました。
その前に琴の演奏も聴いて来られたとのことで、
奥様いわくく「素敵な町ですね...」。
松代の町の印象アップに一役買うことがでk、とても満足な一日でした。
6月からは別のお屋敷も一般使用できるようになるそうです。
松代にお越しの際、どこかで投扇興をやっていたら、ぜひ体験していってくださいね。
なお、信州みすず連のメンバーは随時募集しています。
一度体験してみたいという方も、いつでも受け入れています。
コメント欄にお気軽にどうぞ。
ご一緒に、浅草の団体戦に出場しましょう!

投扇興、ご存知ですか?
扇を投げて的を落とし、落ちた後の「型」による得点を競う遊びです。
江戸時代のお座敷遊びが原点ですが、今では主に東は浅草、西は京都を中心に愛好家が増えています。
私が投扇興と出会ったのは7年前。
たまたま須坂で行われていた会に参加し、優勝してしまったのです。
それから自分でも道具を揃えて猛練習。
2007年には浅草の大会でベスト4にまで進みました(参加約90名)。
2005年からサークルを立ち上げ、篠ノ井で月例会を開始。
その後正式に浅草の支部(信州みすず連)として登録し、
現在は松代と小島田を隔月で交互に会場としています。
3月には地元のNPOと共催で「信州松代投扇興選手権大会」も実施し、
今年で第3回になりました。
今のところ正規のメンバーは9名。
うち4名が初段を取得し、「名取の号(銘)」を貰っています。
因みに私の号は「其扇庵桐扇」。
「型」には源氏物語の「巻」の名前が付いていますが、
これは扇、的、台の位置関係を物語のあらすじや自然現象に見立てたもの。
的に付いた鈴がチリンと鳴る度に、「いとをかし」の雅な世界に遊べます。
一方で競技としての楽しみも多く、
技術だけでなくメンタル面や偶然性にも左右される奥の深さが魅力です。
今月は松代が会場。
これまでは松代支所の和室を借りていたのですが、
せっかく歴史の町で行うのだから、それなりの雰囲気のある所でと思い、
無料で借りられる「山寺常山邸」で初めて開催しました。
ここは母屋等は失われていて、立派な門と書院が残っているだけだが、その書院で十分です。
派手さはありませんが、フスマや欄間に描かれた絵や書が趣を感じさせます。
丸窓の茶室から望む庭もみごと。
東山文化の流れを継いだ、漱石の小説に登場するような佇まいでした。
会場として借りたとはいえ、もちろん貸し切りではないので、
一般の観光客も見学にやって来ます(入場無料)。
PRになっていいのですが、あまりに頻繁に大勢来られると、
気が散るし、風の影響も...。
そんな心配は杞憂に終わりました。
入り口に小さいながら「使用中」という掲示が出たことと、
通路からすぐのガラス戸を閉めておいたお蔭で、
観光客は廊下から見学していきます。
山梨から来られたという夫婦が、私たちの試合の様子を熱心に見学されていて、
特に奥様が興味を示されました。
メンバーの一人がいろいろ解説し、実際に投げて体験してもらったところ、
旦那様が「澪標」(画像参照)を出されて大喝采!
的を倒した扇が台の上にピタッと乗る型で、11点貰える大技です。
我々は常にこれを狙っていますが、初心者で出すのは極めて難しい...。
さっそく携帯で記念写真を撮って行かれました。
その前に琴の演奏も聴いて来られたとのことで、
奥様いわくく「素敵な町ですね...」。
松代の町の印象アップに一役買うことがでk、とても満足な一日でした。
6月からは別のお屋敷も一般使用できるようになるそうです。
松代にお越しの際、どこかで投扇興をやっていたら、ぜひ体験していってくださいね。
なお、信州みすず連のメンバーは随時募集しています。
一度体験してみたいという方も、いつでも受け入れています。
コメント欄にお気軽にどうぞ。
ご一緒に、浅草の団体戦に出場しましょう!

2010年05月23日
「誕生」と「生誕」
「Google」の看板ロゴに懐かしの「パックマン」が登場している。
今日の深夜までの限定だそうで、キーボードの矢印キーで実際に遊べる。
思えば社会人に成り立ての30年前、昼休みに喫茶店でよく遊んだものだ。
インベーダーゲームは今一だったが、このパックマンは大好きで100円玉をつぎ込んだ。
もちろん久々にやってみたが、小さなキーではどうも勝手が悪い。
普段ゲームなどしないので、「十」ではなく「┴」に配置された矢印が扱いにくいのだ。
下に行くつもりが左に行ってしまったりして、あっという間にGAME OVERになってしまった。
このパックマン復活を紹介した記事(朝日新聞)の中に、
前回ちょっと話題にした「誕生」と「生誕」が両方出てきた。
「30年前の1980年5月22日に誕生したゲーム「パックマン」が、...」
「同サイトが生誕30年を祝って、...」
私の認識では、「誕生」は今生きている人に、
「生誕」はすでに亡くなった人(特に有名人)に使う言葉だと思っていた。
日常的によく使われるのは「誕生」だろう。
毎年祝うのは「誕生日」であり、「誕生石」や「誕生花」などもある。
一方「生誕」は「太宰治生誕100年」「坂本龍馬生誕の地」などでお馴染みだ。
ところが、辞書にはそんな定義は載っていない。
Yahoo の辞書機能では両者は同じ意味になっている。
ユニークな定義で知られる「新明解」では次のような記述だ。
「誕生」(胎生動物が、また広義では卵生動物が卵からかえって)生まれること。
(新しく制度・組織・施設などが)出来る意にも用いられる。
狭義では胎生動物だけに使われるなんて知らなかった...。
「生誕」(第一級の学者・宗教家・芸術家などが)生まれること。
坂本龍馬はどこに含まれるのか...。
ということは、「第一級の学者」などには生前でも「生誕」を使っていいのだろうか。
もっとも、死後に業績が認められるということも多いので、不都合は少ないのかも知れない。
パックマンの記事に戻る。
私の感覚では今は廃れてしまったパックマンの方に「生誕」を、
現在隆盛のGoogle に「誕生」を用いるべきではないかと思う。
「新明解」の定義に基づくなら、記者の価値観が反映されていることになる。
Google を「第一級」と考えて「生誕」という尊称を与えたのだろうか...。
謎は解明されないままである。

今日の深夜までの限定だそうで、キーボードの矢印キーで実際に遊べる。
思えば社会人に成り立ての30年前、昼休みに喫茶店でよく遊んだものだ。
インベーダーゲームは今一だったが、このパックマンは大好きで100円玉をつぎ込んだ。
もちろん久々にやってみたが、小さなキーではどうも勝手が悪い。
普段ゲームなどしないので、「十」ではなく「┴」に配置された矢印が扱いにくいのだ。
下に行くつもりが左に行ってしまったりして、あっという間にGAME OVERになってしまった。
このパックマン復活を紹介した記事(朝日新聞)の中に、
前回ちょっと話題にした「誕生」と「生誕」が両方出てきた。
「30年前の1980年5月22日に誕生したゲーム「パックマン」が、...」
「同サイトが生誕30年を祝って、...」
私の認識では、「誕生」は今生きている人に、
「生誕」はすでに亡くなった人(特に有名人)に使う言葉だと思っていた。
日常的によく使われるのは「誕生」だろう。
毎年祝うのは「誕生日」であり、「誕生石」や「誕生花」などもある。
一方「生誕」は「太宰治生誕100年」「坂本龍馬生誕の地」などでお馴染みだ。
ところが、辞書にはそんな定義は載っていない。
Yahoo の辞書機能では両者は同じ意味になっている。
ユニークな定義で知られる「新明解」では次のような記述だ。
「誕生」(胎生動物が、また広義では卵生動物が卵からかえって)生まれること。
(新しく制度・組織・施設などが)出来る意にも用いられる。
狭義では胎生動物だけに使われるなんて知らなかった...。
「生誕」(第一級の学者・宗教家・芸術家などが)生まれること。
坂本龍馬はどこに含まれるのか...。
ということは、「第一級の学者」などには生前でも「生誕」を使っていいのだろうか。
もっとも、死後に業績が認められるということも多いので、不都合は少ないのかも知れない。
パックマンの記事に戻る。
私の感覚では今は廃れてしまったパックマンの方に「生誕」を、
現在隆盛のGoogle に「誕生」を用いるべきではないかと思う。
「新明解」の定義に基づくなら、記者の価値観が反映されていることになる。
Google を「第一級」と考えて「生誕」という尊称を与えたのだろうか...。
謎は解明されないままである。

2010年05月21日
「生前」ということば
新聞を読んでいてふと思った。
亡くなった人が生きていたときのことをなぜ「生前」と言うのか?
「生きていた前」では意味が通じない。
「死後」の反対で「死前」なら納得できるが、そんな言葉は聞いたことがない。
同じことを考えた人は多いらしく、検索したらいろいろな意見があった。
「死んでから別の人生が始まる。死こそ新しい生の始まり。」という説。
仏教の輪廻思想のようなものか。
仏となって真の「人生」が始まるということか...。
「前(さき)の生」の意味だとする説。
死を境に時代を分け、「前」の生きていた時代をこう呼ぶという。
後の「前」から「生」へ、漢文のように戻って読むわけだ。
一番腑に落ちるのは、「死後」という言葉の
「死」と「後」それぞれの対となる字を単純に並べただけという考え方だ。
「死」の反対の「生」+「後」の反対の「前」で「生前」である。
ところが、同様の例を探しても、そんな反意語の作り方は他には見つからない。
「円高」と「円安」、「表面」と「裏面」のように、
一字だけを反対の意味の漢字に換える例がほとんどだ。
「近接」と「遠隔」、「優良」と「劣悪」、「賢明」と「暗愚」などは
近い例かも知れないが、これらはもともと似た意味の漢字を並べた熟語である。
「死後」のように、前の字が後の字を修飾している熟語(「死」の「後」)では、
そんな反意語は皆無である。
結局、よくわからないままだ。
「生前」の反意語は普通に考えれば「生後」だろう。
しかしこの言葉は全く違う意味になる。
「生後」は「生まれて後」のことであり、「生後3ヶ月」のように使う。
それなら「生前」は「生まれる前」になって、母親の胎内にいるときのことになってもよさそうだ。
「紀元前」のように、「生前1ヶ月」は生まれる1ヶ月前を指すのなら論理的だが、
そんな言い方は聞いたことがない。
「生前」はあくまで「死後」の対義語なのである。
生や死に伴う言葉には、不思議なものがまだありそうだ。
仏教用語がかなり影響しているのではないか。
「誕生」と「生誕」の使い分けも興味深いテーマなので、また考えてみたい。

亡くなった人が生きていたときのことをなぜ「生前」と言うのか?
「生きていた前」では意味が通じない。
「死後」の反対で「死前」なら納得できるが、そんな言葉は聞いたことがない。
同じことを考えた人は多いらしく、検索したらいろいろな意見があった。
「死んでから別の人生が始まる。死こそ新しい生の始まり。」という説。
仏教の輪廻思想のようなものか。
仏となって真の「人生」が始まるということか...。
「前(さき)の生」の意味だとする説。
死を境に時代を分け、「前」の生きていた時代をこう呼ぶという。
後の「前」から「生」へ、漢文のように戻って読むわけだ。
一番腑に落ちるのは、「死後」という言葉の
「死」と「後」それぞれの対となる字を単純に並べただけという考え方だ。
「死」の反対の「生」+「後」の反対の「前」で「生前」である。
ところが、同様の例を探しても、そんな反意語の作り方は他には見つからない。
「円高」と「円安」、「表面」と「裏面」のように、
一字だけを反対の意味の漢字に換える例がほとんどだ。
「近接」と「遠隔」、「優良」と「劣悪」、「賢明」と「暗愚」などは
近い例かも知れないが、これらはもともと似た意味の漢字を並べた熟語である。
「死後」のように、前の字が後の字を修飾している熟語(「死」の「後」)では、
そんな反意語は皆無である。
結局、よくわからないままだ。
「生前」の反意語は普通に考えれば「生後」だろう。
しかしこの言葉は全く違う意味になる。
「生後」は「生まれて後」のことであり、「生後3ヶ月」のように使う。
それなら「生前」は「生まれる前」になって、母親の胎内にいるときのことになってもよさそうだ。
「紀元前」のように、「生前1ヶ月」は生まれる1ヶ月前を指すのなら論理的だが、
そんな言い方は聞いたことがない。
「生前」はあくまで「死後」の対義語なのである。
生や死に伴う言葉には、不思議なものがまだありそうだ。
仏教用語がかなり影響しているのではないか。
「誕生」と「生誕」の使い分けも興味深いテーマなので、また考えてみたい。

2010年05月20日
なまえ随想~その2~
昨日の続き。
女の子の名前に「子」が付かなくなって久しい。
私の同世代は、ほとんどの女子が「○子」という名前だった。
他には「○恵」や「○美」があった程度で、たまに見かける「早月(さつき)」や「香織(かおり)」などは
かなりオシャレに感じたものだ。
今では当たり前のひらがなだけの名前もずいぶん珍しかった。
「○子」が廃れたのはいつ頃からだろう。
私の子どもの世代(昭和59年~平成元年生まれ)になると、東京ではほとんど「○子」がなかったが、
長野に来てみたら同級生や姉妹にまだあった。
最近では長野でもほとんどお目にかかれない。
たまに「○子」があると、逆に新鮮なくらいである。
そう言えば、親の名から一字を取って子どもに命名する習慣もなくなりつつある。
ときどき塾の生徒にそんな例を見かけると、そこに込められた親の思いを聞いてみたくなる。
何か強い信念をお持ちなのではないか...。
「○子」が減少した頃から、子どもの名前には音(オン)が重視されるようになったように思う。
わが家でも命名の際に、まずは聞いたときの語感を優先して候補を挙げ、
後からその音に合う漢字を選んだ。
一応字画も気にしたし、漢字の意味も念入りに調べたが、取っかかりは音であった。
最初の子に「世界で通用するように」と、そのまま英語に採り入れても違和感のない名前を付けたので、あとの2人にもその方針を貫いた。
本人たちはどう思っているか知らないが、親としては今でも音、漢字ともに気に入っている。
最近の子どもの名前には読めないものが結構ある。
「週刊長野」に載っている誕生祝いのコーナーを見ては、驚いたり感心したり...。
入塾の際に書いてもらう申込書にも「ふりがな」の欄は欠かせない。
やはり音を優先してあとから漢字を考えるため、当て字的なものが多くなっているのだろう。
まあ、認められた漢字さえ使っていれば読み方は自由に決められるのだが、
初対面の人に一々読み方を説明しなければならないのでは大変だろうと想像する。
もう一つ、お節介を承知の上で言うと、女の子の名前にあまりに可愛らしさや可憐さをイメージした名前を付けると、その子が年を取ってから「名前負け」しないだろうか。
みんながそうならいいか...。
あ、ウチの子もそうだった...。
名前の音の響きが、その子の性格に影響を与えるのでは?と考えたことがある。
特に母音である。
最近読んだ外山滋比古氏の本に、こんな記述があった。
「由来、女子の名には五十音のイ列とウ列の音の組み合わせで可憐さを表象していた。
ゆき子、きみ子、ゆみ子などである。」(from 外山滋比古「日本語の作法」)
近年はア列の音に人気があるという。
かつては可愛らしい女性になってほしいという願いで小さな母音が好まれたのが、
戦後、明るく伸びやかであってほしいという気持ちから、大きな母音を多用する名前が増えたとしている。
因みにア列の音は、昔は「太め」を暗示していたそうである。
これは親の側の願いであるが、その名で呼び続けることで子どもの側も影響を受けるのでは?と思う。
生まれてから何千回、何万回と呼びかけられる音韻が、性格の形成に無関係とは思えないのだ。他の条件が同じであれば、ア列の音が多い子どもの方が明るく大らかに育つのではないだろうか。
そんな研究が今までにあるのかどうか、ちょっと調べてみたい。

女の子の名前に「子」が付かなくなって久しい。
私の同世代は、ほとんどの女子が「○子」という名前だった。
他には「○恵」や「○美」があった程度で、たまに見かける「早月(さつき)」や「香織(かおり)」などは
かなりオシャレに感じたものだ。
今では当たり前のひらがなだけの名前もずいぶん珍しかった。
「○子」が廃れたのはいつ頃からだろう。
私の子どもの世代(昭和59年~平成元年生まれ)になると、東京ではほとんど「○子」がなかったが、
長野に来てみたら同級生や姉妹にまだあった。
最近では長野でもほとんどお目にかかれない。
たまに「○子」があると、逆に新鮮なくらいである。
そう言えば、親の名から一字を取って子どもに命名する習慣もなくなりつつある。
ときどき塾の生徒にそんな例を見かけると、そこに込められた親の思いを聞いてみたくなる。
何か強い信念をお持ちなのではないか...。
「○子」が減少した頃から、子どもの名前には音(オン)が重視されるようになったように思う。
わが家でも命名の際に、まずは聞いたときの語感を優先して候補を挙げ、
後からその音に合う漢字を選んだ。
一応字画も気にしたし、漢字の意味も念入りに調べたが、取っかかりは音であった。
最初の子に「世界で通用するように」と、そのまま英語に採り入れても違和感のない名前を付けたので、あとの2人にもその方針を貫いた。
本人たちはどう思っているか知らないが、親としては今でも音、漢字ともに気に入っている。
最近の子どもの名前には読めないものが結構ある。
「週刊長野」に載っている誕生祝いのコーナーを見ては、驚いたり感心したり...。
入塾の際に書いてもらう申込書にも「ふりがな」の欄は欠かせない。
やはり音を優先してあとから漢字を考えるため、当て字的なものが多くなっているのだろう。
まあ、認められた漢字さえ使っていれば読み方は自由に決められるのだが、
初対面の人に一々読み方を説明しなければならないのでは大変だろうと想像する。
もう一つ、お節介を承知の上で言うと、女の子の名前にあまりに可愛らしさや可憐さをイメージした名前を付けると、その子が年を取ってから「名前負け」しないだろうか。
みんながそうならいいか...。
あ、ウチの子もそうだった...。
名前の音の響きが、その子の性格に影響を与えるのでは?と考えたことがある。
特に母音である。
最近読んだ外山滋比古氏の本に、こんな記述があった。
「由来、女子の名には五十音のイ列とウ列の音の組み合わせで可憐さを表象していた。
ゆき子、きみ子、ゆみ子などである。」(from 外山滋比古「日本語の作法」)
近年はア列の音に人気があるという。
かつては可愛らしい女性になってほしいという願いで小さな母音が好まれたのが、
戦後、明るく伸びやかであってほしいという気持ちから、大きな母音を多用する名前が増えたとしている。
因みにア列の音は、昔は「太め」を暗示していたそうである。
これは親の側の願いであるが、その名で呼び続けることで子どもの側も影響を受けるのでは?と思う。
生まれてから何千回、何万回と呼びかけられる音韻が、性格の形成に無関係とは思えないのだ。他の条件が同じであれば、ア列の音が多い子どもの方が明るく大らかに育つのではないだろうか。
そんな研究が今までにあるのかどうか、ちょっと調べてみたい。

2010年05月19日
なまえ随想~その1~
子どもの名前を付けるとき、かつては言葉や漢字の意味に重きを置いていた。
従って、性別によって使われる漢字がだいたい決まっていた。
「勇」や「剛」「武」「毅」など、たくましさを感じさせる漢字は男の子。
「美」「香」「愛」「麗」など、美しさや優しさを漂わせる漢字は女の子...。
その名を付けられた子どもの側も、多かれ少なかれ、名前の持つ意味を意識していたように思う。
親の期待が込められた名前に恥じないような人生を送りたい、と考える者も多かった。
そこまで深刻に考えなくても、たとえば「孝行」という名前だったら、
「俺は名前どおりに親孝行しているだろうか?」と振り返ることもあっただろう。
「良」や「善」が入っていたら悪事には決して手を染めないでおこうと自戒したり、
「志」や「雄」があれば夢を大きく持って生きようと決意したりするのも自然な流れである。
これも「言霊」の一つの例と言えよう。
「名前負け」という言葉があるのも、それだけ名前の意味を意識していた証だろう。
ただ、これには本人の努力では如何ともしがたい面もあるので気の毒ではある。
名前に「美」や「剛」が入っているのに外見がそれに伴わないことで、
コンプレックスを持っている人も少なからずいると思う。
まあ、本人が思っているほど、周りは意識していないことが普通だが...。
実は私も自分の名が好きではない。
男の名前としてあまりにも弱々しい感じがするのだ。
波風を立てぬように平々凡々と...というメッセージしか聞こえてこないのだ。
書いたときの印象も、いかにも細い!
自分の外観が名前の印象どおりではないか、というコンプレックスがあるのでよけいにそう思う。
だからこそ、内面はそうではない!という信念を持って生きてきたつもりだ。
世の中に流されまい、俺だけは違う、と意地を張ってきた面もある。
人から「変わっている」と言われることを好み、
小さな幸せより波瀾万丈の人生に憧れてきた...。
こう考えてみると、今の自分があるのも、親が付けてくれた名前のお蔭だと言える。
それを反面教師として生きてきたのだ。
名前は一生付いて回るものだけに、人に与える影響は大きい。
次回はその音(響き)について書こうと思う。

従って、性別によって使われる漢字がだいたい決まっていた。
「勇」や「剛」「武」「毅」など、たくましさを感じさせる漢字は男の子。
「美」「香」「愛」「麗」など、美しさや優しさを漂わせる漢字は女の子...。
その名を付けられた子どもの側も、多かれ少なかれ、名前の持つ意味を意識していたように思う。
親の期待が込められた名前に恥じないような人生を送りたい、と考える者も多かった。
そこまで深刻に考えなくても、たとえば「孝行」という名前だったら、
「俺は名前どおりに親孝行しているだろうか?」と振り返ることもあっただろう。
「良」や「善」が入っていたら悪事には決して手を染めないでおこうと自戒したり、
「志」や「雄」があれば夢を大きく持って生きようと決意したりするのも自然な流れである。
これも「言霊」の一つの例と言えよう。
「名前負け」という言葉があるのも、それだけ名前の意味を意識していた証だろう。
ただ、これには本人の努力では如何ともしがたい面もあるので気の毒ではある。
名前に「美」や「剛」が入っているのに外見がそれに伴わないことで、
コンプレックスを持っている人も少なからずいると思う。
まあ、本人が思っているほど、周りは意識していないことが普通だが...。
実は私も自分の名が好きではない。
男の名前としてあまりにも弱々しい感じがするのだ。
波風を立てぬように平々凡々と...というメッセージしか聞こえてこないのだ。
書いたときの印象も、いかにも細い!
自分の外観が名前の印象どおりではないか、というコンプレックスがあるのでよけいにそう思う。
だからこそ、内面はそうではない!という信念を持って生きてきたつもりだ。
世の中に流されまい、俺だけは違う、と意地を張ってきた面もある。
人から「変わっている」と言われることを好み、
小さな幸せより波瀾万丈の人生に憧れてきた...。
こう考えてみると、今の自分があるのも、親が付けてくれた名前のお蔭だと言える。
それを反面教師として生きてきたのだ。
名前は一生付いて回るものだけに、人に与える影響は大きい。
次回はその音(響き)について書こうと思う。

2010年05月18日
歴史教科書の文章~その2~
昨日塾で、中2の女子が歴史の問題を解いていた。
ちょうど先日、私が記事にした「承久の乱」の辺りだ。
「六波羅探題」と答えるべき箇所が無解答だったので、言葉の意味を確認する。
「六波羅探題って何?」
しばらく教科書を読んでいたが、答えられない。
仕方ないので助け舟を出す。
「そもそも六波羅探題って人なの?場所なの?」
「場所...?」
正確には京都六波羅に置いた役職のことだが、まあこれでも合格としよう。
続けて訊く。
「じゃあ、何のために六波羅探題を置いたの?」
「...?」
「どんな事件があったから?」
「...??」
参考までに、先日も紹介した現行の歴史教科書(平成18年版:東京書籍刊:長野市立中学用)の該当箇所を再掲する。
幕府は大軍を率いてこれを破り(承久の乱)、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視するとともに、
上皇側についた貴族や西国の武士の領地を取り上げ、地頭に東国の武士を任命し、幕府の支配力
はいちだんと強まりました。
この前に、後鳥羽上皇が幕府を倒すべく挙兵したことが書かれている。
六波羅探題設置のきっかけやその目的は、頻繁にテストに出る定番の記述問題なのだ。
さて、何分か考えてからの彼女の答である。
「島流しとかあったから...。」
え???
上皇が隠岐に流されたことは今の教科書には記述がないが、それは何かで知っていたのだろう。
しかし、それは承久の乱が失敗に終わった結果であって、六波羅探題とは直接関係ない。
訊き方を変える。
「この時代に一番力を持っていたのは誰?」
「...後鳥羽上皇...。」
「だったら何も事件も起こす必要ないじゃん...。」
結局、承久の乱が起こった背景から六波羅探題設置の目的まで、
彼女にわかるであろう言葉で説明せざるを得なくなった。
本当はこちらが教えるのではなく、本人が気づいて自分の口から正解を言ってくれるようにしたいのだが、これだけ理解が浅いとどうしようもない。
彼女の成績は平均より少し上くらいである。
国語力が特に低いというわけでない。
してみると、やはり歴史教科書の記述に問題があるのではないか?
ただ、わかりにくさを逆手に取って、それを利用してしまうのも面白そうだ。
この教科書の文章を題材に、国語の問題を作るのだ。
まさに一石二鳥!
国語力もアップするし、歴史の理解も深まる。
さっそく試してみたい。

ちょうど先日、私が記事にした「承久の乱」の辺りだ。
「六波羅探題」と答えるべき箇所が無解答だったので、言葉の意味を確認する。
「六波羅探題って何?」
しばらく教科書を読んでいたが、答えられない。
仕方ないので助け舟を出す。
「そもそも六波羅探題って人なの?場所なの?」
「場所...?」
正確には京都六波羅に置いた役職のことだが、まあこれでも合格としよう。
続けて訊く。
「じゃあ、何のために六波羅探題を置いたの?」
「...?」
「どんな事件があったから?」
「...??」
参考までに、先日も紹介した現行の歴史教科書(平成18年版:東京書籍刊:長野市立中学用)の該当箇所を再掲する。
幕府は大軍を率いてこれを破り(承久の乱)、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視するとともに、
上皇側についた貴族や西国の武士の領地を取り上げ、地頭に東国の武士を任命し、幕府の支配力
はいちだんと強まりました。
この前に、後鳥羽上皇が幕府を倒すべく挙兵したことが書かれている。
六波羅探題設置のきっかけやその目的は、頻繁にテストに出る定番の記述問題なのだ。
さて、何分か考えてからの彼女の答である。
「島流しとかあったから...。」
え???
上皇が隠岐に流されたことは今の教科書には記述がないが、それは何かで知っていたのだろう。
しかし、それは承久の乱が失敗に終わった結果であって、六波羅探題とは直接関係ない。
訊き方を変える。
「この時代に一番力を持っていたのは誰?」
「...後鳥羽上皇...。」
「だったら何も事件も起こす必要ないじゃん...。」
結局、承久の乱が起こった背景から六波羅探題設置の目的まで、
彼女にわかるであろう言葉で説明せざるを得なくなった。
本当はこちらが教えるのではなく、本人が気づいて自分の口から正解を言ってくれるようにしたいのだが、これだけ理解が浅いとどうしようもない。
彼女の成績は平均より少し上くらいである。
国語力が特に低いというわけでない。
してみると、やはり歴史教科書の記述に問題があるのではないか?
ただ、わかりにくさを逆手に取って、それを利用してしまうのも面白そうだ。
この教科書の文章を題材に、国語の問題を作るのだ。
まさに一石二鳥!
国語力もアップするし、歴史の理解も深まる。
さっそく試してみたい。

2010年05月17日
この言い方は正しいのか?~その4~
またも信濃毎日新聞の記事からである。
昨日のスポーツ欄。
我らが阪神タイガースが辛勝したことを伝え、藤川球児の言葉を紹介しているくだり...。
「今季初の失点を許した守護神は...」
「失点」とは言うまでもなく「点を失うこと」だ。
「失点を」をと来たら「喫した」、あるいは単純に「した」でなければならない。
「許した」を生かすなら「得点を許した」、もしくは「点を許した」であろう。
この「失点を許す」という言い方はけっこう実況放送でも耳にする。
その度に気になって仕方ない。
おそらく「失点は許されません」という受け身形と混同しているのではないか。
「失点は許されません」ならわかる。
この場合の「許す」の主体はファンであり、監督やコーチである。
彼らが、「点を失うこと」を許さないのだ。
しかし「失点を許す」の主体(主語)はあくまで投手、あるいはチームであるはずだ。
相手に「許す」のは「点を入れること」であり、それを失うことではない。
瞬時に言葉を選ばなければならない実況放送なら、まだ大目に見ることもできるが、
活字に残る新聞記事には正しい日本語表現を要求したい。

昨日のスポーツ欄。
我らが阪神タイガースが辛勝したことを伝え、藤川球児の言葉を紹介しているくだり...。
「今季初の失点を許した守護神は...」
「失点」とは言うまでもなく「点を失うこと」だ。
「失点を」をと来たら「喫した」、あるいは単純に「した」でなければならない。
「許した」を生かすなら「得点を許した」、もしくは「点を許した」であろう。
この「失点を許す」という言い方はけっこう実況放送でも耳にする。
その度に気になって仕方ない。
おそらく「失点は許されません」という受け身形と混同しているのではないか。
「失点は許されません」ならわかる。
この場合の「許す」の主体はファンであり、監督やコーチである。
彼らが、「点を失うこと」を許さないのだ。
しかし「失点を許す」の主体(主語)はあくまで投手、あるいはチームであるはずだ。
相手に「許す」のは「点を入れること」であり、それを失うことではない。
瞬時に言葉を選ばなければならない実況放送なら、まだ大目に見ることもできるが、
活字に残る新聞記事には正しい日本語表現を要求したい。

2010年05月16日
「原因」のふりがな
中3の生徒が、その日の中間テストの出来を話し合っていた。
国語のテストで、漢字の読みに「原因」というのがあったらしい。
中3のテストにしては簡単すぎないか?と思ったのだが、話を聞いていると一人が
「げいいん」と書いたという。
もう一人は「げんいん」と答えたそうで、どちらが正しいかわからないようだ。
もちろん「げんいん」が正解である。
「原」を「げい」と読む例など聞いたことがない。
ただ、音を聞いたり発したりするときは「ん」をあまり意識していないのかも知れない。
「い」の方が言いやすいのかも...。
小学生にはこの間違いが結構ある。
「全員」が「ぜいいん」になったり、「店員」を「ていいん」と書いたり...。
それには慣れていたが、まさか中3がそんな間違いをするとは思ってもいなかった。
文頭に「なので」や「なのに」を使う。
「やはり」を「やっぱ」、「いやだ」を「やだ」と書く。
「見てる」(正しくは「見ている」)「~けど」(「~けれど」)などは、
ごく当たり前の書き方になっている。
話し言葉をそのまま書き言葉に使うことに全く抵抗がないのだ。
やはり書くことを柱に据えた「言語力」を養成しなければいけない。
本離れ、メールの普及などの現状を見ていると、放っておいて自然に育つ力ではないと思う。
学校の国語の授業にも、今のところあまり期待できないのだ。
因みにATOKで「げいいん」と打ってみると、変換候補として「鯨飲」の次に「原因」も出てくる。
「「げんいん」の誤り」という注釈つきである。
それだけ間違って覚えている人が多いということか...。
日本語変換ソフトの開発者も大変である。

国語のテストで、漢字の読みに「原因」というのがあったらしい。
中3のテストにしては簡単すぎないか?と思ったのだが、話を聞いていると一人が
「げいいん」と書いたという。
もう一人は「げんいん」と答えたそうで、どちらが正しいかわからないようだ。
もちろん「げんいん」が正解である。
「原」を「げい」と読む例など聞いたことがない。
ただ、音を聞いたり発したりするときは「ん」をあまり意識していないのかも知れない。
「い」の方が言いやすいのかも...。
小学生にはこの間違いが結構ある。
「全員」が「ぜいいん」になったり、「店員」を「ていいん」と書いたり...。
それには慣れていたが、まさか中3がそんな間違いをするとは思ってもいなかった。
文頭に「なので」や「なのに」を使う。
「やはり」を「やっぱ」、「いやだ」を「やだ」と書く。
「見てる」(正しくは「見ている」)「~けど」(「~けれど」)などは、
ごく当たり前の書き方になっている。
話し言葉をそのまま書き言葉に使うことに全く抵抗がないのだ。
やはり書くことを柱に据えた「言語力」を養成しなければいけない。
本離れ、メールの普及などの現状を見ていると、放っておいて自然に育つ力ではないと思う。
学校の国語の授業にも、今のところあまり期待できないのだ。
因みにATOKで「げいいん」と打ってみると、変換候補として「鯨飲」の次に「原因」も出てくる。
「「げんいん」の誤り」という注釈つきである。
それだけ間違って覚えている人が多いということか...。
日本語変換ソフトの開発者も大変である。

2010年05月15日
歴史教科書の文章
中学の社会の教科書は退屈だ。
教科書なんてそんなものだと言ってしまえばそれまでだが、もう少し何とかならないものか。
手元に平成8年発行と18年発行(現行)の歴史教科書がある(いずれも東京書籍)。
新しい方はB5版になり、全ページにカラーの写真や図表が満載だ。
初めに「これからみなさんといっしょに学習していく友だち」が出てくる。
本文中の随所でそのイラストが登場して、
「どんなちがいがあるかな」「何をしているんだろう」などと生徒に語りかける構成だ。
小学校の教科書と大差ない。
文体も8年版の「である」調から「ですます」調に変わった。
そのために文末表現が恐ろしく単調になり、「~しました」「~でした」の連発である。
事実の羅列のみになるのは仕方ないが、文章に全くリズムが感じられず、読み進めるのが苦痛になる。
おまけに一文が長い!
例として、18年版の鎌倉時代の記述を挙げる。
承久の乱の説明で、後鳥羽上皇が挙兵した後の文である。
幕府は大軍を率いてこれを破り(承久の乱)、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視するとともに、
上皇側についた貴族や西国の武士の領地を取り上げ、地頭に東国の武士を任命し、幕府の支配力は
いちだんと強まりました。
句読点を入れて101文字である。
スラスラ頭に入ってくるのは、精々50字程度の文ではなかろうか。
この文には主語が2つ出てくるので(「幕府は」と「支配力は」)よけいに読みにくい。
同じ箇所が8年版ではこうなっている。
しかし上皇がわの期待に反して、東国の武士の大部分は北条氏についたため、大軍の前に敗れ去って、
上皇は隠岐(島根県)に流された。これを承久の乱という。
乱のあと、幕府は、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視し、西国の支配に当たらせた。また、上皇
がわについた貴族や武士の領地を取り上げて、その地の地頭に東国の武士を任命したので、幕府の全
国に対する支配力はいちだんと強くなった。
どうだろう?
8年版の方がはるかに読みやすく、記述が生き生きとしている感じがしないだろうか?
「である」調で1文も適度の長さに切ってあるため、リズムがある。
「上皇がわの期待に反し」や「大軍の前に敗れ去って」という表現も味がある。
「また、」以降の文にはやはり主語が2つあるが、「~ので」を入れたことでわかりやすくなっている。
「ゆとり教育」の影響で教科書が薄くなり、字数に制限があるのだろうが、
それなら「ですます」調をやめて少しでも字数を減らせばいい。
カラフルな写真にスペースを割くより本文を充実させればいい。
他教科の教科書にも、おしなべて同じことが言える。
薄くなって本文が減った。「親しみやすさ」ばかりが目につく。
中身が少なくなったから楽になるかといえば、事実は全く逆である。
説明が少ない分、かえってわかりにくくなっているのだ。
塾では昔の教科書や高校の教科書を見るよう指導している。
薄っぺらな、「親しみやすい」教科書は、生徒を馬鹿にしているとしか思えない。
ゆとり教育見直しで教科書の中身は少しはましになるかも知れないが、
文章も良質なものに改めてほしいと強く望む。

教科書なんてそんなものだと言ってしまえばそれまでだが、もう少し何とかならないものか。
手元に平成8年発行と18年発行(現行)の歴史教科書がある(いずれも東京書籍)。
新しい方はB5版になり、全ページにカラーの写真や図表が満載だ。
初めに「これからみなさんといっしょに学習していく友だち」が出てくる。
本文中の随所でそのイラストが登場して、
「どんなちがいがあるかな」「何をしているんだろう」などと生徒に語りかける構成だ。
小学校の教科書と大差ない。
文体も8年版の「である」調から「ですます」調に変わった。
そのために文末表現が恐ろしく単調になり、「~しました」「~でした」の連発である。
事実の羅列のみになるのは仕方ないが、文章に全くリズムが感じられず、読み進めるのが苦痛になる。
おまけに一文が長い!
例として、18年版の鎌倉時代の記述を挙げる。
承久の乱の説明で、後鳥羽上皇が挙兵した後の文である。
幕府は大軍を率いてこれを破り(承久の乱)、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視するとともに、
上皇側についた貴族や西国の武士の領地を取り上げ、地頭に東国の武士を任命し、幕府の支配力は
いちだんと強まりました。
句読点を入れて101文字である。
スラスラ頭に入ってくるのは、精々50字程度の文ではなかろうか。
この文には主語が2つ出てくるので(「幕府は」と「支配力は」)よけいに読みにくい。
同じ箇所が8年版ではこうなっている。
しかし上皇がわの期待に反して、東国の武士の大部分は北条氏についたため、大軍の前に敗れ去って、
上皇は隠岐(島根県)に流された。これを承久の乱という。
乱のあと、幕府は、京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視し、西国の支配に当たらせた。また、上皇
がわについた貴族や武士の領地を取り上げて、その地の地頭に東国の武士を任命したので、幕府の全
国に対する支配力はいちだんと強くなった。
どうだろう?
8年版の方がはるかに読みやすく、記述が生き生きとしている感じがしないだろうか?
「である」調で1文も適度の長さに切ってあるため、リズムがある。
「上皇がわの期待に反し」や「大軍の前に敗れ去って」という表現も味がある。
「また、」以降の文にはやはり主語が2つあるが、「~ので」を入れたことでわかりやすくなっている。
「ゆとり教育」の影響で教科書が薄くなり、字数に制限があるのだろうが、
それなら「ですます」調をやめて少しでも字数を減らせばいい。
カラフルな写真にスペースを割くより本文を充実させればいい。
他教科の教科書にも、おしなべて同じことが言える。
薄くなって本文が減った。「親しみやすさ」ばかりが目につく。
中身が少なくなったから楽になるかといえば、事実は全く逆である。
説明が少ない分、かえってわかりにくくなっているのだ。
塾では昔の教科書や高校の教科書を見るよう指導している。
薄っぺらな、「親しみやすい」教科書は、生徒を馬鹿にしているとしか思えない。
ゆとり教育見直しで教科書の中身は少しはましになるかも知れないが、
文章も良質なものに改めてほしいと強く望む。
2010年05月14日
言霊
先日長野日大中学の塾関係者向け説明会に行った。
終了後平安堂東和田店に寄ったら、欲しい本がいっぱいあって、厳選の後6冊を購入。
この書店とは妙に相性がいいのだ。
同じ平安堂でも、川中島店ではこうはならない。
その中の1冊がなかなか良かった。
金田一秀穂著「15歳の日本語上達法」である。
講談社から「15歳の寺子屋」シリーズとして刊行されているものの一つだ。
まず表紙のキャッチフレーズに大いに賛同。
「大切なのは漢字を記憶することより、言葉で考えることだ!」
100ページ足らずで中学生向けの文章なので、あっという間に読み終えた。
言葉の持つ力の大きさ、言葉で表現することの限界などが説かれており、
日本語力をアップする必要性を訴えている。
わかりやすくするために多くの例が挙げられているが、こんな話が印象に残った。
英語には「肩が凝る」という表現はないという。
従って、英語圏の人は後頭部や背中が痛くなることはあっても、肩が凝ることはない。
ところが、日本語の「肩が凝る」を知った途端、肩が凝り始めるそうだ。
逆の例も紹介されている。
アメリカでは「風邪をひくと耳が痛くなる」が常識で、
筆者はそれまでそんな経験はなかったのに、
それを知ってからは、風邪をひく度に耳が痛いというのだ。
まさに言葉の力だ。言霊である!
言葉が人間の思考や心理を支配し、体にまで影響を与えてしまう...。
「疲れた」を連発していると、実際にはたいした疲労でなくてもどっと疲れる。
「無理だ」と言った瞬間に本当に無理になる。
「ブルー・マンデー」も「五月病」も「K・Y」も、そんな言葉があるからちょっとしたことを大袈裟に考えてしまうのではないか。
「うつ」だってそうだ。
その言葉がなければ、そんなに深刻にならずに済むのかも知れない。
「言葉なんか おぼえるんじゃなかった」と言ったのは田村隆一(詩人)である。
もちろん、逆にそれがあるお蔭で喜びを感じたり救われたりする言葉もあるだろう。
「愛」「幸せ」「ぬくもり」「思いやり」「オンリー・ワン」などなど...。
そう言えば、私はかなり大きくなるまで、カニ蒲を本物のカニだと信じていた。
事実を知らないままの方が、ずっと幸せだったかも知れない。
なまじ知識があるために柔軟な発想ができなかったり、技術を持つが故にもっとうまい方法を探そうとしなかったり、ということもあろう。
勉強すること、練習すること、進化することなどについて、いろいろ考えさせられた一日であった。

終了後平安堂東和田店に寄ったら、欲しい本がいっぱいあって、厳選の後6冊を購入。
この書店とは妙に相性がいいのだ。
同じ平安堂でも、川中島店ではこうはならない。
その中の1冊がなかなか良かった。
金田一秀穂著「15歳の日本語上達法」である。
講談社から「15歳の寺子屋」シリーズとして刊行されているものの一つだ。
まず表紙のキャッチフレーズに大いに賛同。
「大切なのは漢字を記憶することより、言葉で考えることだ!」
100ページ足らずで中学生向けの文章なので、あっという間に読み終えた。
言葉の持つ力の大きさ、言葉で表現することの限界などが説かれており、
日本語力をアップする必要性を訴えている。
わかりやすくするために多くの例が挙げられているが、こんな話が印象に残った。
英語には「肩が凝る」という表現はないという。
従って、英語圏の人は後頭部や背中が痛くなることはあっても、肩が凝ることはない。
ところが、日本語の「肩が凝る」を知った途端、肩が凝り始めるそうだ。
逆の例も紹介されている。
アメリカでは「風邪をひくと耳が痛くなる」が常識で、
筆者はそれまでそんな経験はなかったのに、
それを知ってからは、風邪をひく度に耳が痛いというのだ。
まさに言葉の力だ。言霊である!
言葉が人間の思考や心理を支配し、体にまで影響を与えてしまう...。
「疲れた」を連発していると、実際にはたいした疲労でなくてもどっと疲れる。
「無理だ」と言った瞬間に本当に無理になる。
「ブルー・マンデー」も「五月病」も「K・Y」も、そんな言葉があるからちょっとしたことを大袈裟に考えてしまうのではないか。
「うつ」だってそうだ。
その言葉がなければ、そんなに深刻にならずに済むのかも知れない。
「言葉なんか おぼえるんじゃなかった」と言ったのは田村隆一(詩人)である。
もちろん、逆にそれがあるお蔭で喜びを感じたり救われたりする言葉もあるだろう。
「愛」「幸せ」「ぬくもり」「思いやり」「オンリー・ワン」などなど...。
そう言えば、私はかなり大きくなるまで、カニ蒲を本物のカニだと信じていた。
事実を知らないままの方が、ずっと幸せだったかも知れない。
なまじ知識があるために柔軟な発想ができなかったり、技術を持つが故にもっとうまい方法を探そうとしなかったり、ということもあろう。
勉強すること、練習すること、進化することなどについて、いろいろ考えさせられた一日であった。

2010年05月13日
証拠より論
いろはがるたでもお馴染みの「論より証拠」ということわざがある。
江戸いろはがるたの中では、「花より団子」「楽あれば苦あり」などとともに、平成になっても身近なことわざの一つであろう。
商品の効能をアピールするための表現にもよく使われる。
「論より証拠、これをご覧ください!」学習塾が合格実績を誇らしげにPRするのも同じである。
ビジネスの世界では確かに結果がすべてなのかも知れない。
ただ、日本人はどうも「論」を軽んじて「証拠」ばかりを重視しすぎるように思う。
科学的根拠のない薬や治療法を簡単に信じてしまったり、小さなきっかけで怪しげな新興宗教に洗脳されてしまったりする人が少なくない。
以前の記事で書いたように、自分で考えることを怠ってマスコミや周りのムードに流されているだけの人が多いのも、同じ根っこから発生する現象だと思う。
日本では論理的に考えることに価値が置かれてこなかったのだ。嫌われてきたと言ってもいい。
論理的な説明をしようとすれば「へりくつ」と言われ、結果だけでなくプロセスも大切だと主張すれば「理屈じゃない」と切り捨てられる。
長野県人は「議論好き」だと言われるが、この言葉にはマイナスイメージの方が多いのではないか。
これとセットで言われる「理屈っぽい」という評価を見れば明らかである。
事実や体験を重視することも大事である。
それは否定しない。
生活体験が乏しい子は想像力も貧困になる。
知識を増やすことも必要であろう。
だが、それ以上に重要なのは、論理的に思考して自分の考えを組み立てていく力である。
自分の意見を論理的に表現できる能力である。
特に子どもたちには、結果よりもそこに至る過程を大切にしてほしい。
なぜそうなるのか、「理屈」をしっかり考えてもらいたい。
大人にできることは、成果を急がずじっくり待つことだけだ。
「論より証拠」で子どもたちの考える芽を摘んではならない。

江戸いろはがるたの中では、「花より団子」「楽あれば苦あり」などとともに、平成になっても身近なことわざの一つであろう。
商品の効能をアピールするための表現にもよく使われる。
「論より証拠、これをご覧ください!」学習塾が合格実績を誇らしげにPRするのも同じである。
ビジネスの世界では確かに結果がすべてなのかも知れない。
ただ、日本人はどうも「論」を軽んじて「証拠」ばかりを重視しすぎるように思う。
科学的根拠のない薬や治療法を簡単に信じてしまったり、小さなきっかけで怪しげな新興宗教に洗脳されてしまったりする人が少なくない。
以前の記事で書いたように、自分で考えることを怠ってマスコミや周りのムードに流されているだけの人が多いのも、同じ根っこから発生する現象だと思う。
日本では論理的に考えることに価値が置かれてこなかったのだ。嫌われてきたと言ってもいい。
論理的な説明をしようとすれば「へりくつ」と言われ、結果だけでなくプロセスも大切だと主張すれば「理屈じゃない」と切り捨てられる。
長野県人は「議論好き」だと言われるが、この言葉にはマイナスイメージの方が多いのではないか。
これとセットで言われる「理屈っぽい」という評価を見れば明らかである。
事実や体験を重視することも大事である。
それは否定しない。
生活体験が乏しい子は想像力も貧困になる。
知識を増やすことも必要であろう。
だが、それ以上に重要なのは、論理的に思考して自分の考えを組み立てていく力である。
自分の意見を論理的に表現できる能力である。
特に子どもたちには、結果よりもそこに至る過程を大切にしてほしい。
なぜそうなるのか、「理屈」をしっかり考えてもらいたい。
大人にできることは、成果を急がずじっくり待つことだけだ。
「論より証拠」で子どもたちの考える芽を摘んではならない。

2010年05月11日
横板に雨垂れ
「立て板に水」という表現がある。
「広辞苑」では「弁舌がすらすらとしてよどみのないさま」という説明だ。
この慣用句、プラス評価の言葉なのだろうか?
もちろんプラスで使われることもあるだろう。
アナウンサーや司会者には「立て板に水」の喋りが要求される。
特にスポーツ、競馬などの実況放送にはこの能力が欠かせない。
ところが、講演会やセミナーなどでこの話し方をされると、頭にも心にも一向に残らない。
一本調子で一方的な話は、一つ一つの内容はわかったつもりになっても、
終わってみると印象に残らず、何か物足りない感じがするのだ。
それよりはボソボソ、ポツリポツリという語り口の方が心に響く。
考えながら言葉を選んでいる、という感じが私には好ましく思える。
素朴というか木訥(ぼくとつ)というか、信じていい気がする。
俳優で言えば宇野重吉、笠智衆、大滝秀治といったところか...。
スラスラと話す所もあっていいいのだ。
要はメリハリの付け方、間の取り方であると思う。
絶妙の「間」は聞き手を引きつけ、考えさせる効果を生む。
実は私も、つい早口で一本調子になりがちなので気をつけている。
保護者との面談の際にも、意識的に間をおくことがある。
強弱をつけるとともに、最もふさわしい言葉を探しているのだ。
「立て板に水」の反対は「横板に雨垂れ」と言うそうだ。
何にでも効率が求められる時代、この「横板に...」こそもっと評価すべきではないか。
話す方も聞く方も、本当の贅沢な時間を共有できると思うのだが...。
NHKのアナウンサーの原稿を読むスピードが、数十年前よりずいぶん速くなっているそうだ。
昔のニュースや野球中継の放送を聞くと、ずいぶん悠長に聞こえる。
それだけ早口に慣れてしまったということか...。
芸能で「間」の取り方が悪いことを「間抜け」と言った。
「まぬけ」の語源である...。

「広辞苑」では「弁舌がすらすらとしてよどみのないさま」という説明だ。
この慣用句、プラス評価の言葉なのだろうか?
もちろんプラスで使われることもあるだろう。
アナウンサーや司会者には「立て板に水」の喋りが要求される。
特にスポーツ、競馬などの実況放送にはこの能力が欠かせない。
ところが、講演会やセミナーなどでこの話し方をされると、頭にも心にも一向に残らない。
一本調子で一方的な話は、一つ一つの内容はわかったつもりになっても、
終わってみると印象に残らず、何か物足りない感じがするのだ。
それよりはボソボソ、ポツリポツリという語り口の方が心に響く。
考えながら言葉を選んでいる、という感じが私には好ましく思える。
素朴というか木訥(ぼくとつ)というか、信じていい気がする。
俳優で言えば宇野重吉、笠智衆、大滝秀治といったところか...。
スラスラと話す所もあっていいいのだ。
要はメリハリの付け方、間の取り方であると思う。
絶妙の「間」は聞き手を引きつけ、考えさせる効果を生む。
実は私も、つい早口で一本調子になりがちなので気をつけている。
保護者との面談の際にも、意識的に間をおくことがある。
強弱をつけるとともに、最もふさわしい言葉を探しているのだ。
「立て板に水」の反対は「横板に雨垂れ」と言うそうだ。
何にでも効率が求められる時代、この「横板に...」こそもっと評価すべきではないか。
話す方も聞く方も、本当の贅沢な時間を共有できると思うのだが...。
NHKのアナウンサーの原稿を読むスピードが、数十年前よりずいぶん速くなっているそうだ。
昔のニュースや野球中継の放送を聞くと、ずいぶん悠長に聞こえる。
それだけ早口に慣れてしまったということか...。
芸能で「間」の取り方が悪いことを「間抜け」と言った。
「まぬけ」の語源である...。
2010年05月10日
三角形の合同条件についての疑問
中学で習う三角形の合同条件は、直角三角形の特例を除けば次の3つです。
1.三辺がそれぞれ等しい。
2.二辺とその間の角がそれぞれ等しい。
3.一辺とその両端の角がそれぞれ等しい。
あるとき、この「3」について疑問が湧きました。
三角形の内角の和は180°に決まっているのだから、2角が等しければ当然残りの角も等しい。
ならば、一辺と「その両端の角」でなくても、どこか2つの角が等しければいいのではないだろか...?
たとえば△ABCがBC=4cm、∠A=70°、∠B=60°、∠C=50°とする。
△DEFでEF=4cm、∠D=70°、∠E=60°なら、自動的に∠F=50°になるので、
等しいのが「その両端の角」でなくても合同になるのではないか...。
こう言われると、そう言えばそうだと納得してしまいませんか?
実はこのイチャモンには重大な欠陥があるのです。
やはり一辺と「その両端の角」でなくてはいけないのです(...というか、それが一番わかりやすい)。
上の例、どこがおかしいかわかりますか?
正解は次回...。

1.三辺がそれぞれ等しい。
2.二辺とその間の角がそれぞれ等しい。
3.一辺とその両端の角がそれぞれ等しい。
あるとき、この「3」について疑問が湧きました。
三角形の内角の和は180°に決まっているのだから、2角が等しければ当然残りの角も等しい。
ならば、一辺と「その両端の角」でなくても、どこか2つの角が等しければいいのではないだろか...?
たとえば△ABCがBC=4cm、∠A=70°、∠B=60°、∠C=50°とする。
△DEFでEF=4cm、∠D=70°、∠E=60°なら、自動的に∠F=50°になるので、
等しいのが「その両端の角」でなくても合同になるのではないか...。
こう言われると、そう言えばそうだと納得してしまいませんか?
実はこのイチャモンには重大な欠陥があるのです。
やはり一辺と「その両端の角」でなくてはいけないのです(...というか、それが一番わかりやすい)。
上の例、どこがおかしいかわかりますか?
正解は次回...。





