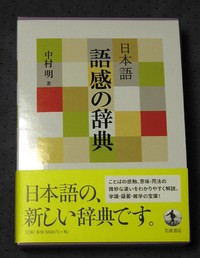2010年05月21日
「生前」ということば
新聞を読んでいてふと思った。
亡くなった人が生きていたときのことをなぜ「生前」と言うのか?
「生きていた前」では意味が通じない。
「死後」の反対で「死前」なら納得できるが、そんな言葉は聞いたことがない。
同じことを考えた人は多いらしく、検索したらいろいろな意見があった。
「死んでから別の人生が始まる。死こそ新しい生の始まり。」という説。
仏教の輪廻思想のようなものか。
仏となって真の「人生」が始まるということか...。
「前(さき)の生」の意味だとする説。
死を境に時代を分け、「前」の生きていた時代をこう呼ぶという。
後の「前」から「生」へ、漢文のように戻って読むわけだ。
一番腑に落ちるのは、「死後」という言葉の
「死」と「後」それぞれの対となる字を単純に並べただけという考え方だ。
「死」の反対の「生」+「後」の反対の「前」で「生前」である。
ところが、同様の例を探しても、そんな反意語の作り方は他には見つからない。
「円高」と「円安」、「表面」と「裏面」のように、
一字だけを反対の意味の漢字に換える例がほとんどだ。
「近接」と「遠隔」、「優良」と「劣悪」、「賢明」と「暗愚」などは
近い例かも知れないが、これらはもともと似た意味の漢字を並べた熟語である。
「死後」のように、前の字が後の字を修飾している熟語(「死」の「後」)では、
そんな反意語は皆無である。
結局、よくわからないままだ。
「生前」の反意語は普通に考えれば「生後」だろう。
しかしこの言葉は全く違う意味になる。
「生後」は「生まれて後」のことであり、「生後3ヶ月」のように使う。
それなら「生前」は「生まれる前」になって、母親の胎内にいるときのことになってもよさそうだ。
「紀元前」のように、「生前1ヶ月」は生まれる1ヶ月前を指すのなら論理的だが、
そんな言い方は聞いたことがない。
「生前」はあくまで「死後」の対義語なのである。
生や死に伴う言葉には、不思議なものがまだありそうだ。
仏教用語がかなり影響しているのではないか。
「誕生」と「生誕」の使い分けも興味深いテーマなので、また考えてみたい。

亡くなった人が生きていたときのことをなぜ「生前」と言うのか?
「生きていた前」では意味が通じない。
「死後」の反対で「死前」なら納得できるが、そんな言葉は聞いたことがない。
同じことを考えた人は多いらしく、検索したらいろいろな意見があった。
「死んでから別の人生が始まる。死こそ新しい生の始まり。」という説。
仏教の輪廻思想のようなものか。
仏となって真の「人生」が始まるということか...。
「前(さき)の生」の意味だとする説。
死を境に時代を分け、「前」の生きていた時代をこう呼ぶという。
後の「前」から「生」へ、漢文のように戻って読むわけだ。
一番腑に落ちるのは、「死後」という言葉の
「死」と「後」それぞれの対となる字を単純に並べただけという考え方だ。
「死」の反対の「生」+「後」の反対の「前」で「生前」である。
ところが、同様の例を探しても、そんな反意語の作り方は他には見つからない。
「円高」と「円安」、「表面」と「裏面」のように、
一字だけを反対の意味の漢字に換える例がほとんどだ。
「近接」と「遠隔」、「優良」と「劣悪」、「賢明」と「暗愚」などは
近い例かも知れないが、これらはもともと似た意味の漢字を並べた熟語である。
「死後」のように、前の字が後の字を修飾している熟語(「死」の「後」)では、
そんな反意語は皆無である。
結局、よくわからないままだ。
「生前」の反意語は普通に考えれば「生後」だろう。
しかしこの言葉は全く違う意味になる。
「生後」は「生まれて後」のことであり、「生後3ヶ月」のように使う。
それなら「生前」は「生まれる前」になって、母親の胎内にいるときのことになってもよさそうだ。
「紀元前」のように、「生前1ヶ月」は生まれる1ヶ月前を指すのなら論理的だが、
そんな言い方は聞いたことがない。
「生前」はあくまで「死後」の対義語なのである。
生や死に伴う言葉には、不思議なものがまだありそうだ。
仏教用語がかなり影響しているのではないか。
「誕生」と「生誕」の使い分けも興味深いテーマなので、また考えてみたい。

Posted by どーもオリゴ糖 at 14:00│Comments(0)
│ことば