2011年09月20日
市議会選挙に思う
騒々しい選挙戦が終わった。
絶好の昼寝どき、大音量にさんざん悩まされたものだ。
あの選挙カーでわめき回る運動は、はたして効果があるのだろうか?
名前と「がんばります」「お願いします」の連呼ばかりで、政策なんて何も伝わってこない。
私など、あまりうるさい奴は、それだけで入れたくなくなる。
昔、小さな町(〇〇郡✕✕町)に住んでいた頃、
隣の集落から新人(若くはないが...)が町議選に立候補したことがある。
私がいた集落は小規模で神社もなかったので、祭りや老人会など、
そのムラと行動を共にすることが多かった。
その候補者自身のこともよく知っていたし、お世話になったこともある。
立候補したからには、受かってくれればいいなとは思っていた。
気楽に構えていたのだが...。
ほどなく、田舎特有の選挙合戦に巻き込まれることになる。
まずは壮行会のお知らせ。
続けざまに、各人の役割分担表が回ってきた。
知らない間に「広報班」に振り分けられている。
なんだこれ?
...そんなこと一言も聞いてないぞ!
自分たちの地区から立候補者が出たら、心情的に応援しようという気はわかる。
ただ、その人物に投票するか否かは別問題である。
わがムラから議員さんが出れば、ムラの公共問題に予算が回ってくる、
自分たちの地区が少しでもよくなる...。
そんな気持ちの人が、田舎であればあるほど多いのが実情だろう。
だが、そんな「せこい」考え方で町会議員を選ぶべきではない。
その頃、町は「平成の大合併」問題にどう対応するか、方向性が問われていた(結局吸収合併された)。
自分のムラのことより町全体のことを優先して考えられる人こそ、議員にふさわしいのではないか...。
結局、私はその選挙に一切協力しなかった。
壮行会だけは出て、候補写本に人直接考えを伝えた。
個人としては応援するが、ムラぐるみの選挙戦には協力できかねると...。
快く了承してもらい、あとは大家さんにだけ意見を話し、
その他大勢には仕事の忙しさを理由にごました。
最終的には私もその人に投票し、無事当選した。
祝賀会にはもちろん出席しなかったが...。
今のムラでも、地区から候補者が出れば同じような展開になるだろう。
密かにそれを恐れている。
街から近いのにムラ意識が強く残るここでは、
前のようにすんなり受け流すわけには行かないかも知れない。
誰に投票するかは、いつも選挙公報を見て決める。
今回もじっくり読んでみたのだが...。
皆同じようなことばかり書いていて、伝わってくるものがない。
万人受けを狙ってあれもこれもと詰め込んでいるので、
この人に!という決め手がないのだ。
これでは、誰々さんに頼まれたからとか、地元の人だからという理由で入れるしかない。
投票率が過去最低の46%に留まったのも頷けるというものだ。
相も変わらぬ地盤、看板、カバン頼みの選挙戦...。
主義・主張や公約で争うという理想が実現するのは、特に地方議会の選挙では、当分難しいようである。

※画像は松代の山寺常山邸。
絶好の昼寝どき、大音量にさんざん悩まされたものだ。
あの選挙カーでわめき回る運動は、はたして効果があるのだろうか?
名前と「がんばります」「お願いします」の連呼ばかりで、政策なんて何も伝わってこない。
私など、あまりうるさい奴は、それだけで入れたくなくなる。
昔、小さな町(〇〇郡✕✕町)に住んでいた頃、
隣の集落から新人(若くはないが...)が町議選に立候補したことがある。
私がいた集落は小規模で神社もなかったので、祭りや老人会など、
そのムラと行動を共にすることが多かった。
その候補者自身のこともよく知っていたし、お世話になったこともある。
立候補したからには、受かってくれればいいなとは思っていた。
気楽に構えていたのだが...。
ほどなく、田舎特有の選挙合戦に巻き込まれることになる。
まずは壮行会のお知らせ。
続けざまに、各人の役割分担表が回ってきた。
知らない間に「広報班」に振り分けられている。
なんだこれ?
...そんなこと一言も聞いてないぞ!
自分たちの地区から立候補者が出たら、心情的に応援しようという気はわかる。
ただ、その人物に投票するか否かは別問題である。
わがムラから議員さんが出れば、ムラの公共問題に予算が回ってくる、
自分たちの地区が少しでもよくなる...。
そんな気持ちの人が、田舎であればあるほど多いのが実情だろう。
だが、そんな「せこい」考え方で町会議員を選ぶべきではない。
その頃、町は「平成の大合併」問題にどう対応するか、方向性が問われていた(結局吸収合併された)。
自分のムラのことより町全体のことを優先して考えられる人こそ、議員にふさわしいのではないか...。
結局、私はその選挙に一切協力しなかった。
壮行会だけは出て、候補写本に人直接考えを伝えた。
個人としては応援するが、ムラぐるみの選挙戦には協力できかねると...。
快く了承してもらい、あとは大家さんにだけ意見を話し、
その他大勢には仕事の忙しさを理由にごました。
最終的には私もその人に投票し、無事当選した。
祝賀会にはもちろん出席しなかったが...。
今のムラでも、地区から候補者が出れば同じような展開になるだろう。
密かにそれを恐れている。
街から近いのにムラ意識が強く残るここでは、
前のようにすんなり受け流すわけには行かないかも知れない。
誰に投票するかは、いつも選挙公報を見て決める。
今回もじっくり読んでみたのだが...。
皆同じようなことばかり書いていて、伝わってくるものがない。
万人受けを狙ってあれもこれもと詰め込んでいるので、
この人に!という決め手がないのだ。
これでは、誰々さんに頼まれたからとか、地元の人だからという理由で入れるしかない。
投票率が過去最低の46%に留まったのも頷けるというものだ。
相も変わらぬ地盤、看板、カバン頼みの選挙戦...。
主義・主張や公約で争うという理想が実現するのは、特に地方議会の選挙では、当分難しいようである。
※画像は松代の山寺常山邸。
2011年09月06日
熟成を待つ
先日新聞に、長野県家庭教師協会のチラシが入ってきた。
いわく、普通の個別指導塾では自習の時間が多いが、
家庭教師なら先生を独り占めできてたくさん教えてもらえるetc....。
これを読んで、やはり家庭教師は高いだけのことはあると思う人も少なくないだろう。
だが、はたしてこれは、生徒の力を育むための理想の指導なのだろうか?
教えれば教えるほど、子どもは伸びるのだろうか...?
答はNoである。
たくさん教えてくれる先生、わからなかったらすぐに教えてくれるのが
いい先生というのは大きな誤解だ。
平均レベルの高校には入れればいい、合格さえすれば高校でつまずいても構わないということなら、
ひたすら教え込めばどうにかなるかも知れない。
しかし、それ以上の力を子どもにつけさせたいのであれば、この方法では限界がある。
少しわからないとすぐに解き方を教わろうとするようでは、
これから先の長い人生、壁にぶつかるたびに挫折することになりかねない。
子どもたちには、自分の頭で考える時間が不可欠である。
教わったことを咀嚼し、消化する時間が絶対に必要なのだ。
意味もわからずただ丸暗記するだけでは、すぐに忘れるし応用が利かない。
新たに得た知識を自分なりに納得し、腑に落ちるまで考えぬく体験を積むことは、
必ずや将来の糧となることだろう。
次から次へ教え込んでいては熟成の時間が取れない。
あえて全部を教えず、ヒントを出したり自分で調べさせたり...。
自分で考えることを促し、生徒の思考を邪魔しない、
必要があればその子の思考に沿った的確なアドバイスを与える...。
そんな指導こそが真の理想型ではないだろうか...。
私も経験があるのだが、家庭教師という形態はどうしても教えすぎてしまう傾向にある。
高いお金をもらっているのだからという意識も働くし、何より1対1だと暇なのだ。
親がお茶でも持って来ようものなら、ここぞとばかり熱心さをアピールして教え込んだり...。
生徒は一方的に教えられるだけで、自分で考える余地はほとんどない。
ちょっと考えてわからなかったら、訊けばすぐ教えてくれるのだから...。
結果として、困ったら人に頼ればいいという受け身の人間を生産することになってしまう。
これは、親がわが子に教える場合にも少なからず共通することだと言えよう。
自分も含め、わが子に対してはどうしても教えたくなってしまう...。
イライラが先に立って、ゆとりを持って接することができないのだ。
勉強に限らず、大人が子どもに何かを身につけさせようとすると、
つい先回りして教え込みたくなるものである。
その方が手っ取り早いのだ。
しかし、上述したように、それでは子どもは成長しない。
教えすぎない我慢、内なる熟成を待つ忍耐こそが肝要である。
親には、子どもの可能性を信じて長い目で見守っていただくようお願いしている。

いわく、普通の個別指導塾では自習の時間が多いが、
家庭教師なら先生を独り占めできてたくさん教えてもらえるetc....。
これを読んで、やはり家庭教師は高いだけのことはあると思う人も少なくないだろう。
だが、はたしてこれは、生徒の力を育むための理想の指導なのだろうか?
教えれば教えるほど、子どもは伸びるのだろうか...?
答はNoである。
たくさん教えてくれる先生、わからなかったらすぐに教えてくれるのが
いい先生というのは大きな誤解だ。
平均レベルの高校には入れればいい、合格さえすれば高校でつまずいても構わないということなら、
ひたすら教え込めばどうにかなるかも知れない。
しかし、それ以上の力を子どもにつけさせたいのであれば、この方法では限界がある。
少しわからないとすぐに解き方を教わろうとするようでは、
これから先の長い人生、壁にぶつかるたびに挫折することになりかねない。
子どもたちには、自分の頭で考える時間が不可欠である。
教わったことを咀嚼し、消化する時間が絶対に必要なのだ。
意味もわからずただ丸暗記するだけでは、すぐに忘れるし応用が利かない。
新たに得た知識を自分なりに納得し、腑に落ちるまで考えぬく体験を積むことは、
必ずや将来の糧となることだろう。
次から次へ教え込んでいては熟成の時間が取れない。
あえて全部を教えず、ヒントを出したり自分で調べさせたり...。
自分で考えることを促し、生徒の思考を邪魔しない、
必要があればその子の思考に沿った的確なアドバイスを与える...。
そんな指導こそが真の理想型ではないだろうか...。
私も経験があるのだが、家庭教師という形態はどうしても教えすぎてしまう傾向にある。
高いお金をもらっているのだからという意識も働くし、何より1対1だと暇なのだ。
親がお茶でも持って来ようものなら、ここぞとばかり熱心さをアピールして教え込んだり...。
生徒は一方的に教えられるだけで、自分で考える余地はほとんどない。
ちょっと考えてわからなかったら、訊けばすぐ教えてくれるのだから...。
結果として、困ったら人に頼ればいいという受け身の人間を生産することになってしまう。
これは、親がわが子に教える場合にも少なからず共通することだと言えよう。
自分も含め、わが子に対してはどうしても教えたくなってしまう...。
イライラが先に立って、ゆとりを持って接することができないのだ。
勉強に限らず、大人が子どもに何かを身につけさせようとすると、
つい先回りして教え込みたくなるものである。
その方が手っ取り早いのだ。
しかし、上述したように、それでは子どもは成長しない。
教えすぎない我慢、内なる熟成を待つ忍耐こそが肝要である。
親には、子どもの可能性を信じて長い目で見守っていただくようお願いしている。
2011年07月25日
不可解な料金差
NTTの固定電話には「住宅用」と「事務用」がある。
一般的なプッシュ回線の場合、基本料は住宅用1,680円(税込)、事務用2,520円(同)となっている。
毎月840円、年にしたら1万円以上違うのだ...。
ホームページを見ても、どういう場合にどちらの種別になるのか、よくわからない。
機能に違いがあるとは思えないし、
「仕事場の電話はすべて事務用」ということでもないらしい。
今のところ判明しているのは、事務用だとタウンページに載せてもらえるということだけだ。
つまり広告料ということになる。
この料金差、はたして妥当だろうか...?
月800円の違いだけなら妥当と思われる方もあるかも知れない。
しかし、実はそれだけではないのだ。
ナンバーディスプレイやボイスワープ(転送サービス)といったオプションの料金も、
住宅用と事務用とで異なる。
この2つのサービスを加えた場合、基本料と併せて月2,000円もの差になるのだ。
これはいくら何でも高すぎないか?
こういったオプションの分まで事務用を高く設定しているのは、
足下を見ているとしか思えない。
住宅用だとタウンページに載らないという弱みにつけ込んだぼったくりではないか。
技術的に事務用の方が金がかかるというわけでもなかろうに...。
もっとも、今どきタウンページ掲載にどれだけの宣伝効果があるかは甚だ疑問である。
ネットで検索して調べる人の方が多かろう。
それに、塾という仕事では、もともとタウンページを見て問い合わせてくる人は稀である。
皆無と言ってもいいくらいだ。
圧倒的に口コミで来る例が多いし、そうでなければ看板や折込チラシが媒体となっている。
というわけで、2年前から始めた第2教室の方は、開設当初から住宅用にした。
活動を共にしている千曲市の若い塾長も、自宅で開いていることもあり、住宅用のままだ。
事務用の場合との比較はできないが、今のところ生徒は順調に増えているし、
影響はほとんどないと思われる。
一度だけ、生徒の親が外出先から電話しようとしたところ、番号がわからなかったということがあった。
また、当然のことながら、タウンページを元に塾のリストを載せているサイトの情報からも洩れる。
タウンページに載っているということが一種のステイタスであり、顧客に安心感を与えるという面もあるかも知れない。
しかし、それらのマイナス面を差し引いても、まだ住宅用の方に歩があるように思う。
セールス系の迷惑電話やFAX、DMも一切来ない。
タウンページに載せるということは、そういう業者に名簿を提供しているのとイコールでもあるのだ。
実は、このNTTの例は一例に過ぎない。
他にも、「事務用」「業務用」というだけで、
さしたる根拠もなく料金や価格がアップしている例がいくらでもあると思う。
個々に、その本質とメリット、デメリットをしかり見極めて対応したいものである。

一般的なプッシュ回線の場合、基本料は住宅用1,680円(税込)、事務用2,520円(同)となっている。
毎月840円、年にしたら1万円以上違うのだ...。
ホームページを見ても、どういう場合にどちらの種別になるのか、よくわからない。
機能に違いがあるとは思えないし、
「仕事場の電話はすべて事務用」ということでもないらしい。
今のところ判明しているのは、事務用だとタウンページに載せてもらえるということだけだ。
つまり広告料ということになる。
この料金差、はたして妥当だろうか...?
月800円の違いだけなら妥当と思われる方もあるかも知れない。
しかし、実はそれだけではないのだ。
ナンバーディスプレイやボイスワープ(転送サービス)といったオプションの料金も、
住宅用と事務用とで異なる。
この2つのサービスを加えた場合、基本料と併せて月2,000円もの差になるのだ。
これはいくら何でも高すぎないか?
こういったオプションの分まで事務用を高く設定しているのは、
足下を見ているとしか思えない。
住宅用だとタウンページに載らないという弱みにつけ込んだぼったくりではないか。
技術的に事務用の方が金がかかるというわけでもなかろうに...。
もっとも、今どきタウンページ掲載にどれだけの宣伝効果があるかは甚だ疑問である。
ネットで検索して調べる人の方が多かろう。
それに、塾という仕事では、もともとタウンページを見て問い合わせてくる人は稀である。
皆無と言ってもいいくらいだ。
圧倒的に口コミで来る例が多いし、そうでなければ看板や折込チラシが媒体となっている。
というわけで、2年前から始めた第2教室の方は、開設当初から住宅用にした。
活動を共にしている千曲市の若い塾長も、自宅で開いていることもあり、住宅用のままだ。
事務用の場合との比較はできないが、今のところ生徒は順調に増えているし、
影響はほとんどないと思われる。
一度だけ、生徒の親が外出先から電話しようとしたところ、番号がわからなかったということがあった。
また、当然のことながら、タウンページを元に塾のリストを載せているサイトの情報からも洩れる。
タウンページに載っているということが一種のステイタスであり、顧客に安心感を与えるという面もあるかも知れない。
しかし、それらのマイナス面を差し引いても、まだ住宅用の方に歩があるように思う。
セールス系の迷惑電話やFAX、DMも一切来ない。
タウンページに載せるということは、そういう業者に名簿を提供しているのとイコールでもあるのだ。
実は、このNTTの例は一例に過ぎない。
他にも、「事務用」「業務用」というだけで、
さしたる根拠もなく料金や価格がアップしている例がいくらでもあると思う。
個々に、その本質とメリット、デメリットをしかり見極めて対応したいものである。

2011年07月15日
批判もできないのか!?
夏期講習に向けた折込チラシがようやく完成し、折込センターへ持って行った。
2教室のうち、1教室分は地元の販売店へ直接依頼するが、
もう1教室の方は、エリアを担当している販売店が複数に分かれるので、
以前から信毎の折込センターに一括して頼んでいる。
販売店に直の方が折込費用が若干安いのだが、手間を考えると仕方ない。
今回も同様に手配を済ませ、やれやれと思っていたら、
昨日、その折込センターから電話がかかってきた。
何事かと思ったら、チラシの記載事項に問題があると言う。
オモテ面のコラムの一つ、「こんな日本語使っていませんか?」の一部だ。
このブログでもお馴染みの、町にあふれるおかしな日本語を指摘し、正しい表現を並べている。
×「十日ぶりに運転が再開し...」(NHKラジオのニュース)
↓
○「十日ぶりに運転を再開し...」
○「十日ぶりに運転が再開され...」
この中の「NHKラジオ」がまずいと言うのだ。
特定の企業の名前を出してはいけないと言う。
たしかに、ほかの例では「民放の」とか「ホームセンターの」という表現を使っているので、
これだけが目立つのかもしれない。
しかし、ここは敢えて「NHK」と付けたのだ。
地方の民放のレベルならまだしも(失礼!)、
天下のNHKがこんな日本語使うなよと言いたいのだ。
裏を返せば、NHKに一目置いているからこその苦言である。
規約に抵触すると言うので、センターの「折込広告基準」というのを読んでみた。
該当するとすればこれか...。
「広告文中において名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となる恐れがある表現のもの。」
つまり、誹謗中傷はダメだということだろう。
それはそうだ。
しかし、私の文章は断じてそうではない。
論理的でまっとうな批判である。
名誉や信用の毀損、業務妨害にはあたらない。
電話の相手に確認する。
万が一NHKとの間に問題が起きたとしても、それは私個人の責任に帰することではないのか?
それとも、そちらにも迷惑がかかるのか?
返事は、折込センター側は責任を追及されないとのことだった。
だったら、なぜそんな圧力をかけてくるのか...。
販売店に直接持ち込んだ方は、そんなこと一言も言ってこない。
今回は4000枚なのでそのまま折り込むが、次回からは注意してほしいと言う。
じゃあ、次からは販売店に持って行くと言って電話を切った。
自分たちの責任は問われないと言いながら、何をそんなにびくびくしているのか...。
自主的な規制は、上からの規制以上に恐ろしい。
言論の自由、ひいては民主主義の崩壊につながりかねない問題だと思っている。

※画像は庭先に来たカラスアゲハ(orミヤマカラスアゲハ)。メタリックな光沢が美しい...。
2教室のうち、1教室分は地元の販売店へ直接依頼するが、
もう1教室の方は、エリアを担当している販売店が複数に分かれるので、
以前から信毎の折込センターに一括して頼んでいる。
販売店に直の方が折込費用が若干安いのだが、手間を考えると仕方ない。
今回も同様に手配を済ませ、やれやれと思っていたら、
昨日、その折込センターから電話がかかってきた。
何事かと思ったら、チラシの記載事項に問題があると言う。
オモテ面のコラムの一つ、「こんな日本語使っていませんか?」の一部だ。
このブログでもお馴染みの、町にあふれるおかしな日本語を指摘し、正しい表現を並べている。
×「十日ぶりに運転が再開し...」(NHKラジオのニュース)
↓
○「十日ぶりに運転を再開し...」
○「十日ぶりに運転が再開され...」
この中の「NHKラジオ」がまずいと言うのだ。
特定の企業の名前を出してはいけないと言う。
たしかに、ほかの例では「民放の」とか「ホームセンターの」という表現を使っているので、
これだけが目立つのかもしれない。
しかし、ここは敢えて「NHK」と付けたのだ。
地方の民放のレベルならまだしも(失礼!)、
天下のNHKがこんな日本語使うなよと言いたいのだ。
裏を返せば、NHKに一目置いているからこその苦言である。
規約に抵触すると言うので、センターの「折込広告基準」というのを読んでみた。
該当するとすればこれか...。
「広告文中において名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となる恐れがある表現のもの。」
つまり、誹謗中傷はダメだということだろう。
それはそうだ。
しかし、私の文章は断じてそうではない。
論理的でまっとうな批判である。
名誉や信用の毀損、業務妨害にはあたらない。
電話の相手に確認する。
万が一NHKとの間に問題が起きたとしても、それは私個人の責任に帰することではないのか?
それとも、そちらにも迷惑がかかるのか?
返事は、折込センター側は責任を追及されないとのことだった。
だったら、なぜそんな圧力をかけてくるのか...。
販売店に直接持ち込んだ方は、そんなこと一言も言ってこない。
今回は4000枚なのでそのまま折り込むが、次回からは注意してほしいと言う。
じゃあ、次からは販売店に持って行くと言って電話を切った。
自分たちの責任は問われないと言いながら、何をそんなにびくびくしているのか...。
自主的な規制は、上からの規制以上に恐ろしい。
言論の自由、ひいては民主主義の崩壊につながりかねない問題だと思っている。

※画像は庭先に来たカラスアゲハ(orミヤマカラスアゲハ)。メタリックな光沢が美しい...。
2011年07月09日
教科書がおかしい
「なぜこんな計算をさせるのか」の続編です。
今回は中学の数学。
全国的に見てもかなりのシェアを誇るであろう、啓林館版(中1)の教科書だ。
「立体の表面積と体積」という単元にある円錐の側面積の問題。
下の画像を参照願いたい。
<例題1>
底面の半径が6㎝で、母線の長さが9㎝の円錐の側面積を求めなさい。
前回同様、早くもここで突っ込みたくなる。
「6㎝で」の後に「、」いるか...?
まあそれはいいとして、解法を見ると、わざわざ罫線で囲ってゴシック体でこう書いてある。
側面の展開図は,半径9㎝のおうぎ形で,その中心角をχ°とすると,
2Π(パイ)×9×χ/360(360分のχ)=2Π×6
これを解くと,χ=240
したがって,側面積は,
Π×9の2乗×240/360=54Π(㎠)
なぜ、数学に出てくる日本語は、こんなにいい加減なのか?
読点が多すぎてブツ切りだし、そもそも「、」じゃなくて「,」なのが気に入らない。
さらに、文の終わりに「。」がない。
中学生が、その内容以前にまともな型の文さえ書けない一因は、こんな教科書の文にあるのかもしれない。
また話がそれてしまったので、本題に戻る。
この問題で、側面のおうぎ形の中心角を出す意味がわからない。
途中でおうぎ形の弧の長さ(12Π)を出しているのだから、
仮想円(円周18Π)に占める割合は、12Π/18Π=2/3とわかる。
ならば、面積も仮想円(81Π㎠)の2/3であることは、簡単に理解できるだろう。
中心角など持ち出すから、まわりくどくなるのだ。
教科書には、その横に
「側面のおうぎ形が,円全体のどれだけの大きさかを考えてもいいね」 (「。」なし)とある。
「~てもいい」だと...?
じゃあ、上の解き方ではそう考えていないんかい?
中心角を出す解き方でも、、結局は仮想円に対する割合を出しているのではないのか...。
で、繰り返すが、割合を出すだけなら、中心角を出す必要はないのだ!!!
生徒を見ていると、この種の問題にはお題目のようにχ/360を持ち出す子が多い。
なぜそんな面倒な作業をするのかと不思議に思っていたが、
まさか教科書に、こんなバカな解き方が堂々と載っているとは思わなかった。
弧の長さから割合を出す方法を載せると、かえって生徒が混乱するとでも思っているのだろうか?
だとしたら、あまりにも子どもを馬鹿にしている。
余計なことは考えず、「公式」に当てはめて解けということだ。
教科書が、子どもたちの考える力を奪っている...。
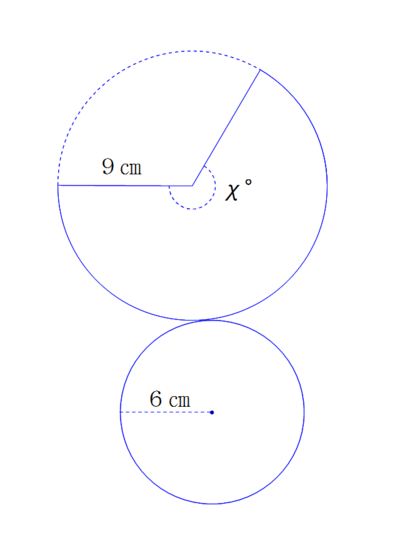
今回は中学の数学。
全国的に見てもかなりのシェアを誇るであろう、啓林館版(中1)の教科書だ。
「立体の表面積と体積」という単元にある円錐の側面積の問題。
下の画像を参照願いたい。
<例題1>
底面の半径が6㎝で、母線の長さが9㎝の円錐の側面積を求めなさい。
前回同様、早くもここで突っ込みたくなる。
「6㎝で」の後に「、」いるか...?
まあそれはいいとして、解法を見ると、わざわざ罫線で囲ってゴシック体でこう書いてある。
側面の展開図は,半径9㎝のおうぎ形で,その中心角をχ°とすると,
2Π(パイ)×9×χ/360(360分のχ)=2Π×6
これを解くと,χ=240
したがって,側面積は,
Π×9の2乗×240/360=54Π(㎠)
なぜ、数学に出てくる日本語は、こんなにいい加減なのか?
読点が多すぎてブツ切りだし、そもそも「、」じゃなくて「,」なのが気に入らない。
さらに、文の終わりに「。」がない。
中学生が、その内容以前にまともな型の文さえ書けない一因は、こんな教科書の文にあるのかもしれない。
また話がそれてしまったので、本題に戻る。
この問題で、側面のおうぎ形の中心角を出す意味がわからない。
途中でおうぎ形の弧の長さ(12Π)を出しているのだから、
仮想円(円周18Π)に占める割合は、12Π/18Π=2/3とわかる。
ならば、面積も仮想円(81Π㎠)の2/3であることは、簡単に理解できるだろう。
中心角など持ち出すから、まわりくどくなるのだ。
教科書には、その横に
「側面のおうぎ形が,円全体のどれだけの大きさかを考えてもいいね」 (「。」なし)とある。
「~てもいい」だと...?
じゃあ、上の解き方ではそう考えていないんかい?
中心角を出す解き方でも、、結局は仮想円に対する割合を出しているのではないのか...。
で、繰り返すが、割合を出すだけなら、中心角を出す必要はないのだ!!!
生徒を見ていると、この種の問題にはお題目のようにχ/360を持ち出す子が多い。
なぜそんな面倒な作業をするのかと不思議に思っていたが、
まさか教科書に、こんなバカな解き方が堂々と載っているとは思わなかった。
弧の長さから割合を出す方法を載せると、かえって生徒が混乱するとでも思っているのだろうか?
だとしたら、あまりにも子どもを馬鹿にしている。
余計なことは考えず、「公式」に当てはめて解けということだ。
教科書が、子どもたちの考える力を奪っている...。
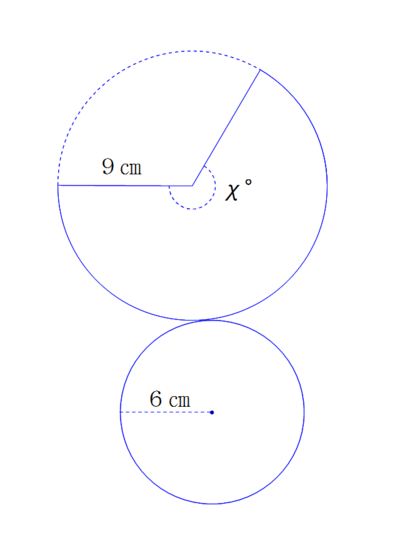
2011年07月04日
なぜこんな計算をさせるのか?
小学校の算数で多くの子がつまずくのが「一あたりの数」を求める計算です。
たとえば「250kmの道のりを5時間で行ったときの時速は?」
「200㎡で30kgの肥料を使うとすると、1㎡では何kgの肥料が必要か?」という問題のことです。
「全体の数」と「いくつ分の数」から「一あたりの数」を出すわけですが、
言葉の意味をきちんと理解できている子はごく少数でしょう。
ほとんどの子はこうやって計算するという「公式」を覚えて当てはめているだけです。
分数の計算を習うと、さらにやっかいな問題が登場します。
手元にある東京書籍の「小6・上」の教科書を見てみましょう。
「4分の3㎗のペンキで、板5分の2㎡をぬれました。このペンキ1㎗では、板を何㎡ぬれますか。」
国語的に突っ込みたいところもありますが(読点の打ち方)、
それはともかく、どういう計算をすればいいかすぐにわかりますか?
教科書には「ぬった面積」÷「使った量」=「1㎗でぬれる量」という式があり、
分数でも整数や小数のときと同じようにわり算にするという説明が続きます。
理屈はそうですが、4分の3で割るという行為は大人でもしっくり来ません。
図を描いて、まず4分の1㎗で塗れる面積を求め、それを4倍して1㎗分を出した方がよほどわかりやすいのではないでしょうか。
先日、この手の問題が満載の宿題に苦戦していた6年生に聞いてみると、
学校ではいきなり分数で割るやり方しか習っていないとのこと。
その宿題には分数のかけ算を使う問題も含まれていて、
掛けるのか割るのか、どれをどれで割るのか、完全に混乱していました。決して算数が苦手な子ではありません。
図を描くやり方を教えたらすんなりと正解を出していました。
私にはこの問題を6年生に与える必要性がわかりません。
「一あたり」の概念を理解させるには整数同士で十分ではないか、
双方を分数にして複雑にする意味がどこにあるのか、
なぜ(5分の2)÷(4分の3)という解き方を機械的に教え込まなければならないのか...。
脱ゆとり教育で教科書が厚くなった分、こういう悪問も増えるのではないかと危惧しています。
算数嫌いを大量に生み出す結果にならないことを祈ります。

※ 画像は国蝶のオオムラサキです。
毎年、同じエノキの葉を食べるテングチョウが乱舞し始めると、ほどなくして姿を見せてくれます。
いつ見ても気品があります...。
たとえば「250kmの道のりを5時間で行ったときの時速は?」
「200㎡で30kgの肥料を使うとすると、1㎡では何kgの肥料が必要か?」という問題のことです。
「全体の数」と「いくつ分の数」から「一あたりの数」を出すわけですが、
言葉の意味をきちんと理解できている子はごく少数でしょう。
ほとんどの子はこうやって計算するという「公式」を覚えて当てはめているだけです。
分数の計算を習うと、さらにやっかいな問題が登場します。
手元にある東京書籍の「小6・上」の教科書を見てみましょう。
「4分の3㎗のペンキで、板5分の2㎡をぬれました。このペンキ1㎗では、板を何㎡ぬれますか。」
国語的に突っ込みたいところもありますが(読点の打ち方)、
それはともかく、どういう計算をすればいいかすぐにわかりますか?
教科書には「ぬった面積」÷「使った量」=「1㎗でぬれる量」という式があり、
分数でも整数や小数のときと同じようにわり算にするという説明が続きます。
理屈はそうですが、4分の3で割るという行為は大人でもしっくり来ません。
図を描いて、まず4分の1㎗で塗れる面積を求め、それを4倍して1㎗分を出した方がよほどわかりやすいのではないでしょうか。
先日、この手の問題が満載の宿題に苦戦していた6年生に聞いてみると、
学校ではいきなり分数で割るやり方しか習っていないとのこと。
その宿題には分数のかけ算を使う問題も含まれていて、
掛けるのか割るのか、どれをどれで割るのか、完全に混乱していました。決して算数が苦手な子ではありません。
図を描くやり方を教えたらすんなりと正解を出していました。
私にはこの問題を6年生に与える必要性がわかりません。
「一あたり」の概念を理解させるには整数同士で十分ではないか、
双方を分数にして複雑にする意味がどこにあるのか、
なぜ(5分の2)÷(4分の3)という解き方を機械的に教え込まなければならないのか...。
脱ゆとり教育で教科書が厚くなった分、こういう悪問も増えるのではないかと危惧しています。
算数嫌いを大量に生み出す結果にならないことを祈ります。
※ 画像は国蝶のオオムラサキです。
毎年、同じエノキの葉を食べるテングチョウが乱舞し始めると、ほどなくして姿を見せてくれます。
いつ見ても気品があります...。
2011年06月27日
安協会費不払い運動
前々回の記事の続き。
「車両割」の存在理由と徴収方法に疑問を持った私は、ネットでいろいろ調べてみた。
先の会議での「上に聞いておく」は、いつ返事が来るかわからない。
集金に移る前に、自分なりのスタンスを明確にしておかなければならない。
結果、免許更新時に入会を勧められる「免許割」についてのページは多かったが、
肝心の「車両割」については数えるほどしか意見がなかった。
そんなもの、とっくに廃止している所が多いということか...。
逆に、地区の役員が強制的に徴収しているとの話もあったが...。
松代安協のホームページはなかったので、長野県交通安全協会のサイトからメールも出してみた。
「車両割」は何のためにあるのか?
「免許割」と二重に徴収しているのは問題ではないのか?
「車両割」だけでは会員ではないというのは不公平ではないのか?
「免許割」も含めた金の流れを明確に示してほしい。
もちろん松代安協の地区役員であることも明記した。
自分自身は「免許割」「車両割」ともに払っていないことも...。
仕事場から出したメールに返事が来ないので、5日後に家のPCからも再送する。
今度は文末に、「納得できる返事がもらえなければ、集金に協力できかねる」と付け加えておいた。
それなのに2週間たっても返事が来ない。
なめてるのか、回答のしようがないのか...。
先週の金曜日、とうとう電話してみた。
メールを見ていないのかと思い確認すると、チェックしていると言う。
それなら返事が来ないのはどういうわけだと問い詰めた。
こちらの名を聞いて担当者に替わる。
すると、そのじいさん、こんなことを言った。
「遅くなりましたが、さっき返事を出しました。」
そんなタイミングの良い話があるかと思ったが、
「そこにも書いたように松代安協にも話をしておいたので、何か連絡があると思う」というもっともらしいセリフに、
若干「本当かも?」と感じる。
ところが...今日になっても、仕事場にも自宅にもメールは届いていない!
まったく、開いた口がふさがらない。
よく、そんなすぐにばれる嘘をつくものだ...。
これで気持ちが決まったので、今日、受け持ち分の4軒を訪問した。
義務ではないこと、払わないのが悪ではないこと、
払うなら、何のメリットもない寄付だと認識してほしいことなどを伝える。
1軒は留守で保留。
2軒は、私が去年「払わなくてもいい」と言っておいたのを「若い衆」と相談し、今年はやめるとのこと。
しめしめ...。
ところがもう1軒に驚いた。
応対に出たのは私と同年代の息子だ。
払わなくてもいいのはわかっている、寄付でもいいから払うという。
それなら断る理由もない。
タイトルには「不払い運動」と書いたが、私の目的は「車両割」の真実を知ってもらうことなのだ。
しかし、こういう人たちをどう理解したらいいのだろう。
純粋な寄付行為とは少し違う気がする。
もう一つ、「日赤奉仕団」という戦時中のような組織もあるのだが、
これも含めて、村社会での微妙な立ち位置が関係しているのかも知れない。
ともあれ、残りの1軒への対応、そして県安協への追及をしっかりしなければ...。
結果によっては、また続編を書きます。

※ 画像は家の前で見つけたクジャクチョウ。
その派手さから、東アジア産のものは geisha と呼ばれているそうです。
「車両割」の存在理由と徴収方法に疑問を持った私は、ネットでいろいろ調べてみた。
先の会議での「上に聞いておく」は、いつ返事が来るかわからない。
集金に移る前に、自分なりのスタンスを明確にしておかなければならない。
結果、免許更新時に入会を勧められる「免許割」についてのページは多かったが、
肝心の「車両割」については数えるほどしか意見がなかった。
そんなもの、とっくに廃止している所が多いということか...。
逆に、地区の役員が強制的に徴収しているとの話もあったが...。
松代安協のホームページはなかったので、長野県交通安全協会のサイトからメールも出してみた。
「車両割」は何のためにあるのか?
「免許割」と二重に徴収しているのは問題ではないのか?
「車両割」だけでは会員ではないというのは不公平ではないのか?
「免許割」も含めた金の流れを明確に示してほしい。
もちろん松代安協の地区役員であることも明記した。
自分自身は「免許割」「車両割」ともに払っていないことも...。
仕事場から出したメールに返事が来ないので、5日後に家のPCからも再送する。
今度は文末に、「納得できる返事がもらえなければ、集金に協力できかねる」と付け加えておいた。
それなのに2週間たっても返事が来ない。
なめてるのか、回答のしようがないのか...。
先週の金曜日、とうとう電話してみた。
メールを見ていないのかと思い確認すると、チェックしていると言う。
それなら返事が来ないのはどういうわけだと問い詰めた。
こちらの名を聞いて担当者に替わる。
すると、そのじいさん、こんなことを言った。
「遅くなりましたが、さっき返事を出しました。」
そんなタイミングの良い話があるかと思ったが、
「そこにも書いたように松代安協にも話をしておいたので、何か連絡があると思う」というもっともらしいセリフに、
若干「本当かも?」と感じる。
ところが...今日になっても、仕事場にも自宅にもメールは届いていない!
まったく、開いた口がふさがらない。
よく、そんなすぐにばれる嘘をつくものだ...。
これで気持ちが決まったので、今日、受け持ち分の4軒を訪問した。
義務ではないこと、払わないのが悪ではないこと、
払うなら、何のメリットもない寄付だと認識してほしいことなどを伝える。
1軒は留守で保留。
2軒は、私が去年「払わなくてもいい」と言っておいたのを「若い衆」と相談し、今年はやめるとのこと。
しめしめ...。
ところがもう1軒に驚いた。
応対に出たのは私と同年代の息子だ。
払わなくてもいいのはわかっている、寄付でもいいから払うという。
それなら断る理由もない。
タイトルには「不払い運動」と書いたが、私の目的は「車両割」の真実を知ってもらうことなのだ。
しかし、こういう人たちをどう理解したらいいのだろう。
純粋な寄付行為とは少し違う気がする。
もう一つ、「日赤奉仕団」という戦時中のような組織もあるのだが、
これも含めて、村社会での微妙な立ち位置が関係しているのかも知れない。
ともあれ、残りの1軒への対応、そして県安協への追及をしっかりしなければ...。
結果によっては、また続編を書きます。

※ 画像は家の前で見つけたクジャクチョウ。
その派手さから、東アジア産のものは geisha と呼ばれているそうです。
2011年06月07日
「車両割」ってなんだ?
昨年、今年と地区の安協(交通安全協議会)の役員をしている。
何年も前から免許更新時に安協の入会手続きをしていないので、
会員ではないのだが、役だけは自治会の門順で回ってくる。
5日に今年度の総会があった。
県の安協の支部組織である松代安協の、そのまた分会の総会である。
今年も、各地区で「車両割」の会費を集めてほしいという。
加えて、松代の中でもわが分会が極端に額が低いので、
新たな加入も呼びかけてほしいとのことだ。
この「車両割」という存在がよくわからない。
本来は各戸で所有している車種、台数によって違うようだが、一律1,200円になっている。
ちなみに免許更新の際に加入するのは「免許割」という名称だ。
自治会を通じて集めるということは、
赤い羽の募金のように半ば強制なのかと思ったら、そうでもない。
私の集落では、70軒ほどのうち、「車両割」の対象はわずか10軒だ。
(もちろん、我が家は対象ではない!)
集金はたいした労ではないが、わけのわからない金を扱うのも気が引ける。
そもそも、安協への加入は任意のはずだ。
上述のように、私は一銭も払っていない。
支出のうち交通安全のために使われているのはごく一部で、
大半は職員の給与や退職金、飲食費に消えていると聞いた。
そんな警察の天下り組織のために協力する気にはなれない。
車を維持するだけで多額の税金を払っているのだから、
交通安全のための経費はそこから出せば十分ではないか...。
昨年集金してわかったことだが、「車両割」を払っている人は
免許更新時にも「免許割」を納めている人が多い。
義務だととらえているようだ。
お上から言われるままに、何の疑問もなく二重に払っているのだ。
「集める側がこんなこと言うのも何だけど、これ(車両割)別に払わなくてもいいんだよ」と
ある家で教えたら、「でもせっかく集めに来てくれたんだから...」と1,200円を差し出した。
なんだか申し訳ない気持ちになる。
断ることを知らない、人のよいお年寄りが損をしているというのが現状ではないのか...。
で、取りあえず、総会の席で質問してみた。
「車両割」とは何なのか?
「免許割」との関係はどうなっているのか...?
結果、驚くべきことがわかった。
集めた「車両割」の額によって、各分会に活動費が還付され、
それで立て看板や旗などの備品代をまかなう。
「免許割」からも若干の分配があるようだが、主は「車両割」のようだ。
それが「車両割」の存在理由の最たるものらしいが、
先にも書いたように、そんなものは自動車税やガソリン税から出せばいい。
百歩譲って、「免許割」からの分配の割合を増やせばいい話だ。
しかし、それはまだ想定内だった。
一番驚いたのは、「車両割」を払っていても安協の会員ではないということだ。
総会の資料の中に、普及を促進するためのパンフレットがあった。
長野県交通安全協会の会員になると、シートベルトを締めていて事故に遭った場合、
重度障害や死亡で10万円の見舞金が支払われるという内容だ。
しかし、「車両割」で入っていても会員ではないので対象外ということになる。
それならこんなパンフレットがあっても、我々が加入を促進する役には立たないではないか...。
支離滅裂で意味がわからない。
では、「車両割」を払うメリットは何なのか?
毎年1,200円ということは、「免許割」の2~3倍の金額を払っていることになる。
それで正会員ではなく、数ヶ月に一度中身のない会報が配布されるだけだ。
他には何もない!
そんな制度を、誰が勧めることができようか...。
だいたい、「車両割」の領収書に「会費」と明記してあるではないか。
それを払うことで、自分は安協の会員だと思っている方が自然ではないのか...。
他の出席者からも「おかしい」という声が多く上がった。
結論は上(松代安協)に確認、要望するということで終わり。
さて、今年は去年以上に、「車両割」の支払いをやめるよう説得して回ろうか...。

※ 投扇興の大会で浅草に行ってきました。結果はさんざん...。
スカイツリーの近くでは、みんなが上向いて写真撮っていました。
何年も前から免許更新時に安協の入会手続きをしていないので、
会員ではないのだが、役だけは自治会の門順で回ってくる。
5日に今年度の総会があった。
県の安協の支部組織である松代安協の、そのまた分会の総会である。
今年も、各地区で「車両割」の会費を集めてほしいという。
加えて、松代の中でもわが分会が極端に額が低いので、
新たな加入も呼びかけてほしいとのことだ。
この「車両割」という存在がよくわからない。
本来は各戸で所有している車種、台数によって違うようだが、一律1,200円になっている。
ちなみに免許更新の際に加入するのは「免許割」という名称だ。
自治会を通じて集めるということは、
赤い羽の募金のように半ば強制なのかと思ったら、そうでもない。
私の集落では、70軒ほどのうち、「車両割」の対象はわずか10軒だ。
(もちろん、我が家は対象ではない!)
集金はたいした労ではないが、わけのわからない金を扱うのも気が引ける。
そもそも、安協への加入は任意のはずだ。
上述のように、私は一銭も払っていない。
支出のうち交通安全のために使われているのはごく一部で、
大半は職員の給与や退職金、飲食費に消えていると聞いた。
そんな警察の天下り組織のために協力する気にはなれない。
車を維持するだけで多額の税金を払っているのだから、
交通安全のための経費はそこから出せば十分ではないか...。
昨年集金してわかったことだが、「車両割」を払っている人は
免許更新時にも「免許割」を納めている人が多い。
義務だととらえているようだ。
お上から言われるままに、何の疑問もなく二重に払っているのだ。
「集める側がこんなこと言うのも何だけど、これ(車両割)別に払わなくてもいいんだよ」と
ある家で教えたら、「でもせっかく集めに来てくれたんだから...」と1,200円を差し出した。
なんだか申し訳ない気持ちになる。
断ることを知らない、人のよいお年寄りが損をしているというのが現状ではないのか...。
で、取りあえず、総会の席で質問してみた。
「車両割」とは何なのか?
「免許割」との関係はどうなっているのか...?
結果、驚くべきことがわかった。
集めた「車両割」の額によって、各分会に活動費が還付され、
それで立て看板や旗などの備品代をまかなう。
「免許割」からも若干の分配があるようだが、主は「車両割」のようだ。
それが「車両割」の存在理由の最たるものらしいが、
先にも書いたように、そんなものは自動車税やガソリン税から出せばいい。
百歩譲って、「免許割」からの分配の割合を増やせばいい話だ。
しかし、それはまだ想定内だった。
一番驚いたのは、「車両割」を払っていても安協の会員ではないということだ。
総会の資料の中に、普及を促進するためのパンフレットがあった。
長野県交通安全協会の会員になると、シートベルトを締めていて事故に遭った場合、
重度障害や死亡で10万円の見舞金が支払われるという内容だ。
しかし、「車両割」で入っていても会員ではないので対象外ということになる。
それならこんなパンフレットがあっても、我々が加入を促進する役には立たないではないか...。
支離滅裂で意味がわからない。
では、「車両割」を払うメリットは何なのか?
毎年1,200円ということは、「免許割」の2~3倍の金額を払っていることになる。
それで正会員ではなく、数ヶ月に一度中身のない会報が配布されるだけだ。
他には何もない!
そんな制度を、誰が勧めることができようか...。
だいたい、「車両割」の領収書に「会費」と明記してあるではないか。
それを払うことで、自分は安協の会員だと思っている方が自然ではないのか...。
他の出席者からも「おかしい」という声が多く上がった。
結論は上(松代安協)に確認、要望するということで終わり。
さて、今年は去年以上に、「車両割」の支払いをやめるよう説得して回ろうか...。

※ 投扇興の大会で浅草に行ってきました。結果はさんざん...。
スカイツリーの近くでは、みんなが上向いて写真撮っていました。
2011年05月30日
うるう年を知らない!
中学生が言葉を知らないのには驚かなくなった。
それ以前に、一般常識と言っていいことを知らないのだ。
小学生はともかく、中学生なら当然知っておくべき、
あるいは知っておいてほしいことを知らなすぎる。
一例を挙げよう。
ある日の塾での一コマである。
「1ヶ月が30日以下の月は?」という問に、中2の女子が悩んでいた。
実はこの問題、正解率がきわめて低い。
中学生で10%を切るのではないか...。
そのとき在室していた他の生徒(中2が他に2名、中1、小5が各1名)も
いずれこの問題にぶつかることになるので、この機会にまとめて教えることにする。
以下、私と生徒とのやり取りである。
私「この問題わかる人いる?」
生徒A(中2)、B(中2)、C(中2)、D(中1)、E(小5)「....。」
私「う~ん...。じゃ、その前に...28日までしかない月は知っているよね?」
(多くの子がうなずくので生徒Cを指名。)
生徒C「 ...4月...。」
私「2月だ。...2月が29日になる年もあるよね。」
(今度はほぼ全員が「?」という顔をする。)
私「うるう年って知らない?...1年が1日長くなるの...。」
全員「えーっ?!」
私「1年は何日だ?」(生徒Dを指名。)
生徒D「30日...。」
私「1ヶ月じゃなくて1年!」
生徒「ああ...365日。」
私「そう。それが4年に一度2月が29日まであって、1年が366日なるの。
これがうるう年。20××年の××が4で割り切れる年がうるう年です。」
しばし、うるう年がある理由と、その仕組みについて説明した。
(4年に一度うるう年。100年に一度うるう年をやめる。400年に一度うるう年を復活させる。)
そこからやっと、本来の「30日以下の月」の話に入る。
「大の月」「小の月」から始めて、
最後は「小の月」の覚え方=「西向く侍」を伝授。
このくらいのことは常識として覚えておくよう言い聞かせた。
大人になったら1日多いか少ないかは大きな問題だと...。
他にもいくらでもある。
アマゾンがどこにあるか知らない。
日本の県名も西日本になると壊滅的だ。
日本が戦争に負けたことを知らない。
日本は先進国ではなく発展途上国だと思っている。
村や町の存在を知らない(すべて「市」だと思っている)。
ツツジやスギナは見たことがないと言う。
1kmがどれくらいの距離か見当も付かない...などなど。
切符の買い方を知らないという高校生もいた。
島崎藤村や武者小路実篤、ヘミングウェイは、高校生でも知らないことの方が「常識」なんだそうだ。
こうした現状の一因を学校教育に求めることもできよう。
小学校でちゃんと教えてくれなければ困ると...。
しかし、上に挙げた例の大半は、学校よりもむしろ家庭で教えるべきことである。
毎日の生活の中で、親から子へ伝える一般常識である。
手伝いをさせたり、家族で遠出をしたり、ときには一人で「冒険」をさせたり...。
家族との豊富な会話や様々な生活体験を通じて、自然に身につける知識ではないだろうか。
私自身も、「西向く侍」や多くのことわざ、言い伝えなどは親から教わった記憶がある。
今、企業が新入社員に求める能力の1位はコミュニケーション能力である。
裏を返せば、それが貧弱な若者がいかに多いかということだろう。
その一因が一般常識の不足にあることは、十分考えられることではなかろうか..。
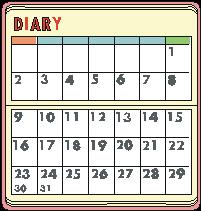
それ以前に、一般常識と言っていいことを知らないのだ。
小学生はともかく、中学生なら当然知っておくべき、
あるいは知っておいてほしいことを知らなすぎる。
一例を挙げよう。
ある日の塾での一コマである。
「1ヶ月が30日以下の月は?」という問に、中2の女子が悩んでいた。
実はこの問題、正解率がきわめて低い。
中学生で10%を切るのではないか...。
そのとき在室していた他の生徒(中2が他に2名、中1、小5が各1名)も
いずれこの問題にぶつかることになるので、この機会にまとめて教えることにする。
以下、私と生徒とのやり取りである。
私「この問題わかる人いる?」
生徒A(中2)、B(中2)、C(中2)、D(中1)、E(小5)「....。」
私「う~ん...。じゃ、その前に...28日までしかない月は知っているよね?」
(多くの子がうなずくので生徒Cを指名。)
生徒C「 ...4月...。」
私「2月だ。...2月が29日になる年もあるよね。」
(今度はほぼ全員が「?」という顔をする。)
私「うるう年って知らない?...1年が1日長くなるの...。」
全員「えーっ?!」
私「1年は何日だ?」(生徒Dを指名。)
生徒D「30日...。」
私「1ヶ月じゃなくて1年!」
生徒「ああ...365日。」
私「そう。それが4年に一度2月が29日まであって、1年が366日なるの。
これがうるう年。20××年の××が4で割り切れる年がうるう年です。」
しばし、うるう年がある理由と、その仕組みについて説明した。
(4年に一度うるう年。100年に一度うるう年をやめる。400年に一度うるう年を復活させる。)
そこからやっと、本来の「30日以下の月」の話に入る。
「大の月」「小の月」から始めて、
最後は「小の月」の覚え方=「西向く侍」を伝授。
このくらいのことは常識として覚えておくよう言い聞かせた。
大人になったら1日多いか少ないかは大きな問題だと...。
他にもいくらでもある。
アマゾンがどこにあるか知らない。
日本の県名も西日本になると壊滅的だ。
日本が戦争に負けたことを知らない。
日本は先進国ではなく発展途上国だと思っている。
村や町の存在を知らない(すべて「市」だと思っている)。
ツツジやスギナは見たことがないと言う。
1kmがどれくらいの距離か見当も付かない...などなど。
切符の買い方を知らないという高校生もいた。
島崎藤村や武者小路実篤、ヘミングウェイは、高校生でも知らないことの方が「常識」なんだそうだ。
こうした現状の一因を学校教育に求めることもできよう。
小学校でちゃんと教えてくれなければ困ると...。
しかし、上に挙げた例の大半は、学校よりもむしろ家庭で教えるべきことである。
毎日の生活の中で、親から子へ伝える一般常識である。
手伝いをさせたり、家族で遠出をしたり、ときには一人で「冒険」をさせたり...。
家族との豊富な会話や様々な生活体験を通じて、自然に身につける知識ではないだろうか。
私自身も、「西向く侍」や多くのことわざ、言い伝えなどは親から教わった記憶がある。
今、企業が新入社員に求める能力の1位はコミュニケーション能力である。
裏を返せば、それが貧弱な若者がいかに多いかということだろう。
その一因が一般常識の不足にあることは、十分考えられることではなかろうか..。
2011年04月30日
新聞を読め!
新聞を取らない家庭が増えているという。
塾の生徒の家でも同様だ。
忙しくて読む暇がない、必要な情報はテレビやネットで手に入れれば十分という考え方のようだ。
うちの子は国語ができないと嘆く家庭に限って、新聞を取っていないことが多い。
子どもは驚くほど言葉を知らない。
社会常識も乏しい。
塾では国語力をつける方法の一つとして、
新聞の読者投稿を書き写し、要約したり感想を書いたりすることを勧めている。
だが、肝心の新聞が家庭にないのでは話にならない。
新聞があっても、子どもはテレビ欄くらいしか見ないかも知れない。
それでもやがて、たまにでもスポーツ欄や家庭欄を見る子どもが出でくる。
何より、大人が新聞を読んでいる風景、日常的に活字が身近にある環境が大切なのだ。
新聞読む暇がないと言いながら、テレビは長時間見ている。
親がそうであれば、子どもも当然そうなるだろう。
国語力の基礎は家庭生活にあることは言うまでもない。
「新聞を取る」という表現を知らない子もいる。
オリジナル教材で「新聞を取っていないこと」が正解の問題があるのだが、
「新聞を読んでいない」「~買っていない」「~配達していない」などと書いてくる。
「買っていない」では、駅の売店を連想してしまう。
「配達していない」って、新聞販売店ではあるまいし...。
毎朝定期的に家に届けてもらうという日本の文化は、
やがて消え去っていくのか...。
前にも書いたが、確かにネットは効率的だが、それ故に寄り道ができない。
新聞なら目的の情報とともに、その他の「無駄な話」も仕入れることができる。
今は無駄に思えても、いつそれが役に立つかわからない。
たとえ実利的な得はなくても、
幅広い知識や常識、教養を身につけるためには、この寄り道こそが欠かせないのだ。
今知りたい情報、すぐに役に立つ知識ばかりを詰め込んでいては、薄っぺらな人間にしかなれない。
家庭にはまず、新聞や本などの活字がある環境を作ってもらいたい。
私は自宅と塾で2誌を取り、毎日切り抜きをしている。
忙しいときは面倒に思うこともあるが、寄り道で世界が広がる体験は捨てがたい。
一日の中でも贅沢な時間だと思っている。

塾の生徒の家でも同様だ。
忙しくて読む暇がない、必要な情報はテレビやネットで手に入れれば十分という考え方のようだ。
うちの子は国語ができないと嘆く家庭に限って、新聞を取っていないことが多い。
子どもは驚くほど言葉を知らない。
社会常識も乏しい。
塾では国語力をつける方法の一つとして、
新聞の読者投稿を書き写し、要約したり感想を書いたりすることを勧めている。
だが、肝心の新聞が家庭にないのでは話にならない。
新聞があっても、子どもはテレビ欄くらいしか見ないかも知れない。
それでもやがて、たまにでもスポーツ欄や家庭欄を見る子どもが出でくる。
何より、大人が新聞を読んでいる風景、日常的に活字が身近にある環境が大切なのだ。
新聞読む暇がないと言いながら、テレビは長時間見ている。
親がそうであれば、子どもも当然そうなるだろう。
国語力の基礎は家庭生活にあることは言うまでもない。
「新聞を取る」という表現を知らない子もいる。
オリジナル教材で「新聞を取っていないこと」が正解の問題があるのだが、
「新聞を読んでいない」「~買っていない」「~配達していない」などと書いてくる。
「買っていない」では、駅の売店を連想してしまう。
「配達していない」って、新聞販売店ではあるまいし...。
毎朝定期的に家に届けてもらうという日本の文化は、
やがて消え去っていくのか...。
前にも書いたが、確かにネットは効率的だが、それ故に寄り道ができない。
新聞なら目的の情報とともに、その他の「無駄な話」も仕入れることができる。
今は無駄に思えても、いつそれが役に立つかわからない。
たとえ実利的な得はなくても、
幅広い知識や常識、教養を身につけるためには、この寄り道こそが欠かせないのだ。
今知りたい情報、すぐに役に立つ知識ばかりを詰め込んでいては、薄っぺらな人間にしかなれない。
家庭にはまず、新聞や本などの活字がある環境を作ってもらいたい。
私は自宅と塾で2誌を取り、毎日切り抜きをしている。
忙しいときは面倒に思うこともあるが、寄り道で世界が広がる体験は捨てがたい。
一日の中でも贅沢な時間だと思っている。
2011年04月11日
会釈ぐらいしろ!
最良は小学生。
最悪はおばさんとじじい。
横断歩道を渡ろうとしているのに気づいて、車を止めたときの反応だ。
私はわりと、歩行者に道を譲ることが多い方だと思っている。
小学生は渡り終わったら「ありがとうございました!」と挨拶してくれる子が多いが、
最近は知らんふりで行ってしまう子も増えた。
おばさんとじじいは、ほとんどが「止まって当然」という顔で渡っていく。
ちょっと会釈してくれたり、手を挙げてくれるだけでも気持ちいいのに...。
そんなちょっとした気遣いもしたくないのか...。
横断歩道近くで立ち話をしていて、渡る意志があるのかないのか、
判断に苦しむ場合もある。
最近では、急いでいるときはおばさんやじじいには譲らないことも出てきた。
自分が歩行者になったときは、もちろん軽く挨拶している。
まったく、近頃の年寄りときたら...。
もう一つ、前にも一度書いたが、
道を譲ってあげたときの対向車の反応。
相変わらず福祉関係の車が礼儀知らずのことが多いのは、
いったいどういうわけか?福祉の車は優先されて当然と思っているのか...。
運転中にはできるだけ腹を立てたくないものである。

最悪はおばさんとじじい。
横断歩道を渡ろうとしているのに気づいて、車を止めたときの反応だ。
私はわりと、歩行者に道を譲ることが多い方だと思っている。
小学生は渡り終わったら「ありがとうございました!」と挨拶してくれる子が多いが、
最近は知らんふりで行ってしまう子も増えた。
おばさんとじじいは、ほとんどが「止まって当然」という顔で渡っていく。
ちょっと会釈してくれたり、手を挙げてくれるだけでも気持ちいいのに...。
そんなちょっとした気遣いもしたくないのか...。
横断歩道近くで立ち話をしていて、渡る意志があるのかないのか、
判断に苦しむ場合もある。
最近では、急いでいるときはおばさんやじじいには譲らないことも出てきた。
自分が歩行者になったときは、もちろん軽く挨拶している。
まったく、近頃の年寄りときたら...。
もう一つ、前にも一度書いたが、
道を譲ってあげたときの対向車の反応。
相変わらず福祉関係の車が礼儀知らずのことが多いのは、
いったいどういうわけか?福祉の車は優先されて当然と思っているのか...。
運転中にはできるだけ腹を立てたくないものである。

2011年04月04日
おとなしいだけでいいのか?
大地震、大津波、さらに原発騒動...。
未曾有の災害に遭っても秩序を乱さず、整然と行動する日本人のマナーに、海外からは称賛の声が上がった。
ところが、時が経つに従って疑問の方が増えてきているという。
「なぜもっと声を上げないのか?」
私も初めからそう思っていた。
日本人はおとなしすぎる...。
「おとなしい」は「大人しい」だ。
日本では、「大人である」とは自制心を持つことである。
周りの空気を読み、突出した言動をしないことである。
震災後のCMやイベントの「自粛」ムードにも、横並び意識が垣間見える。
出る杭は打たれ、「もっと大人になれ」と戒められる。
主張や不満があっても、デモなどの行動に出ることは稀である。
「若さ」は「バカさ」でもあるが、「若年寄」が多くなった。
そして歳を重ねるにつれ、より「まるくなる」ことが求められる。
先週発売された「週刊現代」にも、「優しすぎる日本人へ」と題する記事があった。
「仕方がない」で許してしまっていいのか?
なぜもっと、政府や東電を追及しないのか...?
避難所では、みな周りに迷惑をかけないよう、気を遣って暮らしているに違いない。
ストレスも貯まっているだろうが、マスコミの取材には謙虚な姿勢と感謝の言葉を忘れない。
身内に犠牲者が出た人ほど、逆に明るく振る舞ったり、率先して行動したりしているとも聞く。
素晴らしいことではあるが、心の奥底に本当の気持ちが鬱積していくことを危惧してしまう。
もっと感情を出せばいい。
泣きわめけばいい。
文句を言えばいい。
...そうは言っても、日本人には難しいだろう。
だからこそ...と誰かがラジオで言っていた。
救援物資にアルコール類も入れればいい。
酒の力を借りれば、少しは感情を表に出してすっきりすることもできるだろうと...。
大いに賛成である。
「人に迷惑をかけない」を子育ての根本に置いている家庭は多かろう。
それはもちろん、人として大切なことではある。
しかし、それだけではいいのか...。
おとなしいだけでは何も変わらない...。
もっと声を上げよう。
政府はもっと迅速に行動しろ!
「安全」と言うばかりでなく、どうなれば危険なのかを示せ!
東電は、「入院」で逃げている社長を出せ!
大本営発表を素直に信じ、どんな状況でも「仕方がない」と耐えてくれる国民ほど、
為政者にとって御しやすいものはないのである。

未曾有の災害に遭っても秩序を乱さず、整然と行動する日本人のマナーに、海外からは称賛の声が上がった。
ところが、時が経つに従って疑問の方が増えてきているという。
「なぜもっと声を上げないのか?」
私も初めからそう思っていた。
日本人はおとなしすぎる...。
「おとなしい」は「大人しい」だ。
日本では、「大人である」とは自制心を持つことである。
周りの空気を読み、突出した言動をしないことである。
震災後のCMやイベントの「自粛」ムードにも、横並び意識が垣間見える。
出る杭は打たれ、「もっと大人になれ」と戒められる。
主張や不満があっても、デモなどの行動に出ることは稀である。
「若さ」は「バカさ」でもあるが、「若年寄」が多くなった。
そして歳を重ねるにつれ、より「まるくなる」ことが求められる。
先週発売された「週刊現代」にも、「優しすぎる日本人へ」と題する記事があった。
「仕方がない」で許してしまっていいのか?
なぜもっと、政府や東電を追及しないのか...?
避難所では、みな周りに迷惑をかけないよう、気を遣って暮らしているに違いない。
ストレスも貯まっているだろうが、マスコミの取材には謙虚な姿勢と感謝の言葉を忘れない。
身内に犠牲者が出た人ほど、逆に明るく振る舞ったり、率先して行動したりしているとも聞く。
素晴らしいことではあるが、心の奥底に本当の気持ちが鬱積していくことを危惧してしまう。
もっと感情を出せばいい。
泣きわめけばいい。
文句を言えばいい。
...そうは言っても、日本人には難しいだろう。
だからこそ...と誰かがラジオで言っていた。
救援物資にアルコール類も入れればいい。
酒の力を借りれば、少しは感情を表に出してすっきりすることもできるだろうと...。
大いに賛成である。
「人に迷惑をかけない」を子育ての根本に置いている家庭は多かろう。
それはもちろん、人として大切なことではある。
しかし、それだけではいいのか...。
おとなしいだけでは何も変わらない...。
もっと声を上げよう。
政府はもっと迅速に行動しろ!
「安全」と言うばかりでなく、どうなれば危険なのかを示せ!
東電は、「入院」で逃げている社長を出せ!
大本営発表を素直に信じ、どんな状況でも「仕方がない」と耐えてくれる国民ほど、
為政者にとって御しやすいものはないのである。

2011年03月27日
原発、その後...
大地震からすでに2週間が経過した。
福島第一原発では、未だに暴走を止められない。
各地の放射線量の発表が、天気や花粉飛散量の予報のように日常的になってきた。
当初は最悪の事態を説明するときに盛んに使われていた「メルトダウン」という言葉を、
最近あまり耳にしない。
現にそれが起こってしまっているから、恐ろしくて使えないのか...。
「直ちに人体に影響はないレベル」の、「直ちに」が気になる。
今は大丈夫でも、数年後、数十年後に影響が出るのでは困る。
それが放射能の恐ろしさなのだから...。
原発近くの海で、高濃度の放射能汚染が確認された。
普段から漁をしている海域ではないし、拡散するので大丈夫と言っているが、
温かい水を求めてもともと魚が集まる所である。
魚が汚染されれば体内で濃縮され、放射線レベルはさらに高まるだろう。
それをまた大きな魚が食べて...。
回遊魚が汚染されれば、日本だけの危機ではなくなる。
避難指示が出ている地域では、犠牲者の遺体収容も滞っていると聞く。
いったいいつになったら戻れるのか...。
大気中の放射線量が減っても、土壌や水は汚染されているだろう。
風評被害も含め、農業や漁業はいつ再建できるのか、見通しも立たないに違いない。
避難している人の中にも、それでも原発は必要だと言う人がいる。
他に働き場所がないからだと...。
では、初めから原発など造りようがない山間部の過疎地はどうするのだ?原発なんかなくたって何とかやっている。
決して余裕のある暮らしではないかも知れないが、
目に見えない恐怖に晒されることはなく、穏やかに生活しているではないか。
原発ってよほど待遇がいいのだろうか...。
ドイツでは、原発の即時停止を求める大規模なデモが起きている。
日本も、原発の問題を含め、暮らし方を根本から考え直す時期にあることは間違いないだろう。

※ 29日から春期講習が始まり多忙になります。しばらく記事がアップできませんのでご了承ください。
福島第一原発では、未だに暴走を止められない。
各地の放射線量の発表が、天気や花粉飛散量の予報のように日常的になってきた。
当初は最悪の事態を説明するときに盛んに使われていた「メルトダウン」という言葉を、
最近あまり耳にしない。
現にそれが起こってしまっているから、恐ろしくて使えないのか...。
「直ちに人体に影響はないレベル」の、「直ちに」が気になる。
今は大丈夫でも、数年後、数十年後に影響が出るのでは困る。
それが放射能の恐ろしさなのだから...。
原発近くの海で、高濃度の放射能汚染が確認された。
普段から漁をしている海域ではないし、拡散するので大丈夫と言っているが、
温かい水を求めてもともと魚が集まる所である。
魚が汚染されれば体内で濃縮され、放射線レベルはさらに高まるだろう。
それをまた大きな魚が食べて...。
回遊魚が汚染されれば、日本だけの危機ではなくなる。
避難指示が出ている地域では、犠牲者の遺体収容も滞っていると聞く。
いったいいつになったら戻れるのか...。
大気中の放射線量が減っても、土壌や水は汚染されているだろう。
風評被害も含め、農業や漁業はいつ再建できるのか、見通しも立たないに違いない。
避難している人の中にも、それでも原発は必要だと言う人がいる。
他に働き場所がないからだと...。
では、初めから原発など造りようがない山間部の過疎地はどうするのだ?原発なんかなくたって何とかやっている。
決して余裕のある暮らしではないかも知れないが、
目に見えない恐怖に晒されることはなく、穏やかに生活しているではないか。
原発ってよほど待遇がいいのだろうか...。
ドイツでは、原発の即時停止を求める大規模なデモが起きている。
日本も、原発の問題を含め、暮らし方を根本から考え直す時期にあることは間違いないだろう。

※ 29日から春期講習が始まり多忙になります。しばらく記事がアップできませんのでご了承ください。
2011年03月16日
原発は本当に必要か?
大震災で福島の原発が大変なことになっている。
東京電力の対応は、余計な刺激を与えないようにという配慮からか、
妙に冷静すぎる感じが否めない。
のんきすぎると言ってもいいくらいだ。
燃料棒がすべて露出するなんて、かなり危険なことではないのか?
海外の反応はもっと深刻だ。
「東京に原発を」という本が売れたのは30年も前のことだ。
原発が絶対安全だというなら、送電コストも安くなる東京に造ればいい。
想定被害が少ない地方に造るのは、万が一ということがあるからに他ならない。
この、地方に負担を押しつけて都会は恩恵だけを受けるという構図は、どうにかならないものか。
県内のダムも東京へ送電しているものばかりだ。
そんなことだから、東京への一極集中がますます進むのだ。
利益を受けるなら、リスクも合わせて受容すべきではないか...。
おいしい所だけ持って行こうなんて虫がよすぎる。
昨日の信濃毎日新聞にも、どこかの助教授のそんな意見が載っていた。
なんだか、今行われている計画停電も、東電の策略かと疑念を抱いてしまう。
原発が機能しないとこんなに大変なことになりますよ。
だから原発は必要です。
もっとどんどん増やしましょう。
という筋書きになるような...。
原発は本当に必要なのか?
今回のような危険を加味してまで、CO2を出さないというメリットが優先されるべきなのか?
世界各国も原発のあり方を再考し出している。
日本もこれを機会に、エネルギー問題をどうするのか、
徹底的に議論すべきだと思う。
その際の一つの視点として、拡大成長を望まない、
エネルギーの消費を縮小するという選択もありだと思う。
原発に頼らざるを得ないくらいなら、電力の不足も我慢するという立場だ。
そういう意味では、今回の計画停電もいい機会になるかもしれない。
無駄な照明や過度の空調はやめる。
ご飯は鍋で炊き、お湯はやかんで沸かす。
まず需要ありきではなく、供給量の中でやりくりするという路線は取れないものだろうか...。
終わりに一つの文章を紹介しておく。
かつて原発の現場で働いていたという人が書かれたものだ。
「原発がどんなものか知ってほしい」

p.s.通信回線が込んでいる影響か、メールが滞っていることがあるようだ。
震災当日の千葉からのメールは、深夜にまとめて3通届いた。
パソコンに届くメールもいつもより少ない。
大量に舞い込む迷惑メールも極端に少ないのはありがたいが...。
東京電力の対応は、余計な刺激を与えないようにという配慮からか、
妙に冷静すぎる感じが否めない。
のんきすぎると言ってもいいくらいだ。
燃料棒がすべて露出するなんて、かなり危険なことではないのか?
海外の反応はもっと深刻だ。
「東京に原発を」という本が売れたのは30年も前のことだ。
原発が絶対安全だというなら、送電コストも安くなる東京に造ればいい。
想定被害が少ない地方に造るのは、万が一ということがあるからに他ならない。
この、地方に負担を押しつけて都会は恩恵だけを受けるという構図は、どうにかならないものか。
県内のダムも東京へ送電しているものばかりだ。
そんなことだから、東京への一極集中がますます進むのだ。
利益を受けるなら、リスクも合わせて受容すべきではないか...。
おいしい所だけ持って行こうなんて虫がよすぎる。
昨日の信濃毎日新聞にも、どこかの助教授のそんな意見が載っていた。
なんだか、今行われている計画停電も、東電の策略かと疑念を抱いてしまう。
原発が機能しないとこんなに大変なことになりますよ。
だから原発は必要です。
もっとどんどん増やしましょう。
という筋書きになるような...。
原発は本当に必要なのか?
今回のような危険を加味してまで、CO2を出さないというメリットが優先されるべきなのか?
世界各国も原発のあり方を再考し出している。
日本もこれを機会に、エネルギー問題をどうするのか、
徹底的に議論すべきだと思う。
その際の一つの視点として、拡大成長を望まない、
エネルギーの消費を縮小するという選択もありだと思う。
原発に頼らざるを得ないくらいなら、電力の不足も我慢するという立場だ。
そういう意味では、今回の計画停電もいい機会になるかもしれない。
無駄な照明や過度の空調はやめる。
ご飯は鍋で炊き、お湯はやかんで沸かす。
まず需要ありきではなく、供給量の中でやりくりするという路線は取れないものだろうか...。
終わりに一つの文章を紹介しておく。
かつて原発の現場で働いていたという人が書かれたものだ。
「原発がどんなものか知ってほしい」

p.s.通信回線が込んでいる影響か、メールが滞っていることがあるようだ。
震災当日の千葉からのメールは、深夜にまとめて3通届いた。
パソコンに届くメールもいつもより少ない。
大量に舞い込む迷惑メールも極端に少ないのはありがたいが...。
2011年02月22日
釈然としない...
確定申告の時期だ。
年明けからせっせと、PCの青色申告ソフトに入力してきた。
作業はほぼ終了したが、今回改めて気づいたことがある。
昨年8月の自宅の電話料金(BBフォン)が異常に高いのだ。
いつもの月より5,000円も多い。
内訳を調べてみたら、家から携帯にかけた料金だった。
自宅の電話から携帯にかけることは少ない。
この半年間の携帯への通話料を調べてみると、
ゼロの月もあるし、せいぜい400円くらいだ。
それが2010年8月だけ2,719円もある!
心当たりがないので、通話明細を調べようとした。
ところがネットでは、請求明細は過去1年分調べられるが、
通話明細は過去3ヶ月分しか見られない。
そこでYahoo BB に問い合わせることに...。
いろいろ見たが、問い合わせ先がよくわからない。
自分が知りたい内容にふさわしい窓口はどこなのか...。
やっと見つけた電話番号にかけてみる。
例の、「○○の方は1を...」という自動応答メッセージが流れる。
○○の中に「通話明細」がないので、仕方なく「請求について」を選んだら、
しばらく待たせて「○、百、△、十、×、円、です」という無機質な音が返ってきた。
...そんなのネットで確認できる。
知りたい項目になかなかたどり着けないのでイライラしてきた。
何番を選んでも機械が答えるだけだ。
生の人間に直接つながるルートはないらしい。
ラチが明かないのでメールにする。
メールの宛先も、担当ごとにいろいろあるようだが、
面倒なのでよろず相談的な所に送る。
まったく、なんでこんなに手間がかかるのか...。
数時間後やっと返事が来た。
いわく、
「個人情報漏洩防止の観点から、3ヶ月を経過した時点でデータを削除しているので、
通知することはできない」とのこと。
自分の通話明細、しかもたかだか半年前のものを知ることができないって...。
削除していると言うが、犯罪捜査などで警察からの要請があれば応じられるのではないか...。
どうも釈然としない。
最近、何かといえば「個人情報」だ。
何にでも大袈裟に、まるで伝家の宝刀のようにこれを振りかざす風潮が、私は嫌いだ。
世の中がどんどんギスギスしてくる。
電話をかけても、出た相手はほとんどの場合名乗らない。
「はい、○○です」と出ることが習慣付いている私には、どうもこれが馴染めないのだが、
それについてはまた次回触れることにする。

<画像について> 久々の釘隠。大修理が終わって公開が再開された松代・真田邸にて。
年明けからせっせと、PCの青色申告ソフトに入力してきた。
作業はほぼ終了したが、今回改めて気づいたことがある。
昨年8月の自宅の電話料金(BBフォン)が異常に高いのだ。
いつもの月より5,000円も多い。
内訳を調べてみたら、家から携帯にかけた料金だった。
自宅の電話から携帯にかけることは少ない。
この半年間の携帯への通話料を調べてみると、
ゼロの月もあるし、せいぜい400円くらいだ。
それが2010年8月だけ2,719円もある!
心当たりがないので、通話明細を調べようとした。
ところがネットでは、請求明細は過去1年分調べられるが、
通話明細は過去3ヶ月分しか見られない。
そこでYahoo BB に問い合わせることに...。
いろいろ見たが、問い合わせ先がよくわからない。
自分が知りたい内容にふさわしい窓口はどこなのか...。
やっと見つけた電話番号にかけてみる。
例の、「○○の方は1を...」という自動応答メッセージが流れる。
○○の中に「通話明細」がないので、仕方なく「請求について」を選んだら、
しばらく待たせて「○、百、△、十、×、円、です」という無機質な音が返ってきた。
...そんなのネットで確認できる。
知りたい項目になかなかたどり着けないのでイライラしてきた。
何番を選んでも機械が答えるだけだ。
生の人間に直接つながるルートはないらしい。
ラチが明かないのでメールにする。
メールの宛先も、担当ごとにいろいろあるようだが、
面倒なのでよろず相談的な所に送る。
まったく、なんでこんなに手間がかかるのか...。
数時間後やっと返事が来た。
いわく、
「個人情報漏洩防止の観点から、3ヶ月を経過した時点でデータを削除しているので、
通知することはできない」とのこと。
自分の通話明細、しかもたかだか半年前のものを知ることができないって...。
削除していると言うが、犯罪捜査などで警察からの要請があれば応じられるのではないか...。
どうも釈然としない。
最近、何かといえば「個人情報」だ。
何にでも大袈裟に、まるで伝家の宝刀のようにこれを振りかざす風潮が、私は嫌いだ。
世の中がどんどんギスギスしてくる。
電話をかけても、出た相手はほとんどの場合名乗らない。
「はい、○○です」と出ることが習慣付いている私には、どうもこれが馴染めないのだが、
それについてはまた次回触れることにする。

<画像について> 久々の釘隠。大修理が終わって公開が再開された松代・真田邸にて。
2011年02月01日
とんでもない答
たとえば0.3の2乗を0.9としたり、85×99を765と答えて平然としている生徒がいる。
答がおよそいくつくらいになるか、見当をつけることを知らないのだ。
かける数が1より小さければ、答はもとの数より小さくなるはず。
0.3に0.3をかけて0.9になるはずない。
だったら、ケタを1つ下げて0.09かな?と修正できる。
85×99は、85×100から85を引けばいいのだが、85×10から引くと765になってしまう。
これも、この答が3ケタになるはずがないとわかれば防げるミスである。
方程式の文章題で、家から学校までの距離が300kmになったり、
自転車が時速120kmになったりしてもおかしいと思わない子も多い。
cmやmなら感覚がつかめても、kmや、増して速さになると実感が伴わないのだろう。
策として、長い距離や速さのだいたいの目安を覚えておくよう言っている。
自分の家から学校までの距離はどれくらいか?
駅まではどうか?2kmとはどの辺までの距離か...?
鉄道で長野から東京までは約200km、東京から大阪までが約500km、
北海道から沖縄まで直線距離で約2000km、地球一周が約4万km。
速さでは、ゆっくり歩く速さが時速4km、自転車で時速10~15km、
車(一般道)が時速40~60km、電車が時速80~100km...。
これくらいは、中学生にも頭に入れておいてほしい。

答がおよそいくつくらいになるか、見当をつけることを知らないのだ。
かける数が1より小さければ、答はもとの数より小さくなるはず。
0.3に0.3をかけて0.9になるはずない。
だったら、ケタを1つ下げて0.09かな?と修正できる。
85×99は、85×100から85を引けばいいのだが、85×10から引くと765になってしまう。
これも、この答が3ケタになるはずがないとわかれば防げるミスである。
方程式の文章題で、家から学校までの距離が300kmになったり、
自転車が時速120kmになったりしてもおかしいと思わない子も多い。
cmやmなら感覚がつかめても、kmや、増して速さになると実感が伴わないのだろう。
策として、長い距離や速さのだいたいの目安を覚えておくよう言っている。
自分の家から学校までの距離はどれくらいか?
駅まではどうか?2kmとはどの辺までの距離か...?
鉄道で長野から東京までは約200km、東京から大阪までが約500km、
北海道から沖縄まで直線距離で約2000km、地球一周が約4万km。
速さでは、ゆっくり歩く速さが時速4km、自転車で時速10~15km、
車(一般道)が時速40~60km、電車が時速80~100km...。
これくらいは、中学生にも頭に入れておいてほしい。

2011年01月27日
快適さの落とし穴
この寒さはいったいいつまで続くのか...。
築100年超えのわが家は、断熱材など一切使われていない。
下からも横からも冷気が染みこんでくる。
薪ストーブをガンガン焚いても、暖かいのは2部屋くらいだ。
古からの「夏を旨とすべし」という教えに従って造られているので、
寒さは我慢するしかない。
「真冬でも暖か」などとCMで見るたびに、少し羨ましくなる。
先日、地元の集落のどんど焼き&新年会のときに、大工さんと話をした。
仲間が家を建てたそうだ。
高気密、高断熱の最新型。
わが家よりさらに山奥にあるのだが、
冬の朝でも室内は20°近くあるという。
日が当たれば半袖で過ごせるくらいだそうだ。
へえ...と感心してたら、続けて言った。
「だから、子どもがしょっちゅう風邪をひいてる」...。
なるほど、そりゃあそうだ。
暑さや寒さを体験する中で、自然に体が鍛えられていく。
体温を一定に保つために、自律神経がせっせと働いてくれるのだ。
その限界を超えた気温に対しても、徐々に抵抗力がついてくる。
夏でも冬でも、早朝でも深夜でも、
常に快適な温度に管理されている温室で育っていては、
神経も皮膚もひ弱になるのは自明の理であろう。
衣服の脱ぎ着で体温を調節することができない。
そんな子が多いという投書も目にした。
ストーブの効いた部屋からトイレに行く。
一歩廊下に出れば寒い。
だから1枚羽織って行く。
当たり前のことだ。
生徒が塾に来ても、まだ部屋が十分に暖まっていないときがある。
だったらコートを着ていればいいのに、入室と同時に脱ぐ。
もっとも、車で送られてくる生徒はコートなど着てないが...。
そうかと思えば、部屋が暖まったのにまだコートを着ている。
暑くないのか...。
夏の終わりの急に涼しくなった日、半袖で震えている子もいた。
暮らしが快適になればなるほど、人間は弱くなり退化していく。
案外、こんなことで人類は滅亡していくのかも知れない。
少なくとも、長生きできる日本人は、
これからどんどん少なくなっていくのは間違いないだろう。
我々はどこに向かって進んでいるのか...。

築100年超えのわが家は、断熱材など一切使われていない。
下からも横からも冷気が染みこんでくる。
薪ストーブをガンガン焚いても、暖かいのは2部屋くらいだ。
古からの「夏を旨とすべし」という教えに従って造られているので、
寒さは我慢するしかない。
「真冬でも暖か」などとCMで見るたびに、少し羨ましくなる。
先日、地元の集落のどんど焼き&新年会のときに、大工さんと話をした。
仲間が家を建てたそうだ。
高気密、高断熱の最新型。
わが家よりさらに山奥にあるのだが、
冬の朝でも室内は20°近くあるという。
日が当たれば半袖で過ごせるくらいだそうだ。
へえ...と感心してたら、続けて言った。
「だから、子どもがしょっちゅう風邪をひいてる」...。
なるほど、そりゃあそうだ。
暑さや寒さを体験する中で、自然に体が鍛えられていく。
体温を一定に保つために、自律神経がせっせと働いてくれるのだ。
その限界を超えた気温に対しても、徐々に抵抗力がついてくる。
夏でも冬でも、早朝でも深夜でも、
常に快適な温度に管理されている温室で育っていては、
神経も皮膚もひ弱になるのは自明の理であろう。
衣服の脱ぎ着で体温を調節することができない。
そんな子が多いという投書も目にした。
ストーブの効いた部屋からトイレに行く。
一歩廊下に出れば寒い。
だから1枚羽織って行く。
当たり前のことだ。
生徒が塾に来ても、まだ部屋が十分に暖まっていないときがある。
だったらコートを着ていればいいのに、入室と同時に脱ぐ。
もっとも、車で送られてくる生徒はコートなど着てないが...。
そうかと思えば、部屋が暖まったのにまだコートを着ている。
暑くないのか...。
夏の終わりの急に涼しくなった日、半袖で震えている子もいた。
暮らしが快適になればなるほど、人間は弱くなり退化していく。
案外、こんなことで人類は滅亡していくのかも知れない。
少なくとも、長生きできる日本人は、
これからどんどん少なくなっていくのは間違いないだろう。
我々はどこに向かって進んでいるのか...。

2011年01月23日
マナーって何だ?
先日深夜の番組で、結婚披露宴に出席するときのマナーが採り上げられていた。
民放の新入社員の女性がいくつかの場面を想定して行動し、
そのVTRを見てマナーの問題点を指摘するという趣向。
採点するのは昨年(?)「接遇道」でブレイクした平林郁である。
私はこの人が苦手だ。
スパルタ式という触れ込みで、とにかく怒鳴りまくる。
「笑顔!!」「声が小さい!!」
...体育会系のシゴキにしか見えない。
些細なミスですぐキレる。
感情に任せて怒っている、
罵声を浴びせてストレスを発散してるとしか思えない。
あまりの厳しさに相手が涙でも見せようものなら、
ここぞとばかりにさらに激しく責め立てる。
かなりのサドではなかろうか...。
そもそも、マナーを教える講師が、あんな汚い言葉遣いでいいのだろうか。
教え方にもマナーがあるのではないか?
「カリスマ講師」的に持ち上げられているようだが、
本当にそんな優れた人物なのか...。
彼女が実際に会社の研修の講師にでもなったら、社員は戦々恐々だ。
怒鳴られて伸びる人も中にはいるだろうが、
ほめられて伸びるタイプの人はたまらないだろう。
他人が怒られているのを見ているだけでびびってしまう。
「笑顔!!」と一喝されても、萎縮してひきつった笑顔しか作れそうもない...。
その番組中でも新人さんは終始怒られっぱなしで、半分泣きそうな顔をしていた。
同席した上司(男性)に救いを求める目もしていたのだが、
実はその上司も、部下の監督がなっていないと平林氏からダメ出しをされていたのだ...。
披露宴の受付でご祝儀袋を渡すとき、自分の席を探して坐るとき...と、
その度に何十回と怒声が飛ぶ。
で、いよいよ新婦の友人代表としてのスピーチの場面。
「○○さん(新郎の下の名前)、△△さん(新婦の下の名前)、並びに両家のご親族の皆さん、
本日は誠におめでとうございます。」と、始まったらもう文句がついた。
「さん」など馴れ馴れしい。
新郎は「××○○様(フルネーム)」、新婦は「旧□□△△様」と呼べという。
ええっ?!
そんなの聞いたことないけど...。
そもそも披露宴は、新郎新婦が客を招待するものではないのか。
招いた側に「様」を付けるのはおかしいのではないか。
最近病院で流行っている「××様」と同じで、
「様」さえ付けておけば間違いないと思っているんじゃなかろうか...。
だいたい、友人挨拶なんてのは、少しくだけたくらいが丁度いいのだ。
新婦だって、馬鹿騒ぎしいた友だちに突然「様」なんて付けられては気味が悪かろう。
マナーって何だろう?
いったい何のためにあるのだろう?
私は、人と人とが気持ちよく付き合うための知恵だととらえている。
その場にいる人が不快になったり、不利益を被ることはしてはならない。
そうでない限りは、そんなに杓子定規に考える必要はないのではないか。
新郎新婦を「~さん」で呼ぶことで不快になる人がどれほどいるのか。
むしろ、「様」付けに違和感を覚える人が圧倒的だと思う。
そんなことで怒鳴られてはたまらない。
でも立場上ハイハイと聞いているしかなく、
何度も練習をさせられる新人さんは可哀想だった。
誰か一度でいいから、徹底的に反抗してくれないか。
あのおばさん、少し調子に乗りすぎている...。

民放の新入社員の女性がいくつかの場面を想定して行動し、
そのVTRを見てマナーの問題点を指摘するという趣向。
採点するのは昨年(?)「接遇道」でブレイクした平林郁である。
私はこの人が苦手だ。
スパルタ式という触れ込みで、とにかく怒鳴りまくる。
「笑顔!!」「声が小さい!!」
...体育会系のシゴキにしか見えない。
些細なミスですぐキレる。
感情に任せて怒っている、
罵声を浴びせてストレスを発散してるとしか思えない。
あまりの厳しさに相手が涙でも見せようものなら、
ここぞとばかりにさらに激しく責め立てる。
かなりのサドではなかろうか...。
そもそも、マナーを教える講師が、あんな汚い言葉遣いでいいのだろうか。
教え方にもマナーがあるのではないか?
「カリスマ講師」的に持ち上げられているようだが、
本当にそんな優れた人物なのか...。
彼女が実際に会社の研修の講師にでもなったら、社員は戦々恐々だ。
怒鳴られて伸びる人も中にはいるだろうが、
ほめられて伸びるタイプの人はたまらないだろう。
他人が怒られているのを見ているだけでびびってしまう。
「笑顔!!」と一喝されても、萎縮してひきつった笑顔しか作れそうもない...。
その番組中でも新人さんは終始怒られっぱなしで、半分泣きそうな顔をしていた。
同席した上司(男性)に救いを求める目もしていたのだが、
実はその上司も、部下の監督がなっていないと平林氏からダメ出しをされていたのだ...。
披露宴の受付でご祝儀袋を渡すとき、自分の席を探して坐るとき...と、
その度に何十回と怒声が飛ぶ。
で、いよいよ新婦の友人代表としてのスピーチの場面。
「○○さん(新郎の下の名前)、△△さん(新婦の下の名前)、並びに両家のご親族の皆さん、
本日は誠におめでとうございます。」と、始まったらもう文句がついた。
「さん」など馴れ馴れしい。
新郎は「××○○様(フルネーム)」、新婦は「旧□□△△様」と呼べという。
ええっ?!
そんなの聞いたことないけど...。
そもそも披露宴は、新郎新婦が客を招待するものではないのか。
招いた側に「様」を付けるのはおかしいのではないか。
最近病院で流行っている「××様」と同じで、
「様」さえ付けておけば間違いないと思っているんじゃなかろうか...。
だいたい、友人挨拶なんてのは、少しくだけたくらいが丁度いいのだ。
新婦だって、馬鹿騒ぎしいた友だちに突然「様」なんて付けられては気味が悪かろう。
マナーって何だろう?
いったい何のためにあるのだろう?
私は、人と人とが気持ちよく付き合うための知恵だととらえている。
その場にいる人が不快になったり、不利益を被ることはしてはならない。
そうでない限りは、そんなに杓子定規に考える必要はないのではないか。
新郎新婦を「~さん」で呼ぶことで不快になる人がどれほどいるのか。
むしろ、「様」付けに違和感を覚える人が圧倒的だと思う。
そんなことで怒鳴られてはたまらない。
でも立場上ハイハイと聞いているしかなく、
何度も練習をさせられる新人さんは可哀想だった。
誰か一度でいいから、徹底的に反抗してくれないか。
あのおばさん、少し調子に乗りすぎている...。

2010年12月29日
CMにつっこむ(2)~なめとんか!?
昨日の続き。
(その3)エプソンのプリンタ「カラリオ」。
黒木メイサと役所広司のテレビCM。
年賀状の時期になってからしつこいくらい流れている。
パソコンとかに弱いオヤジに、
若い女性が「これならホラ、こんなに簡単」と、年賀状作りを指南するという設定だ。
まず、黒木の言葉遣いが気に入らない。
年配の男性をバカにしたような態度で、終始タメ口だ。
「まだ迷ってるの?」
「迷ってるんですか?」だろ!
プリンタの性能を自分の技術のように自慢して、
「こんなことも知らないのか」という接し方をしてくる。
で、役所が文面を書き上げて、最後に「卯」と書こうと思ったらミスをする。
ここでまた、カチンとくる黒木の一言。
「それ、卵じゃない?」
そばに付き添ってずっと手元を見ていたんだから、
全部書き上げる前に指摘しろよ!
左半分を書いただけでわかるだろ...。
完璧に「卵」になってから言って、恥をかかせてやろうという魂胆だったに違いない。
まあ面白いことは面白いんだが、あのCM、今一素直に見られない。
あと何日かで流れなくなるだろうからいいか...。
でも、続編も同じような設定で作るんだろうな...。

(その3)エプソンのプリンタ「カラリオ」。
黒木メイサと役所広司のテレビCM。
年賀状の時期になってからしつこいくらい流れている。
パソコンとかに弱いオヤジに、
若い女性が「これならホラ、こんなに簡単」と、年賀状作りを指南するという設定だ。
まず、黒木の言葉遣いが気に入らない。
年配の男性をバカにしたような態度で、終始タメ口だ。
「まだ迷ってるの?」
「迷ってるんですか?」だろ!
プリンタの性能を自分の技術のように自慢して、
「こんなことも知らないのか」という接し方をしてくる。
で、役所が文面を書き上げて、最後に「卯」と書こうと思ったらミスをする。
ここでまた、カチンとくる黒木の一言。
「それ、卵じゃない?」
そばに付き添ってずっと手元を見ていたんだから、
全部書き上げる前に指摘しろよ!
左半分を書いただけでわかるだろ...。
完璧に「卵」になってから言って、恥をかかせてやろうという魂胆だったに違いない。
まあ面白いことは面白いんだが、あのCM、今一素直に見られない。
あと何日かで流れなくなるだろうからいいか...。
でも、続編も同じような設定で作るんだろうな...。

2010年12月24日
電話のかけ方も知らんのか!
塾をやっている最中に電話が鳴る。
欠席の連絡かな?
でも今日はもうみんな来てるし...。
もしかしたら新規の問い合わせかと、若干の期待を持ちつつ受話器を取ると、
NTTうんぬん、Yahoo Japan の代理店うんぬん...。
一方的にまくし立てる雰囲気なので、「今、授業中です」と機先を制する。
「では、また別の時間に...」と言うので、
「結構です。要りません!」と断った。
電話というのは相手の都合に振り回される通信手段だ。
どんなに忙しくても、電話が鳴ったら出なければならない。
メールやFAX のように、忙しいときには放っておくというわけには行かないのだ。
(もっとも、若者のケータイメールのやり取りは、即レスでないとまずいらしいが...。)
その分、電話をかける側には、相手の時間を奪っているという自覚が必要となる。
相手が出たら、初めに「今、お時間よろしいですか?」と確認する気配りを持ちたい。
その一言もなしに、いきなり本題に入ろうとするから、
生徒の指導を中断して応対しているこちらは、無性に腹が立つのだ。
そんな礼儀も知らんのか!?
下手に「今、大丈夫ですか?」と尋ねて、「忙しい」と断られることを警戒しているのか?
断られても、少なくとも相手に与える不快感は、その方が軽減されると思うのだが...。
そもそも、電話をかけてくる時間が間違っている。
何を見てかけてくるのか知らないが、業種別の名簿ならもちろん、
そうでなくても名前から、学習塾であることはすぐわかるはずだ。
夕方から夜にかけては忙しい時間であることは、容易に想像がつくだろう。
逆にその時間なら確実につながると思ってかけてくるのかも知れないが、
ちょっと時間をずらすなどの配慮がほしい。
(因みに、塾の電話は不在でもケータイに転送されるようセットしてある。)
せめて「お忙しいところ申し訳ありませんが...」という気持ちがあれば、
先に書いたような一言が自然に出てくるのではなかろうか。
中には、何度も同じ時間帯(授業中)にかけて来るバカもいる。
相手に合わせようという気持ちなど微塵もないのか...。
自分の都合しか考えていない奴の話など、絶対に聞きたくないのだ。
電話セールスも結構だが、まずマナーや気配りの教育を徹底してもらいたい。

欠席の連絡かな?
でも今日はもうみんな来てるし...。
もしかしたら新規の問い合わせかと、若干の期待を持ちつつ受話器を取ると、
NTTうんぬん、Yahoo Japan の代理店うんぬん...。
一方的にまくし立てる雰囲気なので、「今、授業中です」と機先を制する。
「では、また別の時間に...」と言うので、
「結構です。要りません!」と断った。
電話というのは相手の都合に振り回される通信手段だ。
どんなに忙しくても、電話が鳴ったら出なければならない。
メールやFAX のように、忙しいときには放っておくというわけには行かないのだ。
(もっとも、若者のケータイメールのやり取りは、即レスでないとまずいらしいが...。)
その分、電話をかける側には、相手の時間を奪っているという自覚が必要となる。
相手が出たら、初めに「今、お時間よろしいですか?」と確認する気配りを持ちたい。
その一言もなしに、いきなり本題に入ろうとするから、
生徒の指導を中断して応対しているこちらは、無性に腹が立つのだ。
そんな礼儀も知らんのか!?
下手に「今、大丈夫ですか?」と尋ねて、「忙しい」と断られることを警戒しているのか?
断られても、少なくとも相手に与える不快感は、その方が軽減されると思うのだが...。
そもそも、電話をかけてくる時間が間違っている。
何を見てかけてくるのか知らないが、業種別の名簿ならもちろん、
そうでなくても名前から、学習塾であることはすぐわかるはずだ。
夕方から夜にかけては忙しい時間であることは、容易に想像がつくだろう。
逆にその時間なら確実につながると思ってかけてくるのかも知れないが、
ちょっと時間をずらすなどの配慮がほしい。
(因みに、塾の電話は不在でもケータイに転送されるようセットしてある。)
せめて「お忙しいところ申し訳ありませんが...」という気持ちがあれば、
先に書いたような一言が自然に出てくるのではなかろうか。
中には、何度も同じ時間帯(授業中)にかけて来るバカもいる。
相手に合わせようという気持ちなど微塵もないのか...。
自分の都合しか考えていない奴の話など、絶対に聞きたくないのだ。
電話セールスも結構だが、まずマナーや気配りの教育を徹底してもらいたい。





