2011年05月30日
うるう年を知らない!
中学生が言葉を知らないのには驚かなくなった。
それ以前に、一般常識と言っていいことを知らないのだ。
小学生はともかく、中学生なら当然知っておくべき、
あるいは知っておいてほしいことを知らなすぎる。
一例を挙げよう。
ある日の塾での一コマである。
「1ヶ月が30日以下の月は?」という問に、中2の女子が悩んでいた。
実はこの問題、正解率がきわめて低い。
中学生で10%を切るのではないか...。
そのとき在室していた他の生徒(中2が他に2名、中1、小5が各1名)も
いずれこの問題にぶつかることになるので、この機会にまとめて教えることにする。
以下、私と生徒とのやり取りである。
私「この問題わかる人いる?」
生徒A(中2)、B(中2)、C(中2)、D(中1)、E(小5)「....。」
私「う~ん...。じゃ、その前に...28日までしかない月は知っているよね?」
(多くの子がうなずくので生徒Cを指名。)
生徒C「 ...4月...。」
私「2月だ。...2月が29日になる年もあるよね。」
(今度はほぼ全員が「?」という顔をする。)
私「うるう年って知らない?...1年が1日長くなるの...。」
全員「えーっ?!」
私「1年は何日だ?」(生徒Dを指名。)
生徒D「30日...。」
私「1ヶ月じゃなくて1年!」
生徒「ああ...365日。」
私「そう。それが4年に一度2月が29日まであって、1年が366日なるの。
これがうるう年。20××年の××が4で割り切れる年がうるう年です。」
しばし、うるう年がある理由と、その仕組みについて説明した。
(4年に一度うるう年。100年に一度うるう年をやめる。400年に一度うるう年を復活させる。)
そこからやっと、本来の「30日以下の月」の話に入る。
「大の月」「小の月」から始めて、
最後は「小の月」の覚え方=「西向く侍」を伝授。
このくらいのことは常識として覚えておくよう言い聞かせた。
大人になったら1日多いか少ないかは大きな問題だと...。
他にもいくらでもある。
アマゾンがどこにあるか知らない。
日本の県名も西日本になると壊滅的だ。
日本が戦争に負けたことを知らない。
日本は先進国ではなく発展途上国だと思っている。
村や町の存在を知らない(すべて「市」だと思っている)。
ツツジやスギナは見たことがないと言う。
1kmがどれくらいの距離か見当も付かない...などなど。
切符の買い方を知らないという高校生もいた。
島崎藤村や武者小路実篤、ヘミングウェイは、高校生でも知らないことの方が「常識」なんだそうだ。
こうした現状の一因を学校教育に求めることもできよう。
小学校でちゃんと教えてくれなければ困ると...。
しかし、上に挙げた例の大半は、学校よりもむしろ家庭で教えるべきことである。
毎日の生活の中で、親から子へ伝える一般常識である。
手伝いをさせたり、家族で遠出をしたり、ときには一人で「冒険」をさせたり...。
家族との豊富な会話や様々な生活体験を通じて、自然に身につける知識ではないだろうか。
私自身も、「西向く侍」や多くのことわざ、言い伝えなどは親から教わった記憶がある。
今、企業が新入社員に求める能力の1位はコミュニケーション能力である。
裏を返せば、それが貧弱な若者がいかに多いかということだろう。
その一因が一般常識の不足にあることは、十分考えられることではなかろうか..。
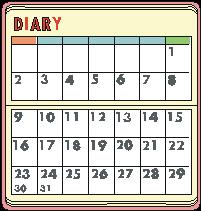
それ以前に、一般常識と言っていいことを知らないのだ。
小学生はともかく、中学生なら当然知っておくべき、
あるいは知っておいてほしいことを知らなすぎる。
一例を挙げよう。
ある日の塾での一コマである。
「1ヶ月が30日以下の月は?」という問に、中2の女子が悩んでいた。
実はこの問題、正解率がきわめて低い。
中学生で10%を切るのではないか...。
そのとき在室していた他の生徒(中2が他に2名、中1、小5が各1名)も
いずれこの問題にぶつかることになるので、この機会にまとめて教えることにする。
以下、私と生徒とのやり取りである。
私「この問題わかる人いる?」
生徒A(中2)、B(中2)、C(中2)、D(中1)、E(小5)「....。」
私「う~ん...。じゃ、その前に...28日までしかない月は知っているよね?」
(多くの子がうなずくので生徒Cを指名。)
生徒C「 ...4月...。」
私「2月だ。...2月が29日になる年もあるよね。」
(今度はほぼ全員が「?」という顔をする。)
私「うるう年って知らない?...1年が1日長くなるの...。」
全員「えーっ?!」
私「1年は何日だ?」(生徒Dを指名。)
生徒D「30日...。」
私「1ヶ月じゃなくて1年!」
生徒「ああ...365日。」
私「そう。それが4年に一度2月が29日まであって、1年が366日なるの。
これがうるう年。20××年の××が4で割り切れる年がうるう年です。」
しばし、うるう年がある理由と、その仕組みについて説明した。
(4年に一度うるう年。100年に一度うるう年をやめる。400年に一度うるう年を復活させる。)
そこからやっと、本来の「30日以下の月」の話に入る。
「大の月」「小の月」から始めて、
最後は「小の月」の覚え方=「西向く侍」を伝授。
このくらいのことは常識として覚えておくよう言い聞かせた。
大人になったら1日多いか少ないかは大きな問題だと...。
他にもいくらでもある。
アマゾンがどこにあるか知らない。
日本の県名も西日本になると壊滅的だ。
日本が戦争に負けたことを知らない。
日本は先進国ではなく発展途上国だと思っている。
村や町の存在を知らない(すべて「市」だと思っている)。
ツツジやスギナは見たことがないと言う。
1kmがどれくらいの距離か見当も付かない...などなど。
切符の買い方を知らないという高校生もいた。
島崎藤村や武者小路実篤、ヘミングウェイは、高校生でも知らないことの方が「常識」なんだそうだ。
こうした現状の一因を学校教育に求めることもできよう。
小学校でちゃんと教えてくれなければ困ると...。
しかし、上に挙げた例の大半は、学校よりもむしろ家庭で教えるべきことである。
毎日の生活の中で、親から子へ伝える一般常識である。
手伝いをさせたり、家族で遠出をしたり、ときには一人で「冒険」をさせたり...。
家族との豊富な会話や様々な生活体験を通じて、自然に身につける知識ではないだろうか。
私自身も、「西向く侍」や多くのことわざ、言い伝えなどは親から教わった記憶がある。
今、企業が新入社員に求める能力の1位はコミュニケーション能力である。
裏を返せば、それが貧弱な若者がいかに多いかということだろう。
その一因が一般常識の不足にあることは、十分考えられることではなかろうか..。
2011年05月25日
完成!超国語教材
およそ1年かけて、待望の国語教材が完成した。
名付けて「超国語教材(1)おじいさんのランプ」。
現在、平安堂長野店(駅前)の参考書売り場で販売している(税込1,500円)。
数年前から、長野市周辺の個人塾経営者で「こだわり学習」研究会を結成し、
情報交換、教材作りなどの活動を行っている。
そこから発行された書物の第3弾ということになった。
ちなみに1冊目は勉強法に関するメンバーの対談集、
2冊目は別の塾長が書いた「高校入試のための数学」である。
経費節減のため、印刷から製本まで自分たちで行っている。
印刷はこれまで、インクジェットプリンタの自動両面印刷を使ってきた。
私の塾にあるhpのプリンタは、ビジネス用の中でもかなり速い。
それでも両面印刷となると、片面を印刷し終わってから乾燥のためしばらく停止するので、
1部(約180ページ)刷り終わるのに1時間弱かかってしまう。
仕上がりは綺麗なのだが...。
今回、ちょうどいいタイミングでリースのコピー機を入れ替えた。
パソコンと繋げばプリンタにもなる。
普通にB5の両面印刷ではカウンタ料金が割高になるが、
B4両面で印刷して裁断すれば半分の料金で済む。
ワープロソフトでレイアウトを指定すれば、9枚ずつ5回裁断すれば簡単にページがそろう計算だ。
多少の手間はかかるが、なんせスピードが格段に速い。
1部の印刷にかかるのはわずか7分。
...これまでの8倍だ!
ただ、コピー機だと熱がかかる分、紙が波うってしまう。
B5サイズぴったりに、ちょうど半分に裁断するのも難しい。
できあがりを見るとわずかな凸凹が気になる...。
これは今後の課題だ。
製本は8,000円くらいで買ったコンパクトな製本機を使う。
専用のカバー(表紙だけ透明)は背表紙の内側にのりが付いていて、
なかみを挟み込んで製本機に差し込むと、30秒ほどでのりが溶けて接着が完了。
熱が冷めるまで立てかけておけば立派な冊子になる。
背表紙に、DVDケース用のラベルでタイトルを貼って完成だ。
カバーのサイズ(各種あり)に合わせてページ数を整えなければならないし、
1ページも脱落しないよう、製本機にかける前に慎重な準備をする必要もあるが、
これだけ手軽に見栄えのよい物が作れるのはありがたい。
肝心の内容は、もちろん新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材にしている。
単なる読解教材ではなく、書かせる問題が圧倒的に多い。
なぜそう答えるか根拠を述べさせたり、本文中には書かれていないことを想像させたり、
主人公の言動を評価させたり...。
とにかく記述式問題が中心である。
語彙を広げる問題、言葉にこだわった問題も多い。
一つの言葉でどんな心情や状況が読み取れるか。
この言葉をこう換えるとどんな違いがあるのか...。
文を組み立てたり書き換えたりする問題、おかしな文を直す問題は、
日本語の表現技術を高めるためのものだ。
巻末にはそれをさらに磨くための補充問題も入れた。
なお、「超国語」と歌っているとおり、地理や歴史、科学と絡めた問題も随所にある。
算数の問題の解き方、考え方を論理的に説明させるページは、特にお薦めだ。
初めは空欄補充で基本的な手順を学び、同様の問題で完全記述に挑む。
子どもたちに最終的に身につけてほしいと考えている力の一つが「説明力」だ。
その入門編とも言うべき位置づけである。
記述式が主のため、解答例及び解説がかなり詳しくなった。
全体の3分の1、60ページを割いている。
塾の生徒に実際に解いてもらった結果、思いもよらぬ答が続出し、
解答例も解説もどんどん多くなってしまった。
もちろん、これでもすべての答に対応できているとは思えないが、
予測しうる答への最大限の対処は施したつもりである。
中学生の声は、思っていた以上に「難しい」が多かった。
中3になると正解率が高かったが、やはり中1には手応えがあったようだ。
生徒の反応を見て、特に難易度が高いと判断した問題については、
別の問題に差し替えたりヒントを添えるなどした。
それでもこの教材、おそらく大人が解いても十分やり甲斐を感じられるはずである。
ブロガーの皆さん、文章力養成にいかがですか?
「欲しいけど長野駅前まで行けない」という方は、コメント欄でお伝えください。
いかようにも善処しますよ。
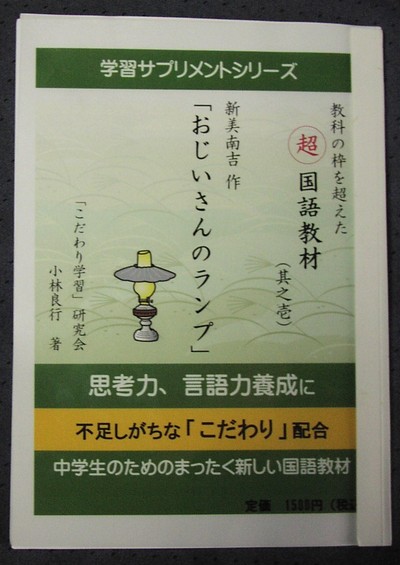
名付けて「超国語教材(1)おじいさんのランプ」。
現在、平安堂長野店(駅前)の参考書売り場で販売している(税込1,500円)。
数年前から、長野市周辺の個人塾経営者で「こだわり学習」研究会を結成し、
情報交換、教材作りなどの活動を行っている。
そこから発行された書物の第3弾ということになった。
ちなみに1冊目は勉強法に関するメンバーの対談集、
2冊目は別の塾長が書いた「高校入試のための数学」である。
経費節減のため、印刷から製本まで自分たちで行っている。
印刷はこれまで、インクジェットプリンタの自動両面印刷を使ってきた。
私の塾にあるhpのプリンタは、ビジネス用の中でもかなり速い。
それでも両面印刷となると、片面を印刷し終わってから乾燥のためしばらく停止するので、
1部(約180ページ)刷り終わるのに1時間弱かかってしまう。
仕上がりは綺麗なのだが...。
今回、ちょうどいいタイミングでリースのコピー機を入れ替えた。
パソコンと繋げばプリンタにもなる。
普通にB5の両面印刷ではカウンタ料金が割高になるが、
B4両面で印刷して裁断すれば半分の料金で済む。
ワープロソフトでレイアウトを指定すれば、9枚ずつ5回裁断すれば簡単にページがそろう計算だ。
多少の手間はかかるが、なんせスピードが格段に速い。
1部の印刷にかかるのはわずか7分。
...これまでの8倍だ!
ただ、コピー機だと熱がかかる分、紙が波うってしまう。
B5サイズぴったりに、ちょうど半分に裁断するのも難しい。
できあがりを見るとわずかな凸凹が気になる...。
これは今後の課題だ。
製本は8,000円くらいで買ったコンパクトな製本機を使う。
専用のカバー(表紙だけ透明)は背表紙の内側にのりが付いていて、
なかみを挟み込んで製本機に差し込むと、30秒ほどでのりが溶けて接着が完了。
熱が冷めるまで立てかけておけば立派な冊子になる。
背表紙に、DVDケース用のラベルでタイトルを貼って完成だ。
カバーのサイズ(各種あり)に合わせてページ数を整えなければならないし、
1ページも脱落しないよう、製本機にかける前に慎重な準備をする必要もあるが、
これだけ手軽に見栄えのよい物が作れるのはありがたい。
肝心の内容は、もちろん新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材にしている。
単なる読解教材ではなく、書かせる問題が圧倒的に多い。
なぜそう答えるか根拠を述べさせたり、本文中には書かれていないことを想像させたり、
主人公の言動を評価させたり...。
とにかく記述式問題が中心である。
語彙を広げる問題、言葉にこだわった問題も多い。
一つの言葉でどんな心情や状況が読み取れるか。
この言葉をこう換えるとどんな違いがあるのか...。
文を組み立てたり書き換えたりする問題、おかしな文を直す問題は、
日本語の表現技術を高めるためのものだ。
巻末にはそれをさらに磨くための補充問題も入れた。
なお、「超国語」と歌っているとおり、地理や歴史、科学と絡めた問題も随所にある。
算数の問題の解き方、考え方を論理的に説明させるページは、特にお薦めだ。
初めは空欄補充で基本的な手順を学び、同様の問題で完全記述に挑む。
子どもたちに最終的に身につけてほしいと考えている力の一つが「説明力」だ。
その入門編とも言うべき位置づけである。
記述式が主のため、解答例及び解説がかなり詳しくなった。
全体の3分の1、60ページを割いている。
塾の生徒に実際に解いてもらった結果、思いもよらぬ答が続出し、
解答例も解説もどんどん多くなってしまった。
もちろん、これでもすべての答に対応できているとは思えないが、
予測しうる答への最大限の対処は施したつもりである。
中学生の声は、思っていた以上に「難しい」が多かった。
中3になると正解率が高かったが、やはり中1には手応えがあったようだ。
生徒の反応を見て、特に難易度が高いと判断した問題については、
別の問題に差し替えたりヒントを添えるなどした。
それでもこの教材、おそらく大人が解いても十分やり甲斐を感じられるはずである。
ブロガーの皆さん、文章力養成にいかがですか?
「欲しいけど長野駅前まで行けない」という方は、コメント欄でお伝えください。
いかようにも善処しますよ。
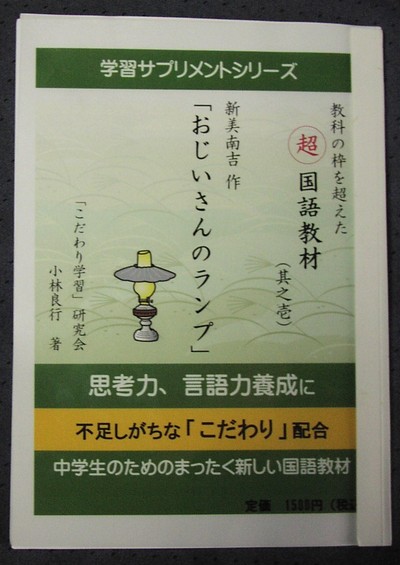
2011年05月20日
急募!
長野市稲葉の塾で、高校生の理系科目を教えられる方を募集します。
※数学ⅢCまで・物理・化学・生物(工業系専門科目も教えられれば尚可)
※月・水・金のうち1回または2回/20:00~22/00(時間は変更可)
※時給1300円~
※年齢、経験不問
※個別指導なので授業は不要です。個々の生徒へのアドバイスが主な仕事です。
※委細面談
<お問い合わせ> 026-222-0892 エクセルゼミナール
(不在の場合は携帯に転送されるので、しばらくお待ちください。)

※ 画像は松代・梅翁院の藤。棚の下は芳香に包まれていました。
※数学ⅢCまで・物理・化学・生物(工業系専門科目も教えられれば尚可)
※月・水・金のうち1回または2回/20:00~22/00(時間は変更可)
※時給1300円~
※年齢、経験不問
※個別指導なので授業は不要です。個々の生徒へのアドバイスが主な仕事です。
※委細面談
<お問い合わせ> 026-222-0892 エクセルゼミナール
(不在の場合は携帯に転送されるので、しばらくお待ちください。)

※ 画像は松代・梅翁院の藤。棚の下は芳香に包まれていました。
2011年05月14日
いまどきのユースホステル
前回の続き。
G.W.に妻と小布施のYH(ユースホステル)に泊まった話だ。
正式名称は「おぶせの風ユースホステル」という。
学生時代はYHの全盛期で、ローカル線を巡りながらあちこちのYHに泊まった。
初日の出を見に行った尻屋崎YH(青森県)や、卒論の調査で泊まり込んだ面河YH(愛媛県)はもうない。
唐桑YH(宮城県気仙沼市)は「地震の影響で休館」とのこと。
当時は若者ばかりで、男女別相部屋が当たり前だった。
酒もタバコも禁止。
食器は自分で洗う。
夜具のセッティングと片付けも、もちろん各自の仕事だ。
シーツと毛布カバー、枕カバーが一体になった「スリーピングシーツ」なるものがあったっけ...。
(やっとこの名前を思い出した...。)
夕食後には「ペアレント}(オーナー)を囲み、宿泊者全員で「ミーティング」。
自己紹介をしたり、ゲームをしたり、旅や宿の情報を交換したり...。
そこで仲良くなった人と翌日の行動を共にしたこともある。
正月だったので、青森駅前の市場でリンゴと餅を買い、
津軽鉄道のストーブ列車で餅を焼いて食べた。
一人旅の貧乏学生にとって、YHは不可欠な存在だった。
見知らぬ人と同室になることや、半ば強制的にミーティングに参加させられることを、
ときには負担に思うこともあったが、
料金の安さと新たな出会いの魅力は捨てがたかった。
実を言うと、妻と知り合ったのも山形県の小さな島のYHだったのだ。
あれから30年ほどになる。
時代は変わった。
かつてのYHのスタイルは若者に受け入れられなくなった。
廃業するところが増える一方で、
YHの概念をがらりと変える方向にシフトして生き残ってきた宿もある。
今回の小布施YHもまさにそんな宿だった。
ツインルームがいっぱいで、トリプルにツイン料金で泊まらせてもらったのだが、
まるでペンションのような小綺麗な設備だった。
「スリーピングシーツ」の面影もない羽毛布団のベッド。
浴衣やアメニティグッズも揃っている。
共同だがトイレはウォシュレット付きで、風呂にはジェットバスまであった。
もちろんお酒も飲めるし、食器も洗わなくていい...。
宿泊客は他に、東京・墨田区の職人さんの集団(美術館で催し物があったらしい)、
同年代の埼玉の夫婦、そして30~40代の一人旅ライダーが3人(大阪・福井・東京)。
職人さんたちは外に飲みに行ったが、
残りのメンバーは夕食後談話室に集まった。
妻が誕生日と言っておいたので、オーナーがワインを2本も振る舞ってくれたのだ。
よくしゃべるオーナーと、ヘルパー(アルバイト)の女子大生(信大農学部)も加わり、
12時近くまで大いに飲み、語り合った。
これがいまどきのYHだ。
昔とはずいぶん違うが、今は今の良さがある。
快適な空間、大人同士の落ち着いた交流。
オーナーに聞いてみた。
このYHの、ペンションとの違いは何か?存在意義はどこにあるのか?
...答えは「相部屋を残していること」、そして「宿泊者同士の団らんの場を提供すること」だった。
料金ももちろんそれなりだ。
昔は二食付きで2000円以下だった記憶がある。
小布施YHは相部屋で素泊まり3600円(YH会員)。朝食630円、夕食1050円。
私たちは非会員でツインルームだったので、夕食付きで1人6000+α円だった。
それでもまた行ってみたくなる。
夫婦や家族だけの時間を楽しむのもいいが、
ときにはこんな宿も利用してみてはいかがだろうか?
きっと、新たな発見があるはずだ。

※画像は「小布施ワイナリー」。おいしいワインでした。
G.W.に妻と小布施のYH(ユースホステル)に泊まった話だ。
正式名称は「おぶせの風ユースホステル」という。
学生時代はYHの全盛期で、ローカル線を巡りながらあちこちのYHに泊まった。
初日の出を見に行った尻屋崎YH(青森県)や、卒論の調査で泊まり込んだ面河YH(愛媛県)はもうない。
唐桑YH(宮城県気仙沼市)は「地震の影響で休館」とのこと。
当時は若者ばかりで、男女別相部屋が当たり前だった。
酒もタバコも禁止。
食器は自分で洗う。
夜具のセッティングと片付けも、もちろん各自の仕事だ。
シーツと毛布カバー、枕カバーが一体になった「スリーピングシーツ」なるものがあったっけ...。
(やっとこの名前を思い出した...。)
夕食後には「ペアレント}(オーナー)を囲み、宿泊者全員で「ミーティング」。
自己紹介をしたり、ゲームをしたり、旅や宿の情報を交換したり...。
そこで仲良くなった人と翌日の行動を共にしたこともある。
正月だったので、青森駅前の市場でリンゴと餅を買い、
津軽鉄道のストーブ列車で餅を焼いて食べた。
一人旅の貧乏学生にとって、YHは不可欠な存在だった。
見知らぬ人と同室になることや、半ば強制的にミーティングに参加させられることを、
ときには負担に思うこともあったが、
料金の安さと新たな出会いの魅力は捨てがたかった。
実を言うと、妻と知り合ったのも山形県の小さな島のYHだったのだ。
あれから30年ほどになる。
時代は変わった。
かつてのYHのスタイルは若者に受け入れられなくなった。
廃業するところが増える一方で、
YHの概念をがらりと変える方向にシフトして生き残ってきた宿もある。
今回の小布施YHもまさにそんな宿だった。
ツインルームがいっぱいで、トリプルにツイン料金で泊まらせてもらったのだが、
まるでペンションのような小綺麗な設備だった。
「スリーピングシーツ」の面影もない羽毛布団のベッド。
浴衣やアメニティグッズも揃っている。
共同だがトイレはウォシュレット付きで、風呂にはジェットバスまであった。
もちろんお酒も飲めるし、食器も洗わなくていい...。
宿泊客は他に、東京・墨田区の職人さんの集団(美術館で催し物があったらしい)、
同年代の埼玉の夫婦、そして30~40代の一人旅ライダーが3人(大阪・福井・東京)。
職人さんたちは外に飲みに行ったが、
残りのメンバーは夕食後談話室に集まった。
妻が誕生日と言っておいたので、オーナーがワインを2本も振る舞ってくれたのだ。
よくしゃべるオーナーと、ヘルパー(アルバイト)の女子大生(信大農学部)も加わり、
12時近くまで大いに飲み、語り合った。
これがいまどきのYHだ。
昔とはずいぶん違うが、今は今の良さがある。
快適な空間、大人同士の落ち着いた交流。
オーナーに聞いてみた。
このYHの、ペンションとの違いは何か?存在意義はどこにあるのか?
...答えは「相部屋を残していること」、そして「宿泊者同士の団らんの場を提供すること」だった。
料金ももちろんそれなりだ。
昔は二食付きで2000円以下だった記憶がある。
小布施YHは相部屋で素泊まり3600円(YH会員)。朝食630円、夕食1050円。
私たちは非会員でツインルームだったので、夕食付きで1人6000+α円だった。
それでもまた行ってみたくなる。
夫婦や家族だけの時間を楽しむのもいいが、
ときにはこんな宿も利用してみてはいかがだろうか?
きっと、新たな発見があるはずだ。

※画像は「小布施ワイナリー」。おいしいワインでした。
2011年05月09日
いちめんのなのはな
5月5日~6日、高山村と小布施町に行ってきた。
以前から妻が行きたいと言っていた小布施YH (ユースホステル)宿泊がメインだ。
高山村のしだれ桜は満開を過ぎていたのでパス。
ちょうど盛りの「黒部のエドヒガン桜」を見に行く。
推定樹齢500年の古木は味わいがある。
周りの菜の花との取り合わせが美しい。
小布施に入り、岩松院(卍)の天井絵(北斎作)を拝観。
隠し絵で富士山が描かれていると聞いていたので探した。
これかな?というのはあったが、確信は持てず...。
一度YHに車を置き、レンタサイクルで小布施ワイナリーへ。
車で行ったのでは私が試飲できない。
強風の中、アップダウンの激しい道を久々に自転車をこいだら疲れた。
ワイナリーは畑の中、民家に紛れてひっそりとあった。
ハデな看板もなく、家族経営のような小さな蔵だ。
でも、試飲したワインはなかなかの出来映え...。
赤を1本、衝動買いしてしまった。
その後、これも妻のリクエストでおぶせミュージアム・中島千波館へ。
桜の絵が有名だが、新作で、さっき見てきたばかりの「黒部のエドヒガン桜」が展示されていた。
グッド・タイミング!
何時間見ていても飽きないであろう奥深い作品に、しばし時を忘れる。
5時を過ぎ、いよいよYHへ。
ところが、YHのことについて書き始めたら止まらなくなった。
かなりの長文になりそうなので、この部分は次回に回す。
翌日は夕方から仕事だったので、午前中だけ小布施を散策して帰宅。
まずはYHのすぐ近くの北斎館へ。
期待していた割に収蔵作品が少なくてがっかり...。
玄照寺の三門はみごとだった。
年を取ったせいか、最近寺社の建築物に惹かれる。
もう1カ所、条光寺の薬師堂(室町時代築)を素通りしてしまったのが残念だ。
その後、ハイウェイオアシスで一服してから千曲川河畔の公園へ。
菜の花と桜が素晴らしいと聞いていたし、
ちょうど前日夕方のテレビでも放映されていたので、ぜひとも行きたかった。
様々な色彩の花が織りなす絶景!
満開の八重桜に花桃、一面に広がる菜の花、遠くに雪が残る黒姫や妙高...。
小布施にこんな花見の名所があるなんて知らなかった。
山村暮鳥の詩「風景」を思い出す。
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
かすかなるむぎぶえ
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
ひばりのおしやべり
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
やめるはひるのつき
いちめんのなのはな。
走行距離100kmにも満たない小さな旅だったが、
大いに満足できるものだった。



以前から妻が行きたいと言っていた小布施YH (ユースホステル)宿泊がメインだ。
高山村のしだれ桜は満開を過ぎていたのでパス。
ちょうど盛りの「黒部のエドヒガン桜」を見に行く。
推定樹齢500年の古木は味わいがある。
周りの菜の花との取り合わせが美しい。
小布施に入り、岩松院(卍)の天井絵(北斎作)を拝観。
隠し絵で富士山が描かれていると聞いていたので探した。
これかな?というのはあったが、確信は持てず...。
一度YHに車を置き、レンタサイクルで小布施ワイナリーへ。
車で行ったのでは私が試飲できない。
強風の中、アップダウンの激しい道を久々に自転車をこいだら疲れた。
ワイナリーは畑の中、民家に紛れてひっそりとあった。
ハデな看板もなく、家族経営のような小さな蔵だ。
でも、試飲したワインはなかなかの出来映え...。
赤を1本、衝動買いしてしまった。
その後、これも妻のリクエストでおぶせミュージアム・中島千波館へ。
桜の絵が有名だが、新作で、さっき見てきたばかりの「黒部のエドヒガン桜」が展示されていた。
グッド・タイミング!
何時間見ていても飽きないであろう奥深い作品に、しばし時を忘れる。
5時を過ぎ、いよいよYHへ。
ところが、YHのことについて書き始めたら止まらなくなった。
かなりの長文になりそうなので、この部分は次回に回す。
翌日は夕方から仕事だったので、午前中だけ小布施を散策して帰宅。
まずはYHのすぐ近くの北斎館へ。
期待していた割に収蔵作品が少なくてがっかり...。
玄照寺の三門はみごとだった。
年を取ったせいか、最近寺社の建築物に惹かれる。
もう1カ所、条光寺の薬師堂(室町時代築)を素通りしてしまったのが残念だ。
その後、ハイウェイオアシスで一服してから千曲川河畔の公園へ。
菜の花と桜が素晴らしいと聞いていたし、
ちょうど前日夕方のテレビでも放映されていたので、ぜひとも行きたかった。
様々な色彩の花が織りなす絶景!
満開の八重桜に花桃、一面に広がる菜の花、遠くに雪が残る黒姫や妙高...。
小布施にこんな花見の名所があるなんて知らなかった。
山村暮鳥の詩「風景」を思い出す。
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
かすかなるむぎぶえ
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
ひばりのおしやべり
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
やめるはひるのつき
いちめんのなのはな。
走行距離100kmにも満たない小さな旅だったが、
大いに満足できるものだった。






