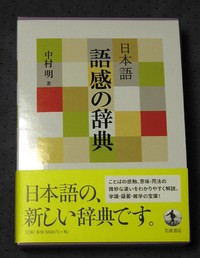2010年05月20日
なまえ随想~その2~
昨日の続き。
女の子の名前に「子」が付かなくなって久しい。
私の同世代は、ほとんどの女子が「○子」という名前だった。
他には「○恵」や「○美」があった程度で、たまに見かける「早月(さつき)」や「香織(かおり)」などは
かなりオシャレに感じたものだ。
今では当たり前のひらがなだけの名前もずいぶん珍しかった。
「○子」が廃れたのはいつ頃からだろう。
私の子どもの世代(昭和59年~平成元年生まれ)になると、東京ではほとんど「○子」がなかったが、
長野に来てみたら同級生や姉妹にまだあった。
最近では長野でもほとんどお目にかかれない。
たまに「○子」があると、逆に新鮮なくらいである。
そう言えば、親の名から一字を取って子どもに命名する習慣もなくなりつつある。
ときどき塾の生徒にそんな例を見かけると、そこに込められた親の思いを聞いてみたくなる。
何か強い信念をお持ちなのではないか...。
「○子」が減少した頃から、子どもの名前には音(オン)が重視されるようになったように思う。
わが家でも命名の際に、まずは聞いたときの語感を優先して候補を挙げ、
後からその音に合う漢字を選んだ。
一応字画も気にしたし、漢字の意味も念入りに調べたが、取っかかりは音であった。
最初の子に「世界で通用するように」と、そのまま英語に採り入れても違和感のない名前を付けたので、あとの2人にもその方針を貫いた。
本人たちはどう思っているか知らないが、親としては今でも音、漢字ともに気に入っている。
最近の子どもの名前には読めないものが結構ある。
「週刊長野」に載っている誕生祝いのコーナーを見ては、驚いたり感心したり...。
入塾の際に書いてもらう申込書にも「ふりがな」の欄は欠かせない。
やはり音を優先してあとから漢字を考えるため、当て字的なものが多くなっているのだろう。
まあ、認められた漢字さえ使っていれば読み方は自由に決められるのだが、
初対面の人に一々読み方を説明しなければならないのでは大変だろうと想像する。
もう一つ、お節介を承知の上で言うと、女の子の名前にあまりに可愛らしさや可憐さをイメージした名前を付けると、その子が年を取ってから「名前負け」しないだろうか。
みんながそうならいいか...。
あ、ウチの子もそうだった...。
名前の音の響きが、その子の性格に影響を与えるのでは?と考えたことがある。
特に母音である。
最近読んだ外山滋比古氏の本に、こんな記述があった。
「由来、女子の名には五十音のイ列とウ列の音の組み合わせで可憐さを表象していた。
ゆき子、きみ子、ゆみ子などである。」(from 外山滋比古「日本語の作法」)
近年はア列の音に人気があるという。
かつては可愛らしい女性になってほしいという願いで小さな母音が好まれたのが、
戦後、明るく伸びやかであってほしいという気持ちから、大きな母音を多用する名前が増えたとしている。
因みにア列の音は、昔は「太め」を暗示していたそうである。
これは親の側の願いであるが、その名で呼び続けることで子どもの側も影響を受けるのでは?と思う。
生まれてから何千回、何万回と呼びかけられる音韻が、性格の形成に無関係とは思えないのだ。他の条件が同じであれば、ア列の音が多い子どもの方が明るく大らかに育つのではないだろうか。
そんな研究が今までにあるのかどうか、ちょっと調べてみたい。

女の子の名前に「子」が付かなくなって久しい。
私の同世代は、ほとんどの女子が「○子」という名前だった。
他には「○恵」や「○美」があった程度で、たまに見かける「早月(さつき)」や「香織(かおり)」などは
かなりオシャレに感じたものだ。
今では当たり前のひらがなだけの名前もずいぶん珍しかった。
「○子」が廃れたのはいつ頃からだろう。
私の子どもの世代(昭和59年~平成元年生まれ)になると、東京ではほとんど「○子」がなかったが、
長野に来てみたら同級生や姉妹にまだあった。
最近では長野でもほとんどお目にかかれない。
たまに「○子」があると、逆に新鮮なくらいである。
そう言えば、親の名から一字を取って子どもに命名する習慣もなくなりつつある。
ときどき塾の生徒にそんな例を見かけると、そこに込められた親の思いを聞いてみたくなる。
何か強い信念をお持ちなのではないか...。
「○子」が減少した頃から、子どもの名前には音(オン)が重視されるようになったように思う。
わが家でも命名の際に、まずは聞いたときの語感を優先して候補を挙げ、
後からその音に合う漢字を選んだ。
一応字画も気にしたし、漢字の意味も念入りに調べたが、取っかかりは音であった。
最初の子に「世界で通用するように」と、そのまま英語に採り入れても違和感のない名前を付けたので、あとの2人にもその方針を貫いた。
本人たちはどう思っているか知らないが、親としては今でも音、漢字ともに気に入っている。
最近の子どもの名前には読めないものが結構ある。
「週刊長野」に載っている誕生祝いのコーナーを見ては、驚いたり感心したり...。
入塾の際に書いてもらう申込書にも「ふりがな」の欄は欠かせない。
やはり音を優先してあとから漢字を考えるため、当て字的なものが多くなっているのだろう。
まあ、認められた漢字さえ使っていれば読み方は自由に決められるのだが、
初対面の人に一々読み方を説明しなければならないのでは大変だろうと想像する。
もう一つ、お節介を承知の上で言うと、女の子の名前にあまりに可愛らしさや可憐さをイメージした名前を付けると、その子が年を取ってから「名前負け」しないだろうか。
みんながそうならいいか...。
あ、ウチの子もそうだった...。
名前の音の響きが、その子の性格に影響を与えるのでは?と考えたことがある。
特に母音である。
最近読んだ外山滋比古氏の本に、こんな記述があった。
「由来、女子の名には五十音のイ列とウ列の音の組み合わせで可憐さを表象していた。
ゆき子、きみ子、ゆみ子などである。」(from 外山滋比古「日本語の作法」)
近年はア列の音に人気があるという。
かつては可愛らしい女性になってほしいという願いで小さな母音が好まれたのが、
戦後、明るく伸びやかであってほしいという気持ちから、大きな母音を多用する名前が増えたとしている。
因みにア列の音は、昔は「太め」を暗示していたそうである。
これは親の側の願いであるが、その名で呼び続けることで子どもの側も影響を受けるのでは?と思う。
生まれてから何千回、何万回と呼びかけられる音韻が、性格の形成に無関係とは思えないのだ。他の条件が同じであれば、ア列の音が多い子どもの方が明るく大らかに育つのではないだろうか。
そんな研究が今までにあるのかどうか、ちょっと調べてみたい。

Posted by どーもオリゴ糖 at 14:59│Comments(0)
│ことば