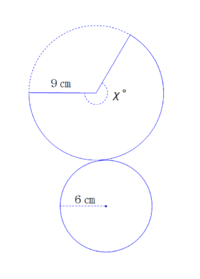2010年06月23日
虫を愛でる文化
知らなかった。
アメリカでは虫を飼う習慣はないのだそうだ。
欧米人の耳には秋の虫の声も雑音にしか聞こえない、ということは知っていた。
それでも子どもたちは、日本と同じようにカブトムシやセミを捕まえるのだろうと思っていた。
ところが、アメリカでは虫好きは変わり者扱いされるというのだ。
20日付の朝日新聞「ひと」欄で、
ジェシカ・オーレックという若い女性の話を読んだ。
幼い頃から大の虫好きで、アメリカでは肩身の狭い思いをしていた彼女は、
来日して日本人の「昆虫愛」に感激し、映画まで作ってしまった。
彼女は言う。
日本で虫が愛される理由の根底には「もののあはれ」があると...。
「日本の人々は虫たちのはかない生命に美を感じることができる。
米市民にはその文化がない」
他の国はどうなのだろう。
虫の姿や声に季節の移ろいを感じ取るのは
日本独特の文化なのだろうか...。
古来、短歌や俳句には様々な虫たちが登場してきた。
チョウ、トンボ、セミ、キリギリス...。
ホタルやチョウはときに魂の象徴ともされてきた。
メジャーな昆虫ばかりではない。
一茶を始めとして、ハエ、蚊、ハチやアリなどを詠んだ句や歌は多い。
小さな虫たちへの温かい目が感じられる。
そう言えば、蛾や毛虫まで可愛がるお姫様の話もあった。
堤中納言物語の中の「虫めづる姫君」。
私は高校時代にこれに出会って、古典の魅力に取り憑かれたのだった。
アメリカでは蛾もチョウも「バグ」と一括りで扱うという話も聞いた。
対人間以上に「差別」がない。
それだけ虫に対する関心が薄いということだろう。
あるいは繊細さの問題か...。
もっとも、最近では日本でも、虫を極端に嫌う子どもが少なくない。
夜、小さな羽虫が入ってきただけで、男の子も大騒ぎだ。
チョウを怖がる女の子も珍しくない。
生活様式と共に、日本人の虫に対する意識も、徐々にアメリカナイズされてきたということか...。
夏休みの定番だった昆虫採集も、とんと見かけなくなった。
残酷だとか、自然保護だとかの声に押され、旗色が悪い。
子どもの昆虫採集くらいで破壊されるほど、自然はヤワではないという意見も多いのだが...。
虫を遠ざける背景には、前にも書いた異常な清潔志向もあると思う。
虫は汚い、不潔だ、すぐに捨てなさい...!
こうして虫から遠ざけられた子どもたちは、
はかない命に対する美意識とは無縁に育つ。
本来子どもは残酷なものであり、小さな虫を殺したり、
大切に飼っていたカブトムシを死なせてしまったりという体験を通して
命について学んできたはずだからだ。
一方でホタルを増やしたり、
オオムラサキの棲息地を整備しようという動きも盛んである。
しかし今本当に必要なのは、そういう特別な活動よりも、
身の周りの名もない虫たちとの距離を縮めることだと思う。
虫を愛でる文化、「もののあはれ」を解する心は日本人の宝である。
これを将来に渡って守り続けていくためには、
その伝統を自覚し、誇りを持つことが何より重要であろう。
今年はハルゼミの声を聞かない...。
行水の 捨て所なし 虫の声 (上島鬼貫)

※数年前、庭先に来たオオムラサキである。
アメリカでは虫を飼う習慣はないのだそうだ。
欧米人の耳には秋の虫の声も雑音にしか聞こえない、ということは知っていた。
それでも子どもたちは、日本と同じようにカブトムシやセミを捕まえるのだろうと思っていた。
ところが、アメリカでは虫好きは変わり者扱いされるというのだ。
20日付の朝日新聞「ひと」欄で、
ジェシカ・オーレックという若い女性の話を読んだ。
幼い頃から大の虫好きで、アメリカでは肩身の狭い思いをしていた彼女は、
来日して日本人の「昆虫愛」に感激し、映画まで作ってしまった。
彼女は言う。
日本で虫が愛される理由の根底には「もののあはれ」があると...。
「日本の人々は虫たちのはかない生命に美を感じることができる。
米市民にはその文化がない」
他の国はどうなのだろう。
虫の姿や声に季節の移ろいを感じ取るのは
日本独特の文化なのだろうか...。
古来、短歌や俳句には様々な虫たちが登場してきた。
チョウ、トンボ、セミ、キリギリス...。
ホタルやチョウはときに魂の象徴ともされてきた。
メジャーな昆虫ばかりではない。
一茶を始めとして、ハエ、蚊、ハチやアリなどを詠んだ句や歌は多い。
小さな虫たちへの温かい目が感じられる。
そう言えば、蛾や毛虫まで可愛がるお姫様の話もあった。
堤中納言物語の中の「虫めづる姫君」。
私は高校時代にこれに出会って、古典の魅力に取り憑かれたのだった。
アメリカでは蛾もチョウも「バグ」と一括りで扱うという話も聞いた。
対人間以上に「差別」がない。
それだけ虫に対する関心が薄いということだろう。
あるいは繊細さの問題か...。
もっとも、最近では日本でも、虫を極端に嫌う子どもが少なくない。
夜、小さな羽虫が入ってきただけで、男の子も大騒ぎだ。
チョウを怖がる女の子も珍しくない。
生活様式と共に、日本人の虫に対する意識も、徐々にアメリカナイズされてきたということか...。
夏休みの定番だった昆虫採集も、とんと見かけなくなった。
残酷だとか、自然保護だとかの声に押され、旗色が悪い。
子どもの昆虫採集くらいで破壊されるほど、自然はヤワではないという意見も多いのだが...。
虫を遠ざける背景には、前にも書いた異常な清潔志向もあると思う。
虫は汚い、不潔だ、すぐに捨てなさい...!
こうして虫から遠ざけられた子どもたちは、
はかない命に対する美意識とは無縁に育つ。
本来子どもは残酷なものであり、小さな虫を殺したり、
大切に飼っていたカブトムシを死なせてしまったりという体験を通して
命について学んできたはずだからだ。
一方でホタルを増やしたり、
オオムラサキの棲息地を整備しようという動きも盛んである。
しかし今本当に必要なのは、そういう特別な活動よりも、
身の周りの名もない虫たちとの距離を縮めることだと思う。
虫を愛でる文化、「もののあはれ」を解する心は日本人の宝である。
これを将来に渡って守り続けていくためには、
その伝統を自覚し、誇りを持つことが何より重要であろう。
今年はハルゼミの声を聞かない...。
行水の 捨て所なし 虫の声 (上島鬼貫)

※数年前、庭先に来たオオムラサキである。
Posted by どーもオリゴ糖 at 11:31│Comments(0)
│よしなしごと