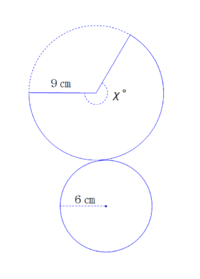2010年05月02日
温故知新
隅田川のほとりに建設中の「東京スカイツリー」。
地震対策として、五重塔にも使われている「心柱」を採用するという。
「心柱」というのは五重塔の中心部を地面から最上層まで貫く柱で、各層とは直結しておらず、
塔の先端の「相輪」と呼ばれる部分を支えているだけだそうだ。
これがあるお蔭で、地震の際には各層が互い違いの方向に揺れ、震動を吸収するという。
今一つ構造が理解できないのだが、スカイツリーの場合、下部は心柱を本体に固定し、上部はオイルダンパーを間に入れて心柱が自由に動ける仕組みになっているらしい。
五重塔の場合も、各層とは緩い連結になっているのでは、と想像する。
これは私が今住んでいるような、いわゆる「古民家」の作りと共通する。
我が家は「築年不詳」。仲介業者からは「百年は経っている」と言われた。
古民家の屋根裏には、柱と梁が固定されていない「かんぬき」と呼ばれる構造がある。
関所や大名屋敷の門にある「かんぬき」と同じように、柱をくり抜いた穴を梁が貫通していると考えてほしい。
穴は梁の太さより少し大きめに作ってあるので、梁は水平方向に自由に動ける。
地震が起きれば、柱と梁は別方向に揺れることになる。
古民家は他にも、柱が土台に固定されていなかったり、壁が崩れやすい土でできていたりすることで、
地震の際のエネルギーをうまく逃がす構造になっている。
いわゆる「免震」という考え方で、柱の位置がずれたり、壁が壊れたりという小さな損壊と引き換えに、致命的な建物本体の倒壊を免れるのである。
がちがちに固めて揺れに対抗する「耐震」ではなく、揺れを受け入れてかわす...。
日本人の自然観が影響しているようで興味深い。
法隆寺の五重塔を修復したときの話を読んだことがあるが、心柱以外にも、建物を長く持たせる様々な工夫が施されていることに驚いた。
釘に使っている鉄は純度が極めて高いので錆びない。
釘の形もヒノキにしっかり食い込むよう考えられている。
各層の「ひさし」の部分は「やじろべえ」的な構造になっていて、これも地震に強い。
何よりヒノキの性質を知り尽くした上で、適材適所の用い方をしている
だからこそ、千何百年を経てなお健在の、世界最古の木造建築たりえたのである。
現在の最新技術を駆使して建てられた建築の、いったいどれだけが千年後にも残っているだろう?
大量生産、大量消費のコンセプトの元に作られた建物では、百年もつのが精一杯ではないだろうか。
上述した古民家のような建物を新たにや建てることは、今の建築基準法では不可能らしい。
いにしえの職人たちの技術が、伝えられないまま消えていくのはもったいない。
それを今に生かすことを、もっと積極的に考えてもらいたいと強く望む。

地震対策として、五重塔にも使われている「心柱」を採用するという。
「心柱」というのは五重塔の中心部を地面から最上層まで貫く柱で、各層とは直結しておらず、
塔の先端の「相輪」と呼ばれる部分を支えているだけだそうだ。
これがあるお蔭で、地震の際には各層が互い違いの方向に揺れ、震動を吸収するという。
今一つ構造が理解できないのだが、スカイツリーの場合、下部は心柱を本体に固定し、上部はオイルダンパーを間に入れて心柱が自由に動ける仕組みになっているらしい。
五重塔の場合も、各層とは緩い連結になっているのでは、と想像する。
これは私が今住んでいるような、いわゆる「古民家」の作りと共通する。
我が家は「築年不詳」。仲介業者からは「百年は経っている」と言われた。
古民家の屋根裏には、柱と梁が固定されていない「かんぬき」と呼ばれる構造がある。
関所や大名屋敷の門にある「かんぬき」と同じように、柱をくり抜いた穴を梁が貫通していると考えてほしい。
穴は梁の太さより少し大きめに作ってあるので、梁は水平方向に自由に動ける。
地震が起きれば、柱と梁は別方向に揺れることになる。
古民家は他にも、柱が土台に固定されていなかったり、壁が崩れやすい土でできていたりすることで、
地震の際のエネルギーをうまく逃がす構造になっている。
いわゆる「免震」という考え方で、柱の位置がずれたり、壁が壊れたりという小さな損壊と引き換えに、致命的な建物本体の倒壊を免れるのである。
がちがちに固めて揺れに対抗する「耐震」ではなく、揺れを受け入れてかわす...。
日本人の自然観が影響しているようで興味深い。
法隆寺の五重塔を修復したときの話を読んだことがあるが、心柱以外にも、建物を長く持たせる様々な工夫が施されていることに驚いた。
釘に使っている鉄は純度が極めて高いので錆びない。
釘の形もヒノキにしっかり食い込むよう考えられている。
各層の「ひさし」の部分は「やじろべえ」的な構造になっていて、これも地震に強い。
何よりヒノキの性質を知り尽くした上で、適材適所の用い方をしている
だからこそ、千何百年を経てなお健在の、世界最古の木造建築たりえたのである。
現在の最新技術を駆使して建てられた建築の、いったいどれだけが千年後にも残っているだろう?
大量生産、大量消費のコンセプトの元に作られた建物では、百年もつのが精一杯ではないだろうか。
上述した古民家のような建物を新たにや建てることは、今の建築基準法では不可能らしい。
いにしえの職人たちの技術が、伝えられないまま消えていくのはもったいない。
それを今に生かすことを、もっと積極的に考えてもらいたいと強く望む。

Posted by どーもオリゴ糖 at 15:15│Comments(0)
│よしなしごと