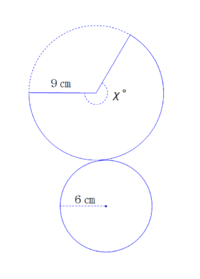2010年08月26日
「諦め」のすすめ
「諦める」という言葉にはマイナスのイメージが伴う。
夢や希望を棄てる、努力をやめるといったニュアンスが感じられる。
しかし、この言葉の語源は「明らむ」だという。
「明らかに見極める。事情をはっきりさせる。」などの意味を持つ。
「諦」という漢字にしても、もともとは「悟りを開く」という意味である。
(以上、「不幸な国の幸福論」(by加賀乙彦)参照。)
「諦める」は、本来よい意味の言葉なのだ。
己の置かれた状況を見極め、これからの指針を明確にする。
努力すれば変えられるものと、自分の力では変えられないものを区別することで、
心身の健康を保つことができる。
軍国主義の世になって、この考え方は一変する。
お国のため、がむしゃらに突き進む勇気、根性、大和魂が美徳とされた。
悟りなど開いている暇はない。
「諦める」ことはいけないこと、弱いことに成り下がったのだ。
戦後は戦後で、経済最優先の世の中になり、アメリカ的な競争主義が蔓延した。
人々は次から次へと「豊かさ」を求め、その欲望は限りを知らない。
「隣の芝生」に憧れ、他者と比べて劣っている点ばかりを憂慮し、
いつまでたっても満足感、幸福感を得られない...。
今の時代こそ、「諦める」ことの重要性が見直されるべきだろう。
「足るを知る」 ということでもある。
こう書くとなんだか貧乏くさい、年寄りじみた言い方に聞こえるかも知れないが、
自分を過小評価したり、己に早めに見切りをつけたりすることを勧めているわけではない。
こじんまりとした、小市民的な幸福に満足せよと言いたいのではないのだ。
先に書いたように、努力しても変えられないことは受け入れよということだ。
血縁、地縁、職場の人間関係、生まれながらの障害、持病などなど...。
他人の性格などそう簡単に変えられるものではない。
お金持ちの家に生まれなかったことを恨んでいても始まらない...。
一方で、「成せば成る」的な思想もわからないではない。
「決して諦めない」姿勢を貫き通すことで、
科学的には説明できない「奇跡」を起こした例も少なからずあるだろう。
それでも敢えて、今の日本に必要なのは「諦め」の思想だと言いたい。
経済大国になっても、不機嫌な顔の国民がこんなに多いのはなぜなのか...。
おそらく、江戸時代までの庶民は「諦める」ことを実践できていたのだと思う。
みんな貧しかったに違いないが、今よりずっとニコニコと楽しく暮らしていたのではなかろうか...。
「大和魂」なんていうのは、為政者が都合よく作り上げた観念だと私は思っている。

夢や希望を棄てる、努力をやめるといったニュアンスが感じられる。
しかし、この言葉の語源は「明らむ」だという。
「明らかに見極める。事情をはっきりさせる。」などの意味を持つ。
「諦」という漢字にしても、もともとは「悟りを開く」という意味である。
(以上、「不幸な国の幸福論」(by加賀乙彦)参照。)
「諦める」は、本来よい意味の言葉なのだ。
己の置かれた状況を見極め、これからの指針を明確にする。
努力すれば変えられるものと、自分の力では変えられないものを区別することで、
心身の健康を保つことができる。
軍国主義の世になって、この考え方は一変する。
お国のため、がむしゃらに突き進む勇気、根性、大和魂が美徳とされた。
悟りなど開いている暇はない。
「諦める」ことはいけないこと、弱いことに成り下がったのだ。
戦後は戦後で、経済最優先の世の中になり、アメリカ的な競争主義が蔓延した。
人々は次から次へと「豊かさ」を求め、その欲望は限りを知らない。
「隣の芝生」に憧れ、他者と比べて劣っている点ばかりを憂慮し、
いつまでたっても満足感、幸福感を得られない...。
今の時代こそ、「諦める」ことの重要性が見直されるべきだろう。
「足るを知る」 ということでもある。
こう書くとなんだか貧乏くさい、年寄りじみた言い方に聞こえるかも知れないが、
自分を過小評価したり、己に早めに見切りをつけたりすることを勧めているわけではない。
こじんまりとした、小市民的な幸福に満足せよと言いたいのではないのだ。
先に書いたように、努力しても変えられないことは受け入れよということだ。
血縁、地縁、職場の人間関係、生まれながらの障害、持病などなど...。
他人の性格などそう簡単に変えられるものではない。
お金持ちの家に生まれなかったことを恨んでいても始まらない...。
一方で、「成せば成る」的な思想もわからないではない。
「決して諦めない」姿勢を貫き通すことで、
科学的には説明できない「奇跡」を起こした例も少なからずあるだろう。
それでも敢えて、今の日本に必要なのは「諦め」の思想だと言いたい。
経済大国になっても、不機嫌な顔の国民がこんなに多いのはなぜなのか...。
おそらく、江戸時代までの庶民は「諦める」ことを実践できていたのだと思う。
みんな貧しかったに違いないが、今よりずっとニコニコと楽しく暮らしていたのではなかろうか...。
「大和魂」なんていうのは、為政者が都合よく作り上げた観念だと私は思っている。

Posted by どーもオリゴ糖 at 13:09│Comments(0)
│よしなしごと