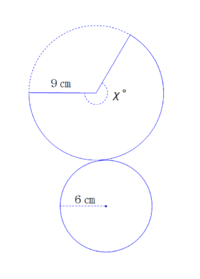2010年11月17日
ローマ字
少し前、新聞の投稿欄に、小学校でのローマ字指導についての意見が載っていた。
「訓令式」のローマ字を教えることに対する疑問である。
小学校で教わる「訓令式」というのは、日本独自の表記だ。
「シ」をsi、「ジ」をzi、「チャ」をtyaと表す。
残念ながら、一般生活で使われることは皆無に等しい。
一方、国際的に通用し、広く使われているのは「ヘボン式」だ。
訓令式と共通するものがほとんどだが、一部異なる。
たとえば「シ」はshi、「ジ」はji、「チャ」はchaという具合だ。
ローマ字を教える目的は、一つには世界に通用する表音文字を身につけさせることであり、
同時に英語への導入という役割もあるだろう。
であれば、ヘボン式の方がはるかに都合がよい。
siと書くと、外国人は「シ」と読んでくれない。「スィ」になってしまう。
「シ」と読ませるためには、sの後にhが必要なのだ。
see だと「スィー」、she だと「シー」になるのと同じである。
tiは「ティ」、tuは「トゥ」、ziは「ズィ」になってしまうので、
それぞれchi、tsu、jiと表さなければならない。
「あつし」という名前を訓令式で Atusi と書けば、「アトゥティ」と発音されてしまうだろう。
塾に通う6年生に英語への準備指導を始めているが、
まず確かめるのはローマ字の定着度合である。
あやふやな子はもちろん徹底訓練するが、
訓令式をほぼ完璧にマスターしている子でも、ここで新たにヘボン式を教えなければならない。
数は少ないが、教わる方にしてみれば二度手間である。
体系的にまとまっているのは訓令式だ。
各行の子音と、五つの母音を機械的に組み合わせるだけで済む。
ヘボン式のような不規則性はない。
初めて習う子どもにはわかりやすいだろう。
だからと言って、結局は通用しない、学び直さねばならないものを、
わざわざ勉強するのも如何なものか...。
特にsyaやzyoなど面倒なものについては、その感が強い。
小学校でもヘボン式を教えればいい。
訓令式を原則とし、「シ」や「チャ」はヘボン式も教える。
どちらでもいいが、国際的にはこうだということもきちんと伝えればすむことだ。
自分の名前を「ダイティ」や「スィオリ」と読まれたくない子は、
積極的にヘボン式を覚えるだろう。
因みにキーボードではsiやtuでも「シ」「ツ」と出るが、
これは訓令式の名残か、スピードアップのためか...。
その分、外国人より得しているのか...。
小学校でも英語の授業が始まることで、
ローマ字の扱いがどうなって行くのか、注目したいところである。

「訓令式」のローマ字を教えることに対する疑問である。
小学校で教わる「訓令式」というのは、日本独自の表記だ。
「シ」をsi、「ジ」をzi、「チャ」をtyaと表す。
残念ながら、一般生活で使われることは皆無に等しい。
一方、国際的に通用し、広く使われているのは「ヘボン式」だ。
訓令式と共通するものがほとんどだが、一部異なる。
たとえば「シ」はshi、「ジ」はji、「チャ」はchaという具合だ。
ローマ字を教える目的は、一つには世界に通用する表音文字を身につけさせることであり、
同時に英語への導入という役割もあるだろう。
であれば、ヘボン式の方がはるかに都合がよい。
siと書くと、外国人は「シ」と読んでくれない。「スィ」になってしまう。
「シ」と読ませるためには、sの後にhが必要なのだ。
see だと「スィー」、she だと「シー」になるのと同じである。
tiは「ティ」、tuは「トゥ」、ziは「ズィ」になってしまうので、
それぞれchi、tsu、jiと表さなければならない。
「あつし」という名前を訓令式で Atusi と書けば、「アトゥティ」と発音されてしまうだろう。
塾に通う6年生に英語への準備指導を始めているが、
まず確かめるのはローマ字の定着度合である。
あやふやな子はもちろん徹底訓練するが、
訓令式をほぼ完璧にマスターしている子でも、ここで新たにヘボン式を教えなければならない。
数は少ないが、教わる方にしてみれば二度手間である。
体系的にまとまっているのは訓令式だ。
各行の子音と、五つの母音を機械的に組み合わせるだけで済む。
ヘボン式のような不規則性はない。
初めて習う子どもにはわかりやすいだろう。
だからと言って、結局は通用しない、学び直さねばならないものを、
わざわざ勉強するのも如何なものか...。
特にsyaやzyoなど面倒なものについては、その感が強い。
小学校でもヘボン式を教えればいい。
訓令式を原則とし、「シ」や「チャ」はヘボン式も教える。
どちらでもいいが、国際的にはこうだということもきちんと伝えればすむことだ。
自分の名前を「ダイティ」や「スィオリ」と読まれたくない子は、
積極的にヘボン式を覚えるだろう。
因みにキーボードではsiやtuでも「シ」「ツ」と出るが、
これは訓令式の名残か、スピードアップのためか...。
その分、外国人より得しているのか...。
小学校でも英語の授業が始まることで、
ローマ字の扱いがどうなって行くのか、注目したいところである。

Posted by どーもオリゴ糖 at 12:01│Comments(0)
│よしなしごと